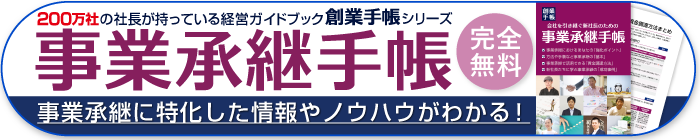廃業する際のコストとは?退職金や資金調達方法、流れなどの疑問を解決しよう
廃業するにもコストがかかる
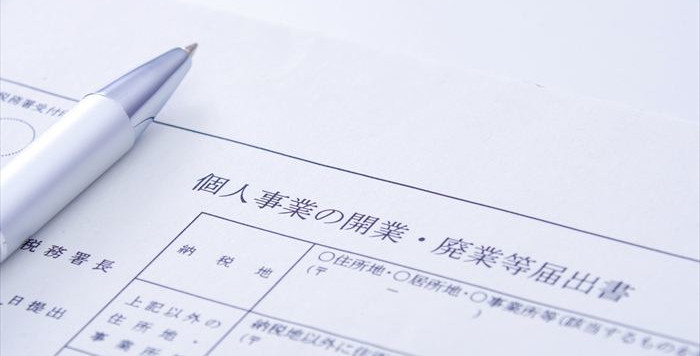
「事業の発展が難しい」「跡継ぎもいないために経営継続が困難」など、事業の継続が難しくなれば廃業を選択する人もいます。
多くの経営者にとって廃業は初めての経験となります。
そのため、どのくらいのコストが発生するのか、手続きの仕方を含めてわからないことも多いかもしれません。
そこで今回は、法人及び個人事業主が廃業する際にかかるコストや法人が廃業する際の流れについて、コストが足りない場合の資金調達方法などについて解説していきます。
廃業を検討している経営者は、参考にしてみてください。
廃業を決める前に、もう一つの選択肢を。
後継者不在・コスト増で悩む経営者のために、創業手帳の『事業承継手帳』は、承継の進め方・実例・チェックリストを一冊に整理。
「会社を残す」「雇用と取引を守る」道筋を、今すぐ確認できます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
法人が廃業する際にかかるコスト

法人が廃業する際には、様々な手続きが必要になり、その分コストも発生します。
諸費用を支払う必要があるため、前もってどの程度の費用が必要になるのか把握しておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。
廃業にかかる詳しいコストの内訳を解説していきます。
登記にかかる費用
法人が廃業する際には、解散登記・清算人の選任登記・清算結了登記の3つの登記費用が発生します。目安としては、以下の表を参考にしてください。
| 登記 | 費用の目安 |
| 解散登記 | 30,000円 |
| 清算人の選任登記 | 9,000円 |
| 清算結了登記 | 2,000円 |
会社が倒産した際には、2週間以内に解散の登記をする必要があります。その際に発生するのが登録免許税となり、30,000円となります。
清算人とは、解散した会社の清算にかかる手続きを行う人を指し、債券の現金化や債権の回収、弁済などを担う人物です。
清算人の選任登記には9,000円の費用がかかり、解散後2週間以内に登記を行う必要があります。
また、精算が終了した段階で清算結了登記をしなければいけません。この登録免許税として2,000円の費用が必要です。
登記にかかる費用だけでも41,000円かかることを覚えておきましょう。
官報公告の費用
官報とは、国民に対して周知すべき重要な情報を掲載する国の機関紙です。
行政機関の休日を除いて毎日発刊されており、株式会社は会社法に基づいて決算公示などを官報にて行う義務があります。
株式会社が解散した際には、官報において解散や債券申出に関する事項を公示しなければいけません。
公示を行うには費用がかかり、1行につき3,947円(税抜3,589円)となります。
通常、解散公示は9行~11行ほどとなるため、35,531円~43,426円の費用が発生します。
公開されている公告は、官報公示のホームページをチェックしてみてください。
在庫や設備の処分費用
事業で生じた在庫や設備があれば、処分する必要があります。廃業をしても、在庫の量が多ければ確定申告による税負担が多くなるため注意が必要です。
そのため、リスクを抑えるためにもまとめて処分する必要があります。
一般的には、仕入れ値よりも安い価格で売却する他、処分しきれない在庫を引き取ってくれる業者に依頼します。
業者に処分する場合には、費用が必要になるケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
事業活動で活用した設備や機械なども廃業時に処分します。
同業他社に引き取りを依頼できれば、買取してもらうことも可能ですが、老朽化している場合や機密情報が含まれている場合は、買取は依頼できません。
その場合は、専門の業者に廃棄費用を支払って廃棄を依頼します。
廃棄処分にかかる費用は業者によって異なりますが、トラック1台で数万円からが目安です。
事業規模が大きければ使用していた設備や機械も多いため、処分に1,000万円以上かかるケースもあります。
見積もりを依頼して、安く処分できる業者を探すことでコストを抑えられます。
物件の原状回復費用
個人宅もしくは保有している建物で事業を実施していた場合であれば、原状回復の必要がないため、コストはかかりません。
しかし、賃貸借物件で事業を行っていた場合は、廃業した後に原状回復をして物件を引き渡す必要があります。
一般的に、一坪数万~10万円ほどが原状回復でかかると言われています。借りている事業所の面積が広ければ、その分かかるコストも多くなってしまうでしょう。
また、設備の位置を変更しているケースもあり、その場合はさらに費用負担が増加する可能性があります。
専門家への依頼費用
登記を始め、様々な手続きを会社だけではできないケースもあります。多くの書類が必要になり、専門的な手続きも多いため、滞りなく進めるためにも専門的な知識が必要です。
税理士や司法書士、弁護士といった専門家に依頼をすれば、廃業の手続きを代行してもらうことが可能です。
廃業や解散、清算などの手続きを依頼する際、報酬は依頼する専門家や事務所によって異なります。
一般的には、60万円~70万円ほどとなるため、費用を抑えたいのであれば、複数の事務所に見積もりを依頼してみてください。
ただし、費用のみで依頼をすると後悔するケースもあります。専門家との相性やサポート力など、あらゆる面を考慮して依頼する専門家を選ぶようにしましょう。
個人事業主が廃業する際にかかるコスト

個人事業主は、法人と異なり廃業時に登記を行う必要はありません。そのため、法人と比較すると廃業にかかるコストが安く済む傾向にあります。
しかし、0円で廃業できるとは限らないので注意してください。個人事業主が廃業する際にかかるコストは、以下の通りです。
-
- 在庫や設備を処分するための費用
- 賃貸物件の原状回復費
- 専門家への依頼費用
個人事業主の場合は、自宅を作業場にして小規模な事業を続けている人も多いでしょう。その場合は、原状回復費用は発生しません。
在庫や設備は、法人と同様に安く売ることで処分できるケースもあれば、在庫の引き取りを依頼できるケースもあります。
まだ使用できる設備であれば中古品として売却することも可能です。
法人が廃業する際の流れ

ここからは、法人が廃業する際の流れを解説していきます。どういった手順で廃業すればいいのかわからない人は、参考にして手続きを進めていきましょう。
1.営業終了日の決定
廃業することを決めたら、まずは営業終了日を決めます。ただし、「明日にでも廃業したい」といったような急な廃業は難しいです。
書類の準備や様々な手続きを踏まえて、数カ月先に設定することが一般的です。2カ月以上は余裕を持って決めるよう考えてみてください。
2.株主総会での決議
廃業日が決定したら、取引先や関係者に廃業を伝える文章を送り、従業員に対しては30日前までに解雇通告を行います。そして、株式会社であれば株主総会での承認も必要です。
発行済株式総数の過半数の人数を集めた株主総会を開き、議決権の2/3以上の賛成を得られれば承認されます。
賛成が集まらずに書面決議になれば全員の賛成が必要となるため注意してください。
なお、株主が少数の場合には、株主総会を省略し、株主全員の同意による書面決議で解散を決めることも少なくありません。
3.解散登記・清算人の登記
定款で清算人を定めていない場合には、株式総会で清算人を決める必要もあります。中小企業においては、代表取締役が清算人として選出されるのが一般的です。
そして解散決議で廃業が決まれば、清算人による解散登記が行われます。解散登記は管轄の法務局で行います。
前述したように、決議から2週間以内に解散登記を行う必要があるため、期間が過ぎないよう注意してください。
解散登記では、登記申請書・定款・株式総会の議事録といった書類が必要になるため、あらかじめ用意しておくと、スムーズな手続きが可能です。
4.廃業届の提出
解散登記が終わったら廃業届の提出や各種届出を行います。
都道府県の税事務所や管轄の税務署、市町村の役所に届出を行い、従業員を解雇する場合には、労務局もしくは労働基準監督署、社会保険事務所などにも届出を行わなければいけません。
また、商工会議所の他、各加入団体に対して退会手続きを行います。具体的な提出先と提出が必要な書類は以下の通りです。
・税務署
廃業届、異動届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・都道府県税事務所
解散についての届出書
・労働基準監督署
労働保険料還付請求書、確定保険料申告書
・ハローワーク
雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書、雇用保険適用事業所廃止届
・日本年金機構
健康保険/厚生年金保険適用事業所全喪届
5.官報での解散公告
解散公示を官報にて行います。解散公示は、会社法499条で定められている事項なので、必ず実施する必要があります。
解散後は速やかに実施するようにしてください。また、公示掲載期間は2カ月以上必要です。
6.清算人による清算
清算人は、就任した後に会社の財産を的確に把握しなければいけません。会社資産の売却や債権の回収などを実施し、債務の弁済を行っていきます。
また、資産が残っているようであれば、株主に分配します。純資産が赤字であれば、破産の手続きも必要です。
併せて、解散日時点の財産目録と貸借対照表の作成も行います。株主総会に提出し、承認を受けた上で清算結了登記が完了するまで保存する必要があります。
7.解散・清算の確定申告
廃業時には3種類の確定申告を行う必要があります。
・解散事業年度確定申告
解散する事業年度の始まりから解散日までの確定申告となり、解散日の翌日から2カ月以内に申告します。
・清算事業年度確定申告
事業年度をまたいで清算の手続きを行う際に必要となる確定申告です。事業年度が終了した2カ月以内に実施します。
・残余財産確定事業年度確定申告
残余財産額が確定した時に必要な確定申告です。金額が確定してから1カ月以内に行う必要があります。
8.清算決算報告書の承認・清算結了登記
清算確定申告が終わったら清算決算報告書を作成します。その後、株式総会で承認を受けることで会社消滅となります。
また、承認された日から2週間以内に清算結了登記を法務局にて実施してください。その際には、登記申請書や株式総会の議事録、委任状などを用意します。
廃業コストが足りない場合の資金調達方法

廃業するにも様々なコストが発生します。場合によっては費用を捻出できないケースもあるでしょう。
そのような時には、以下の資金調達方法の活用を検討してみてください。
金融機関による融資の活用
近年は、金融機関も廃業支援に力を入れています。融資やローン商品を用意しているため、コストが足りない場合には一度相談してみるのもおすすめです。
ただし、廃業となれば収入がなくなるため、通常の融資よりも条件が厳しいケースもあります。それを踏まえた上で活用を検討してみてください。
自主廃業支援保証制度の活用
自主的な廃業を選んだ中小企業に対して必要となる事業資金の調達を支援する制度が自主廃業支援保証制度です。
各都道府県の信用保証協会によって運営されており、県によって内容が異なるケースがあります。
例えば、茨城県であれば、保証限度額は3,000万円、保証期間は1年以内です。
事業所をおいている県において制度の活用を検討している場合には、要件や保証限度額、保証期間や必要な書類などをあらかじめ確認してから申請するようにしましょう。
小規模企業共済による廃業準備貸付け
中小機構が運営をしている小規模企業共済制度では会社の解散を円滑に行うためにも、必要な資金を低金利で貸付ける廃業準備貸付けを提供しています。
借入れた資金は、設備の処分費用や事業債務の清算など、廃業の準備にかかる資金に充てられます。
一般貸付けの資格を所有している共済契約者で、廃業計画を立てており、中小機構から承認を受けていることが借入の要件です。
申込みは、廃業予定の1年前から可能となっており、掛け金の範囲内で50万円以上1,000万円の借入ができます。利率は年0.9%となっており、借入期間は12カ月です。
まとめ・廃業時に必要なコストや流れを知り、円滑に準備を進めよう
廃業するとなれば、様々なコストがかかります。必要な手続きも複数あるため、手間がかかり負担に感じてしまうケースもあるでしょう。
しかし、必要なコストや流れを事前に把握しておくことで、スムーズに手続きができるようになります。今回解説した内容を参考に、準備を進めてみてください。
そして、必要であれば税理士や弁護士などの専門家に依頼をすることで、手続きを代行してくれます。
複雑な部分も多いため、不明な点が多ければ早い段階で相談することをおすすめします。