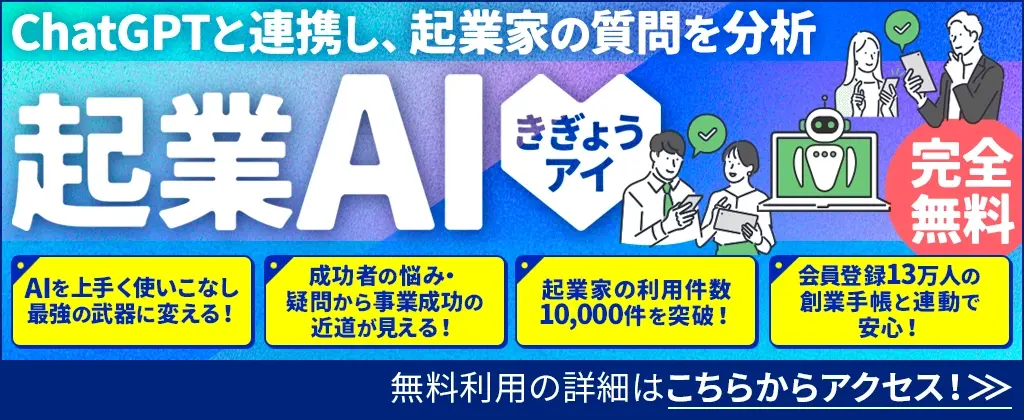事業主が取るべきカスハラ対策とは?企業の対策方法や取り組み事例も紹介
2025年4月より東京都で「カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行

カスハラ(カスタマー・ハラスメント)が社会問題になっています。従業員がカスハラ被害を受けると心身共に消耗してしまい、休職や離職につながりかねません。
従業員を守るためにも、事業主がカスハラ対策に取り組むことは有意義です。自治体や大手企業においても、カスハラ対策を進めているため、参考にするとよいでしょう。
今回は、カスハラの定義や事業主がカスハラ対策を行う意義、メリットなどを解説します。カスハラに対しては毅然と対応し、従業員を守りましょう。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
カスハラとは

厚生労働省によると、カスハラとは「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」を指します。
企業は労働契約上、安全配慮義務を負っています。従業員が安心して働ける環境を整備する責任があるため、カスハラに対して毅然と対応する体制作りは欠かせません。
まずは、カスハラが社会的に問題視され始めた背景から確認しましょう。
なぜカスハラが問題視され始めたのか
サービス業やコールセンター、役所などの顧客と直接接する現場で、顧客から無理な要求や暴言が浴びせられる事案が問題視されています。従業員がカスハラの被害に遭ってしまうと、当該従業員が心身共に消耗してしまいます。
従業員が精神疾患を発症してしまい、休職や離職につながってしまうと、生活に悪影響が出てしまうでしょう。事業主としても、カスハラにより優秀な従業員を失ってしまうのは大きな損失です。
実際に、厚生労働省の令和5年度「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害に関する事案の労災補償状況は以下のとおりでした。
- 請求件数は3,575件で前年度比892件の増加
- 支給決定件数は883件で前年度比173件の増加
精神障害に関する労災請求、支給決定件数ともに増加傾向です。執拗なカスハラは精神障害の発症にもつながるため、事業主は従業員を守るべく、カスハラ対策を行う必要があります。
安心して働ける環境を整備し、従業員のエンゲージメントや定着率を高めるためにも、カスハラ対策をする意義は大きいはずです。
カスハラとクレームの違い
カスハラと混同しやすい行為にクレームもあります。正当なクレームは、顧客が商品やサービスに対して品質の改善を目的として主張する行為をいいます。
これは、より良い商品やサービス向上のために改善を求めるものです。
一方で、カスハラは顧客である立場を利用した迷惑行為を示します。不当な言いがかりや過剰な要求をすることで自己の欲求を満たそうとするものです。
カスハラと正当なクレームは別物ではありますが、明確に線引きがあるわけではありません。そのため、現場の感覚とのギャップが生まれ混乱も発生します。
カスハラと呼ばれる顧客にもその人なりの正義感があり、指摘することで相手のためになると考えて一線を越えてしまう傾向があります。
お互いの立場を理解しながら対応を行わなければいけません。
カスハラが増えた要因

近年になってカスハラが増えた背景には、複数の要因があるはずです。それぞれを詳しく解説します。
SNSの普及
カスハラが増えた背景として、SNSやスマートフォンのような情報通信機器、ツールの普及が考えられます。
これらの普及によって簡単に写真や動画、自分の意見を世界に向けて発信できるようになりました。苦情を通報するにも企業に伝えるよりもSNSで投稿するほうが簡単です。
コミュニケーションコストが低い方法が普及したことで、顧客が企業や従業員に対して不満を持った時に写真や動画をSNSに投稿して従業員の名誉を傷つける、過剰に被害を訴えるといった事態が発生しています。
こうした投稿は、企業イメージを著しく損ねる可能性があります。
経済格差問題や孤立によるストレス
社会的動向の変化もカスハラが増えた要因です。社会全体の孤独、孤立化が進むことにカスハラ増加のつながっていると考えられます。
支援や監視の目が行き届かない孤立状態の人は、よりカスハラや犯罪に手を出す傾向があるといわれています。
都市化で住民のつながりが希薄になった上コロナ禍で孤立化が進み、他社との活発な交流が減少していることは社会の大きな課題です。
今の日本社会は経済格差の広がりなど不満や憤りを抱く人は増加しています。不満を持ちながら孤独な人がストレスを溜めてカスハラに至ってしまうことが推定されます。
カスハラの判断基準と具体例

顧客から威圧的な言動を受けたとしても、すべてがカスハラに該当するとは限りません。自社にも落ち度がある場合や、またはよく話を聞いてみると生産性のある指摘だった、という可能性があるためです。
厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考に、カスハラの判断基準や具体例を見ていきましょう。
顧客等の要求内容に妥当性はあるか
顧客等の要求内容が妥当性を欠き、自社に落ち度がない場合は、カスハラに該当します。
例えば、提供している商品やサービスに瑕疵や過失がないにも関わらず、全く欠陥がない商品を新しい商品に交換するよう要求するケースです。
また、要求の内容が自社の商品やサービスの瑕疵とは関係がない場合も、カスハラに該当します。販売した商品とは全く関係のない私物の故障について、賠償を要求する行為が代表例です。
要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当か
要求を実現するための手段・態様が違法だったり、社会通念上不相当だったりする場合は、カスハラに該当します。具体的な行為は、以下のとおりです。
| ①身体的な攻撃 | ・就業者に物を投げつける、唾を吐くなどの行為を行うこと ・就業者を殴打する、足蹴りを行うなどの行為を行うこと |
| ②精神的な攻撃 | ・就業者や就業者の親族に危害を加えるような言動を行うこと ・就業者を大声で執拗に責め立て、金銭等を要求するなどの行為を行うこと ・就業者の人格を否定するような言動を行うこと ・多数の人がいる前で就業者の名誉を傷つける言動を行うこと |
| ③威圧的な言動 | ・就業者に声を荒らげる、睨む、話しながら物を叩くなどの言動を行うこと ・就業者の話を遮るなど高圧的に自らの要求を主張すること ・就業者の話の揚げ足を取って責め立てること |
| ④土下座の要求 | ・就業者に謝罪の手段として土下座をするよう強要すること |
| ⑤執拗な(継続的な)言動 | ・就業者に対して必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返すこと ・就業者に対して何度も電話をして自らの要求を繰り返すこと |
| ⑥拘束する行動 | ・長時間の居座りや電話等で就業者を拘束すること ・就業者から店舗等から退去するように言われたにもかかわらず、正当な理由なく長時間にわたって居座り続けること ・就業者を個室等で拘束し、長時間にわたって執拗に自らの要求を繰り返すこと |
| ⑦差別的な言動 | ・就業者の人種、職業、性的指向等に関する侮辱的な言動を行うこと |
| ⑧性的な言動 | ・就業者へわいせつな言動や行為を行うこと ・就業者へのつきまとい行為を行うこと |
| ⑨個人への攻撃や嫌がらせ | ・就業者の服装や容姿等に関する中傷を行うこと ・就業者を名指しした中傷をSNS等において行うこと ・就業者の顔や名札等を撮影した画像を本人の許諾なくSNS等で公開すること |
上表に該当する行為は、場合によっては暴行罪や傷害罪、脅迫罪などの犯罪行為に該当します。必要に応じて、警察への通報も検討すべきでしょう。
「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の内容

東京都では、独自の取り組みとして「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を定めました。2025年4月1日より施行されます。
東京都がカスハラ対策を条例で定めた目的は、「働く全ての人が持てる力を十分に発揮することにより、事業者が安定した事業活動を行い、誰もが等しく豊かな消費生活を営むことができる環境を創出」するためです。
条例内において、「顧客等からの著しい迷惑行為であるカスタマー・ハラスメントは、働く人を傷つけるのみならず、商品又はサービスの提供を受ける環境や事業の継続に悪影響を及ぼすものとして、個々の事業者にとどまらず、社会全体で対応しなければならない」とあります。
条例違反による罰則は設けられていません。しかし、「暴行、脅迫その他の違法な行為または正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為」は「著しい迷惑行為」として禁止されます。
また、条例においては事業主に対して、以下の努力義務が課せられています。
- 事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない
- 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
提供する商品やサービスによって必要な措置の内容は異なるため、自社の実情に合わせてカスハラ対策を進めましょう。
事業主がカスハラ対策を実施する意義とメリット

厚生労働省の「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」では、過去3年間に各ハラスメントの相談があったと回答した企業の割合をみると、高い順にパワハラ(64.2%)、セクハラ(39.5%)、顧客等からの著しい迷惑行為(27.9%)となっています。
4社に1社以上の割合でカスハラ被害を受けているため、決して他人事ではありません。以下で、事業主がカスハラ対策を実施する意義やメリットなどを解説します。
従業員の心身の健康を確保する
トップの責任者である事業主がカスハラ対策をすることにより、従業員の心身の健康を守れます。
厚生労働省の「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、カスハラを受けた際の心身への影響として「怒りや不満、不安などを感じた」の割合が63.8%と最も高く、次いで「仕事に対する意欲が減退した」の割合が46.1%でした。
カスハラ被害を受けると、何らかの形で精神的な負担となっていることがわかります。ストレスが蓄積されると健康被害が出てしまい、従業員にとっても事業主にとっても不幸な事態になりかねません。
カスハラ対策を整備して、毅然と対応する環境を作れば、生産性のないカスハラ対応によって生じるストレスを軽減できるでしょう。従業員が「自分の健康や安全が守られている」と感じれば、エンゲージメントやモチベーションも向上します。
業務生産性の維持
事業主がカスハラ対策を行い、従業員の健康維持を図ることは、生産性の向上にも寄与します。
「カスハラを受けたらどうしよう」という不安やストレスを抱えた状態では、業務に集中できず、判断力や作業効率が低下してしまいます。しかし、対策を講じて従業員を保護することで、従業員は日々の業務に集中できるようになるでしょう。
また、カスハラが発生すると、従業員は生産性のない対応に多くの時間や労力を割かざるを得なくなります。従業員が生産性の高い業務に集中し、高いパフォーマンスを発揮できるようにサポートすることで、企業全体の生産性が向上するはずです。
企業イメージの向上
東京都でもカスハラを禁止しているように、社会全体でカスハラを防ぐ重要性は高まっています。カスハラ対策を推進すると「従業員を大切にする企業」「従業員の安全と健康を最優先に考えている」として印象をアピールでき、企業イメージが向上するでしょう。
さらに、カスハラ対策を行っている旨を大々的に伝えることで、顧客側への抑止力となる可能性があります。
人材流出の抑止と人材定着の促進
企業にとって、従業員は業務の運営を支えてくれる財産ですから、顧客よりも大切な存在といえます。従業員を守ることを第一に考えて安心して働ける環境を整備すれば、従業員の離職を防ぎ、人材定着を図れるでしょう。
カスハラ対策を行えば、従業員が長期にわたって企業に貢献し続ける基盤ができます。既存の従業員の定着だけでなく、新しく雇用する際にも優秀な人材を惹きつける効果が期待でき、人材採用の面でも有利になるでしょう。
企業が取り組む具体的なカスハラ対策

事業主からすると、カスハラをする人物はもはや「カスタマー(顧客)」とはいえません。まともに取り合う価値がない相手からの被害を防ぐためにも、以下のような対策を進めましょう。
| 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発 | ・組織のトップが、カスタマーハラスメント対策への取組の基本方針・基本姿勢を明確に示す ・カスタマーハラスメントから、組織として従業員を守るという基本方針・基本姿勢、従業員の対応の在り方を従業員に周知・啓発し、教育する |
| 従業員(被害者)のための相談対応体制の整備 | ・カスタマーハラスメントを受けた従業員が相談できるよう相談対応者を決めておく、または相談窓口を設置し、従業員に広く周知する ・相談対応者が相談の内容や状況に応じ適切に対応できるようにする |
| 対応方法、手順の策定 | カスタマーハラスメント行為への対応体制、方法等をあらかじめ決めておく |
| 社内対応ルールの従業員等への教育・研修 | 顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームへの社内における具体的な対応について、従業員を教育する |
| 事実関係の正確な確認と事案への対応 | ・カスタマーハラスメントに該当するか否かを判断するため、顧客、従業員等からの情報を基に、その行為が事実であるかを確かな証拠・証言に基づいて確認する ・確認した事実に基づき、商品に瑕疵がある、またはサービスに過失がある場合は謝罪し、商品の交換・返金に応じる。瑕疵や過失がない場合は要求等に応じない |
| 従業員への配慮の措置 | ・被害を受けた従業員に対する配慮の措置を適正に行う ・繰り返される不相当な行為には一人で対応させず、複数名で、あるいは組織的に対応する ・メンタルヘルス不調への対応 |
| 再発防止のための取組 | ・同様の問題が発生することを防ぐ(再発防止の措置)ため、定期的な取組の見直しや改善を行い、継続的に取組を行う |
| その他 | ・相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員に周知する ・相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、従業員に周知する |
カスハラに対する明確な対応策や従業員を守る仕組みを整備すれば、現場レベルでも毅然と対応できます。
また、過去に発生した事案を記録しておけば、対応案やノウハウを蓄積させてブラッシュアップにつなげられるでしょう。
カスハラが起きた際の対処法

カスハラが発生すれば、ほかのお客様に迷惑をかけたり、業務に支障が出たりする可能性があります。どのように対処するかを知っておくことでより早く穏便に解決に導けます。
カスハラが起きた際の対処法をまとめました。
状況を正確に把握し、正しく共有できるようにする
カスハラの対応で大切なのは、正確に状況を把握することです。まずは相手の話をきちんと聞いて状況を確認します。
相手の話をよく聞いて不満な点について謝罪するだけで相手が納得するケースもあります。
状況を把握するには、いつ、どこで、誰が誰に対して、どういった言動があったのかを具体的に確認してください。
複数人で対応する
カスハラの対応は、必ずひとりではなく複数人で対応してください。従業員の中には自分が担当だからと抱え込んでしまうケースもあります。
不快な思いをした、恫喝されたといったネガティブな様子は必ず上司に報告します。報告を受けた側は問題を先送りせずに必要な対策を講じなければいけません。
安易な謝罪や要求を認めないようにする
間違ったカスハラ対応のひとつが、安易に謝罪することです。過剰な要求や理不尽な主張まで認めてしまえばさらなる要求がされるかもしれません。
状況によっては、安易にに謝罪することで刺激して事態を悪化させてしまいます。
非がある部分において謝罪や説明は必要ですが、相手の勢いに負けて謝罪や要求を呑んでしまうのは避けてください。
現場で対応できるか判断する
カスハラ対応では、相手の感情を鎮静化させてすぐに解決させようと思うかもしれません。しかし、実際には現場で対応できないケースもあります。
現場での対応可否を判断して、法的な対応や企業の方針を超えるような要求がある時には警察や弁護士の介入も検討します。
状況によって本社に対応を委ねる判断も下さなければいけません。
企業におけるカスハラ対策事例

実際に、カスハラ対策を行っている企業の事例を紹介します。
ヤマト運輸株式会社
ヤマト運輸では、コールセンターの従業員が受ける理不尽な暴言や脅迫への対策として、2020年10月に「カスタマーハラスメント対応マニュアル」を作成しました。
マニュアルには「カスハラ発言リスト」が含まれ、「死ね」「殺すぞ」などの即時対応が必要な発言と、「あほ」など繰り返されるとカスハラと判断される発言を区別し、その後の対応方法を明確に定めました。
カスハラ発言があった場合、一次対応者から管理者へ電話を交代する仕組みを確立しています。また「文言集」を用意して対応に悩む社員をサポートする仕組みを整備したり、さらに相談窓口を設けたりして、会社を挙げてカスハラ対策を行っています。
フリー株式会社
フリー株式会社では、2022年夏にサポートデスクで発生した脅迫的なクレームをきっかけに、カスタマーハラスメント対策プロジェクトを立ち上げました。プロジェクトチームが社内アンケート調査と厚生労働省のマニュアルを参考にしながら、明確な指針となる「カスタマーハラスメントに対するfreeeの考え方」を作成しました。
具体的な取り組みとして、カスハラ専門チームの設置や専門窓口の設置と連携フローの周知、被害者ケア体制の構築などを行っています。
一連の対策をした結果、社内では「自分自身がハラスメントを受けるか受けないかに関わらず、安心感につながる」という声が上がっているようです。
株式会社イトーヨーカ堂
イトーヨーカ堂では、悪質クレームの増加と労働組合からの要請を受け、従業員が販売業務に専念できる環境づくりを目指してカスハラ対策に取り組んでいます。
全店舗に厚生労働省のカスハラ対策マニュアルを配布し、社会通念上不相応な要求が2回以上あった場合の判断基準や、対応方法を明確化しました。事件性があるカスハラに関しては総務部渉外も加わり、必要に応じて警察と連携する体制を構築することで、従業員の安心につながっています。
一連の取り組みにより、悪質クレームへの判断がスムーズになり、従業員は「会社の方針」として毅然とした対応ができるようになったようです。
まとめ
カスハラにより従業員が健康被害を受けてしまう事態を防ぐためにも、事業主がカスハラ対策を行うことは有意義です。自社の実情に合わせて対策マニュアルやガイドラインを策定し、「毅然と対応すること」「従業員を守ること」を明らかにしましょう。
カスハラが原因で、貴重な労働力である従業員を休職や離職で失ってしまうのは、企業にとっても損失です。安心して働ける職場環境を整備するためにも、事業主がトップとなってカスハラ対策を進めましょう。
創業手帳では、経営の悩みを素早く解決できる「起業AI」を無料で提供しています。ChatGPTと連携し、経営や法務に関する悩みに関する相談や壁打ちができます。
先駆者である創業者や企業から実際に抱えていた悩みがデータベースとなっているため、さまざまな問題解決につながるでしょう。ぜひ、有効活用してみてください。
(編集:創業手帳編集部)