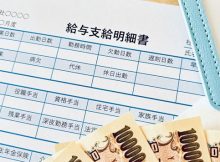【2025年度】中小企業の初任給の平均は?金額を決める際のポイントも解説
就活生が企業選びで重要視する項目は何?

労働力不足が懸念される中、どの企業も就活生の獲得を目指して様々な工夫を凝らしています。
就活生に魅力的な企業と思ってもらうためには、就活生が何を重視して企業を選んでいるかを把握することが重要です。
特に、初任給は就活生が重視する要素であるため、就活生が納得できる金額に見直すのも戦略のひとつといえます。
今回は、中小企業の初任給の平均や金額を決める際のポイントや、初任給以外で重要な要素を紹介します。就活生の採用を成功させたい人は、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、採用でお悩みの方へ「雇用で差がつく助成金10選」を無料で配布しています。採用に関する資金に不安があったり、まずは何から手をつけるべきなのか分からない方におすすめのガイドブックです。課題✕効果が分かるので、目的別に狙うべき助成金が分かります。この機会ぜひご活用ください。
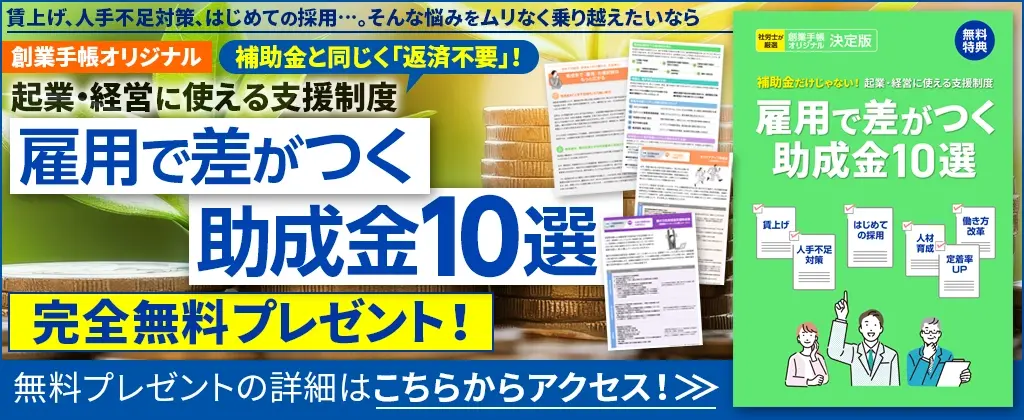
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
中小企業の初任給の平均

就活生の初任給を決める前に、中小企業の平均がどのくらいなのか参考として把握しておくことが大切です。
ここからは、2025年度の初任給の平均や引き上げた企業の割合・平均金額などについて解説します。
2025年度の初任給の平均
東京労働局のデータを参考にすると、学歴別の2024年度と2023年度の初任給の平均金額は以下のとおりです。
| 学歴 | 2024年度の初任給 | 2023年度の初任給 |
| 大学卒 | 21万6,600円 | 21万2,500円 |
| 短大卒 | 20万2,400円 | 20万円 |
| 専修卒 | 20万1,000円 | 20万円 |
| 高卒 | 18万9,200円 | 18万3,300円 |
初任給は学歴や企業規模、産業・職種などの条件によって変動しますが、上記のデータを参考にすると18~22万円前後が平均といえます。
2024年度と2023年度を比較すると、初任給は全体的に増加傾向にあります。
前年度よりも初任給の金額が増えている理由は、各企業で賃上げの動きが見られているためです。
初任給を引き上げた企業の割合
帝国データバンクの調査によると、初任給の引き上げを行った企業の割合は以下のとおりです。
| 引き上げた | 71.0% |
|---|---|
| 引き上げない | 29.0% |
初任給の引き上げについて回答した490社のうち、引き上げを行った企業の割合は71.0%と、多くの企業が引き上げています。
また、初任給引き上げを行った企業のうち、規模別の割合は以下のとおりです。
| 大企業 | 69.6% |
|---|---|
| 中小企業 | 71.4% |
| 小規模企業 | 62.2% |
規模別で見ると、中小企業(69.6%)が大企業(69.6%)を上回る結果となりました。
このことから、中小企業でも初任給引き上げの動きが強まっていることがわかります。
初任給の平均引き上げ額
同データによると、2025年度の初任給引き上げ額の平均は9,114円となっています。
引き上げ額別の割合は以下のとおりです。
| 5,000円未満 | 18.1% |
| 5,000~1万円未満 | 30.7% |
| 1~2万円未満 | 41.3% |
| 2~3万円未満 | 7.5% |
| 3万円未満 | 2.4% |
最も多く占めているのが1~2万円未満(41.3%)で、次いで5,000~1万円未満(30.7%)でした。
割合は少ないものの、2~3万円未満や3万円未満で初任給を引き上げている企業も一定の割合で存在します。
就活生が持つ給与のイメージ
全国の就活生(大学生・大学院生)に対して実施した調査によると、就活生の多くが「就職先の給与のみで最低限の生活ができる(49.4%)」と回答しています。
また、その次に多いのは「就職先の給与にのみで満足する生活が続けられそう(36.7%)」という回答でした。
多くの就活生は、生活に十分な給与をもらえるというイメージを持っています。
ただし、給与額は最低限の生活ができる金額であり、趣味を楽しんだり嗜好品を購入したりするなど、余裕ある生活をするための給与をもらえないと認識しているようです。
企業側は就活生のこのようなイメージを持っていることを理解した上で、就活生が納得できる初任給や給与の設定しなければなりません。
就活生が企業選びで意識すること

就活生の獲得に向けた戦略を立てるためには、就活生が企業選びで何を意識しているのか把握することが求められます。
ここからは、就活生が求める企業選びに求める要素とその理由をはじめ、就活生が避ける傾向にある企業の特徴を紹介します。
給料・安定性を求める就活生は多い
就活生の多くは、給料の良さや安定性を重視している傾向にあるようです。
就活生を対象にした実態調査によると、企業選びで重視している項目ベスト3は以下のようになっています。
-
- 1位:安定している(48.8%)
- 2位:やりたい仕事ができる(30.5%)
- 3位:給料がいい(21.4%)
このうち、「安定している」という回答は5年連続で最多の回答です。
また、「安定している」の回答率は3年連続、「給与がいい」の回答率は2年連続で増加しています。
この結果から、安定志向や待遇の高さに関心を持つ就活生が多いことがわかります。
就活生が「安定性」を求める理由
就活生が安定性を重視して企業を選ぶ理由は、生活基盤に不安を抱えているためです。
待遇や福利厚生を重視する就活生は、企業選びにおいて以下のような意見や考え方を持っています。
-
- 少しでも安定して生活できるだけの給与が欲しい
- 結婚や出産後も働き続けられる職場を選びたい
- 福利厚生が充実している企業は資格取得支援やクラスなどが充実している
近年は物価が上昇しており、金銭的な不安を抱えている人は少なくありません。安定した生活が送れる企業に入りたいと考える就活生が多いです。
また、長期的に働くことや将来のライフイベントなどにも考慮して、経済的な安定感やサポートが充実した環境が整った企業に魅力を感じています。
就活生が行きたくないと思う企業
就活生が特に行きたくないと思う企業は、「ノルマがきつそうな企業」です。同データによると、就活生が行きたくない企業のベスト3は以下のようになっています。
-
- 1位:ノルマがきつそうな企業(38.8%)
- 2位:転勤が多い会社(29.6%)
- 3位:雰囲気が暗い会社(24.1%)
企業によってはノルマを設けているケースがありますが、それに対してプレッシャーを感じる就活生は少なくありません。
将来は「楽しく働きたい」と考える学生が増えています。厳しいノルマが設定された仕事は避けたいと考えられています。
なお、転勤が多い会社や雰囲気が暗い会社も注意が必要です。安定志向の就活生が増えている中、転勤は安定とはかけ離れたものとなると考える人が多くいます。
また、雰囲気が悪い職場も避けられる傾向です。
企業が初任給を決めるポイント

給与は就活生が気にしている要素であり、初任給の設定を慎重に行うことが求められます。
ここからは、企業が初任給を決める際に押さえておきたいポイントを紹介します。
世間水準と比較して決める
初任給は、世間との水準を比較して妥当な金額を決めるのがおすすめです。競合よりも高い初任給は、優秀な人材を確保する上で有利に働く可能性があります。
また、他社の基準と比べて公平かどうかを気にする人も多いです。世間の水準をもとに金額を決めることで外部公平性が保たれ、社員のモチベーションの維持につながります。
世間の水準は、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」や都道府県労働局が作成する統計データなどを参考にするのがおすすめです。
統計データには、地域や事業規模、職業・産業など区分されて賃金情報が掲載されています。事業所のある地域や規模など自社に近い条件の水準を参考にしてみてください。
既存社員との調整が必要
初任給の調整に合わせて、既存社員の給与の調整も必要です。初任給を調整して既存社員の給与と不公平が生じれば、社内に不満を招いてしまいます。
初任給が既存社員の給与とほとんど変わらなかったり上回ったりすれば、既存社員のモチベーションは低下します。
企業に対する愛着がなくなり、離職につながる可能性が高いです。
このようなトラブルを避けるために、初任給を調整する時は既存社員の賃金テーブルの見直しが求められます。
ただし、無理な賃上げを行えば、経費が増えます。既存社員の賃金テーブルを見直す時は、長期的な視点を持つことが大切です。
賞与・手当も考慮する
賞与や手当も考慮して初任給を設定してください。残業代は固定支給と別途支給に分かれ、どちらを採用するのかによって初任給の見栄えが変わってきます。
仮に月給を25万円とすれば、この金額に残業代がプラスされます。
一方、固定支給であれば、一定の残業時間分の残業代+基本給で月収25万円という形になるため、残業代の別途支給よりも基本給が低くなるケースが多いです。
また、賞与の回数や支給額、地域手当や資格手当などの各種手当の有無によって手取り金額は変わってきます。
基本給以外の部分によって給与が高く見え、実際の基本給はそれほど高くないというケースは少なくありません。
競合他社の給与の内訳をチェックして基本給を把握し、賞与や手当を含めた時のイメージを持って初任給を決めてください。
新入社員への説明も実施する
初任給が決まった後は、新入社員への説明を実施することをおすすめします。
説明の際に初任給の根拠を提示すれば、新入社員の企業に対する信頼や帰属意識を高めることが可能です。
給与の基準や評価基準が不透明であれば、目標を持って仕事に取り組めない社員が増えるかもしれません。
入社した時点で給与や評価基準について明確に提示することは、社員のモチベーションを高めることにつながります。
定期的に見直しをする
初任給は定期的な見直しが大切です。賃金は上昇傾向にあり、今後も賃金相場は上がると考えられます。
賃金見直しを放置すれば、将来的に世間水準以下となり、後から調整が厳しくなる可能性があります。
そのため、統計データを毎年確認して、市場の動向や企業の成長に合わせた給与の見直しが大切です。
初任給以外に就活をする上で重要な要素

就活生の多くは初任給に注目していますが、チェックしている部分はそれだけではありません。
ここからは、初任給以外に就活生が重視している要素を紹介します。
成長できるキャリアアップ制度の充実
就活生が注目する要素のひとつが、キャリアアップ制度です。
ただ仕事をこなすのみではなく、スキルを磨いて理想のキャリアを目指す人は少なくありません。
そのため、資格取得や最新技術の習得など、社内で成長できる環境があるかどうかに注目しています。
成長できる環境が整っていないと、社員が今の企業では成長が望めないと感じれば転職をしてしまう可能性が高まります。
優秀な人材の流出を抑えるためにも、キャリアアップ制度の構築や充実化は重要です。
柔軟な労働環境の提供
柔軟な労働環境を求める就活生も多くいます。柔軟な労働環境というのは、以下の内容が該当します。
-
- テレワーク
- 時短勤務
- フレックスタイム
- 副業・兼業
- 育児・介護休暇
テレワークであれば、従業員は自宅やレンタルオフィスなどあらゆる場所から業務を行えます。
通勤のストレスが緩和されたり、家庭と仕事を両立しやすかったりするなど、様々なメリットがある働き方です。
また、短時間で働く時短勤務や勤務時間を自由に設定できるフレックスタイムを導入すれば、従業員は離職を選ぶことなく、家庭の事情に合わせて柔軟に働けます。
ほかにも、副業・兼業の対応や育児・介護休暇制度を充実化させることも、就活生にとって魅力や安心感を与える要素となります。
充実した福利厚生の提供
福利厚生も重視されやすい要素です。福利厚生には手当や祝金、保養施設の利用、ヘルスケアのサポートなど様々なものがあります。
福利厚生が充実していると安心感や働きやすさにつながり、社員のモチベーション低下を防ぐことが可能です。
そのため、福利厚生が充実している企業も就活生から選ばれやすくなっています。
ただし、福利厚生を充実させれば良いわけではなく、社員の声を聞いて本当に必要な制度・サービスを導入することがポイントです。
初任給と基本給・手取りの違い

初任給や基本給、手取りについて詳しく知りたいと思っている就活生は多く、面接時に質問される可能性があります。
そのため、初任給と基本給、手取りのそれぞれの意味を理解しておかなければなりません。
ここからは、初任給と基本給・手取りのそれぞれの違いについて紹介します。
初任給と基本給の違い
基本給とは、雇用されている間、毎月支払われる一定金額の融資のことです。基本給には、各種手当やインセンティブは含まれません。
一方の初任給は、基本給に各種手当やインセンティブを含めて、社員に初めて支給する給与のことです。
つまり、2回目以降の給与を初任給と呼ぶことはありません。
賞与は基本給をベースに掲載することが多いので、試算する時は初任給と混同しないように注意してください。
初任給と手取りの違い
手取りとは、従業員が実際に受け取る給与のことです。
給与は所得税・住民税、社会保険料などが毎月天引きされた状態で支給されるため、給与額を満額手取りとして受け取れるわけではありません。
なお、初任給は、税金や社会保険料などが天引きされていない金額です。
一般的には、2回目の給与から厚生年金や健康保険料が天引きされ、住民税は2年目から天引きされます。
初任給よりも手取りが少なくなってしまうケースは多くあり、期待と現実のギャップを埋めるための工夫が必要です。
まとめ・就活生から選ばれる企業を目指そう
安定志向や待遇の良さを求める就活生が増えていることから、初任給は企業選びにおいて注目される要素となっています。
近年は人材獲得競争が激化しており、世間水準に基づいて初任給を見直して就活生からの関心を集めることも必要です。
キャリアアップ制度の整備や福利厚生の充実化など、従業員が働きやすい環境に整える努力もして、就活生から選ばれる企業を目指してください。
創業手帳(冊子版)では、給与や採用など経営に欠かせない基本知識やノウハウを紹介しています。起業・開業に必要な情報を知りたい人は、ぜひお役立てください。
創業手帳では、採用や人材定着を目指す方へ「雇用で差がつく助成金10選」を無料配布しています。採用、助成金の初心者の方でも、支給額・助成率、スケジュールなどをわかりやすく解説しています。ぜひお気軽にご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。