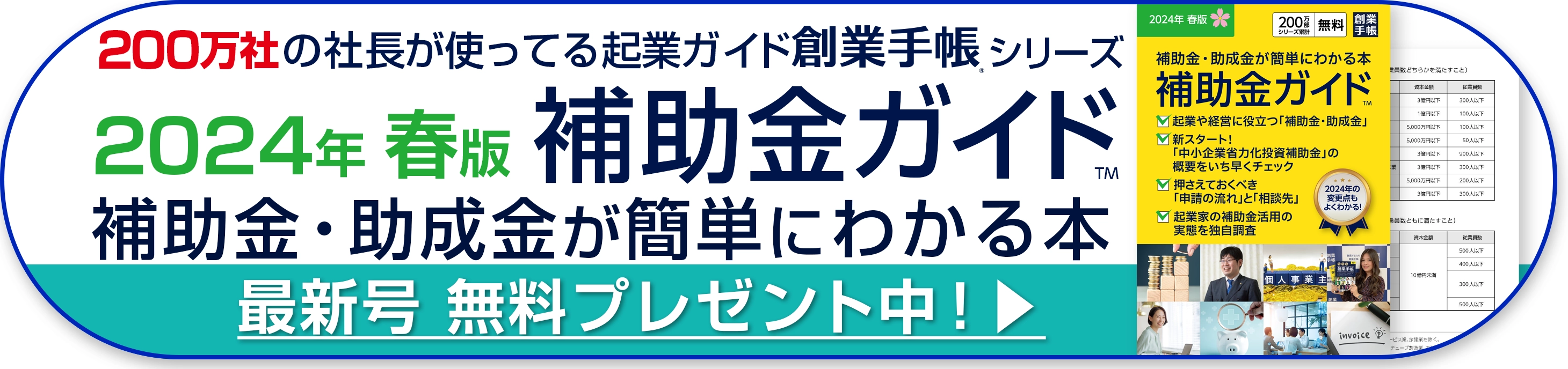地方移住で補助金を活用!注目の制度や申請時の注意点を解説
地方移住の金銭的な不安は補助金制度で解決

地方へ移住し、新たなビジネスの立ち上げや起業したいと考える人もいるかもしれません。
しかし、地方へ移住するには費用がかかるるため、資金面に不安を感じる人もいるはずです。
そのような人におすすめしたいのが、地方移住で活用できる補助金制度です。今回は、地方移住に使える補助金制度について解説します。
補助金を申請する際に気を付けたいポイントも解説しているため、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、経営者の方々よく利用される補助金を厳選して解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。こちらもあわせてお読みください。

この記事の目次
地方移住に使える補助金は3種類

地方移住に使える補助金制度には、主に3つのタイプがあります。それぞれの特徴について解説します。
ビジネスに関する補助金制度
ビジネスに関する補助金制度は、地域が抱える課題の解決や地域活性化などを目的に提供される制度です。
ビジネスに関する補助金制度には条件が細かく設定されている場合が多くあります。
しかし、自治体が決めた条件をすべて満たすと、数百万円以上の補助金を受けられる場合もあります。
住まいに関する補助金制度
住まいに関する補助金制度は、地方で住宅を購入する際に、解体費用やリフォーム工事費用などを補助してくれる制度です。
若者や子育て世帯に向けて支給金額が増額されているケースや、空き家の利用によって特典が受けられるケースなどもあります。
また、固定資産税の減免制度などを受けられる場合もあり、都市部で住宅を購入するよりも金銭的な負担を抑えることが可能です。
子育てに関する補助金制度
地方移住の補助金制度の中には、子育てに関する補助金もあります。
例えば、出産や子育てにかかる費用の支援や子どもの医療費助成、学校給食費用の支援、習い事に関する支援など様々です。
それぞれの自治体によって実施している補助金制度は異なるため、事前にどのような制度を利用できるのか確認してみてください。
地方移住に使える補助金「移住支援金」

地方移住に使える補助金として、「移住支援金」が挙げられます。移住支援金の対象者や、移住先・就業先の条件も含めて解説します。
東京圏外への移住で支給される移住支援金とは
移住支援金とは、東京23区内に在住または通勤をしている人が、東京圏外(東京圏内の条件不利地域も含む)へ移住し、起業・就業などを行う人に対して都道府県と市区町村が共同で補助金を支給する制度です。
単身者には60万円以内、世帯の場合には100万円以内と、各都道府県が設定する金額が支給されます。
18歳未満の世帯員が帯同して移住する世帯であれば、18歳未満の子1人につき最大100万円が加算されます。
対象者
移住支援金を利用するためには、対象者の条件を満たす必要があります。
移住前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)から23区に通勤している人が条件です。
なお、東京圏(条件不利地域以外)に在住しており、東京23区内の大学に通っていて、東京23区内の企業に就職した人であれば、大学に通学していた期間も移住元の対象期間に加算できます。
つまり、移住前の10年間で4年間大学に通い、1年以上23区内の企業へ通勤していた人も移住支援金を受け取ることが可能です。
移住先・就業の条件
移住支援金には移住先と就業の条件も明記されています。
- 【移住先】
-
- 東京圏外または東京圏で条件不利地域に該当する市町村
- 【就業】
-
- 地域の中小企業や農林水産業などへの就業
- 地域課題解決を目的とした起業
- 移住前の業務をテレワークによって継続 など
移住支援金を受け取るためには、道府県が運営するマッチングサイトを使って現地で就職するか、移住前の仕事をテレワークで継続するかが要件でした。
しかし、マッチングサイトで紹介される就業先のほとんどは中小企業であり、思うように移住支援金を受け取ることができない人もいました。
2025年度からは農業や自営業、医療福祉の分野も追加されるようになり、より多くの人へ支援が行き渡るようになったのです。
地方での起業で支給される「起業支援金」は併用できる
移住支援金とは別に、地域の課題解決を目的とする社会的事業を起業した人に向けて、起業支援金が支給されています。起業支援金は、移住支援金と併用することが可能です。
起業などに向けた伴走支援と、事業費への助成として必要な経費の1/2に相当する額(最大200万円)が支給されます。
社会的事業とありますがその内容は幅広く、子育て支援につながるものから地域の特産品を活用した飲食店、買い物弱者への支援、まちづくりの推進なども含まれます。
対象者
起業支援金の対象は、新たに起業する人と事業承継または第二創業する人で条件が異なります。
- 【新たに起業する人】
-
- 東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域で、社会的事業の起業をする
- 国の交付が決まった日以降、補助事業期間が完了するまでに個人開業届または法人設立を行う
- 起業地の都道府県内に居住している、または居住する予定がある
- 【事業承継または第二創業する人】
-
- 東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域で、Society5.0関連業種など付加価値の高い分野で、社会的事業を事業承継・第二創業で行う
- 国の交付が決まった日以降、補助事業期間が完了するまでに事業承継または第二創業を行う
- 事業を行う都道府県に居住している、または居住する予定がある
【自治体別】地方移住の補助金

移住支援金・起業支援金以外にも、各地方自治体で移住に関する補助金制度を実施している場合もあります。
ここでは、自治体別に地方移住の補助金をいくつかピックアップして紹介します。
【北海道深川市】住宅持家促進助成・中古住宅等取得助成
北海道深川市では、地域の活性化に寄与する住宅・住環境づくりの促進を目的に、8つの助成制度を設けています。
住宅持家促進助成は、住宅を新築する人に対して、費用の一部を助成する制度です。
助成額は市外業者に依頼する場合30万円以内、市内業者に依頼する場合100万円以内(対象工事費の5/100が上限)になります。
移住世帯(1年以上市外に居住して市内に移住しようと考えている世帯、または転入後2年以内で以前市外に1年以上継続して住んでいた世帯)の場合、上記の助成額に10万円が加算されます。
また、住宅持家促進助成以外にも、移住世帯が利用できる制度が「中古住宅等取得助成」です。
中古住宅等取得助成は、中古住宅やその宅地を取得した人に費用の一部を助成します。助成額30万円以内で、移住世帯には10万円が加算されます。
【広島県呉市】呉市移住希望者住宅取得支援事業
広島県呉市では、UIJターン促進と中古住宅の流通促進を促すために、市外からの移住希望者が中古一戸建てを購入した場合の費用を一部補助する事業を行っています。
基本額として購入費の1/2(上限50万円)に、加算額最大50万円がプラスされ、最大100万円の助成を受けることが可能です。加算対象と加算額は以下のようになっています。
-
- 新婚世帯:30万円
- 子育て世帯:30万円
- 親世帯と近居:10万円
- 居住誘導区域内:10万円
- 島しょ部:10万円
なお、補助要件として呉市に5年以上定住することや、自治会に加入する必要もあるため、あらかじめ確認してください。
【長野県安曇野市】移住者支援補助
長野県安曇野市では、移住者が空き家バンクに掲載された物件を購入もしくは賃貸で3年以上住む場合、不動産事業者に支払う仲介手数料や引越し費用などを補助する制度を設けています。
補助率は補助対象経費(仲介手数料・引越し費用)の1/3で、上限額は最大10万円です。
移住者支援補助の申請を着手前に行わなければ補助金を受け取れないことに注意してください。
なお、移住者支援補助を利用するためには以下の要件をすべて満たさなくてはなりません。
-
- 個人である(法人ではない)
- 市税・国民健康保険税を滞納していない
- 安曇野市空き家バンクから物件を購入または賃貸している
- 移住者である
- 引越し後その物件に住民登録し、3年以上居住する
- 安曇野市空き家バンクから購入または賃貸した物件である
- 交付申請日時点で物件の売買契約または賃貸借契約の締結から1年以内である
- 物件の前所有者または貸主が、申請者の3親等以内にいない
- 戸建て物件である
- 過去に同じ補助金の交付を受けた物件ではない
- 補助対象経費が合計5万円以上
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告がある
- 補助対象経費について、他の補助金と併用していない
【和歌山県橋本市】転入夫婦新築住宅取得補助金
和歌山県橋本市では若年層夫婦の転入を支援するために、橋本市内で新築住宅を取得し、転入する夫婦に対して補助金制度を設けています。
2021年4月1日以降に市内で取得した新築住宅で、夫婦双方またはいずれかの名義で所有権を保存し、移転の登記が2021年4月1日から2026年3月31日までに完了していることが条件とです。
また、床面積50㎡以上の住宅用に供する建物であることも条件となります。
なお、対象者は市内に定住する意思がある夫婦で、申請日現在いずれかが満40歳未満でなければいけません。
補助金額は30万円ですが、地域通貨5万円分も含まれています。登記の日付は2026年3月31日までですが、申請受付期間は2027年3月31日までです。
【愛媛県上島町】上島町移住者住宅改修支援事業
愛媛県の上島町は、空き家バンクに登録された物件の購入または賃貸借契約を結び、県外から移住した人(子育て世帯・働き手世帯)を対象に、家屋の改修工事や荷物の搬出にかかる経費を一部助成しています。
対象は、2020年4月1日以後に移住した人で、空き家バンクに登録されていた物件に5年以上居住している人です。
補助金額は対象経費の2/3となりますが、働き手世帯と子育て世帯で補助金額が若干異なることに注意してください。
-
- 働き手世帯(世帯構成員のうち1人が18歳以上60歳未満):住宅改修100万円まで
- 子育て世帯(働き手世帯で18歳未満の子どもがいる世帯):住宅改修18歳未満1人につき100万円(最大400万円)
家財道具の搬出にかかる費用については、働き手世帯・子育て世帯ともに20万円までが上限です。
地方移住の補助金を申請する際の注意点
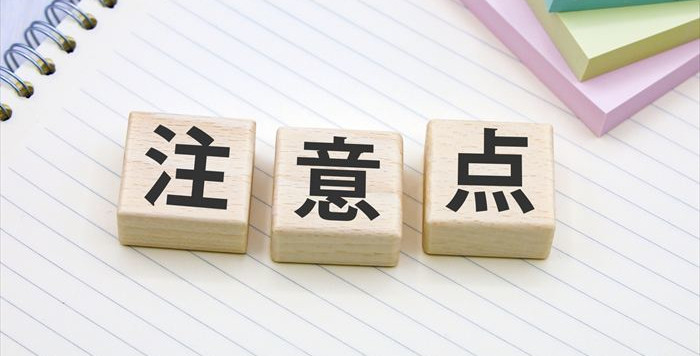
地方移住の補助金を申請する場合、いくつか注意しなくてはいけないポイントもあります。ここで、補助金を申請する際の注意点について解説します。
条件やスケジュールを確認する
移住支援金に加え、各地方自治体では様々な移住支援制度を用意している場合もあります。
しかし、それぞれの制度は条件が異なるため、条件を満たしているかどうかを事前に確認しておく必要があります。
また、申請のスケジュールやタイミングについても確認しておかなくてはなりません。
例えば、移住支援金の場合、移住支援金の申請は転入後1年以内であることや、申請してから5年以上継続してその市町村に居住する意思があることを条件としています。
申請のタイミングが決まっていたり、条件として数年間はその地域に居住する必要があったりするため、忘れずにチェックしておいてください。
補助金や支援制度の内容のみで移住先を決めない
いくら地方移住の支援制度が魅力的な内容でも、それだけで移住先を決めるのは避けたほうが良いです。
移住して実際に住んでみると、イメージと異なる可能性もあるためです。
支援制度はあくまで補助的な役割であり、移住先を決めるのであれば就業環境や子育て環境、生活環境などを重視する必要があります。
また、支援制度の中には決まった期間住み続けなければ、支給した金額を返還しなくてはならない制度もあるため、移住先は慎重に選ぶことが大切です。
まとめ・地方移住をするなら補助金も活用しよう
地方へ移住するためにはどうしても金銭的な不安はありますが、補助金をうまく活用することによって負担を軽減できます。
各地方自治体では移住支援金を含め、様々な補助金制度を実施しているため、自分に合った補助金がないか探してみてください。
創業手帳では、登録いただいた都道府県の補助金や助成金の情報について、月2回メールでお届けする「補助金AI」サービスを実施しています。見落としがちな自治体の支援策についても、これで定期的に把握しておくことができます。無料でお使いいただけるサービスなので、ぜひご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)