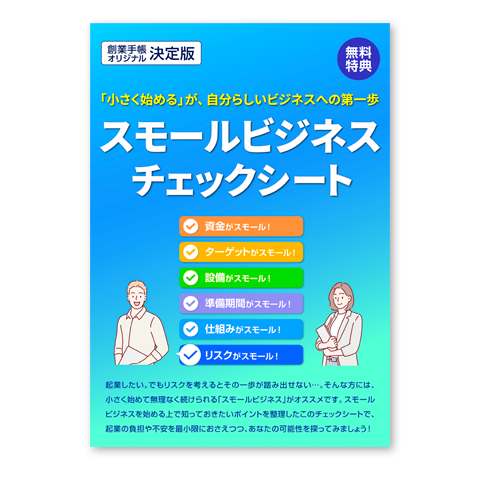農業のリスクとその回避策!成功するために知っておくべきポイント
農業経営で失敗しないためにリスクとその対策方法を知ろう

一次産業の中でも国民の「食」を支える農業は、需要も高いことから農業経営にチャレンジしようと考える人もいるかもしれません。
農業経営を始めるにあたって様々なリスクについて事前に把握し、万全な体制を講じることが重要となってきます。
そこで今回は、農業経営における様々なリスクとその対策方法について解説します。リスクに対してどのような対策を講じればいいのか知りたい人も、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、脱サラしてブルーベリー観光農園を開業し、年60日で年収2000万円稼ぐようになった「ブルーベリーファームおかざき」の代表畔柳さんと一緒に制作した「ブルーベリーガイド」を無料で配布しています。ブルーベリー観光農園ではなくとも、農業に関する様々な知識を伝授。ぜひお申し込みください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
農業経営でみられるリスク

まずは農業経営でみられるリスクを8つ紹介します。具体的にどのようなリスクが存在するのか、事前に把握しておきましょう。
初期コスト・運用コストがかかりやすい
最初に、初期コスト・運用コストがかかりやすい点です。
農業を始めるにあたって農作物の苗や農具を準備する必要がありますが、利益を出すためにはそれなりの規模で農作物をつくっていくことになります。
そうなると、安定した数をつくるために肥料や農薬が必要になり、機械の導入や人件費なども必要となってきます。
しかし、現在はロシアによるウクライナ侵攻の影響を受け、重油や灯油代、肥料の価格が高騰している状況です。
また、鉄の値段が上がってしまったことで、ビニールハウスなど設備の価格も上がっています。さらに最低賃金の上昇から人件費も高くなっているのです。
初期コストや運用コストが増加すると収益を出すのも難しくなり、経営リスクに陥ってしまいます。
技術不足で収穫量が増えない
これまで農業をやってこなかった人がいきなり農業経営にチャレンジすると、技術不足が原因で失敗するリスクが高まります。
野菜や果物、穀物などはそれぞれ特性が異なり、その農作物に適した栽培方法を行う必要があります。この特性を無視してしまうとうまく育てられず、収穫量も増えません。
また、農業経営を始める場合、農業に関する技術や知識だけでなく、農作物を販売するためのマーケティングに関する知識も身に付けておく必要があります。
自然災害や害虫被害などで収穫量が減少する場合がある
農業にとって気候の変動や自然災害、害虫被害は大きなリスクです。
例えば大切に育ててきた果物が、台風による強い風を受けて枝から落ちてしまい、商品として売れず経済的損失をもたらす可能性があります。
台風以外に洪水や干ばつ、大雨なども収穫量に影響してきます。大きな自然災害だけでなく、気温の急激な上昇なども収穫量や品質に影響してしまうかもしれません。
また、農業では害虫対策も必須です。農作物の種類によって発生する害虫も異なり、それぞれ対策が必要となります。
何かしらの対策を講じないと害虫は増える一方であり、場合によっては自分の農場だけでなく近隣の農場にまで影響を与えてしまう可能性があるため、注意が必要です。
農作物の市場価格が低下する場合がある
農業経営では、農作物がいくらでどれくらい売れるのかによって収益が変わってきます。
そのため、農作物の市場価格が低下してしまった場合、経営リスクに陥る可能性があります。
例えば市場の同じ野菜が多く出回れば、その分市場価格は低くなりやすいです。
また、天候の影響を受けていつもより多く出荷できる状態になっても、市場に出回る量が増えてその農作物の価格は下がってしまいます。
品質の良いものをたくさん収穫できたとしても、単純に売上げが増えるわけではないことを理解しておくことが大切です。
長時間・過重労働になりやすい
農業は育てる農作物によって異なるものの、基本的には長時間作業をしなくてはならないケースが多いです。
収穫時期は早朝から夜まで働くことも増え、過重労働になりやすい傾向にあります。
特に個人農家はひとりで作業する必要があるため、睡眠時間を削って作業したり体調が悪くても関係なかったりするなど、負担は大きいといえます。
また、農業は会社のように決められた時間に仕事をすることはなく、比較的自分のペースで働けるものの、農作物の状況を毎日確認しなくてはならないため、休みを取りにくいです。
収穫後にまとめて休みを取る人も多いですが、固定休みや世間が大型連休で休んでいる間も作業しなくてはならないのはデメリットです。
人手不足に陥りやすい
農業経営で利益を上げるためには規模を大きくする必要があり、それにともなって人手も必要となってきます。
しかし、農林水産省が発表した「令和5年新規就農者調査」 によると、新規就農者の数は43,460人で、前年より5.2%減少していることがわかっています。
新規就農者数の推移は年々減少しており、農業を希望する人が少なくなっているのです。
人手不足に陥ってしまうと、ひとりですべての作業を担うことになり負担も大きくなってしまいます。
さらに、農業従事者の高齢化や後継者不足なども問題となっています。
現在は農業経営ができていたとしても、将来的に人手不足にともなうリスクが発生するかもしれません。
季節によって収入が安定しない
農業は一般的な働き方と異なり、季節によって収入が安定しないというリスクもあります。
例えば米農家の場合、3月頃から苗を育て始めて4月~5月に田植えを行い、夏に水の管理や追肥を行って、9月~10月に稲刈りを行います。
稲刈り後は乾燥やもみすりなどの作業をして米を出荷していきますが、11月以降から翌3月の冬場は農閑期です。
育てている農作物によって収穫時期などは異なりますが、農繁期は多忙になり、睡眠時間を十分に確保できないほど忙しくなることも多いです。
逆に農繁期が終わると、時期が来るまで作業をする必要もなくなります。
収穫後に休みを取る人は多いものの、その期間中は売上げがなくなってしまうため、安定して収入を確保できないという問題も発生してしまいます。
地域コミュニティからのサポートが得られない
農業は地域に関係なく、個人で行うものとイメージする人もいますが、実際には地域社会と関わることの多い仕事です。
そのため、もし近隣の農家や住民とトラブルに発展してしまうと、地域のコミュニティから様々なサポートを得られなくなる可能性があります。
例えばトラクターの泥を落とさないまま公道を走行した結果、道に泥が落ちてしまい走行した車を汚してしまったり、ニオイの強い堆肥を使ったことで広範囲にニオイが広がってしまったりするなどのトラブルがあります。
農業経営リスクへの対策方法

上記で挙げた農業経営のリスクは、事前に対策を講じることで回避することも可能です。ここで、農業経営リスクへの対策方法を紹介します。
農業経営収入保険制度を活用する
農業経営収入保険制度とは、自然災害や市場価格の下落など、収入が大幅に減少してしまった際に農家の収入を守ってくれる制度です。
すべての農産物が対象に含まれ、一部の加工品も含まれています。
収入保険は過去5年間の収入の平均値から基準収入を設定し、この基準収入を下回ると保険が適用されるようになってます。
農業経営収入保険制度の対象者は、青色申告を行う個人・法人です。また、青色申告の実績を1年分あると申し込みできるようになります。
すべての農作物と一部の加工品が対象となることから、多くの農家が利用できる点はメリットです。
ただし、収入減の原因が生産コスト(燃料・資材など)の高騰による場合は対象外となります。
また、収入保険制度を申し込むと農作業日誌の記入・保存が必須となるため、作業負担が増える点にも注意が必要です。
農業共済制度を活用する
農業共済制度とは、農業保険法に基づき農業者の経営安定を図ることを目的に、収穫量減少などの損失を補てんするための共済制度です。
共済の種類は以下の6つに分類されます。
-
- 農作物共済(水稲、陸稲、麦)
- 家畜共済(牛、馬、豚)
- 果樹共済(リンゴ、ぶどう、指定かんきつなど)
- 畑作物共済(大豆、いんげん、玉ねぎなど)
- 園芸施設共済(園芸施設(附帯施設、施設内農作物を含む))
- 任意共済(建物、農機具、保管中農作物)
農業共済は加入者の負担を軽減するために、掛金の原則50%を国が負担しています。
加入するためには、農業共済組合が指定する面積以上の耕作地を持っていることが条件となります。
また、農業共済で補償されるのは自然災害時の収穫量減少のみです。適用範囲が収入保険と比べて狭くなってしまうので注意してください。
収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)を活用する
収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)とは、米や畑作物を対象に収入が大きく減少してしまった場合に利用できる保険のような制度です。
収入額の合計が標準的な収入額を下回ってしまった場合、差額の9割を補てんしてもらえます。
補てんの財源は農家が積み立てた金額と国から交付された金額が1対3の割合で負担され、残った金額は翌年度に繰り越されることから、掛け捨てにならないというメリットがあります。
交付対象者は認定農業者や集落営農、認定新規就農者です。いずれも規模に関する要件はありません。
ただし、収入保険と重複して加入することはできないので注意してください。
農業体験や副業から始めてみる
農業経営で失敗しないためにも、まずは副業から始めてみるのがおすすめです。スモールスタートによってリスクも小さく抑えられます。
例えば、本業で最低限の収入を得ながら農業を行う「兼業農家」にチャレンジしてみるのもおすすめです。
兼業農家は本業と農業を両立させなくてはいけないので大変ではありますが、安定した収入を確保できるメリットがあります。
また、農業の知識や経験がほとんどないのであれば、農業体験に参加してみましょう。
農林水産省がサポートする「農業インターンシップ」をはじめ、農協や自治体、民間企業でも農業体験イベントを実施しています。
農業体験を行うことで農業の大変さや魅力が伝わり、農業経営に向けたモチベーションにもつながります。
研修などで農業経営の知識や技術を身に付ける
本格的に農業経営を始めたい人は、研修に参加するのがおすすめです。農業体験に比べてより本格的な農業に関する知識と技術の習得が可能です。
農業研修は地方自治体で実施しており、農業に関する入門的な講座から特定の農作物に関する専門的な講座まで多岐にわたります。
農業研修に参加する期間は各研修によって異なりますが、約1週間で終わるものもあれば、半年間参加するケースもあります。
長期間になると月に数回や土日のみ開催している場合もあるため、仕事をしながら研修で農業について学びたい人も参加しやすいでしょう。
スマート農業の導入を検討する
人手不足や体力的な問題を解決するために、スマート農業の導入も検討してみてください。
スマート農業とは、ICT(情報通信技術)やロボット技術、AIなどを取り入れ、作業の効率化や品質向上などを実現する農業です。
可能な範囲で農業の自動化を進めることにより、労力が軽減して人件費も抑えやすくなります。
ただし、導入コストは決して安くないため、本当に必要かどうか慎重に検討する必要があります。
また、スマート農業を導入したとしてもすぐに成果が表れるわけではなく、中長期的な計画の策定が必要です。
地域全体で協力し合える支援体制を構築する
農業経営を行う場合、近隣の農家や住民との関係性も重要となってきます。
トラブルを起こさないためにも、コミュニケーションを積極的に取るようにしてお互いに理解し合えるよう努めていくことが大切です。
また、自分の農地だけでなく、近隣も含めて地域全体で農業を続けられる支援体制も構築することが重要となります。
自分の農地を放置していて雑草が生えっぱなしになっていたり、害虫対策を怠ったりすると近隣の農地にも悪影響を及ぼす可能性があります。
周囲に迷惑をかけないよう、自分の農地を管理しながら地域全体で農業の発展を目指すことが大切です。
金融機関と良好な関係を築く
収入保険制度や農業共済制度などを活用したとしても、経営破綻のリスクに陥る場合もあります。
このような事態に陥った際に、金融機関から融資を受けることで解決する場合も多いです。
しかし、普段から金融機関との関係性が良くないと融資してもらえない可能性もあります。
金融機関と良好な関係を築くためには、決算書を作成したら金融機関に実績を報告したり、そのデータをもとに収益の増減要因を分析して改善策を提示したりするのがおすすめです。
また、金融機関の担当者を農場に案内して、生産に対して正しいイメージを持ってもらうことも大切です。
まとめ・農業経営のリスクは万全な体制で備えておこう!
農業経営を行うにあたって、様々なリスクが起こり得ます。これらのリスクを回避するためには、事前の準備が必要不可欠です。
また、収入保険制度や農業共済制度、交付金などを活用することで、万が一収入減に陥ってしまった場合でも補てんしてもらえます。
農業経営には様々なリスクがあるものの、リスクに対応できる万全な体制を整えておき、回避もしくは被害を最小限に抑えられるようにしましょう。
農業経営の参考にぜひこちらの「ブルーベリーガイド」もご参考ください。ブルーベリーの観光農園に限らない話が満載です。無料でお取り寄せ可能です。
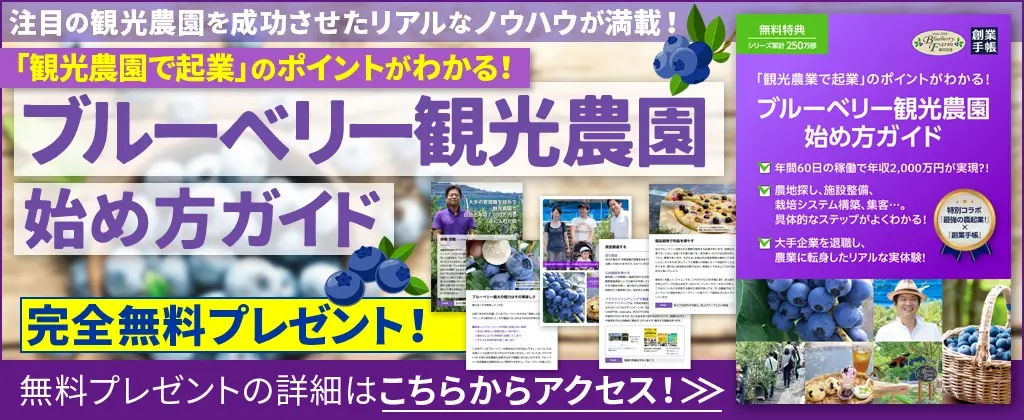
(編集:創業手帳編集部)