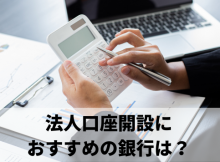法人設立後にかかる維持費はいくらかかる?費用の目安や抑えるためのポイントを解説
法人設立前に「維持費」を把握しておこう

法人を設立すると開業時の登記費用だけでなく、毎年かかる「維持費」も発生します。
様々な維持費がかかってくることから、運営を続けるためのコストは個人事業主よりも高くなりがちです。
せっかく設立した会社をスムーズに経営していくためには、これらの維持費を事前にしっかり把握する必要があります。
この記事では、法人を設立した後に毎年必要となる主な維持費の内訳と目安、維持費を抑えるポイントまで詳しく解説します。
法人設立後の維持費がどれくらいになるか確認しておきたい人は、ぜひ参考にしてください。
起業を考えている方は、無料でもらえる「創業手帳」もあわせてご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
法人維持費の年間平均額はいくら?

法人維持費は会社の形態によって内訳などが異なってきます。
会社形態に関わらず法人設立後にかかる維持費と、株式会社を設立した場合にのみかかる維持費には違いがあるので、注意してください。
法人維持費の目安を表にまとめたので、参考にしてください。
| 合同会社・合名会社・合資会社など | 株式会社 | |
| 税金 | 年7万円~ | 年7万円~ |
| 社会保険料 | 社員1人あたり給与の約15% | 社員1人あたり給与の約15% |
| 事業所の家賃・水道光熱費・通信費 | 従業員数・規模によって異なる | 従業員数・規模によって異なる |
| 給与 | 月54万5,000円(役員1人) | 月55万4,000円(役員1人) |
| 福利厚生費 | 1人あたり月5万円~ | 1人あたり月5万円~ |
| 士業など専門家への報酬 | 月3~5万円 ※決算時は追加報酬を支払う |
月3~5万円 ※決算時は追加報酬を支払う |
| 決算広告費 | ― | 官報公告:8~16万円 新聞掲載:約10~100万円以上 電子公告:無料 |
| 役員の就任・重任に関する登記費用 | ― | 1~7万円 |
| 株主総会の開催費用 | ― | 規模によって異なる |
| その他 | 企業によって異なる | 企業によって異なる |
会社形態に関わらず法人設立後にかかる維持費の内訳・目安

法人を設立すると、様々な費用がかかってきます。まずは会社形態に関わらず、ほとんどの法人にかかってくる維持費の内訳と目安について解説します。
税金
法人化した場合、赤字経営に陥っていたとしても一定額の税金は納める必要があります。法人が対象となる税金は以下のとおりです。
-
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税・特別法人事業税
- 消費税・地方消費税
特に法人住民税(均等割)は、会社の規模が小さかったとしても毎年7万円を納めなくてはなりません。
法人税や法人事業税は事業活動によって得た所得によって課されるため、税務上所得が赤字になっている場合は納めなくても良いことになっています。
ただし、資本金1億円超の外形標準課税が適用されている場合、赤字でも納付しなくてはなりません。
社会保険料
法人になった場合、売上げ・利益に関係なく必ず社会保険に加入することになります。
社会保険料の金額は役員や従業員数、報酬・給与額によって異なりますが、従業員1人に対して会社が負担する社会保険料の目安は給料の約15%です。
例えば2人の従業員に対して毎月40万円の給与を支払っている場合、1人あたり6万円で合計約12万円を会社側が負担することになります。
事業所の家賃・水道光熱費・通信費
法人設立時に事業所を設けた場合、その事業所の家賃や水道光熱費、通信費なども維持費としてかかってきます。
家賃や水道光熱費、通信費などは会社の規模や状況によって相場が大きく異なってくるため、一概にいくらと示すことができません。
例えば、小規模法人やスタートアップの場合、まずはコワーキングスペースを借りて事業所を用意するケースもあります。
コワーキングスペースなら比較的家賃を低コストに抑えることが可能です。
例えば工場を稼働させる場合、エネルギー消費量が大きいため水道光熱費の支出が高くなりがちです。
通信費はPCをメインに使用するか、問い合わせ対応のために固定電話を準備するか、などによっても違ってきます。
給与
法人設立時には毎月給与も発生します。
給与は、ひとり法人なら関係ないと思われるかもしれませんが、経営者自身も給与を受け取ることになるため、毎月かかる固定費といえます。
給与の金額は事業活動による利益と直結しているため、目安を出すのも難しいでしょう。
ただし、国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、役員の平均給与は資本金2,000万円未満の株式会社で665万円(1カ月あたり55万4,000円)、その他の法人で653万8,000円(1カ月あたり約54万5,000円)になっています。
あくまで平均額になりますが、他に従業員を雇用していなかった場合でも、最低54万円~55万円はかかるといえます。
福利厚生費
従業員を雇用している場合、モチベーションや生産性の向上を図るために福利厚生費を用意しておく必要があります。
福利厚生費は、法律で義務付けられている「法定福利費」と、企業が独自で用意する「法定外福利費」の2つに分かれます。
厚生労働省の「令和3年就労条件総合調査の概況」によると、常用労働者1人1カ月あたりの平均法定福利費は50,283円で、平均法定外福利費は4,882円でした。
福利厚生費は、法定福利費以外は用意しなくても問題ありませんが、福利厚生が充実していないと人が集まらない可能性があります。
ただし、内容を充実させたとしても必ず人が集まるわけではありませんし、高額な福利厚生費によって経営が圧迫する可能性も考えられます。
会社側と従業員側の両者にとって適切なバランスを見極めて、福利厚生を提供することが重要です。
士業など専門家への報酬
法人は事業年度が終了したら決算書を作成し、税務署などへ提出が必要となります。
経営者自ら決算書を作成することも可能ですが、会計や税務などの専門的な知識が必要であり、慣れていない人が1人で取り組むのは困難です。
そのため、決算書を作成する際は税理士に依頼するケースが多いです
会社に顧問税理士をつける場合、毎月報酬を支払うことになります。税理士事務所やプラン内容によって報酬額は異なるものの、相場は月3万円~5万円です。
さらに、決算書を作成する際には別途費用を支払わなくてはなりません。決算時の報酬は会社の売上げ規模によって異なります。
その他
上記で挙げた以外にも、以下のものがあります。
-
- 設備投資や備品
- 消耗品などの購入費
- 取引先との会食や打ち合わせに必要な交際費
- 火災保険や損害賠償保険などの保険料
- 業界団体や商工会などに加入した場合の会費・加盟料など
いずれも企業によって必要なものが異なるため、目安の金額を出すのは難しいですが、一つひとつの金額は小さくても積み重なることで大きな経費となります。
そのため、どんなことに経費を使うのか事前に洗い出しておくと良いでしょう。
起業を考えている方は、無料でもらえる「創業手帳」もあわせてご活用ください。
株式会社を設立した場合のみにかかる維持費の内訳・目安
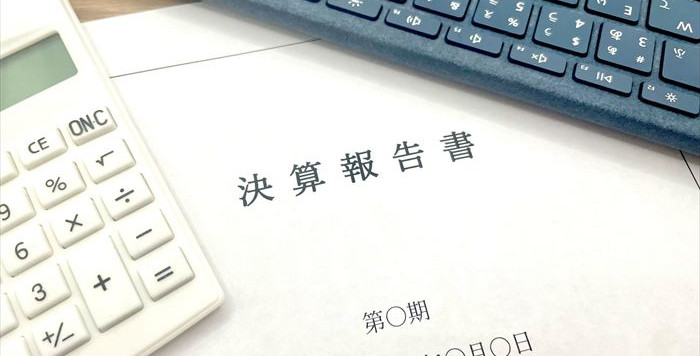
会社形態の中で、株式会社を設立した場合にだけかかる維持費もあります。どのような維持費が追加されるのか、その内訳と目安を解説します。
決算公告費
決算公告とは、企業の年間決算を公表し、ステークホルダーに財政状況や年間の経営成績を知らせることを指します。
決算を公表する方法は3つあり、それぞれでかかる費用が異なります。
-
- 官報公告:8~16万円
- 新聞掲載:約10~100万円以上
- 電子公告:無料
電子公告は自社サイトなどで公表する方法で、掲載すること自体にコストはほとんどかかりません。小規模法人であれば電子公告で済ませても問題ありません。
役員の就任・重任に関する登記費用
会社役員の就任や再任、退任などで役員変更登記が必要となった場合、登記費用を支払う必要があります。
株式会社だと役員には任期が設けられており、同じ人物が長年役員を続けている場合でも、定期的に役員変更登記をしなくてはなりません。
任期は取締役で2年、監査役で4年となっていますが、非公開の株式会社であれば最長10年まで伸ばすことも可能です。
役員変更登記にかかる費用は、登録免許税と印鑑証明書、司法書士に依頼した場合の報酬などが挙げられます。
登録免許税は資本金1億円未満の会社で1万円、1億円を超える会社は3万円です。
また、役員の本人確認証明書としての印鑑証明書は1通300円、司法書士に依頼した場合の報酬は案件によって異なりますが、約3万円~6万円が相場です。
なお、株式会社ではない会社形態の場合、役員の任期は決められていないため、役員交代などがない限り登記費用は不要となります。
株主総会の開催費用
株式会社は原則年1回の頻度で株主総会を開催することになっています。株主総会は規模によって開催費用が異なります。
例えば、自社に株主を呼んでも十分なスペースがあれば会場費はかかりませんし、逆に上場企業などで株主が多い場合は会場を準備しなければなりません。
また、お弁当代やお茶代、その後懇親会を開催する場合はその費用もかかってきます。
法人・個人事業主における維持費の違い

ここまで、法人設立後にかかる維持費の内訳と目安を紹介してきましたが、個人事業主と比較した場合、どのような違いがあるのでしょう。
法人の場合、赤字であっても法人税の均等割を納める必要があるため、毎年7万円は納める必要があります。
一方、個人事業主だと個人事業税が課されますが、事業の種類によっては課税対象にならなかったり、事業所得が290万円以下だったりすると納税の必要がありません。
維持費だけに注目すると個人事業主のほうが負担は小さいですが、法人だと税制面での優遇を受けられ、収益が増えれば増えるだけその恩恵も大きくなっていきます。
個人事業主に比べて節税面で優れているため、個人事業主は事業規模を拡大させたいなら法人成りをすることも検討してみてください。
起業を考えている方は、無料でもらえる「創業手帳」もあわせてご活用ください。
法人設立後の維持費を抑えるためのポイント

法人設立後にかかる維持費を少しでも節約したいと思う人は多いでしょう。ここで、法人設立後の維持費を抑えるためのポイントを解説します。
合同会社で設立する
コストをできるだけ抑えて法人を設立したい場合には、合同会社として設立するのがおすすめです。
合同会社は会社の所有者と経営者が同じであるタイプの法人を指します。
株式会社だと会社の所有者と経営者は異なるため、執行役や取締役などを設置する必要がありますが、合同会社では不要です。
しかも、合同会社だと株式会社と同じく節税対策や社債の発行もできます。経営の自由度が比較的高いのは大きなメリットといえます。
株式会社より知名度が低いというデメリットはあるものの、出資者同士の話し合いだけで柔軟に対応できるため、効率的な事業運営も可能です。
固定費を抑える
経費は主に「固定費」と「変動費」に分けることができます。
固定費は売上げの増減を問わない費用で、変動費は原材料の価格や販売手数料、外注費など、売上げによって変動する費用です。
維持費を削減しようとすると、つい削減しやすい変動費ばかりに目を向けがちですが、固定費にも注目することが大切です。
固定費には事業所の賃料や水道光熱費、人件費などが挙げられます。
特にオフィスコスト(賃料や備品費、通信費など)は、テレワークの導入によって削減することが可能です。
ペーパーレス化を図る
維持費を抑えるポイントとして挙げられるのが、ペーパーレス化です。法人ではコピー用紙やトナー、文房具など事務用品を準備する必要があります。
事務用品は一つひとつの価格自体はそれほど高いものではないものの、ペーパーレス化を図ることで事務用品を購入するための費用も大幅に抑えられます。
例えば、モノクロ・A4サイズの書類を印刷するのに、1枚3~4円かかります。毎月1万枚印刷すれば、3万円~4万円のコストがかかってくる計算です。
また、書類は物理的に保管するスペースを用意しなくてはなりません。
多くの書類を扱うとなると、保管するスペースも含めてオフィスを選ぶ必要があり、賃料にも影響してきます。
こうした理由から、維持費を抑えたいのであればペーパーレス化を図ることも大切です。なお、ペーパーレス化によってDX化が促進され、業務の効率化にもつながります。
アウトソーシングの活用も検討する
従業員を雇用するとなると、年間で1人あたり数百万円規模の費用がかかってきます。この人件費を少しでも削減するためには、アウトソーシングの活用も検討してみてください。
アウトソーシングは社内の業務を社外に委託することを指します。
例えば経理などの事務作業はアウトソーシングに依頼し、経営者や従業員はコア業務に注力することが可能です。
人材を雇用する際のコストを抑えられるだけでなく、コア業務に専念できることで売上げアップにつながる可能性も期待できます。
ただし、アウトソーシングで事務作業などを委託した場合、情報漏洩のリスクが高まってしまいます。
情報漏洩のリスクを最小限に抑えるためにも、豊富な実績を持ち情報セキュリティに関する認証を取得している委託会社かどうか確認しておくと安心です。
まとめ・法人設立時は初期費用だけでなく維持費にも目を向けよう
法人を設立する際は、登記などの初期費用に注目しがちですが、実際の経営では継続的に発生する維持費の管理も重要です。
士業など専門家への報酬や社会保険料、オフィスの賃料などは毎月・毎年かかるため、あらかじめ資金計画に組み込んでおくことで、資金繰りのトラブルを防げます。
維持費の内容を正しく理解し、コストを最適化することで、健全な経営を続けやすくなります。
法人設立を検討している人は、初期費用と合わせて維持費も見据えた準備を進めましょう。
創業手帳(冊子版)では、法人設立時に知っておきたい様々な情報をお届けしています。これから法人を設立しようとお考えの人は、ぜひ創業手帳をお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)