法人の利益が出過ぎた時の対処法!節税対策や注意点とは
利益が出過ぎると法人税の負担が大きくなる

法人が利益を出し過ぎると、高額な法人税が課せられる可能性があります。納税負担が大きくなれば事業継続にも影響を与えるため、節税対策を施すことが重要です。
しかし、「節税方法がわからない」「本当に節税できるのか不安」などと疑問を感じている人もいるでしょう。
そこで今回は、法人で利益が出過ぎた場合に取組める節税対策について解説していきます。
節税時の注意点も紹介していくので、有効な方法を知りたい人はぜひ参考にしてみてください。
利益が大きいと税負担も大きくなりますが、正しい知識があれば納税額を最小限に抑えることができます。
創業手帳オリジナルの『税金チェックシート』では、法人が押さえておくべき節税の基本ポイントをまとめています。知らないまま損をしないために、ぜひご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
法人の利益が出過ぎたら?知っておきたい4つの基本策
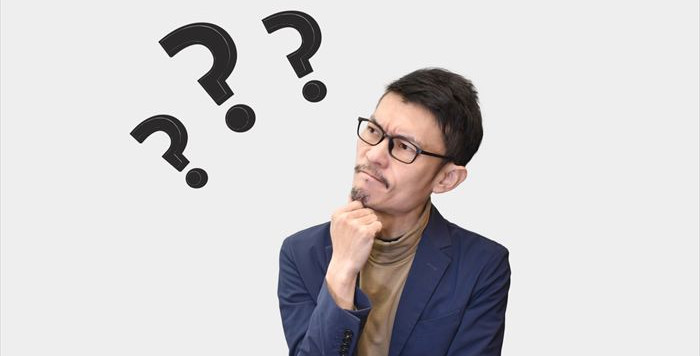
法人が利益を出し過ぎた場合の節税方法には様々な種類がありますが、基本策としては以下の4つが挙げられます。
-
- 経費を増やす
- 資産を動かす
- 給与を見直す
- 保険に加入する
経費を増やして利益を減らしたり、資産があれば優遇措置を受けられたりする可能性があります。
また、給与の見直しや保険への加入も節税につながる方法です。ここから具体的な手法を紹介していくため、節税方法を知りたい人は参考にしてください。
法人の利益が出過ぎた場合の節税対策①経費

経費を増加して利益を減少させる節税方法を紹介します。従業員の満足度を上昇させることにもつながるため、企業にとっては様々な魅力があるはずです。
福利厚生
会社の福利厚生は経費計上できるため、節税対策として有効です。
-
- レクリエーション
- 社員旅行
- パーティー など
これらのイベントを実施すれば福利厚生として経費に計上できます。ただし、社員のうち50%以上の参加が要件となることに注意してください。
また、社宅制度も利益の圧縮になります。従業員が住むための社宅の家賃は経費計上が可能です。
ただし、従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%未満だと社宅の貸与として認められません。
現物支給の給与として課税対象となってしまうことに注意が必要です。
広告宣伝費
企業や商品、サービスを広く知ってもらうためには、広告宣伝が企業活動において欠かせません。
ターゲットとなる顧客に興味を持ってもらったり、認知度上昇や購入や利用を促したりすることが目的ですが、利益が出過ぎた時には節税対策として有効です。
-
- ホームページの制作
- ホームページの更新
- ランディングページの制作
- 人材採用専門のページの制作
- インターネット広告
- チラシの作成
- 動画の撮影や配信 など
広告のための手段はマーケティングにおいて重要な販売戦略となりますが、経費がかさむ点がデメリットです。
しかし、有効活用すれば経費計上ができて節税対策になります。また、未来への投資にもなるため、活用を検討してみてください。
ただし、チラシは決算終了時に残っていると経費ではなく資産になるため、残らない程度の枚数を作る必要があります。
健康診断
企業は従業員の健康を守るために、健康診断の実施義務があります。健康診断の費用は、利益が出過ぎた場合に節税対策として活用できます。
簡易的な健康診断を実施している企業であれば、より詳細な検査や人間ドッグを実施するなど、グレードアップを図れば節税につながります。
また、従業員の健康管理をより強化できるだけではなく、病気の早期発見や早期治療につながるかもしれません。
ただし、全従業員の50%以上が受診をすることが必要です。健康診断の魅力を伝えるなどして受診の魅力を伝える工夫をしましょう。
短期前払費用
短期前払費用の特例でも節税が可能です。
通常、毎月の債務が発生したタイミングで経費計上することが可能ですが、以下のケースであれば支払った年に全額を損金算入できます。
-
- 年払いである
- 物品購入ではない
- 1年以内にサービスの提供を受ける
保険料や賃貸料、リース料などの継続使用が決定し、年払いの契約をしていれば翌期の役務を待たずに今期分の経費にできます。
ただし、1年以内という要件があることに注意してください。
法人の利益が出過ぎた場合の節税対策②資産の変動

資産を動かすことも納税額に大きな影響を与えます。保有している資産の見直しを行い、今後購入する資産では優遇措置が受けられないか確認してみてください。
不要な在庫の処分
不要な在庫を処分することで利益を減らせるため、節税が可能です。
売上総利益は、「売上高-売上原価」で求められますが、売上原価には棚卸資産(在庫)が含まれています。
在庫を処分すれば売上原価が増えるため、結果的に売上総利益の減少につながるでしょう。
通常の在庫は翌期の売上ですが、不要な在庫を処分すれば節税になり、赤字の場合でも処分をすればキャッシュに代えられるため、大きなメリットとなります。
不要な固定資産を処分
不要な固定資産の処分も節税対策の一種です。固定資産は、廃棄もしくは売却、除却すると以下のように経費計上が可能です。
-
- 廃棄:固定資産廃棄損
- 売却:固定資産売却損
- 除却:固定資産除却損
固定資産が減れば現金を増やせ、管理をするために費用を投入する必要もありません。
使用していないものや使用頻度の低い固定資産がないか確認してみてください。
少額減価償却資産
少額減価償却資産の特例の活用で節税ができます。
少額減価償却資産とは、特定の要件に該当している中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した際に全額を損金算入できる特例です。
-
- 従業員が500人以下
- 資本金1億円以下
- 青色申告を実施する
以上の要件を満たせば特例の活用が可能です。
器具備品や機械装置といった有形減価償却資産のみではなく、特許権や商標権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産も対象で、中古資産も含まれます。
ただし、限度額が年間300万円となっているため、使い過ぎには注意してください。
設備投資
生産性向上につながる設備投資でも節税が可能です。
高額な設備投資は減価償却資産に該当するため、利益が大幅に出るとわかったタイミングで購入しても節税効果はあまりないかもしれません。
しかし、設備投資には優遇措置制度があります。業種や事業規模、取得内容といった条件が揃えば、特別償却と税額控除が活用でき、節税につながります。
なお、特別償却であれば、通常の減価償却費とは別に「取得価額×30%」にあたる分を償却可能です。利益が出過ぎた場合には、積極的に活用してみてください。
不動産投資
不動産投資を行えば、土地や建物の購入費用に加え、運用にかかる費用を経費計上できます。
建物部分の購入費は、法定耐用年数に沿って減価償却していくため、複数年にわたって経費にできる点が特徴です。
ほかにも、下記の費用も経費に当てはまるので節税につながります。
-
- 火災保険
- 租税公課
- 減価償却費
- 修繕費
- 管理会社にかかる業務委託料
- ローン金利
- 司法書士への報酬 など
取得した不動産を賃貸にして家賃収入を得られるようになれば、安定したキャッシュフロー確保にもつながります。
ただし、不動産投資での節税効果は減価償却期間中に限ります。減価償却期間が終了する際にどのように処分するか、出口戦略を練っておくことも重要です。
法人の利益が出過ぎた場合の節税対策③給与関連

ここからは、給与関連での節税方法を紹介していきます。
役員報酬
役員報酬は、従業員の給与と同じように会社の経費にすることは原則としてできませんが、要件を満たせば損金算入が可能です。
その方法のひとつが「定期同額給与での支給」です。定期同額給与とは、1カ月以下の一定期間ごとに同額で支払われる役員報酬のことです。
残業代や特別報酬は定期同額給与に含まれないので、従業員の基本給と同じように、月によって金額は変動しません。
定期同額給与の金額変更は、事業年度開始から3カ月以内だけなので、基本的には毎月同じ金額が支給される仕組みです。
決算賞与
利益が出過ぎた際には、決算賞与を支給することで節税対策が可能です。主な要件は以下のとおりです。
-
- 支給額をあらかじめ従業員ごとに確定して伝える
- 決算の翌日から1カ月以内に支給する
- 支給額は未払金として経費計上する
決算賞与は節税できるだけではなく、従業員のモチベーションアップにもつながるので、感謝の気持ちを表すためにも支給を検討してみてください。
役員退職金
退職した役員に対して臨時的に支給される給与を役員退職金といいます。
役員退職金は、基本的に全額を損金として計上できるため、利益圧縮につながり節税効果があります。
また、所得控除額が設けられており、税制上の優遇も期待できます。利益が出過ぎた場合には活用してみてください。
法人の利益が出過ぎた場合の節税対策④保険

保険を活用して節税につなげることもできます。ぜひ参考にしてください。
団体定期保険
企業が契約者となり、全従業員に対しての高度障害や死亡に対応する保険で、遺族の生活を安定させることが目的です。
掛け金は全額損金算入の対象で、節税対策に有効です。
また、受取金を企業にすることもでき、死亡退職金や弔慰金の資金として活用できます。
共済への加入
小規模事業者向けとして、以下のような共済があります。
-
- 経営セーフティ共済
- 中小企業退職金共済
- 小規模企業共済
これらの共済は、経営者や従業員に対する退職金の準備に使えるほか、事業悪化時には無利子で貸し付けができるなど、企業経営を安定化させるためにも有効な手段です。
共済への掛け金は、全額経費になり法人税の節税につながります。それぞれの特徴を理解して、効果的に活用してみてください。
法人で利益が出過ぎた際の3つの注意点

様々な種類の節税方法がありますが、活用する際には注意点もあります。
節税しているつもりでも、メリットを得られなければ無駄遣いになってしまいます。以下を参考に、無駄のない節税を進めてみてください。
無駄な投資は避ける
「経費を多く計上すれば節税になる」といったイメージを持つ人もいます。確かに節税につながりますが、不要なものの購入には意味がありません。
維持やメンテナンスにも費用がかかるので、後々費用が多くかかりマイナスとなる可能性があります。
機器やソフトウェアは購入しても使わずに眠らせてしまうケースが考えられるため、「無駄にならないか」「企業の成長に必要であるか」を考えて、実需と合わない支出は避けるようにしてください。
資金繰りに注意
節税を意識し過ぎて過剰に経費を利用すればキャッシュアウトする恐れがあります。
支払いや投資資金が確保できなくなるリスクがあるため、手元のキャッシュが少ない場合には節税対策の実施が本当に必要か慎重に検討する必要があります。
売上げが好調な時こそ、運転資金の確保や事業拡大のための準備など、将来に備えるための戦略が重要です。
対策は段階的に実施する
決算間近になり税金の負担が大きいことに気づけば、慌てて対策を練ることになります。しかし、その時点で実施できる対策には限りがあります。
こうした事態を避けるためにも、年間のスケジュールを立てて段階的に節税計画を立てることが重要です。
また、決算前に慌てて節税対策を行えば不自然な帳簿になってしまいます。税務調査の対象になる可能性もあるので注意してください。
まとめ・無理のない範囲で節税対策を始めよう
今回は、法人で利益が出過ぎた場合の節税対策について紹介してきました。経費や資産、給与や保険など、法人の節税対策には様々な種類があります。
うまく使えば節税となり負担を抑えることにつながりますが、節税を意識するあまりに無駄な対策を行えばキャッシュアウトする恐れもあります。
節税対策で後悔しないためにも、長期的な節税計画を立てて、無理のない範囲で実施するよう心がけてください。
節税で浮いたお金を事業に再投資できれば、その効果は大きな違いにつながります。
『税金チェックシート』は無料でダウンロードでき、今からすぐに実践できる内容です。法人経営者の方は、ぜひ手に取ってみてください。

(編集:創業手帳編集部)




































