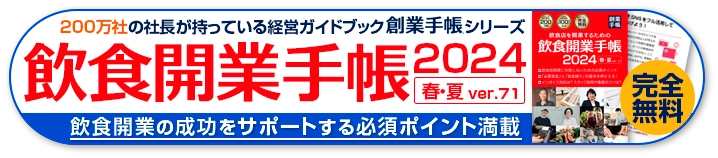儲かる飲食店は「仕組みづくり」が重要!利益を大きくするためのポイントを解説
仕組みを知って儲かる飲食店を目指す

「味には自信があるのに、なぜか利益が出ない」「忙しいのに、手元にお金が残らない」などの悩みを抱える飲食店オーナーは少なくありません。
実は、儲かる飲食店とそうでない店の差は、メニューや接客だけでなく「仕組みづくり」にあります。
売上げを安定させて利益を確保するには、経営の仕組みを整えることが欠かせません。
この記事では、儲かる飲食店の仕組みや構造、利益を最大化するためのポイントなどを解説します。
飲食店を経営しているものの、利益をなかなか出せずに悩んでいる方はもちろん、これから飲食店を開業しようと考えている方も、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、飲食店の開業について詳しく解説した「飲食開業手帳」を無料でお配りしています。出店についてや資金繰り方法など基本的なことから、飲食経営で成功した方々へのインタビューにて成功の秘訣などを網羅。ぜひこちらもあわせてお読みください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
儲かる飲食店とは?成功モデルの共通点

儲かる飲食店には、単なる“料理の質”や“価格の安さ”だけではない「儲かる仕組み」が存在するのです。
ここでは、創業手帳が過去にインタビューした経営者の中から、高収益を実現している店舗の共通点を見ていきます。
人形町今半:老舗ブランドを守り抜く独自戦略
明治創業の老舗「人形町今半」の髙岡慎一郎社長は、「他社と比較して値付けを決めたり経営判断をしたりしないことが、結果としてブランドと利益を守る」と語っています。
競争に巻き込まれないポジショニングと、高価格帯でも納得感を生む品質と接客が、高収益を支える仕組みです。
「自社の価値を下げるような競争には乗らない。『他社がこうだから』ではなく、お客様との関係性を見て判断します」(髙岡慎一郎氏)
DDグループ:業態ごとに最適化された100の仕組み
全国で100業態以上を展開するDDグループ(代表:松村厚久氏)は、「同じ店をコピーしない」ことを戦略としています。
各業態ごとにコンセプトを固め、内装やメニュー、採用・教育までを専用設計することで、現場で最適な仕組みを構築しています。
その徹底が、複数店舗でも高収益を維持できる理由です。
「一軒ずつ“個性”があるからこそ、お客様の期待値を超え続けられる」(松村厚久氏)
儲かる飲食店の仕組み・構造

儲かる飲食店にしていくためには、そもそも儲かる仕組みや構造について理解しておかなくてはなりません。そこで、儲かる飲食店の仕組みや構造を解説していきます。
売上げの内訳
飲食店において「儲け」というのは、主に利益を指します。利益は、企業が得た売上げからその販売にかかった費用を差し引き、最終的に店舗が獲得できる金額です。
飲食店の売上げは主に以下の内訳によって構成されています。
客単価×回転率×座席数
客単価は顧客ひとりが1回の会計で使用する平均金額で、回転率は座席数に対して顧客が何回入れ替わったかを示す割合です。
それぞれの内訳が影響して、売上げにつながっています。
売上げを左右しているのは「客単価」と「回転率」
売上げを上げるためには、どの要素に注目すべきなのか。上記3つのうち、特に売上げを左右しているのは「客単価」と「回転率」です。
座席数は店舗面積がすでに決まっている以上、無理に増やすことはできません。むしろ窮屈になりすぎると、快適性がなくなり顧客が減ってしまう可能性があります。
顧客は一人ひとり支払う金額が異なります。例えば1,000円以下に収まる人もいれば、家族で訪れて数千円支払う人もいるでしょう。
客単価が高くても回転率が下がってしまう場合があるため、若干値段が張ってもお得感が出るように、旬の食材や銘酒などを取り入れて自然な形で客単価を上げることが大切です。
また、回転率は高ければ顧客が入れ替わる頻度も増えるため、その分売上げが上がります。
特にファストフード店や牛丼店などは基本的に滞在時間が短いため、客単価が低くても回転率の高さによって売上げを向上できます。
ただし、滞在時間が長めのカフェや喫茶店、客単価の高い高級レストランなどで無理に回転率を上げてしまうと、客離れにつながってしまうこともあります。
すべての飲食店で回転率の高さ=売上アップにつながるわけではないことを理解してください。
客席稼働率が高まれば回転率も増加する
回転率と合わせて注目したいのが、客席稼働率です。客席稼働率とは、客席が何人に使われているかを示す指標です。
例えば4人席のところに2人座っていれば、すべての卓は埋まっているものの、席自体は空いていることになります。
4人席に4人が座るよりも稼働率が半分に下がった状態になるため、売上げもその分落ちることになります。
回転率だけに注目していても、席が空いている状態が続けば売上げも向上しません。
例えば1時間あたりの回転率が1回から2回に増えたとしても、客席稼働率が50%なら2回で100%になるため、1回100%と効率的に変わらないことになってしまいます。
逆に稼働率が良くても回転率が悪ければ、売上げにつながりにくいです。そのため、回転率と客席稼働率の両方を高めていくことがポイントになります。
儲かる飲食店にするためのポイント

儲かる飲食店にするためには、以下のポイントを押さえることが大切です。それぞれのポイントについて詳しく解説します。
適正な原価率を見極める
原価率とは、売上げのうち原価がどれくらいかかっているのかを示す割合です。
例えばハンバーグをつくるのにかかった原価が600円で、ハンバーグの価格が1,200円だった場合、原価率は600円÷1,200円×100=50%になります。
売上1,200円のうち、半分の600円はそのまま売上げになりますが、もう半分の600円は原価として費用がかかっていることになります。
儲かる飲食店はこの原価率を見直し、適正な割合に設定していることが多いです。
メニューの原価率を一律3割にしない
メニューの原価率は3割に設定することが定番となっています。原価率を3割に設定すれば、食材費と人件費の比率(FL比率)も抑えやすくなります。
FL比率は60%以下に収めたほうが良いとされているため、原価率を3割に設定している飲食店は多いかもしれません。
ただし、ここで注意すべきなのは、一つひとつのメニューの原価率を一律3割にするのではなく、トータルの原価率を3割にすることです。
もし各メニューの原価率を3割に設定してしまった場合、競合店が原価を度外視して高級食材を使った目玉商品を提供していた場合、顧客はそちらのほうに魅力を感じ客離れが起きてしまう恐れがあります。
一律原価3割を貫いていては、魅力的なメニューの開発も難しくなってしまうものです。そのため、メニューの原価率は一律ではなくトータルで3割を目指すことが大切です。
集客商品・収益商品をつくる
トータルで原価率3割を目指すためには、メニューに「集客商品」と「収益商品」をつくることが重要となってきます。
集客商品とは、顧客を呼び込むための看板メニューで、「このお店に来たらこれは食べておくべき」といわれるような目玉商品のことです。
店の看板メニューということもあり、競合店と差別化を図る必要があり、原価率はほかの商品に比べて高くなる傾向にあります。
一方、収益商品は低い原価率で、数が出れば出るほど飲食店が儲かるような商品を指します。
原価率が3割以下になる商品も多く、集客商品と合わせて購入してもらうことでトータルでの原価率3割を目指すことが可能です。
例えば海鮮系居酒屋の場合、豪華な船盛や新鮮な刺身などは集客商品、枝豆やフライドポテトなどの定番フードや酒類・ドリンク系は収益商品です。
集客商品と一緒に収益商品を買ってもらえるように、メニューの最初に収益商品を掲載して目立たせたり、セットメニューを用意したりするといった工夫を取り入れてみてください。
食材の棚卸しを行う
適正な原価率を設定したとしても、なかなか儲けが出ないケースもあります。この場合の原因として、売上原価をきちんと把握できていない点が考えられます。
売上原価を正確に把握するためには、食材の在庫数を確認することも重要です。ここで重要となるのが、「棚卸し」になります。
棚卸しは食材や飲み物の在庫、仕込み中の商品も含めて在庫数を調べ、実在庫金額がどのくらいなのかを把握することです。
飲食店における売上原価は、前月の実在庫金額(期首棚卸高)+今月仕入れた在庫分-今月の実在庫金額(期末棚卸高)で求められます。
棚卸しに必要なもの
棚卸しをする際には、棚卸し表の作成が必要です。棚卸し表は在庫品目や数量、単価、合計金額を記録するための表になります。
商品名や仕入先、購入日、商品単価、在庫数なども記載できるようにすると、より在庫の現状を把握しやすくなります。
棚卸し表は手書きやExcelで作成しても良いですが、効率性を求めるなら在庫管理システムやアプリの活用がおすすめです。
棚卸し表の作成・管理がしやすくなり、記入する際の人的ミスも防げるようになります。
棚卸しのやり方
棚卸しは定期的に決められた日に行うのが基本です。作成した棚卸し表の項目に基づき、食材やドリンクなどの在庫がどれくらいあるのかを数えていきます。
在庫を数える際に注意したいのが、賞味期限が近い商品や開封済みの商品、消耗品類です。
基本的には店舗内にあるすべての在庫を対象にカウントしますが、賞味期限が近い商品は廃棄リストに記載したり、開封済みの商品は正確な数量や価値を測るために、重量を測ったりすることもあります。
また、洗剤や調味料などの消耗品も在庫として数えなくてはなりません。
棚卸し表にすべての在庫情報を記録したら、仕入れ単価を確認して数量とかけ合わせ、各在庫の合計金額を計算します。
さらに全体の合計金額を計算し、売上原価がかかりすぎていないか確認してください。
食材ロスを減らす
食材を仕入れたにも関わらず、廃棄してしまうことを「食材ロス」といいます。
例えばメニューに使用する食材を準備していたものの、消費期限が過ぎてしまい廃棄しなくてはいけなくなるケースもあります。
この食材ロスも原価率が上がってしまう要因となるため、注意が必要です。そこで、食材ロスを減らすためのポイントを解説します。
メニュー開発時に「歩留まり」を考慮する
まずメニューを開発する際に、消費者にとって魅力的なメニューにすることも当然重要となりますが、歩留まりについても考慮しておく必要があります。
歩留まりは、「食材の中でどれくらいの割合をメニューとして使えるか」という考え方です。
例えば魚1kgを仕入れて刺身として提供する際、頭や骨、内臓などは使わず、身だけで600gになったとします。この場合の歩留まりは60%です。
野菜や肉も含めて、原材料はすべてが100%メニューに使えるわけではありません。
しかし、メニューに使わなかった400g分の代金は戻ってこないため、できるだけ歩留まりは100%に近づける必要があります。
メニュー開発の時点で歩留まりを考慮しておかないと、棚卸しの際に売上原価との差が生まれやすくなるので注意が必要です。
オーバーポーションにならないよう気を付ける
オーバーポーションとは、決められた分量以上に食材を使ってしまうことです。
例えばメニューの開発時点で20gのチーズを使うと決まっていたのに、目分量でやっていた結果、実際には25gのチーズが使われていたとします。
この場合、たった5gの差と感じるかもしれません。
しかし、そのメニューが1日40食出た場合、本来なら20g×40食=800gの消費に収まっていたはずが、25g×40食=1000gも消費していることになります。
忙しい現場だとどうしても目分量になりがちです。しかも少ないとクレームが起きる可能性もあることから、基本的には多めに盛り付けてしまう傾向にあります。
盛り付けの分量にばらつきが生じると、顧客満足度にも影響してくるため、レシピをマニュアル化して統一するなどの対策が必要です。
冷凍食品を活用する
食材のロスは調理工程が多かったり、原料に近かったりすると発生しやすいです。
そのような調理工程で発生しやすいロスは、冷凍食品を活用することで減らすことができます。
例えば、居酒屋で提供するポテトは生のじゃがいもを使って調理するよりも、冷凍ですでにカットされた冷凍食品を活用すれば、調理の時短にもつながり、皮などのロスも発生しません。
しかも、冷凍食品は冷蔵よりも賞味期限が長く、注文がそれほどなかったとしてもすぐに腐って使えなくなるといったこともありません。
儲かる飲食店に必要な「経営の仕組み化」

儲かる飲食店を目指すためには、経営の仕組み化も行う必要があります。ここで、儲かる飲食店に必要な、経営の仕組み化について解説します。
KPIで売上げ・利益を可視化する
KPI(重要業績評価指標)とは、目標達成に向けて必要な数値のことです。
例えば飲食店なら「1カ月の売上げを100万円にする」や「来年度までに2店舗目を出店」などの目標を掲げているところも多いです。
しかし、これらの目標は具体的にどのようなことをすべきかがわかりづらくなっています。
そこで、最終的な目標を達成するのに必要な要素を細かく数値目標にして、可視化したものがKPIです。
飲食店で設定されることが多い代表的なKPIは以下のとおりです。
-
- 客数
- 客単価
- 回転率
- 客席稼働率
- 原価率
- 人件費
- FL比率
- 予約数
- リピーター数 など
最終的な目標に合わせてKPIを設定し、売上げや利益を可視化できるようにしてください。
マニュアルと教育体制の整備
飲食店の経営において、従業員の教育・育成に悩む経営者も少なくありません。
従業員を雇用すると教育に時間と費用はかかってしまいますが、一人ひとりのスキルが向上し、業務効率が向上すれば、コスト削減につながる場合もあります。
また、マニュアルによって提供するサービスの質が統一され、オーバーポーションなども防ぐことが可能です。
従業員の教育・育成を効率的に行うためには、マニュアルと教育体制の整備が必要となります。
ただし、いくらわかりやすいマニュアルを作成できたからといって、教育をマニュアル頼りにしてしまうのは良くありません。
経営者だけでなく、従業員間でもコミュニケーションが取りやすいように、職場環境の向上や良好な人間関係を構築していくことが大切です。
例えば定期的に交流会を実施したり、意見交換を兼ねて面談を行ったりすると良いでしょう。
経費削減も飲食店では必要

儲かる飲食店にしていくためには、売上げを向上させるだけでなく経費削減も必要です。ここで、飲食店での経費削減のコツについて解説します。
契約中の電気会社・ガス会社を見直す
飲食店を経営している中で、多くの電気・ガスを使用することになります。
「電気代・ガス代がかかってしまうのは仕方ない」と考え、経費削減を諦めてしまう人もいるかもしれません。
しかし、契約中の電気会社・ガス会社を見直したり、プランを切り替えたりすることで、経費削減につながる場合もあります。
自由化で電気会社・ガス会社を選べるようになったため、店舗にとって最適な会社・プランを探してみてください。
シフト管理やオペレーションの最適化を図る
飲食店の大きな支出項目として挙げられるのが、「人件費」です。一般的に飲食店の売上げに対して人件費の適正な割合は20~30%程度といわれています。
人件費は高くなりすぎると利益が圧迫されてしまいますが、逆に抑えすぎてもサービスの品質低下や離職率の増加などにつながってしまいます。
こうした事態を防ぐためにも、適切な人件費管理を行うためにシフト管理やオペレーションの最適化を図ることが重要です。
例えばテーブルに案内してからメニューと水を運ぶという行為は、最初からテーブルにメニューを置いたり、水をセルフサービスにしたりすることで従業員の作業工程が減ります。
これだけでも年単位で見ると大きな人件費削減につながっているはずです。
また、シフト管理についてもピークタイムの3~4時間だけ働いてもらう短時間勤務の従業員を増やせば、フルタイムの従業員だけで回すよりも効率的になります。
支払手数料を見直す
飲食店における支払手数料とは、金融機関への振込手数料や弁護士・会計士に支払う報酬、クレジットカードの手数料などが挙げられます。
この中でも削減しやすいのは、クレジットカードの支払手数料です。例えば料率が高いクレジットカードに関しては解約を検討することも視野に入れます。
また、料率が低いカードのステッカーを見やすい位置にすることで、料率が高いカードの利用頻度を減らせる可能性もあります。
SNSを活用して無駄にかかっていた広告費を減らす
広告費を減らすために、SNSを活用した宣伝を増やすのもおすすめです。例えば定期的にチラシやDMを作成していた場合、その都度印刷代がかかっていることになります。
しかし、SNSであれば無料でアカウントを作成でき、話題を集めれば拡散効果でより多くの顧客を集められる可能性もあります。
ただし、飲食店のターゲットがあまりSNSを利用しない層だった場合、広告費の削減によって集客の低下を招く恐れもあるため注意が必要です。
更に経費について詳しく知りたい方は、経費の取り扱い方についてわかりやすくまとめた『経費で損しないためのチェックリスト』をご活用ください。このチェックリストでは、経費を「人件費」「交際接待費」「広告宣伝費」など23の経費科目ごとに分解し、それぞれの「経費削減のポイント」と「節税につなげる」ポイントを整理しています。無料でお配りしていますのでぜひご利用ください。
まとめ・仕組みやポイントを取り入れて儲かる飲食店を目指そう
飲食店で安定した利益を上げるためには、味やサービスだけでなく、「仕組みづくり」が欠かせません。
原価や人件費の管理、オペレーションの効率化、スタッフ教育など、経営全体を見直すことで無理なく収益を伸ばすことができます。
思いつきや勢いだけではなく、計画的に仕組みを構築してこそ、長く儲かる飲食店を実現できます。
今回ご紹介したポイントをもとに、自分の店舗に合った経営の仕組みを見直し、利益体質の強いお店を目指してください。
創業手帳では、飲食店の開業や経営について詳しく解説した「飲食開業手帳」を無料でお配りしています。これから出店を考えている人や、現在の経営について改善を検討されているはぜひこちらもご活用ください。無料でお届けしています。
(編集:創業手帳編集部)