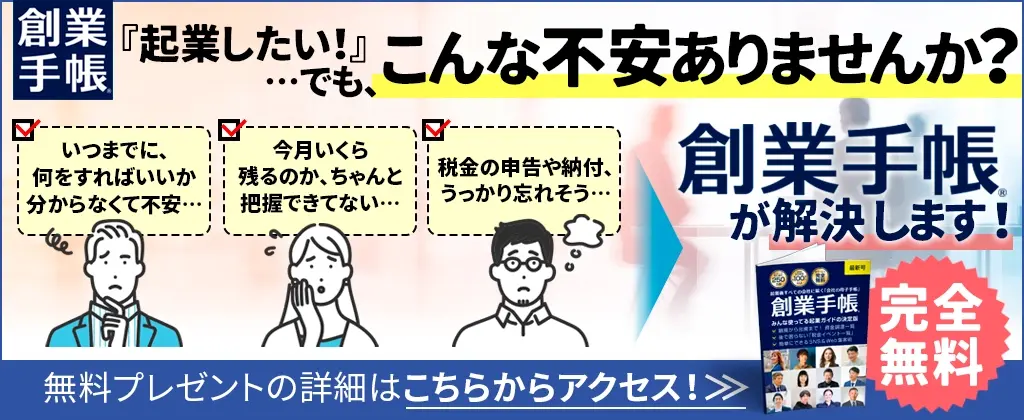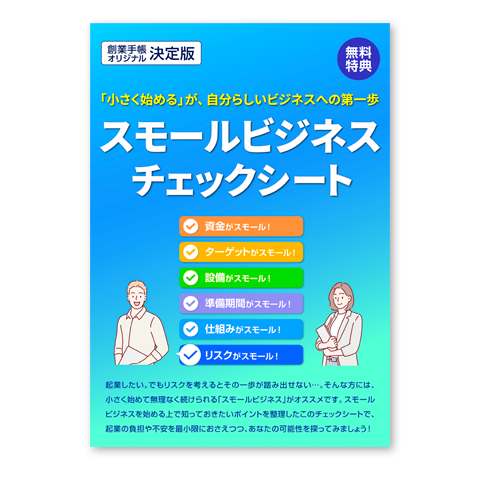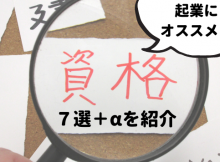起業の前にやるべき棚卸しとは?経験・スキルから見つけるビジネスアイデア
自分自身の“棚卸し”から思わぬヒントに出会えるかも
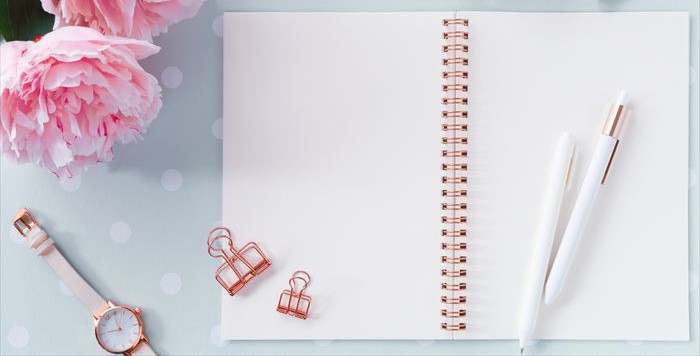
起業を考える人でも「やりたいことがはっきりしない」「自分に何ができるのかわからない」といった悩みにぶつかることは珍しくありません。
そのような時は、過去の経験やスキルを棚卸しすることで、自分に合った起業アイデアが具体的になります。
このページでは、失敗しにくいアイデアを見つけるための実践的な棚卸し方法を紹介します。
スキルや経験の棚卸しから起業アイデアに至るまでをワーク形式で実践的にまとめているので、起業ヒントを探している人はぜひ参考にしてください。
創業手帳は、「起業したいけど何をどう準備したらいいかわからない」という方むけの起業のための無料のガイドブックです。起業を成功へと導いてほしいため、資金繰りや税金の仕組みなど、経営者には把握しておいてほしいことをひとつにまとめた冊子となっています。ぜひこちらもご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
なぜ“棚卸し”が起業アイデアに役立つのか

自身の棚卸とは、起業の動機や過去の経験やスキル、得意なこと、好きなことを振返り分析することをいいます。
自分が持っている資源や能力を把握する作業であり、起業のファーストステップです。なぜ棚卸しが起業アイデアに役立つのかをまとめました。
再現性のある「強み」がわかる
棚卸しには、自分の「強み」を把握することによって、起業の軸を定める役割があります。
自分の強みや得意分野、価値観といった自分の本質的な特徴は起業するための軸となる部分です。
起業の軸がぶれると、他人の意見に惑わされたり、事業計画の一貫性が保てなかったりする危険があります。
自分自身と向き合うことによって、自分がどういった分野、業種、働き方で力を発揮できるかといった起業アイデアにつながっていきます。
「向いていないこと」も見えるようになる
棚卸しは、自分の得意なことを知るだけでなく、自分が苦手な領域ややりたくないことを可視化するのにも有効です。
自分でははっきりとそう感じていなくても、棚卸しの段階で不向きであると気が付くケースは頻繁に発生します。
向いていないことを無理に選ぶと、途中で挫折したりストレスが大きくなって事業に影響したりするかもしれません。
起業するまでよりも、起業してから継続することのほうが苦労をともないます。自分の適性や限界を知ることも、持続可能な起業のための大切なステップです。
好き・得意・経験を軸にすれば、継続しやすい
事業を継続するためには、「好き」「得意」「経験」がポイントです。
棚卸しによって「好き」「得意」「過去の経験」が重なる領域を見つけられれば、無理なく続けられるビジネスのテーマに出会える確率が高まります。
興味関心に根ざした事業は、モチベーションの熱量も高く意欲的に取り組めます。起業者の意欲は、事業の継続性や信頼性にもつながる重要なファクターです。
ステップ1:棚卸しする項目を整理しよう

自分の棚卸しは、頭の中で考え続けていてもなかなかまとまりません。ここからは棚卸しのための工程をひとつずつ紹介していきます。
実際に紙に書いたり、スマートフォンやパソコンに入力して整理してみてください。
① 経験した職種・業務内容
棚卸しの第一歩として、今までに経験した職種や業務内容を書き出します。できるだけ具体的にどういった業務に従事してきたのかを書いてみてください。
営業・接客・企画・事務などのカテゴリだけでは不十分です。
「どのような業務を、誰のために、どのような成果を出したか」まで整理すると今までの取り組んできた仕事の内容と自分の姿勢が明らかになっていきます。
② 学んだこと・身につけたスキル
学校や職場、独学で学んできた知識やスキルも棚卸しします。学んだことやスキルは、資格や技術だけではありません。
仕事に携わる中で身に着けた「プレゼンが得意」「資料作成が早い」など実務的な力も立派な武器です。
自分にとって当たり前でも、他人にとって価値あるスキルが眠っていることも多いので、些細なものであってもまずは思いついたものをどんどん書き出します。
自分の評価だけでなく人からいわれたことも参考にしてください。
③ 人からよく褒められること・頼まれること
自分の強みや特性は、自分自身では当たり前で気が付かないことがあります。自分の棚卸しの時には、人から褒められることや頼まれやすいことも整理してください。
他人の言葉には、自分では気づかない才能が隠れています。些細なことでも問題はありません。
例えば、「話を聞くのが上手」「説明がわかりやすい」「細かい気配りができる」などのほか、どのような時にお礼をいわれたか思い出してみます。
自分が意識せずに自然と評価されることには、起業する時の強みになるヒントが隠されています。
話を聞くのが上手であればコンサルタントや教育分野の適性があるかもしれません。細かい気配りやわかりやすい説明が得意な人はリーダー向きである可能性があります。
④ 趣味や夢中になれる活動
棚卸しは、自分にしかない特性を知って起業アイデアを生み出すために行います。時間を忘れるほど没頭できる活動や趣味には、ビジネスのヒントが眠っているかもしれません。
今まで趣味としか思っていなかったものでもビジネスにつながることがあります。
ゲーム、旅行、イラスト、DIY、読書といった趣味があるなら、それらを「教える」「共有する」「仲間を集める」などの形でサービス化できないかを考えてみてください。
趣味や夢中になれる活動のように情熱を軸にした起業は他人には生み出せない価値があります。起業した後も続けやすく、周囲からに共感されやすい点が魅力です。
ステップ2:強みや特性を言語化する

自分で棚卸しで出てきた経験・スキル・特徴は、そのままでは断片的でわかりにくいものです。
ここでは、それらの要素を「言葉」や「構造」として整理するための具体的な方法を紹介します。
① マトリクス法:強みを4象限に分類して整理する
マトリクス法では、2軸で強みを4象限に分類して整理する方法です。マトリクス法は現状分析や方向性の決定、起業アイデアの発想を引き出すために使われます。
起業時であれば「できること」「やりたいこと」「求められること」「競合と差別化できること」の4つで2軸として「意欲」と「強み」が設定できます。
「できること」かつ「やりたいこと」のゾーンの自分が価値を発揮できるゾーンであり理想的です。
やりたくなくてできないことはスキルもモチベーションもないため選択を避けてください。
ただし、今考えているビジネスが「できること」かつ「やりたいこと」のゾーンにうまくフィットするとは限りません。
そういった時には、自分ができることに目を向けた上で、事業のモチベーションを高めて最適なゾーンに変化しないか考えてみてください。
② 付箋&グルーピング:言葉を出しまくって可視化する
強みや特性は、できるだけ多くイメージするようにします。整理して書き出すのが難しければ付箋を使ってください。
まずは、質よりも量を重視して、言語化したものをどんどん増やしていきます。
思いついたスキルや経験、強みをすべて付箋に書き出したら、机に広げて「似ているもの」や「共通点」でグループ分けしてください。
それぞれのグループに名前やラベルを付けていくことで、ぼんやりしていた要素がまとまりある“テーマ”として見えてきます。
グループ同士の関係性も図解化し可能であれば意味やつながり、全体のストーリーを明確にしていくと強みや特性が可視化されていきます。
③ベン図(3つの円):自分に合ったビジネスの重なりを探す
ベン図とは、「できること(can)」「やりたいこと(will)」「求められること(must)」の3円を描いて重なりを視覚化したものです。
「できること(can)」は、自分だからできること、やりたいこと(will)は今後望むあり方や働き方、最後に求められること(must)では周囲に求められることを記載していきます。
この3つの円が重なり合うところが最もパフォーマンスを発揮しやすいと考えられ、自分のブランディングともいえます。
自分にしかできないサービスやポジションを発見するヒントを探すためにも有効な方法です。
④モーメント法:過去の成功・感謝された場面を書き出す
モーメント法のモーメントとは、「何かをしたいと思う瞬間」や「その瞬間の行動」を指す言葉になります。
モーメント法は、人生の中で「感謝された」「うまくいった」と思えた瞬間を思い出し、それに共通する自分の強みを抽出する方法です。
多くの分析では属性や性格から特徴を割り出そうとします。しかし、モーメント法では置かれた場面での行動からその人の強みを考えます。
「自分がどのような人間か」と考えるよりも「自分がどのような場面で成功したか」を洞察することで自分の価値観や求める働き方が見えてくるでしょう。
感情や実体験に基づいた強みは、起業後のブランディングにも活かせるかもしれません。
⑤強み診断ツールを使ってヒントを得る
自己理解をすすめるには、強み診断ツールも活用してみてください。
16Personalities、グッドポイント診断、ストレングスファインダーなどの診断は第三者視点での特性や価値観を把握できるツールです。
自分のアピールポイントは自分では気づきにくいものです。しかし、強み診断ツールであれば、自分では気づけない強みまで言語化してくれます。
強み診断ツールは無料で使えるものもたくさんあるので、自己理解のサポートに活用してください。
⑥ ChatGPTに棚卸し内容を入力してアイデアを広げる
強みや特性を言語化する時には、ChatGPTも役立ちます。例えば、「◯◯の経験があり、△△が得意です。
この強みを活かしたビジネスアイデアを提案してください」といった内容でAIに投げかけます。
ChatGPTは、提示したプロンプトに対して論理的な補足や新しい視点を打ち返してくれる優秀な相棒です。また、質問を繰り返せば、対話形式で内容を深掘りできます。
起業の前段階だけでなく、起業してからも思考の壁打ちにChatGPTは便利です。
自分の考えやアイデアを伝えてフィードバックを受けることによって新しい視点を得られるほかアイデアのブラッシュアップに活用できます。
ステップ3:棚卸し結果から起業アイデアに変換する方法

棚卸しの結果がまとまったら、いよいよ起業アイデアとして変換していきます。どのようにして起業アイデアにしていくのか、パターンごとにチェックしてください。
パターン①「今の仕事の一部を切り出してサービス化」
起業アイデアに変換する方法として、ある仕事の一部を切り出す方法があります。
現在の仕事の中で、自分が得意だったり評価されている部分を切り出し、個人で提供するサービスに変えてみる方法です。
この方法は、すでに実績があるため顧客からも信頼されやすく、自分でも慣れているためスタートしやすい形といえます。
起業アイデアに行き詰った時には、今の仕事の専門性が起業につながらないか一度検討してみてください。前職の経歴が起業後のブランディングにもなります。
パターン①事例
-
- 会社で営業資料をよく作っていたことから資料作成代行を開業
- SNS運用を任されていた人が中小企業向けSNS代行を請け負い
- 人事で採用面接をしていた人が面接対策コーチング、履歴書添削サービスをスタート
パターン②「過去の悩みや課題をビジネスに」
多くのビジネスが、事業者の個人的な悩みや課題から生まれています。
かつて自分が困っていたこと・悩んでいたことを思い出し、「その時の自分にどのようなサービスがあれば助かったか?」を考えてみてください。
自分が経験した悩みは多くの人が同じように感じています。
過去の悩みや課題から生まれたビジネスは共感されやすく、ユーザー視点に立ったリアルなサービス設計ができる点に強みがあります。
こうした過去の悩みや課題は、大きなものよりも誰でも感じているものである点が重要です。過去の心配も活用して、サービスや商品開発に役立ててください。
パターン②事例
-
- 育児中に孤独を感じた人がママ向け交流サービスを立ち上げ
- 留学中の孤独や情報不足に苦労したことから留学経験者とつながれるコミュニティ運営・相談窓口を開業
- 就職活動で自己分析がうまくいかなかった経験からキャリア支援オンライン講座を立ち上げ
パターン③「スキル×市場ニーズ」で新しい組み合わせを探す
起業では、自分が持っているスキルをどう生かすかを考えてください。
自分の強み(スキル・経験)と、今求められている社会的ニーズを掛け合わせることで、独自のポジションを築くことができます。
市場ニーズを知るには、トレンドや検索ニーズも活用します。どういったニーズがあるのかフックになるモノが見つかった時にはSNSも活用して生の声を集めてください。
パターン③事例
-
- 動画編集スキル × 地方企業のPRニーズから会社紹介やPRなど地方企業向けの動画制作サービス
- 語学力 × 海外展開を目指す中小企業から英語・中国語の多言語マーケティング・翻訳サポートの立ち上げ
- 保育・教育経験 × 子育て家庭の学習・交流ニーズから子ども向けオンライン講座と親の相談サロンの運営
まとめ|「自分の棚卸し」が起業の第一歩になる
起業は特別なアイデアがなければできないものではありません。大切なのは、「できること」から広げるようにしてスタートすることです。
自分の経験やスキルを振り返ることで、自分の強みや特性が棚卸できます。
無理なく継続できるビジネスを生み出すためにも、まずは「自分の棚卸し」からはじめてみてください。
起業を検討中の方はぜひ起業のための無料ガイドブック「創業手帳」をご活用ください。資金繰りや税金の仕組みなど、経営者には把握しておいてほしいことをひとつにまとめた冊子となっています。ぜひこちらもご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)