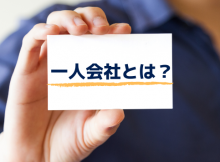開業届には提出期限はいつまで?出し忘れた時の対応策やペナルティ、デメリットなどを解説
開業届は出し忘れてもペナルティはないが出したほうがメリットが多い
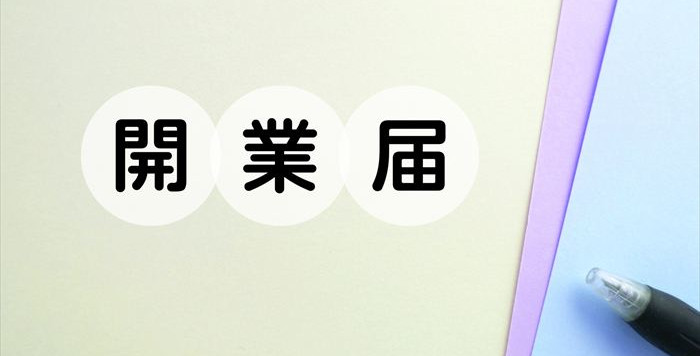
個人事業主として事業を開始するにあたり、開業届を税務署に提出しなければなりません。
開業届を出し忘れてもペナルティはありませんが、提出すれば青色申告ができ、所得控除を受けられます。
ほかにも、屋号付きの銀行口座が開設できたり小規模企業共済に加入できたりするなど、様々な魅力があります。
メリットを受けたいと考えているのなら開業届の提出を検討してください。
今回は、開業届の提出期限や出し忘れた場合のデメリットやリスクなどを解説していきます。
開業届を出し忘れた時の対応策についても紹介していくので、開業届に関する疑問を解決したい人は、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では、その他にも開業に必要なコトやモノ、資金の準備などについていつまでに必要なのかをわかりやすくまとめた「創業カレンダー」を無料でお配りしています。ぜひこちらもあわせてご活用ください。

この記事の目次
開業届の提出期限

開業届は、事業をスタートした日から1カ月以内の提出が所得税法第229条によって定められています。
ただし、提出期限が土曜日や日曜日、祝日であれば、その翌日が期限です。開業届を出す際には、事前に日にちや曜日を確認してから提出するようにしてください。
なお、中には「開業前に出せばいいのでは」と考える人もいるかもしれませんが、開業届は事業を始めたことを申告する書類であるため、開業前に提出することはできません。
事業が始まったばかりで収入を得られていない状態でも問題なく提出できます。
開業届を出し忘れた場合のペナルティ・罰則

事業をスタートさせた日から開業届を1カ月以内に提出できなかった場合や、出し忘れていた場合でも、ペナルティや罰則は特にありません。
ただし、青色申告が選択できないといったデメリットはあります。
なお、確定申告を忘れた場合にはペナルティがあるので注意してください。
無申告加算税や延滞税、重加算税といったペナルティが課される可能性があります。
また、悪質な脱税行為とみなされれば5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されるリスクがあります。
開業届を出し忘れたとしても、確定申告は忘れないようにしてください。
開業届を出し忘れた場合のデメリット・リスク

開業届を出し忘れてしまうと、様々なリスクがあります。
具体的なデメリットを解説していくので、開業届の提出について悩んでいる人はぜひ参考にしてください。
青色申告ができなくなる
開業届を出し忘れたことによって、青色申告ができないデメリットがあります。
青色申告とは、税務署が定めている方法で正しい記帳を行うことで、事業を営む人が様々な税務上のメリットを得られる制度です。
最大のメリットは、青色申告特別控除として最大で65万円を所得から控除でき、その分納める税金を抑えられることです。
また、赤字を最長で3年もの間繰り越しができるので、黒字になった年の税金を抑えられるメリットもあります。
ただし、青色申告のメリットを受けるためには、税務署に事前に申請をして承認を受けなければいけません。
申請では開業届を提出していることが前提となるため、開業届を出さなければ青色申告承認申請書は受け付けてもらえないことに注意してください。
屋号で銀行口座の開設ができない
銀行口座の開設を屋号でできない点もデメリットのひとつです。
個人事業主が銀行で事業用口座を開設する場合、口座名義には個人名が使用されます。しかし、個人名であればプライベート用の口座と間違える恐れがあります。
これまで使用していた口座を事業用として使う場合には、プライベートと事業用でお金を分けて管理する必要があり、手間が増えてしまうかもしれません。
一方、屋号の銀行口座があれば、事業でのお金の動きや経費も簡単に把握できます。
なお、銀行では個人名に屋号を付け加えた口座を開設できますが、その場合は開業届の控えを求められるケースが多いです。
開業届を提出していなければ、屋号での口座開設ができないケースがあることに注意してください。
創業融資が受けられない可能性がある
自治体によっては、起業を促すために創業を考える個人向けに融資を用意しているケースも多いです。
創業融資は、創業して間もない人を対象にしており、起業の実績がない人でも融資を受けられます。
金利が低いといったメリットがあり、返済の負担を抑えられる点が魅力です。
しかし、創業した証拠が必要で、開業届の控えの提出を求められるケースも少なくありません。
創業融資を受けたいのであれば、忘れずに開業届を提出してください。
小規模企業共済に加入できない
フリーランスや小規模企業の経営者を対象にした退職金制度が小規模企業共済です。企業から退職金をもらえない経営者が掛け金を積み立てて将来に備えられます。
また、毎月の掛け金が全額所得控除になるので、活用すればメリットを受けられます。
しかし、小規模企業共済に加入するためには確定申告書の写しが必要です。
事業をスタートしたばかりで確定申告を行っていなければ、開業届の写しを提出しなければいけません。
開業届を出し忘れた際には、確定申告を終えるまで小規模企業共済に加入できないことに注意してください。
補助金・助成金の申請ができない
国や自治体による補助金や助成金を活用できるケースもあります。その場合、申請をする際には開業届の写しが必要になるケースも多いです。
開業届を出していなければ補助金や助成金の申請ができず、資金調達できない可能性もあります。
事業継続に影響を与える可能性もあるため、先行きに不安がある場合や先を見越してリスクを回避したい場合には、開業届の提出を考えて忘れず提出するようにしてください。
開業届を出し忘れた時の対応策
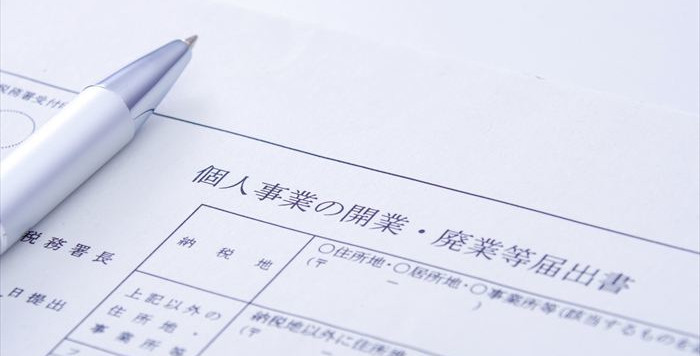
開業届は原則として開業した日から1カ月以内の提出が必要ですが、出し忘れてしまう人もいるかもしれません。気が付いたらすぐに開業届を提出してください。
また、確実に開業届を提出できたか不安になることもあるでしょう。その場合には、控えの有無を確認してみてください。
税務署に直接提出した場合は、提出した日に控えを受け取っているはずです。郵送で提出した場合には、提出した日からおおよそ1週間程度で控えが返送されます。
ただし、e-Taxで提出した場合には、控えは発行されません。受理された日に受診通知が届いており、これが控えの代わりとなります。
なお、控えを紛失した場合は、税務署で再発行することも可能です。
個人情報開示請求の手続きを実施し、開示の決定通知を受け取ったら開業届の控え受け取り方法を提出します。
控えを受け取るためには、おおよそ2週間から1カ月程度かかるので、すぐに控えを受け取りたいのであれば早めに申請してください。
開業届の情報を閲覧するだけであれば、申告書等閲覧サービスの活用もおすすめです。税務署の窓口で申告書等閲覧申請書類を提出することで許可を取得できます。
確定申告への影響について
開業届を出し忘れた場合には青色申告できず、確定申告に影響が生じます。開業届を出し忘れたら青色申告ができず、その年度は特別控除が使えなくなります。
青色申告の提出期限は以下の通りです。
| 開業日 | 青色申告承認申請書の提出期限 |
|---|---|
| 1月1日~1月15日 | 3月15日 |
| 1月16日以降 | 開業から2カ月以内 |
上記の期限を過ぎれば、その年度の確定申告では青色申告ができなくなります。
白色申告で確定申告する場合には青色申告によるメリットを受けられないため、提出期限には注意してください。
なお、事業を開始してから一定期間が経ち、ある時から青色申告したいと考える人もいるかもしれません。
その場合、開業届を提出すれば青色申告することが可能です。
開業届は過去に遡って提出できます。期限を過ぎても正しい開業日を記して提出すれば受理してもらうことが可能です。
開業届の出し方

ここからは、開業届の出し方を解説していきます。
1.開業日を決める
届け出をするためには、まず開業日を決めなければいけません。開業日の決め方にはルールはなく、自分の好きな日にちを設定できます。
例えば、以下のような日を開業日として設定できます。
-
- お店をオープンさせた日
- 初めて仕入れをした日
- 初めて売上を立てられた日
- 広告宣伝を始めた日
- 縁起の良い日
2.開業届を入手する
開業届は、税務署で直接受け取ったり、国税庁の公式ホームページからダウンロードしたりすることが可能です。
国税庁のホームページには書き方も掲載されています。記入方法がわからない場合は参考にしてみてください。
3.必要書類を用意する
届出書に記入をする際には、マイナンバーや事務所の住所がわかる書類、開業日がわかる書類などをあらかじめ用意しておくとスムーズに記入できます。
税務署に持参をして提出する場合には、なりすまし防止のためにも本人確認書類を提出しなければいけません。
マイナンバーカードや運転免許証といった写真付きの身分証明書を用意してください。
開業届への押印は不要ですが、書類に間違いがあった際には訂正印が求められるので、印鑑を用意しておくと安心です。
また、郵送で提出する場合には返信用封筒と返信用切手も必要です。
あらかじめ用意してから記入するとスムーズに提出できます。
4.開業届を提出する
開業届は「窓口」「郵送」「e-Tax」と3種類の提出方法があります。
窓口での提出であれば税務署に足を運ぶ手間がかかりますが、不明点を職員に直接質問できます。また、控えもすぐに受け取ることが可能です。
一方、税務署が開いている時間帯に届け出ができない人や行くのが面倒な人は、郵送での提出を検討してみてください。
控えを受け取るための返信用封筒と切手を用意して提出します。
e-Taxを活用したオンラインでの提出も可能です。自宅にいながら提出を行えるので便利です。
開業届を出す前に理解すべきポイント

最後に、開業届を出す際に気を付けるべき点について解説していきます。
基本手当は受給できなくなる
開業届を提出すると、基本手当を受給できなくなります。基本手当とは、一般的に失業手当と呼ばれているものです。
受給要件を満たしていれば、失業中の生活の安定を図ることや求職活動をしやすくすることを目的に手当てが支給されます。
一方、開業届を提出すれば仕事を開始したことになるため、基本手当は受け取れなくなります。
例え開業をして収入が得られない状態となっても手当を受給できないことに注意してください。
なお、基本手当を受け取るために事業開始を遅らせたとしても、遅れることで事業のチャンスを逃す可能性があります。
十分な備えをしてから開業届を提出するよう心掛けてください。
開業届は取り下げができる
開業届を提出したあとに、諸事情によって事業がスタートできなくなるケースもあります。その場合は、提出を取り下げることも可能です。
ただし、正式な手続き方法はなく、「撤回書」や「取下書」を自分で作成して税務署で処理してもらうことになります。
提出した日や提出した届出名、撤回する理由などを記さなければなりません。
イレギュラーなケースであるため、あらかじめ税務署に相談してから提出するようにしてください。
開業日は偽らずに記載する
青色申告には期限があります。事業を進める中で「青色申告をしたい」と考える人もいるでしょう。
その場合、開業届を提出して2カ月以内であれば問題なく青色申告をすることが可能です。
しかし、開業日を実際よりも後の日にちにして開業届を提出すると不正行為になります。虚偽申請が発覚すれば、青色申請は取消されます。
その後数年間、青色申告の承認が受けられなくなるリスクがあることに注意してください。
まとめ・開業届の提出方法を理解して提出しよう
開業届には1カ月の提出期限がありますが、出し忘れても問題はありません。
しかし、青色申告ができなくなったり、屋号での銀行口座開設ができなかったりします。
また、小規模企業共済に加入できないなどのデメリットやリスクがあることに注意が必要です。
開業届を忘れずに提出するためにも、届け出の仕方や用意すべき書類を事前に理解しておくことが大切です。
創業手帳では、その他にも開業に必要なコトやモノ、資金の準備などについていつまでに必要なのかをわかりやすくまとめた「創業カレンダー」を無料でお配りしています。起業予定日から前後1ヶ月のタスクがカレンダー形式でまとまっているので、ぜひこちらもあわせてご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)