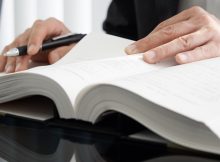家族は役員・従業員のどちらにすべき?それぞれのメリットや違いについて解説!
役員・従業員それぞれにメリットがある

経営者や個人事業主の中には、配偶者に経理や事務作業を担ってもらったり、家族全員で事業を手掛けたりするケースがあります。
この場合、家族に役員もしくは従業員として働いてもらうことになりますが、役員と従業員ではどのような違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、家族を役員・従業員にする場合の違いからそれぞれのメリット・注意点について紹介します。
家族を役員にするか、それとも従業員にするべきかを悩んでいる経営者・個人事業主は、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
家族を役員・従業員にする場合の違い

家族を役員・従業員にする場合、大きく異なってくるのが以下の3点です。それぞれの違いについて詳しく解説していきます。
契約形態の違い
役員と従業員の違いとしてまず挙げられるのは、契約形態の違いです。通常、従業員は会社と雇用契約を結ぶことになりますが、役員は委任契約を結んでいます。
雇用契約は雇用する側(会社)と雇用される側(従業員)の間に主従関係があり、労働基準法・就業規則などに基づいて働くことになります。
一方、役員の委任契約は株主総会の決議によって選任され、会社からの委任で就任する形となるため、主従関係はなく業務上の指揮命令がなくても業務遂行にあたることができます。
また、従業員の場合は時間に応じて給与が発生することから、勤務時間が確認できる出勤簿が必要です。
役員の場合は会社への貢献度がどれくらいあるのかによって報酬が発生しており、議事録にも登記されています。
給与・報酬の違い
従業員への給与は労働の対価として支払うことから、損金として認められ経費として計上することが可能です。
また、従業員に対する厚生年金や中退金なども「人事厚生費」として計上できます。
ただし、家族が従業員になる場合、ほかの従業員と同じくらいの金額にする必要があります。
一方、役員に支払う報酬は年度を通じて金額が一定であり、増額・減額するためには株主総会での決議が必要です。
役員報酬に関しても損金として計上することは可能ですが、一定の条件を満たす支払い方法が必要となります。
定額同額給与とは?
損金として計上させるためには、定額同額給与で役員報酬を支払うことになります。定額同額給与とは、役員に1カ月以下の頻度で報酬を支払う制度です。
月給と同程度のペースで、なおかつ毎回同額を支払うことになるため、給与と一見変わらないように見えるかもしれません。
しかし、定額同額給与はあくまで役員報酬の支払い方法であるため、金額は株主総会によって事前に決められています。
なお、定額同額給与以外に利益連動給与も損金での計上が認められていますが、上場企業のみを対象とした制度となるため、未上場の企業や中小企業における役員報酬は定額同額給与が採用されています。
賞与や退職金の違い
賞与は、従業員の場合だと給与と同様に経費として計上できますが、役員の場合は事前確定届出給与に当てはまるよう支払わないと計上できません。
また、退職金に関しては従業員だと就業規則・労働協定などに則って勤続年数に応じた金額が支給されるものです。
しかし、役員の退職金は「退職慰労金」と呼ばれるもので、株主総会などの決議がなければ支給されません。
社内規定に退職慰労金に関する指定基準を設ける場合にも、株主などに認められていなければ受け取れなくなるので注意が必要です。
事前確定届出給与とは?
事前確定届出給与とは、所定の時期に決まった金額を支払うことを定めた上で、事前に税務署へ届け出を出すことで損金計上ができるようになる制度です。
事前確定届出給与を活用するためには、国税庁のホームページまたは税務署から届出書と付表を準備して、議事録と共に所轄の税務署に提出する必要があります。
税務署へ提出する期限は、事前確定届出給与を定める株主総会などの決議を行った日または職務を開始した日から1カ月以内、会計期間(事業年度)が開始した日から4カ月以内のいずれか早いほうです。
新しく会社を設立した場合は設立した日から2カ月以内が期限となります。事前確定届出給与を活用したい場合は、提出期限を守るように早めに書類を提出してください。
家族を役員にした場合のメリット

家族を役員にすることで様々なメリットが得られます。ここでは、役員にした場合のメリット、4つを紹介します。
所得税を節税できる
家族を役員にすると、所得税を節約できるようになります。日本の所得税は累進課税が適用されており、収入が多ければ多いほど所得税率も高いです。
経営者ひとりに収入が集中してしまうと、それだけ納める所得税も増えてしまいます。
しかし、家族を役員にすることで収入を分配できるようになり、一人ひとりの収入を抑えられるため、所得税の負担軽減につながるのです。
収入を分配することによって社会保険料の負担は増えてしまいますが、高額な所得税を納めるよりも節税効果が期待できます。
将来の年金額も増えるため、家族を役員にするメリットは大きいといえるでしょう。
社会保険に加入できる
社会保険の加入条件を満たしていれば、社会保険に加入することも可能です。社会保険に加入すれば医療保険や年金などでメリットが得られます。
例えば配偶者に役員報酬を支払った場合、年間130万円以上の報酬を支払っていると厚生年金への加入が認められます。
扶養されている配偶者は第3号被保険者に該当するため、通常は国民年金のみを受け取ることになりますが、厚生年金に加入していれば国民年金に厚生年金が上乗せされ、老後資金を増やすことも可能です。
妥当性が認められれば高額な報酬も支払える
役員報酬は株主総会などの決議で決めることになりますが、金額自体は自由に設定することが可能です。
つまり、妥当性さえ認められれば高額な報酬を支払っても問題ありません。妥当性は、税務調査で不当に支払い過ぎていないか判断されます。
実務に見合っていれば高額でも良いですが、そうでない場合は税務調査で指摘される可能性が高いので注意が必要です。
相続税・贈与税の対策にもなり得る
家族を役員にすると、相続税・贈与税の対策にもなり得ます。例えば家族に資産を役員報酬として支払うことで、あらかじめ資産を減らしておくことができます。
相続税は資産を相続する際に課されるため、資産が減ることで相続税の負担を軽減できるはずです。
また、贈与税の場合、年間110万円の基礎控除内なら税金は課されないものの、役員報酬なら年間110万円以上を家族に渡すこともできます。
早いうちから相続税・贈与税対策を行っておきたい場合は、役員報酬を活用するのがおすすめです。
家族を役員にする際の注意点

家族を役員にする場合、注意すべきポイントもあります。どのようなことに気を付ければ良いのか、解説していきます。
勤務実態の記録や取締役会に参加する必要がある
家族が役員となった場合、勤務実態の記録や取締役会への参加が必要です。
役員は会社の取締役や監査役、会計参与などの役職であり、会社の事業方針を定める重要な役割を担います。
役員報酬を支払う際に、その報酬に見合った働きを行ったかどうかも税務調査などで調べられる可能性があるため、家族を役員にした場合でも勤務実態の記録や取締役会への参加は必要です。
ほかの従業員との不公平感が生まれやすい
家族が役員になると、家族経営の企業というイメージが付きやすくなります。
家族経営に対してあまり良いイメージを持っていない人も多く、ほかの従業員との不公平感が生まれやすいです。
特に努力もせず役員として高額な報酬を受け取っていた場合、ほかの従業員の労働意欲も低下して人間関係がさらに悪化する可能性が高いです。
家族を役員にしてもほかの従業員との不公平感が生まれないように、役員への報酬制度を透明性のあるものにしていく必要があります。
役員報酬を年度途中で変更するのは難しい
役員報酬は原則事業年度の途中で変更するのは難しいとされています。
そのため、例えば経営状況が悪化してしまった場合でも、決議された報酬額を支払わなくてはなりません。
財務的に臨機応変な対応ができないのは、デメリットといえます。
経営状況を見て、どうしても役員報酬を減額しなくてはいけないという場合には、年度途中での変更が例外として認められるケースもありますが、基本的には変更できないものと考えておいてください。
副業規定の制約で禁止されている可能性がある
家族が別の会社で働きつつ、自社の役員も務めるといった場合には、もともと働いていた会社の副業規定を確認する必要があります。
これは、副業規定によって家族の会社で役員になることを禁止しているケースもあるためです。
ただし、ほかの会社と雇用契約を結ぶのはNGでも役員のような委任契約であれば問題ないという会社もあるため、必ずしも禁止されているわけではありません。
事前に就業規則を確かめてから、家族を役員にするかどうかを決めるようにしてください。
家族を従業員にした場合のメリット

家族を会社の従業員として働いてもらう場合には、どのようなメリットがあるのでしょう。ここでは、従業員にした場合のメリットを紹介します。
年度途中で給与額の変更や賞与の支給ができる
役員の場合は年度途中で給与額を変更したり、賞与の支給について決定したりすることはできません。
従業員にした場合は年度の途中でも関係なく、給与額の変更や賞与の支給が行えます。
ただし、給与額の変更や賞与の支給ができるからといっても、不当に高額な給与・賞与を渡すことはできないので注意してください。
家族従業員の給与を経費計上できる
家族を従業員として雇用した場合、給与は全額経費計上することが可能となります。全額経費として計上できれば、所得税の負担軽減につながります。
また、1年間の給与から差し引かれる「給与所得控除」によって、家族一人ひとりの税負担を抑えることも可能です。
経営者の所得を家族に分散すれば、家族全員で税額を抑えやすくなるため、節税効果が期待できます。
経営理念が浸透しやすい
家族が従業員として事業をサポートしてくれる場合のメリットとして挙げられるのは、税負担の軽減だけでなく経営理念が浸透しやすい点です。
経営者との接点が多い家族が従業員となることで、経営者が掲げる思想・理念も日々共有でき、事業にも一貫性が出やすくなります。
また、家族が従業員の場合は退職するリスクも少なく、突然従業員が辞めてしまい人手不足に陥ってしまうこともほとんどありません。
家族を従業員にする際の注意点

家族を役員ではなく従業員とした場合、メリットだけでなく注意しなくてはならない点もあります。具体的にどのような注意点があるのか、事前に確認しておくことが大切です。
ほかの従業員と同様に勤務実態の記録が必要
いくら家族だったとしても、従業員として雇用する場合にはほかの従業員と同様に仕事をこなす必要があります。
もし従業員であるにも関わらず勤務実態がないと判断されてしまった場合には、これまで家族に支払ってきた給与が損金算入できなくなってしまう恐れもあるので注意が必要です。
あらかじめ業務内容は決定しておき、勤務実態を普段から記録しておくようにしてください。
みなし役員に認定されないようにする
家族を従業員として雇用しているにも関わらず、経営に関与しているなど役員と同じような扱いと判断された場合には、「みなし役員」に認定される可能性があります。
みなし役員は雇用契約を結んでいて本来は従業員となるものの、税法上では役員として扱われてしまいます。
つまり、従業員のメリットで紹介した給与・賞与の経費計上が認められなくなるので注意が必要です。
みなし役員と認定されてしまう「経営への関与」は、事業を運営していく上で重要な事柄の意思決定に関与していることが挙げられます。
具体的には以下の意思決定に参加していればみなし役員と認定される可能性が高いです。
-
- 売上や仕入価額の決定・変更
- 主要取引先の選定
- 重要な契約に関する決定
- 資金調達の実行・返済
- 採用や昇格・退職の決定
- 取締役会への参加と発言
まとめ・役員と従業員の違いを理解した上でどちらが適切か検討しよう
今回は、家族を役員・従業員にする場合の違いやメリット、注意点について紹介してきました。
役員と従業員は契約形態から異なっており、それぞれ給与や賞与、退職金などにも違いがあります。
それぞれにメリットや注意すべきポイントがあることから、役員と従業員の違いを理解した上で、どちらがより適切なのかを検討することが大切です。
創業手帳(冊子版)では、中小企業の経営者や個人事業主にとって役立つ情報をお届けしています。経営に関する最新のトレンド情報なども紹介しているので、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)