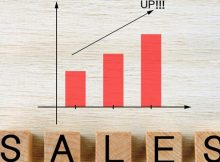バイラルマーケティングとは?ステマとの違いやメリット、成功させるコツをご紹介
バイラルマーケティングは低コストで広範囲にわたる効果が期待できる

商品・サービスの売上げ向上や、ブランドの認知度拡大などを目的とするマーケティング手法は多岐にわたります。
自社に適したマーケティング戦略を構築する中で、少しでもコストを抑えたいと考える人も多いかもしれません。
低コストに抑えつつ自社の認知を拡大させる方法として、「バイラルマーケティング」があります。
今回は、バイラルマーケティングの特徴やステマとの違いをはじめ、メリット・デメリットを解説します。
バイラルマーケティングを実践して成功するためのコツも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
バイラルマーケティングとは?

バイラルマーケティングはWebマーケティング手法のひとつで、インターネットやメールを活用し、口コミを使って多くの人に拡散させていく方法です。
「バイラル」とはVirus(ウイルス)の派生語であり、ウイルスのように拡大していくという意味があります。
XやInstagramなどのSNSで自社の商品やサービスに関する魅力的な投稿が広く拡散されれば、多くのユーザーに認知してもらえるようになります。
Web広告とは異なり、バイラルマーケティングは消費者のつながりを活用した手法で、一方的な宣伝になりにくいのが大きな特徴です。
ステルスマーケティング(ステマ)との違い
ステルスマーケティング(ステマ)とは、口コミを活用して売上げにつなげるマーケティング手法です。
バイラルマーケティングと似ているものの、企業が情報の拡散に介入しているかどうかが違いです。
ステルスマーケティングでは、好意的な口コミを発信するために企業が消費者を装い情報の拡散に介入しています。
一方のバイラルマーケティングも、商品・サービスに付加価値をつけたり、魅力的なコンテンツを作成したりしますが、情報を拡散するかどうかは消費者が決めます。
バズマーケティングとの違い
バズマーケティングも口コミを活用して、消費者に情報を拡散してもらう手法です。企業がコンテンツをバズらせることで注目を集め、口コミにより情報を広く拡散します。
バズマーケティングでは、バズらせるためにインフルエンサーや有名人を採用する手法をはじめ、SNSを活用したプレゼントキャンペーンや、ハッシュタグキャンペーンなどのイベントを実施する手法などが一般的です。
これらの手法では情報を拡散させるために企業が介入する点が、バイラルマーケティングとは異なります。
バイラルマーケティングが注目された背景

バイラルマーケティングは、アメリカのDFJというベンチャーキャピタルがHotmailのマーケティング戦略について説明する際に活用した言葉とされています。
Hotmailを普及させるために、すべてのメールに「Get your own free Hotmail at www.hotmail.com」という一文を加えました。
その結果、ユーザー数はわずか1年で2万人から100万人まで増やすことに成功しています。
Hotmailは拡散される仕組みをつくったものの、実際に情報を拡散したのはHotmailを使用するユーザーです。
こうした成功事例や、ステルスマーケティングの問題が広く知られるようになったことから、企業が情報の拡散に介入しないバイラルマーケティングに注目が集まりました。
バイラルマーケティングによるメリット

ここからは、バイラルマーケティングによるメリットを紹介します。
低コストに抑えられる
バイラルマーケティングのメリットとして、低コストに抑えられる点が挙げられます。
商品・サービスやブランドの認知拡大を図るために広告の出稿が活用されてきましたが、広告の制作から出稿に至るまでにはある程度のコストがかかっていました。
特に、テレビCMや新聞広告などのマスメディアで広告を出稿するためには、莫大な広告費用をかける必要があります。
しかし、バイラルマーケティングなら、拡散性の高いSNSを活用して不特定多数のユーザーに情報を発信できます。
SNSは無料でアカウントを作成できるため、広告にかかる費用を大幅にカットすることも可能です。
潜在層にもアプローチできる
バイラルマーケティングは広く情報を拡散できることから、潜在層へのアプローチにもつなげることが可能です。
また、これまでターゲットとして予測できていなかった層にもアプローチできる可能性があります。
ターゲットとして予測できていなかった層から意外な需要を見出せるため、さらなる需要の拡大や売上げ増加にも効果が期待できます。
ブランドの認知度拡大が期待できる
バイラルマーケティングの活用によって、短期間の施策であってもブランドの認知度拡大に効果が期待できます。
ブランドに関する有益なコンテンツが拡大すれば、ブランドの存在も急速に広まっていくでしょう。
また、フォローしているユーザーから情報が拡散されれば、消費者からの信頼性も得やすくなります。
ブランドに対するポジティブな認知であれば、消費者と信頼関係を構築することが可能です。
広告よりも消費者の興味を引きやすい
ユーザーの中には、広告に対してあまり良いイメージを持っていない人も少なくありません。
SNSのタイムラインに広告が何度も表示されたり、Webサイトを閲覧する際に邪魔になるほど大きなバナーが表示されたりすれば、ユーザーに悪いイメージを与えてしまう可能性があります。
しかし、バイラルマーケティングは信頼できるフォロワーからの情報であるため、信頼しやすく、広告に良いイメージを持っていないユーザーにも効果的なアプローチが可能です。
長期的な効果が見込める
バイラルマーケティングは瞬間的に注目を集める手法ではなく、長期的に効果を生み出せます。SNSなどで拡散された情報は、長期間にわたって残り続けることが理由です。
一定の時間が経過したとしても、より印象的な情報であればブランドに対して良いイメージを長く持ってもらうことも可能です。
長期的なマーケティング施策や戦略にも活躍する手法といえます。
バイラルマーケティングのデメリット

バイラルマーケティングには様々なメリットがありますが、デメリットになってしまう部分もあることに注意が必要です。
ここからは、バイラルマーケティングのデメリットを紹介します。
悪いイメージが広がる恐れがある
企業として拡散したくなるような魅力的なコンテンツを発信したと思っていても、予期せぬことで悪いイメージにつながってしまうことがあるかもしれません。
そうなれば、ブランドイメージを損なってしまう恐れがあります。
また、情報の拡散に介入できないためコントロールできず、そのまま悪いイメージが多くのユーザーに広まる可能性もあります。
誤って悪いイメージを広げないために、内容を慎重に検討し、誤解を招かないコンテンツ作成を行わなければなりません。
効果の測定をしにくい
バイラルマーケティングは従来の広告とは異なり、正確に効果を測定するのが困難です。
1件の投稿に対してどれだけの人の目に入ったかなどは確認できるものの、投稿が売上げに与える影響はわかりません。
利益に関する効果を測定するなら、SNSの投稿から自社サイトに誘導し、CTAボタンを設置するなどの対策が必要です。
なお、バイラルマーケティングの効果測定に用いられる指標として、「シェア数」「いいね数」「コメント数」などが挙げられます。
仕組み化が難しい
バイラルマーケティングで成功できたとしても仕組み化をするのは難しく、再現性が低ければ、再びバイラルマーケティングを成功させるまで時間と手間がかかる可能性があります。
仕組み化が難しい理由として、情報を広く拡散するために偶発的な要素が必要になることが挙げられます。
バイラルマーケティングを成功させるために、毎回戦略を構築し直さなくてはならないため、労力が必要です。
バイラルマーケティングの主な手法

実際にバイラルマーケティングを行うためには、主に3つの手法から選ばなければなりません。主な手法とその特徴は以下のとおりです。
1次的バイラルマーケティング
1次的バイラルマーケティングは、ユーザーから自発的に口コミを拡散してもらう手法です。
ユーザーにとって魅力的なコンテンツを投稿することで、その投稿を見たユーザーがほかの人にも共有し拡散されていきます。
あくまでユーザーが自発的に拡散していることから、強制感がなく、自然に自社の商品・サービスやブランドに対する認知度が向上します。
ただし、1次的バイラルマーケティングで成功するためには、ユーザーがほかの人にも共有したくなるような、魅力的かつインパクトのあるコンテンツを作成しなければなりません。
2次的バイラルマーケティング
2次的バイラルマーケティングとは、コンテンツを共有したユーザーに対して特典やインセンティブを提供する手法です。
友達を紹介することで割引が受けられるキャンペーンなどは、2次的バイラルマーケティングに該当します。
新商品の発売や飲食店で多く活用される手法ですが、1次的なものとは異なり、過度に活用すると強制感が出てしまうことに注意が必要です。
紹介埋め込み
紹介埋め込みとは、サービスを利用することで、宣伝も同時に表示される手法です。
メールやアプリなどで活用される手法であり、サービスを利用するたびに自動で広告が表示・挿入されるため、ユーザーがサービスを利用するほど宣伝効果が高まっていきます。
ユーザーに対して自然的な拡散が期待できるものの、過度な宣伝はユーザー体験が損なわれる恐れもあるため注意が必要です。
バイラルマーケティングを成功させるコツ

ここからは、バイラルマーケティングを成功させるためのコツを紹介します。
目的・ターゲットを明確化する
魅力的なコンテンツ・投稿を広く拡散してもらうためには、ユーザーが「ほかの人にも共有したい」「教えたい」と思えるようなコンテンツにしなくてはなりません。
共感性の高いコンテンツを作成するためには、マーケティングにおける目的やターゲットを明確にする必要があります。
不特定多数のユーザーに情報が拡散されるように、選定したターゲットに確実に届くコンテンツを作成してください。
法的に問題はないか確認する
2023年10月から、ステルスマーケティングは景品表示法違反となり、規制されるようになりました。ユーザーが広告と認識できない表現は違法です。
バイラルマーケティングは情報の拡散に介入しないものの、広告・マーケティングの一種であることから、投稿に対して広告であることを明記しなくてはなりません。
コンテンツの内容や表現などが法的に問題ないか、慎重に確認した上で投稿してください。
質の高いコンテンツをつくる
ユーザーが自発的にほかの人にも共有したくなるコンテンツを作成することは、バイラルマーケティングにおいて特に重要な要素となります。
これまで見たことがないほど独創的なものをはじめ、多くの人に共感してもらえる内容や自分もやってみたいと思える方法の紹介などは拡散されやすいです。
質の高いコンテンツをつくれるように、コンテンツ制作をプロに外注することも検討してみてください。
目的や状況に適した手法・メディアを選択する
多くのユーザーにとって魅力的なコンテンツを作成できたとしても、ターゲット層の利用が少ないメディアに投稿しても効果は低くなってしまいます。
そのため、目的や状況に適したメディアを選択することも重要です。
マーケティングの目的やターゲットの属性なども考慮して、最適な手法・メディアを選んでください。
ユーザーが共有しやすい体制にする
バイラルマーケティングは企業側ができることとして魅力的なコンテンツを作成することが挙げられますが、ユーザーが共有しやすい体制を構築することで、拡散されやすい状況をつくり出すこともできます。
Webページを制作した際に、ページを閲覧した人が拡散しやすくなるように各SNSの共有ボタンを設置することが一例です。
共有ボタンの設置によって、共有までのアクションが簡略化され、情報を拡散してもらいやすくなります。
まとめ・バイラルマーケティングを活用して認知度向上や新規顧客の獲得を目指そう
バイラルマーケティングはほかの手法と比べてコストを抑えつつ、高い宣伝効果も期待できる手法です。
ユーザーによる自発的な拡散によって情報が広がっていくため、広告のような宣伝感や強制感が薄まります。
バイラルマーケティングをうまく取り入れて、認知度の向上や潜在層へのアプローチによる新規顧客の獲得を目指してください。
創業手帳(冊子版)は、バイラルマーケティングを含む様々なマーケティング手法について紹介しています。経営面に加え、自社に最適なマーケティング戦略を構築したい人もぜひお役立てください。
またSNSを活用したマーケティングについては「SNS運用ガイド」もあわせてお読みいただくと、新規顧客の獲得を更に拡大させるヒントがあると思います。どちらも無料でお配りしていますので、ぜひご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)