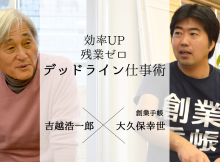定年後に始める農業ビジネス入門|未経験からでも可能な始め方をステップごと紹介
定年後の農業ビジネスで健康的に収入を得よう!

定年後に農業ビジネスを始める人が増えています。自然と触れ合いながら、新たな収入源や生きがいを見つけたい人にとって魅力的な選択肢です。
本記事では、定年後の農業ビジネスの始め方や注意点、成功のポイントを初心者向けにわかりやすく解説します。
新たなる道でビジネスを始めようとしている方はぜひ一度『創業手帳』をお読みください。ビジネスを始める上で最低限知っておいてもらいたい知識がここに満載です。無料でお取り寄せ可能です。
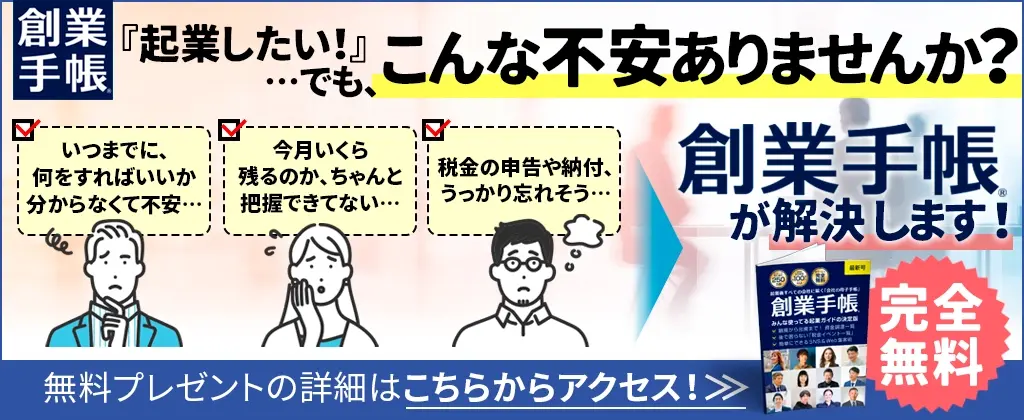
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
定年後に農業ビジネスを始める魅力とは?

定年をきっかけに新しくビジネスを始めようと考えた時、どのようなビジネスを始めるか悩みますが、農業ビジネスに注目する人は多いです。
定年後に農業ビジネスを始めるのに、どのような魅力があるのでしょうか。
自然と触れ合うライフスタイル
会社勤務だった人にとって、新たに農業ビジネスを始めると自然と触れ合う機会が増えます。
自然はストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾール」の量を低くしてくれたり、体内の免疫システムを強化したりするなど、様々な効果が期待できます。
自然と共に暮らす新たな生き方として農業ビジネスを取り入れれば、心のリフレッシュにもつながるでしょう。
生涯現役で収入を得られる
定年を迎えると、生活費は年金や退職金、これまでに貯めてきた貯金を崩して生活することになります。
しかし、年金や貯金などが心もとないと、老後生活への不安も大きくなるはずです。
農業ビジネスなら生涯現役で収入を得られるようになります。年金とは別に副収入を得られれば安心感にもつながります。
農業ビジネスといっても大規模に始める必要はありません。まずは貸農園や自宅の畑で「週末だけ」「朝だけ」活動するのがおすすめです。
採れた野菜は直売所などを活用することで、収入につなげられます。
地域との交流が広がる
農業によって地域の人との交流も増えます。
例えば、自宅の畑で作った野菜を地元の直売所に出荷したり、地元で開催されているイベントに出店したりすると、いろいろな人との交流が生まれるようになります。
場合によっては新たに顔なじみの人ができたり、友人が増えたりするかもしれません。
定年後は家にいることも増えてしまい、社会的孤立につながるリスクも高いですが、農業ビジネスを通じて地域との交流が生まれれば、孤立を防ぐことも可能です。
体力維持や健康促進につながる
農業は体を動かす仕事でもあるため、定年後に起きやすい運動不足も解消され、体力維持や健康促進にもつながります。
例えば、畑を耕したり、野菜を収穫したりする動作は、全身を使う運動になるため、自然と筋力も付いてくるはずです。
最初からハードに動いてしまうと大変ですが、無理のない範囲で続けることで、筋力や柔軟性も保てるでしょう。
自分らしい働き方を選べる自由さ
定年後に農業ビジネスを始める魅力として、自分のペースで働けることも挙げられます。
体力の有無やライフスタイルに合わせ、無理のないスタイルで取り組むことが可能です。
会社勤務だと勤務時間は決まっており、上司からの指示を受けて急遽案件をこなすこともあるかもしれません。
しかし、農業ビジネスなら自分でペースを決めることができ、柔軟に作業に取り組めます。
ワークライフバランスを重視しながら自分らしいリズムで働けることは、大きなやりがいにもつながります。
初心者でも始めやすい!定年後に人気の農業ビジネス例5選

農業ビジネスといっても、その種類は多岐にわたります。ここで、定年後に人気の農業ビジネス例を5つ紹介します。
野菜・果物の直売
農業ビジネスの中でも特に始めやすいのが、野菜・果物の直売です。直売所にも種類があり、生産者が運営する直売所と、グループや企業が運営する直売所があります。
個人の直売所は自宅の敷地内などにスペースを作り、無人で野菜を販売します。
一方、グループや企業が運営する直売所では、マルシェや道の駅、スーパーの野菜売り場の一角などで販売も可能です。
地元のイベントなどに出店すれば、お客さんと直接やり取りをすることもでき、交流を楽しみながら野菜を販売できます。
小規模な有機農業
農薬や化学肥料を使わずに、自然の力を活用して育てる有機農業は、一般的な農業に比べて難しい反面、野菜自体の付加価値は非常に高いです。
小規模だったとしても、こだわって育てた野菜に根強いファンが付くことも珍しくありません。
自治体によっては有機農業を始める農家に向けて、研修制度や補助金などの支援を実施しているところもあり、農業が初めての人も安心して始められます。
体験農園・観光農園
近年、収穫体験や農業体験ができる体験型農園や観光農園が人気を集めています。
普段自然と触れ合う機会が少ない都市部の家族連れはもちろん、観光客からの人気も高いビジネスです。
例えば、果物農園ならいちご狩りやブルーベリー狩り、野菜中心ならさつまいも掘りなどがあります。
季節によって収穫できる野菜・果物は異なるため、1年間を通して収穫体験ができるようにしておくと、収益も安定しやすいでしょう。
加工品(ジャム・漬物・乾物など)の販売
畑で育てた野菜や果物を使って、ジャムや漬物、乾物などを加工品にして販売するのもおすすめです。
野菜や果物をそのまま販売するよりも、加工することで保存が効くようになり、商品の付加価値も高まります。
また、味は悪くないのに見た目が悪く、売れにくい野菜や果物も加工品にしてしまえば売れやすくなります。
自宅のキッチンを使って小規模でスタートでき、直売所やオンラインショップを活用すれば販路も広がるでしょう。
花やハーブの栽培
野菜よりも手軽に始められる、花やハーブの栽培も魅力的です。
ラベンダーやローズマリーなどのハーブは香りがよく、アロマやクラフトの材料に用いられるケースも多いです。
また、花やハーブを使ったクラフトの工房も準備することで、花やハーブそのものを販売するだけでなく、クラフト体験サービスも提供できるようになります。
自分の鑑賞用として楽しみながら育てることもできるので、趣味と実益を兼ねて農業ビジネスを始めたい人には特におすすめです。
定年後の農業ビジネスの始め方【5ステップ】
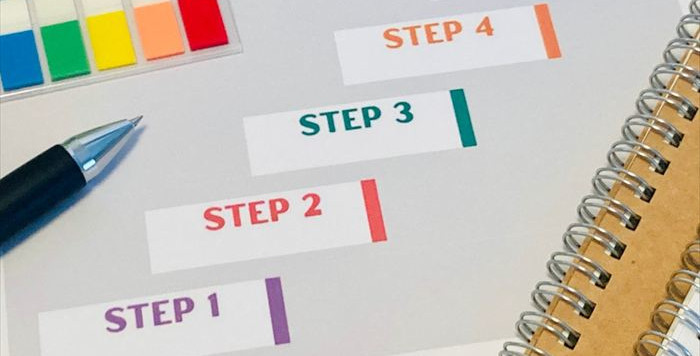
定年後に農業ビジネスを始める場合、どのような流れで始めれば良いかわからない人も多いかもしれません。
そこで、定年後の農業ビジネスの始め方を5ステップに分けて紹介します。
目的やライフプランを明確にする
農業ビジネスを始める上でまず重要となってくるのが、目的やライフプランを明確にすることです。
目的を明確にすることで、農業ビジネスへの取り組み方も変わってきます。
例えば、「農業ビジネスを成功させて大きな収入を得たい」、「健康維持のために体を動かす農業を始めてみたい」などの目的が挙げられます。
また、ライフプランをイメージすることも大切です。
農業ビジネスをどこで始めるのか、どれくらい働くのか、家族にも協力してもらうのか、などを考えながら、農業への取り組み方を考えてみてください。
必要な知識や技術を学ぶ(研修・講座の活用)
農業を始めたいものの、ノウハウがないという人は、農業に関する知識・技術を学ぶ必要があります。
インターネットなどからも情報を得ることは可能ですが、実際に土いじりをしながら実践的に学んでいったほうが技術も習得しやすいです。
農業大学校やJA、自治体などでシニア向けに就農支援講座や短期研修などが開催されています。
農業ビジネスを実行する際に少しでも失敗を減らすためにも、学びの機会を持つことは重要です。
土地・設備を準備する
農業の知識・技術を学んだら、次に農業を始める場所や設備を準備する必要があります。農地を所有していない場合は、市民農園や農地バンクの活用がおすすめです。
農地バンク(農地中間管理機構)とは、農地を貸したい農家と借りたい人を仲介し、農地の貸し借りをできるようにした組織です。
新たに農業を始めた人が個人間で農地を借りようとすると断られてしまうケースもありますが、農地バンクを活用すれば組織が仲介に入るため、貸してもらえないといったリスクも防げます。
農地を準備できたら、次に必要な農機具や資材も準備しておいてください。
小さく始めて経験を積む
ビジネスはいきなり大規模からスタートさせるものではなく、まずは小さくコツコツと始めることが大切です。
未経験から農業ビジネスを始める場合、特に天候の影響や収穫・出荷のタイミングなどは実際に体験してみないとわからない部分でもあります。
また、小さく始めることで初期費用を抑えやすく、失敗したとしてもリカバリーできる範囲に留められます。
うまくいけばそのまま拡大していけば良いので、まずは小さく始めて経験を積んでください。
集客や販売ルートを確保する
収穫した野菜・果物は、どこで・誰に販売するかも検討してください。例えば、地元の直売所やマルシェ、知人を通じた口コミでの販売などがあります。
また、近年は個人農家がネットショップやSNSを活用して販売するケースも増えています。
また、販売方法についても確認しておくことが大切です。
販売方法には農協からの出荷や道の駅などで販売する「委託販売」と、飲食店との取引きや加工業者と契約する「買取販売」、さらに自分で販売する「直接販売」があります。
農業をビジネスとして成立させるためには収益も必要となってくるため、集客や販売ルートなどを確保しておきましょう。
農業ビジネスに必要な資格や届け出は?

農業ビジネスを始めるにあたって、農地取得や加工品販売などで資格取得や届け出の提出が必要になる場合もあります。農業ビジネスに必要な資格や届け出は以下のとおりです。
| 必要な資格・届け出 | 概要 |
| 農地取得や利用のルール | 農地を借りるためには「農地法第3条許可申請書」の提出が必要。権利移動や転用にも農業委員会の許可が必要。 |
| 食品衛生法などの許可申請 | 加工品を販売するには、業種ごとに許認可が必要。保健所の食品衛生担当に相談する。 |
| 農地転用許可 | 農地に倉庫や直売所などを設ける際には農地転用許可が必要。都道府県知事または農業委員会から許認可を受ける。 |
| 直売所出店の申請 | 地元の直売所に出店したい場合、前もって出店申請と契約が必要。各運営団体のルールを確認した上で申請する。 |
| 個人事業主の開業届 | 農業ビジネスで収益をともなう場合、税務署に個人事業主として開業届を提出する。事業開始の事実があった日から1カ月以内に提出。 |
| PL保険(生産物賠償責任保険)への加入 | 加工食品を販売する場合、万が一の事故に備えてPL保険への加入が推奨されている。 |
| 農業共済への加入 | 台風や大雨、干ばつなど自然災害による収穫量の減少などの損失を補てんしてくれるため、加入が推奨されている。 |
定年後農業ビジネスでの資金調達方法

農業ビジネスを小規模からスタートしたとしても、それなりの運転資金が必要です。そこで、定年後農業ビジネスを始める場合の資金調達方法について解説します。
利用できる補助金・助成金
定年後の新規就農者に対して、各自治体で補助金・助成金が利用できます。例えば、以下の補助金・助成金制度が挙げられます。
・南足柄市新規就農支援助成金
南足柄市内で新規就農した人に対し、営農などに使った経費を助成する制度です。
対象となる経費は、農地の賃借や種苗・苗木などの購入、農業機械・設備の購入または賃借などが挙げられます。
補助金額は経費の総額の1/2で、上限額は就農者によって異なります。
- 【新規就農基準による就農者】
-
- 市内在住の人、市内に移住した人:50万円
- 移住しなかった人:25万円
- 【市民農業者制度を利用し、新規就農基準を満たす就農者】
-
- 市民農業者制度利用時:25万円
- 新規就農基準による就農時に市内在住または市内に移住した人:50万円
- 新規就農基準による就農時に移住しなかった人:25万円
・加古川市就農環境向上事業(新規就農者向け)
加古川市では新規就農者向けの補助金事業として、アグリスタート補助金と加古川市認定新規就農者サポートが用意されています。
アグリスタート補助金は、営農開始に向けて研修を受けている人を対象とする「準備型」と、市内で新たに農業経営を開始した人に耕作面積に応じて支援する「開始型」の2種類です。
準備型は上限12カ月で毎月2万円の補助、開始型は1aごとに1万円(上限100万円)の補助を受けられます。
このほかにも、シルバー人材向けの支援を行っている自治体もあるため、利用できる補助金がないかチェックしてみてください。
なお、いずれの補助金・助成金制度にも利用するのに条件や審査などもあるため、早めにJAや自治体の農業振興課に相談するのがおすすめです。
ただし、自治体の支援制度は年齢制限が設けられている場合もあるため、利用する際には注意が必要です。
融資や自己資金の工夫
農業ビジネスを始める際に、融資を活用することも可能です。例えば、以下の融資制度が挙げられます。
| 融資制度 | 特徴 |
| スーパーL資金 | 認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた人)が受けられる長期低利融資制度。 |
| 経営体育成強化資金 | 主業農業者や認定新規就農者に向けて、前向き投資や償還負担の軽減に使える資金を融資する制度。 |
| JAバンクの農業資金 | 長期低利で資金調達をサポートする「農業近代化資金」や、農業に関する様々な資金ニーズに対応できるJAバンク独自の融資「アグリマイティー資金」など、あらゆる融資制度を用意。 |
また、退職金や年金の一部など自己資金を活用することも視野に入れてください。
自己資金を活用する際には、生活費と農業ビジネスに充てる資金を分けて、計画的に活用することがポイントです。
よくある質問(FAQ)

最後に、定年後の農業ビジネスに関するよくある質問を紹介します。
未経験でも農業はできる?
未経験でも農業を始めることはできます。
ただし、農業を始めるにはある程度知識と技術が必要となってくるため、就農プログラムや研修制度などを活用するのがおすすめです。
また、失敗するリスクもあることから、まずは小規模の畑や市民農園からスタートし、農業の一連の流れを体験してみてください。
土地がない場合はどうする?
農地を所有していない場合でも、市民農園や農地バンク、新規就農支援制度などを活用して農地を借りることが可能です。
小規模な区画でも十分に農業ビジネスをスタートできます。
年金との両立は?
年金を受け取りながら農業で収益を得ることは可能です。ただし、農業での収入が一定額を超えると、在職老齢年金制度によって支給額に影響が出る場合もあります。
農業を副収入として楽しみつつ、年金と両立させながら生涯現役を実現しましょう。
どんな研修や制度がある?
各自治体やJA、農業大学校などで実施している研修・講座には、初心者に向けたものもあります。
短期間で学べる体験型から、長期にわたって農業について学べる就農支援プログラムまで、その種類は多岐にわたります。
また、農業ビジネスを始める上で補助金・助成金が使える場合もあるため、就農前に情報収集をしておいてください。
まとめ
定年後からでも農業ビジネスをスタートさせることは可能です。
農業が未経験だったとしても、初心者向けの研修や講座を受けることで、知識や技術をある程度身につけてから農業を始められます。
農業ビジネスは年金以外の収入を増やせるだけでなく、大きなやりがいを感じられたり、地域との交流が増えたりするなど、メリットも多いです。
ぜひ今回の記事を参考に、自分らしい農業ライフを始めてみてはいかがでしょうか。
創業手帳(冊子版)は、定年後に新たなビジネスをスタートさせたい人に向けて、知っておきたい法律や支援制度など、あらゆる情報をお届けしています。定年後に創業・起業を計画されている人も、ぜひご活用ください。
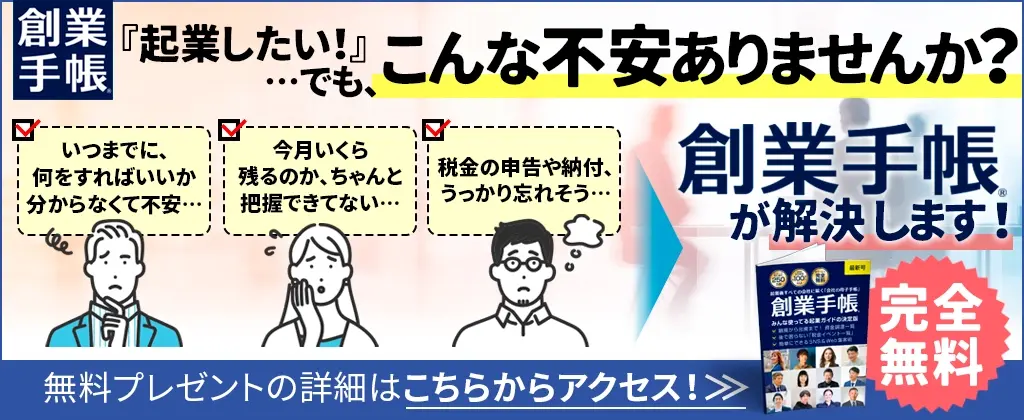
(編集:創業手帳編集部)