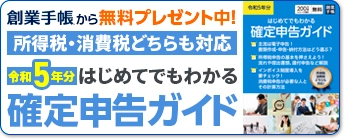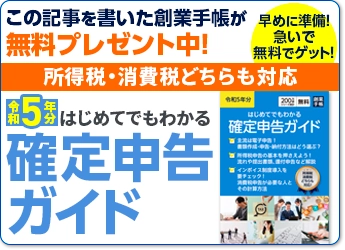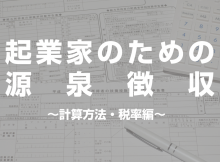住民税の申告方法とは?必要な人の条件をわかりやすく解説
「住民税申告」確定申告や年末調整をしていない人は要注意
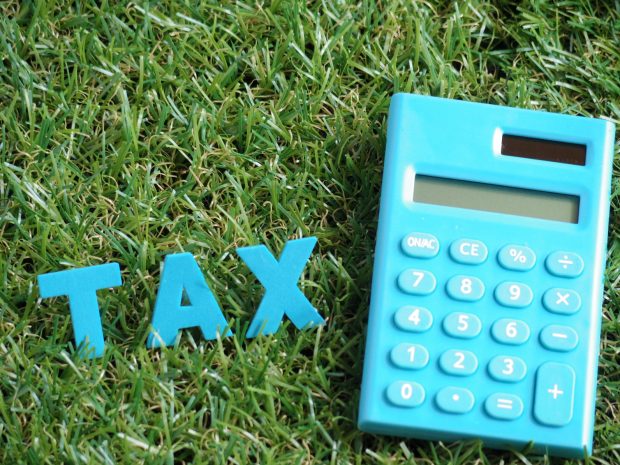
- 住民税申告は地方税のため、市役所に提出する
- 確定申告とは目的と提出先が異なる
- 確定申告をすれば住民税申告は不要
- 住民税申告が必要な人は確定申告や年末調整をしていない人
- 申告期間は2月16日~3月15日(2026年は2月16日~3月16日)
私たちが納めている「住民税」は、毎年の所得から税額を計算しています。
年末調整や確定申告をしていない方の中には、所得の報告を含めて「住民税の申告」をしなくてはならない人がいるのです。いつ誰が住民税の申告対象となるのか、詳しく解説します。
住民税と密接に関係する確定申告の基本を「確定申告ガイド(無料)」にわかりやすくまとめました。確定申告をスムーズに済ませられれば、住民税の申告で悩む必要はありません。
この記事の目次 住民税とは所得に対してかかる税金で、都道府県に支払う税金と市町村に支払う税金を合わせたものです。一般的には住民税と呼ばれていますが、市県民税ともいいます。住民税は地方税であることから、申告先は区役所や市役所です。 住民税と同じく、所得に対してかかる税金に「所得税」があります。両者の違いは管轄や課税対象期間です。 所得税は国税のため、税務署に申告します。さらに所得税は「その年の所得」に対して課税されますが、住民税は「前年の所得」に対して課税されるのです。 極端な話ですが、今年が無収入だったとしても、前年に稼いでいたら住民税は支払わなければなりません。 住民税申告は、地方税である住民税を支払うために自治体に届け出る手続きです。基本的には所得がある人が申告しますが、ほかの税金の計算や証明書の発行に関係することから、所得がなくても申告が必要なケースがあります。 一方、確定申告は自身の所得を申告し所得税を支払うための手続きです。届け先は税務署であり、所得が一定以下なら原則として申告の必要はありません。 このように、住民税の申告と確定申告は目的そのものが違うほか、申告すべき条件も異なります。 確定申告の情報は税務署から市町村へ送られ、それをもとに市町村が住民税の計算をする仕組みです。 したがって、確定申告をすれば自動的に住民税の申告をしたことになり、通常であればわざわざ住民税の申告をする必要はありません。 個人事業主の確定申告で選ぶべきは「青色申告」です。「白色申告」と比べて節税メリットが大きく、住民税の金額も抑えられます。冊子版の創業手帳で節税の詳細を確認しましょう。 住民税の申告が必要なのは、以下に該当している人です。 基本的には確定申告をしない人、会社で年末調整を受けない人は住民税の申告が必要です。 詳しくみていきましょう。 住民税は通常、確定申告をしていれば別途申告はいりません。逆に言えば、確定申告をしていなければ住民税申告をしなければいけない可能性があります。 確定申告の必要がなく、住民税申告のみが必要だと考えられるのは、以下のような例です。 住民税は所得が少ない、あるいは所得がなくなった場合でも申告が必要になります。これは、国民健康保険料等の負担額が変わる可能性があるためです。 会社員やパート、アルバイトは会社が年末調整を行います。ただし給与が一定以下なら年末調整の対象から外れ、住民税の申告が必要な可能性が出てくるのです。 住民税がかかるのは年間所得が100万を超えてからです。なおかつ103万円以下なら年末調整の対象から外れる場合があるので、住民税申告の必要性が出てきます。 年度の途中で退職し、会社で年末調整をしてもらっていない人も同様です。 確定申告や年末調整はしないけれど、控除を受けたり減免制度を使ったりしたい場合は、住民税の申告が必要です。 具体的には以下のようなケースが当てはまります。 各種控除は一般的に、確定申告または年末調整の際にあわせて適用します。どちらも実施しない人は住民税の申告時に適用することになるでしょう。 非課税証明書などの書類がいる人も、住民税の申告を行わないと発行してもらえません。これらの書類は融資や賃貸物件の申し込み時に必要なことがあります。 確定申告や年末調整をしている人は、住民税の申告は必要ありません。控除を使わない方も同様です。 詳細については、各自治体の公式サイトを確認するようにして下さい。 住民税の申告は、市役所の市民税課や、市税事務所の市民税担当窓口などに「住民税申告書」を提出することで行います。提出場所は自治体によって違うので、必ず自治体ホームページを確認してください。 住民税申告書は窓口でもらう、または自治体ホームページからダウンロードしてご利用ください。 住民税の申告期間は、確定申告同様2月16日〜3月15日(2026年は2月16日~3月16日)です。対象になる方は、各書類を早めに準備するよう心がけましょう。 申告書のほかに以下のような書類が必要となるので、詳しく解説します。 所得の証明書類は、給与をもらっている人なら源泉徴収票を用意してください。年金をもらっている人は、公的年金の源泉徴収票が必要です。事業所得がある人は、所得を証明する帳簿や領収書が必要となります。 控除を受ける場合のみ、受けようとする控除の書類を準備しましょう。たとえば、以下のような控除書類が必要となります。 本人確認書類は、マイナンバーカードかマイナンバー通知カードを用意します。申告にはマイナンバーの記入が必要なため、どちらかを準備してください。あわせて運転免許証・健康保険証・パスポートなどの本人確認が必要です。 印鑑は必要ない自治体もありますが、書類を提出する際に持参するといいでしょう。 「非課税証明書」が必要な場合は、住民税の申告をしておかないと証明書が交付されないケースがあります。 非課税証明書は、銀行でローンを組む際や奨学金の申請などで使用するため、申請する可能性がある方は注意しましょう。 住民税の申告をしないと「所得証明書」がもらえず、国民健康保険料や介護保険料などの減額の手続きができなくなります。保険料等の減額制度が正しく適用されないことにもつながるため、所得がなくても住民税申告の必要性があるのです。 住民税を納める必要があるのに申告をしないと、本来支払う住民税に加えて延滞金がかかります。 令和7年の延滞税率は最大で2.4%か8.7%のどちらかで、納期期限から2カ月を超えると税率が上がります。延滞した日数分の延滞金がかかるため注意してください。 副業している人や個人事業主の場合は自己申告が義務となっており、申告忘れに気をつけなくてはなりません。確定申告をすれば、住民税の申告もしたことになります。 住民税は以下の計算式で求められます。 以下の条件の場合の計算例を掲載します。 この場合の住民税額は20万5,000円です。配偶者控除などの「調整控除額」がある場合は、所得割額から減算します。 ※2024年度から実施されている定額減税は、多くの方で適用が完了していますが、所得金額や扶養状況によっては2025年度(令和7年度)の住民税で調整が行われるケースがあります。ご自身の決定通知書で控除額を確認しましょう。 住民税には「均等割額」と「所得割額」があります。 均等割額は、所得額に関係なく負担が決められている固定金額のことです。市町村民税部分(特別区民税)の均等割は一律で3,000円、道府県民税部分(都民税)の均等割は1,000円となっています。2024年からは森林環境税1,000円も加わり、計5,000円です(自治体により変動する場合もあり)。 所得割額は所得に応じてかかる割合金額で、基本的に一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)になります。 このように税の計算は煩雑です。冊子版の創業手帳では、税金の計算が簡単にできる会計ソフトの選び方やおすすめ製品について解説しています。 住民税は普通徴収と特別徴収のいずれかで納税します。 ・納付書による分割または一括納付 ・給与からの天引き納付 このうち、自ら住民税を支払う必要が生じた場合は「普通徴収」となります。次のような支払い方法で納税しましょう。 住民税の納付書を使った現金納付です。毎年5月に送られてくるので、納付書を持ってコンビニや各銀行にて支払います。 4期(6月・8月・11月・1月など)に分けて支払うか、4期分を一括して納付することも可能です。 対応している金融機関であれば、住民税を口座振替で支払うこともできます。金融機関や地域の窓口にて事前の登録が必要です。 口座振替も4期の分割か一括での支払い方法を選べます。自治体ごとの収納可能な金融機関は、各ホームページなどでチェックしましょう。 住民税の支払いについて、クレジットカードや電子マネーを使ったデジタル決済に対応する自治体もあります。 納付書にバーコードがついていればPayPayやLINE Payでのアプリ決済ができるなど、状況に応じて変わるため確認してみてください。 所得税の還付よりも珍しいのであまり知られてはいませんが、以下のような人は住民税でも還付が受けられる場合があります。 住民税は前年の所得から計算されるので、前年の所得申告に訂正があったときに還付・追納が発生します。所得申告に訂正が生じるケースとしては「扶養控除の変更」や「医療費控除の漏れ」などが例です。 そのほか、年の途中で退職しており年末調整をしていない方なども、住民税の申告によって還付が受けられる可能性があります。 基本的には、確定申告や年末調整をしておらず、条件に当てはまる場合には住民税申告の必要性が高まります。反対に、確定申告または年末調整さえしていれば、住民税の申告は不要です。 煩雑に思える確定申告も、重要なポイントを押さえればスムーズに進められます。「確定申告ガイド」なら、必要な書類から申告の方法まで一気通貫で学習可能です。 手続きについては税理士などの専門家に相談するのも一つの手です。住民税の処理をはじめ、煩雑な経理業務は慣れていないと時間がかかります。冊子版の創業手帳では、創業期から税理士と契約するメリットについて詳しく解説しています。
(執筆:創業手帳編集部)

 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
私たちが支払っている「住民税」とは?
住民税と所得税との違い
確定申告と住民税申告の違い
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」住民税の申告が必要な人
確定申告をしていない人
年末調整を受けていない人
控除や減免制度を使う人
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」住民税の申告が不要な人
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」住民税の申告方法・必要書類
所得の証明書類
各控除書類
本人確認書類
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」住民税の申告をしないとどうなる?

住民税を申告しなかった場合、どんな問題が起こるのでしょうか。確定申告や年末調整もしない前提で、住民税が無申告な場合に想定される問題を知っておきましょう。「非課税証明書」を取得できない
「所得証明書」を取得できない
延滞税がかかる恐れがある
住民税の計算方法とは?

こちらでは、住民税の計算方法について詳しくみていきます。住民税の計算例について
住民税の均等割・所得割とは
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」住民税の支払い方法
普通徴収
特別徴収
・給与ではない所得を得ている人に適用される徴収方法
・給与を得ている人に適用される徴収方法
現金納付(コンビニ、銀行)
口座振替
デジタル決済
 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」住民税でも還付が受けられる場合がある?

 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」
【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」まとめ・住民税は確定申告or年末調整の実施状況により申告を