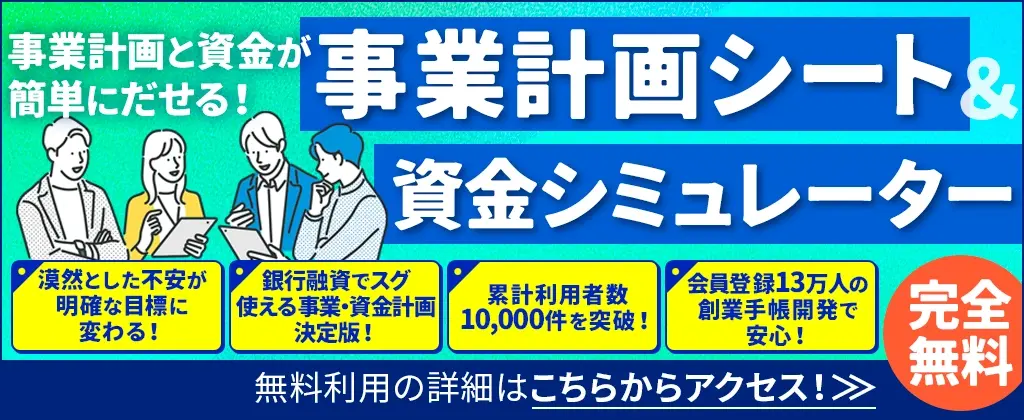固定費と変動費の違いや分類方法は?経営で必要な4つの指標の求め方も解説
事業で発生する固定費・変動費はきちんと区別することが大切

事業で発生する費用は、固定費と変動費に分かれます。双方をしっかり区別することは、利益の予想や新事業の立ち上げ判断などにおいてとても重要です。
しかし、具体的に固定費と変動費の違いや該当する費用についてわかっていない方もいるかもしれません。
今回は、固定費と変動費の違いや区別する重要性について解説します。
固定費と変動費を用いて分析できる指標や削減のポイントなどもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
固定費・変動費の違い
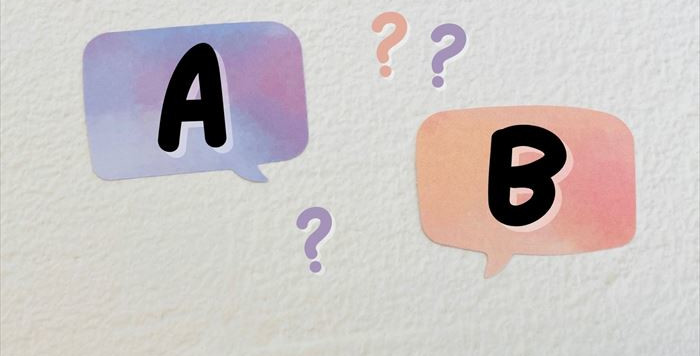
事業で発生する費用を固定費と変動費に分けることで、健全な経営を実現できます。まずは、それぞれの費用の違いや該当する経費をご紹介します。
固定費の特徴
商品・サービスの生産量や売上高の影響を受けず、一定の金額で発生する費用です。固定費に該当する経費は以下のとおりです。
-
- 人件費
- 地代家賃
- 水道光熱費
- 減価償却費
- 広告宣伝費
- OA機器などのリース料 など
上記の経費は事業継続に必要なものであるため、仮に売上げがない状態でも固定費は必ず発生します。
また、売上げが2倍になっても固定費は変わらず一定という特徴もあります。そのため、固定費を圧縮できれば、得られる利益を増やすことが可能です。
変動費の特徴
商品・サービスの生産量や売上高の増減と連動して変動する費用です。変動費に該当する経費は以下になります。
-
- 原材料費
- 仕入原価
- 外注費
- 販売手数料
- 支払運賃
- 車両燃料費
- 派遣・契約社員の給与
- 残業手当 など
例えば、ある月の製品の生産数が1,000個だった場合、その際にかかる原材料費は1,000個分です。
その翌月の生産数が2,000個になった場合、かかる原材料費は2,000個分となります。
このように、変動費は生産量や売上げが増えれば上がり、逆に減れば下がるという特徴があります。
雇用期間に定めがない正社員の人件費は固定費になりますが、契約期間がある派遣社員や契約社員の給与は変動費として扱うことが可能です。
残業手当は繁忙期や閑散期で変動するので、こちらも変動費として扱えます。
固定費と変動費を区別したほうが良い理由

経費を固定費と変動費で区別することには、様々なメリットがあります。区別をした方が良い理由は以下のとおりです。
事業利益を予測するため
事業利益は売上高から固定費と変動費を差し引くことで、予測することができます。
したがって、的確に予測するためには、固定費と変動費を区別し、正しい数値が必要になるというわけです。
双方の費用をしっかり把握しておけば、売上げの減少が見込まれる時もどれだけの利益を出せるのか予測できるので、適切な対応をとることが可能となります。
事業利益を予測することは、生産量や在庫、経費、人員配置、資金繰りなどあらゆる計画の適正化に欠かせません。
正確に事業利益を予測できないと、健全な経営や成長を妨げてしまう恐れがあります。
費用の削減効果に違いがあるため
無駄な経費を減らすことは、利益の最大化や健全な経営の実現に欠かせません。
固定費と変動費は費用の削減効果や難易度に違いがあるため、削減を実現する上でもしっかり区別することが大切です。
固定費の場合、成果が出ていない広告の出稿をやめる、契約しているサービスやプランの変更など支出を見直すことで削減できることがほとんどです。
一方、変動費は原材料費や外注費など生産に必要なコストが含まれるため、削減が難しい傾向にあります。
このように、固定費と変動費では削減の難易度が違います。
そのため、どの経費が固定費と変動費に当てはまるのか区別できれば、財政を圧迫している費目や優先的に削減するべき費目が明確になるでしょう。
事業立ち上げの判断につながるため
新事業を立ち上げる判断をする上でも、固定費と変動費を区別することが重要になってきます。
新事業を立ち上げた時点では売上げが見込めず、固定費のほうが多くなって赤字になる可能性が高いです。
固定費が多く利益を出すことが難しいのであれば、新事業の立ち上げを諦めるという判断もできます。
新事業の立ち上げで赤字が出る可能性があるのか予測するためには、どれだけの固定費がかかるのか把握しておく必要があります。
事前にかかる固定費がわかれば、削減に取り組んで赤字幅を減らすことが可能です。
固定費と変動費を分類する方法

固定費と変動費を分類する方法には、勘定科目法と回帰分析法の2種類があります。それぞれの分類方法の特徴は以下のとおりです。
勘定科目法
費用の勘定科目ごとに固定費と変動費に振り分ける手法を勘定科目法といいます。例えば、原材料費なら変動費、水道光熱費なら固定費というように分類していきます。
シンプルな分類方法であるため、会計実務でよく用いられている手法です。
業種によって、特定の勘定科目が固定費と変動費のどちらに該当するのか変わってきます。
そのため、中小企業庁が発行する「中小企業の原価指標」で紹介している、費用分解基準を参考にするのがおすすめです。
判断しづらい勘定科目は、性質の強いほうで判断すると良いでしょう。
回帰分析法
回帰分析法とは、売上高と総費用のフラグをもとに固定費と変動費率を求める手法です。縦軸を総費用、横軸を売上高でフラグを作り、毎月の数値に点を付けていきます。
年間で計12個の点を近似曲線で結ぶと、「y=ax+b(a=変動費率・b=固定費)」の公式で関係を表すことができます。
近似曲線の傾きと切片から固定費と変動費率を求めることが可能です。
手計算で行うと手間がかかるため、Excelを使って計算することをおすすめします。
また、回帰分析法は正確に分類できるため、勘定科目法の数値と実態が大きく異なる場合に適した手法です。
固定費・変動費を用いて分析できる4つの指標

固定費と変動費が明確になると、経営に役立つ4つの指標を導き出すことができます。その4つの指標とは、限界利益・損益分岐点・安全余裕率・売上高変動費率です。
各指標の概要と算出方法をご紹介します。
1.限界利益
限界利益とは、商品・サービスが1単位で売れるごとに得られる利益のことです。
限界利益が高いほど黒字の状態なので、事業を存続させても問題ないと考えることができます。
限界利益は、「売上高-変動費」で計算することが可能です。
例えば、1個1,000円で仕入れた商品を1,500円で販売した場合、「1,500円(売上高)-1,000円(変動費)=500円(限界利益)」と計算することができます。
この場合、商品1個につき500円の利益が出ていることがわかります。
ただし、限界利益の計算では固定費が考慮されていません。
そのため、事業を継続するためには、限界利益から固定費を差し引いても黒字であるかどうかも重要です。
また、「限界利益÷売上高」で限界利益率を求めることができます。
限界利益率は、売上高のうち限界利益を占める割合を意味するので、この数値が高い商品・サービスの販売に注力することで利益を増やせる可能性があります。
2.損益分岐点
損益分岐点とは、売上高と商品・サービスを生産するための費用が同額で、利益がゼロとなるポイントのことです。
今後売上げが低下した時も利益を得られるかどうかを判断する上で重要な指標になります。
損益分岐点における売上高は、損益分岐点売上高と呼ばれています。損益分岐点売上高は、「固定費÷1-(変動費 ÷ 売上高)」で計算することが可能です。
損益分岐点売上高がわかると、企業がもっと利益を増やすためにはどれだけの売上高が必要になるのか把握できます。
損益分岐点図を作成することで、損益分岐点売上高や固定費と変動費の関係が把握しやすくなるでしょう。
損益分岐点図は縦軸が収益費用、横軸が売上高でフラグを作り、売上高線・総費用線を引いていきます。
その際、売上高と総費用線が重なった点が損益分岐点です。損益分岐点の位置が低いほど、経営に余裕がある状態といえます。
3.安全余裕率
安全余裕率は、経営の安全性を測るための指標です。この指標が高ければ高いほど、余裕のある経営ができていることがわかります。
安全余裕率の計算には損益分岐点売上高を用いるため、事前に把握しておいてください。
安全余裕率の計算式は「1-(損益分岐点売上高÷実際の売上高)×100」です。平均的な目安は10~20%前後とされていますが、40%以上が理想といわれています。
安全余裕率が平均値以下の場合、赤字転落のリスクがあるので経営体制の見直しが必要です。
4.売上高変動費比率
売上高変動費比率は、売上高のうち変動費がどれだけの割合を占めているのか把握するための指標です。
売上高は利益・固定費・変動費の3つで成り立っているため、変動費の割合が大きく、固定費が少ないほど赤字になるリスクが低いといえます。
売上高変動費比率は、「変動費÷売上高×100」で計算することが可能です。
平均的な水準は70~80%程度といわれており、この数値が低いと経営環境の変化に対応しきれない可能性があると判断できます。
ただし、売上高変動費比率の平均は業種や企業規模によって変動するので、中小企業は大企業よりも平均水準が低くなる点に注意してください。
固定費と変動費の削減につながるポイント

固定費や変動費を削減することは、利益の最大化につながります。ここで、固定費と変動費を削減するためのポイントをご紹介します。
固定費の削減方法
固定費は、とにかく無駄を省くことが重要です。コストを削減する手段には、以下の方法が挙げられます。
-
- 業務の自動化や効率化によって時間外労働を減らす
- 派遣社員・契約社員・アウトソーシングを活用して人件費を減らす
- 家賃の安いオフィスに移転する
- 水道光熱費のプランを安いプランに乗り換える
- 電子契約を導入して印紙代を減らす
- 不要なリースやサービスの契約を解除する
- カーシェアリングの活用や電気自動車に切り替えて燃料費・駐車場代などを減らす
固定費の場合、人件費をはじめ、光熱水道費やリース料金、車両費などあらゆる費用を見直すことで費用を軽減できます。
どの費用が負担になっているのか洗い出し、影響度の大きい費用から見直すのがおすすめです。
変動費の削減方法
変動費の削減は固定費の削減よりも優先度は低くなりますが、必要に応じて検討してください。変動費を削減する手段には、以下の方法が挙げられます。
-
- ペーパーレス化によって印刷費用や消耗品費を減らす
- 大量仕入れや現金仕入れに切り替えて仕入単価を下げる
- 仕入先や外注先の変更や交渉によって価格を下げる
変動費の削減は、商品・サービスの生産や品質などに影響を与える可能性があります。
ペーパーレス化といった、売上げに影響が出ない部分から削減するのがポイントです。
また、仕入先や外注先の変更や価格交渉をする場合、商品・サービスの質が落ちないように慎重に行ってください。
固定費・変動費の削減で注意したいこと

固定費・変動費の削減は大切ですが、削減を重視しすぎると逆に不利益を被ってしまう可能性があります。ここで、固定費と変動費を削減する際の注意点をご紹介します。
従業員の負担が増える削減は行わない
固定費や変動費の見直しにより、従業員の働き方が変化する可能性があります。
その働き方が従業員のモチベーション向上や生産性の向上につながるのであれば、問題ありません。
しかし、逆に負担が大きくなるようであれば、従業員から反感を買ってしまう恐れがあるので注意が必要です。
過度なコスト削減は、商品やサービスの品質低下にもつながります。
お客様の満足度が下がれば売上げも減ってしまうので、コストダウンで利益を増やすつもりが逆効果となってしまいます。
現場の理解を促してから削減を行う
コスト削減は現場の理解を促した上で行うことが重要です。先も述べたとおり、コスト削減に取り組むことで、働き方やルールなどが変わってしまう可能性があります。
従業員が十分に理解しておらず、さらに現場の状況を考慮せずに状態で削減を進めてしまうと、労働環境の質低下につながる可能性が高いです。
そのため、現場の状況を判断した上で必要な削減を検討し、それを社内でしっかり周知し、理解を得てもらうことが大切です。
従業員から理解を得られれば、コスト削減の取組みもスムーズに進みます。
長期的な視点で取り組む
コスト削減は半年や1年といった短期的な視点ではなく、5年・10年といった長期的な視点で取り組むことも大切です。
経費の中には簡単に削減できないものが多いため、短期間で成果が出ない可能性があります。
そのため、長期的な取組みによって少しずつ削減していくのが現実的といえます。
特に新型コロナウイルスの感染が拡大した時のような急なパンデミックが起きた場合、経営維持のためにコスト削減が求められるかもしれません。
長期的にコスト削減に取り組んでいれば、慌てることなく事業を継続していくことが可能です。
まとめ・固定費と変動費を正しく理解して経営判断・経営改善に活かそう
事業で生じる費用を固定費と変動費で適切に区別することは、経営判断や改善を実行する上で重要となってきます。
新たな費用が発生すれば、固定費も変動費もその都度把握や見直しが必要となるので、日頃からしっかり管理しましょう。
固定費・変動費を理解すれば、コスト削減も適切に取り組めるようになり、利益をもっと増やせるようになります。
ただし、商品・サービスの質や従業員の負担に影響を与えないように、コストダウンは慎重に行うようにしてください。
創業手帳では、必要な資金を算出することができる「資金シミュレーター」を無料で公開しています。事業を進めるにあたっては、資金繰りが重要です。資金シミュレーターでは金融機関に出せる資金繰り表が作成できますので、融資などの資金調達を検討するときも便利です。是非ご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)