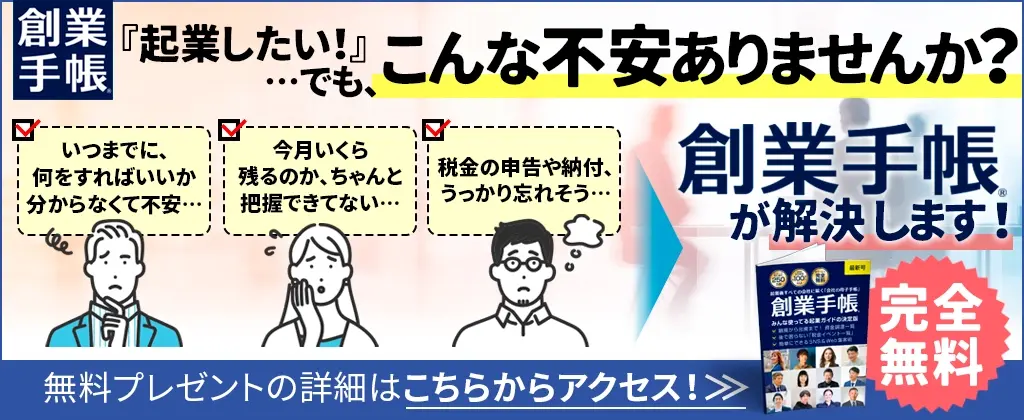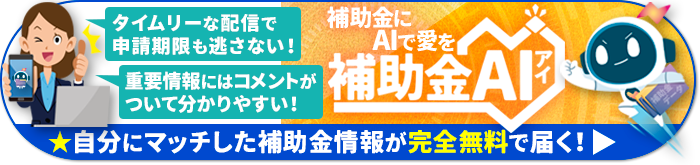自己資金ゼロでも諦めない!起業資金をつくる7つの方法と注意点
自己資金の作り方は様々!

起業したい時にまず考えるのが起業にかかる費用です。まずは起業資金を貯金してから事業をはじめる人もいますが、その間にビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。
社会の変化はスピーディーさを増し、起業するにもスピード感が求められます。
「起業したいけど、貯金がない…」そのようなあなたに向けて、今からはじめられる自己資金づくりの方法と注意点をわかりやすく紹介します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
起業に自己資金はなぜ必要?

自己資金の有無によって起業の進め方はまったく違います。どうして起業に自己資金が必要なのかの紹介です。
自己資金がないと融資が通りにくい理由
事業のために必要な資金を金融機関から借りようとした時、自己資金があったほうが審査での評価で有利になります。
自己資金を多く用意しておくと、起業者がそれだけ計画的に資金準備に励んできた証明になるのです。
自己資金は、起業に対する自信や計画性、熱意の表れと判断されます。
逆に自己資金が少なければ、準備が不十分である、起業への熱意が低いと判断されてしまうことがあります。
自己資金=“信用力”にもつながる
自己資金は、事業へのやる気や熱意の指標になります。起業には金融機関や取引先など多くの人が関わります。
取引きにはリスクがある以上、どれだけ信用できるかは取引きの可否を判断するために重要な指標です。
自己資金は、自分の熱意を第三者に数字で伝える手段として有効です。
逆に、どれだけ熱意をもって事業の魅力を語っても、一切自己資金がなければ信用できないと判断されるかもしれません。
起業したてで、実績が少なければこそ信用力を高めるための努力が重要です。
自己資金をつくる7つの方法

自己資金の重要性は理解していても、自己資金を用意できない人は多いかもしれません。ここでは、自己資金をつくるための7つの方法をまとめています。
1. 不用品を売却して現金化する
自己資金を作るのであれば、まず現金化して事業資金にできるものがないか見直してください。株式や債券といった金融資産は、売却すれば事業資金にできます。
また、大きな金額のものでなくても身の回りにあるものが高値になるかもしれません。最近はフリマアプリやリユースショップもあるので利用してみてください。
適正な金額で売却できるようにあらかじめ相場を調べておくようにおすすめします。
2. 固定費を削減し「強制貯金」する
起業資金を貯めるには、支出を減らすことも検討してください。
支出は変動費と固定費に大きく分けられ、変動費は食費のように毎月金額が変動する項目、固定費は住居費や保険料のように定期的に一定額発生する費用です。
固定費は変動よりも把握しやすく、削減方法を検討しやすい支出です。
毎月の固定費の支出を見直し、不要なサブスクリプションの解約や保険の見直し、電気・ガスのプラン変更などを検討しましょう。
収入を増やすためには、副業したりアルバイトを探したりしなければいけません。しかし、支出を削減すれば同じ収入でも自然と貯金が増えます。
起業してからも利益を残すためには、生活から費用を減らす意識を持つようにしてください。
3. コツコツ資金を作る
すぐにでもはじめておきたいのが、コツコツとした起業資金作りです。
今まで貯金をしたことがなかった人も、毎月受け取る給料の一部を貯金用の口座に移すようにすると意識しなくても貯金できます。
定期積立は期間や金額を自由に設定でき、計画的に目標額を貯める時に最適です。まずはどのような定期積立があるのか、利率はどのくらいか調べてみてください。
4. 家族・親族から支援や借入れを受ける
厳密にいうと自己資金とは異なりますが、急いでまとまった金額を調達するには家族や親族からの支援、借入れも選択肢となります。
家族や友人であれば、すでに関係が構築されているため人柄や起業への熱意をかってくれるかもしれません。
支援の方法にはいろいろありますが、一般的には贈与を受けたり、出資してもらったりする方法があります。
贈与はお金をもらうことになるため、税金の対象にならないように金額を調整しましょう。
出資は、新しい会社に出資してもらうことになり、金額によって出資比率が変わる点に注意しなければいけません。
5. ビジネスコンテスト・助成金を活用する
起業アイデアはあっても、それを実現する資金が足りない時には、ビジネスコンテストや助成金を活用した資金調達をおすすめします。
ビジネスコンテストは応募者が作成した起業アイデアや事業計画について、新規性や将来性といった視点で審査するものです。
ビジネスコンテストによって違いはありますが、入賞すると賞金を受けたり、サポートが受けられたりするものもあります。
地方自治体や大学・企業主催のビジネスコンテストや創業支援プログラムをチェックしてみてください。
ビジネスコンテスト以外にも、国や地方自治体が提供している助成金も活用しましょう。助成金は募集要項やスケジュールが定められていて、採択されれば援助を受けられます。
ビジネスコンテストでの入賞や助成金の採択は実績にもなるので積極的に取り組んでください。
6.副業をする
受け取っている給与では貯金できない、これ以上支出を減らせない場合には副業で収入を増やすことを検討します。
例えば、本業をしていない時間や休日をアルバイトに当てれば収入は増えます。単発で働く場所を探すツールも登場しているので、より副業に取組みやすくなりました。
スキルや経験があればクラウドソーシングサービスを活用して、フリーランスとして収入を得る方法もあります。
クラウドワークスやランサーズでは、初心者向けの案件も多く、実績を積みながら収入を得ることが可能です。
副業で収入を増やせば起業資金に回すお金も増えます。ただし、副業にのめりこんで外食が支出が増えたり健康を損ねたりしないように注意してください。
7.不動産や車など資産の一部を手放す
どうしても起業資金が必要な場合には、不動産や車といった資産の一部を手放せないか考えてみてください。
保有しているものの使っていないような遊休資産があれば、現金化して起業資金にできないか調べてみます。
また、保有している資産が本当に必要なのかどうかも見直してみてください。
休日やたまにしか乗らない車があるなら、車を売却してカーシェアリングに切り替える方法があります。
カーシェアリングを使えば、維持費や税金も削減できるので大きな金額を節約できるでしょう。
実際起業の自己資産っていくら必要なの?

起業は、すべて自己資金ではじめなくても、金融機関から融資を受ける方法もあります。
では、もしも起業のために融資を受けるのであれば、どれだけ自己資金を準備しておけばいいのでしょうか。
日本政策金融公庫総合研究所の『「2024年度新規開業実態調査』では、開業時の資金調達額は平均1,197万円です。
資金調達先は、「金融機関等からの借入れ」平均780万円ともっと割合が多く、平均調達額に占める割合は65.2%です。
つまり、起業資金のうち3割程度が自己資金の目安と考えられます。もしも希望する融資額が500万円であれば3割の150万円程度は必要である計算です。
自己資金づくりで気をつけたいこと
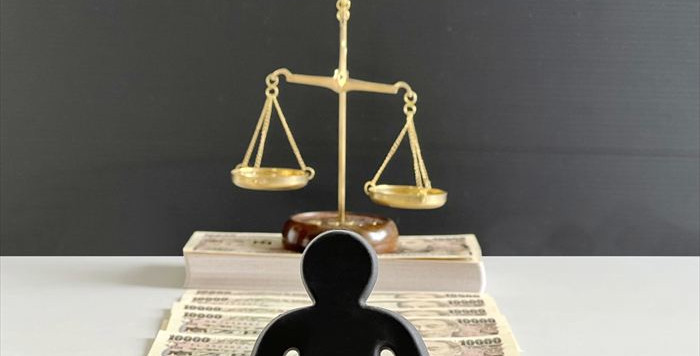
自己資金づくりは、節約しながら副業をしたり、ビジネスコンテストや助成金を探したりと負担は少なくありません。
自己資金を用意する時に気を付けておきたいポイントをまとめました。
明確な目標金額を決めておく
起業準備で自己資金を貯める際は、必ず明確な目標金額を設定します。「なんとなく貯める」のではなく具体的な目標額を設定しなければいけません。
明確な目標金額を定めるには、起業の初期費用や生活費の予備、広告・マーケティング費用など、必要項目を洗い出し「起業のために最低いくら必要か」を明確化します。
具体性がある数字になることで、より計画が立てやすくなり貯蓄のモチベーションや優先度がぐっと高まります。
目的のない節約は続かない
「お金を貯めなきゃ」と漠然と節約に走ると、生活にかかるすべてのお金を節約しなければならないと思い込んでしまうことがあるかもしれません。
しかし、このような目的がない節約は、生活の質を下げすぎてストレスになるため、途中で挫折しやすくなってしまいます。
起業資金を貯めるには、「起業後のこの部分に使うため」という具体的な目的が必要です。
例えば「HP作成の外注費用」「開業後3か月の家賃確保」など、目標の使い道をはっきりさせると節約も前向きに続けられます。
準備に時間をかけすぎて起業機会を逃さない
資金準備は長期戦になるケースがあります。しかし、資金準備を優先するあまり、実際の事業スタートが遅れすぎてチャンスを逃してしまうかもしれません。
特にトレンド性のあるビジネスや、個人スキルを活かす仕事はスピードが重要です。
資金ゼロでいきなりの起業はおすすめできませんが、小規模にして早くスタートすることも検討してください。
最初は小さな副業やプレ開業から動き出すことで、早めに市場の感覚をつか見やすくなります。目標額を貯めることだけを目的にせず、起業機会を逃さないようにしてください。
SNSやインターネットの情報に流されない
副業や貯蓄を調べていると「〇カ月で100万円貯めた!」「この副業で一発逆転」などの情報に行き当たることもあるでしょう。
しかし、SNSやインターネットの情報に過度な期待を持つのは危険です。
内容が本当であっても、他人の成果は、その人の状況や前提があるもので再現性は不明です。
焦らず、自分の生活スタイル・収入・目標に合った現実的な方法で資金づくりを進めることが成功への近道と考えてください。
家族やパートナーに理解を得ること
起業のための自己資金づくりが生活費や時間に影響する場合には、家族やパートナーの理解なしには継続が難しくなるかもしれません。
勝手に節約したり、副業、借金をはじめて不信感を与えるのではなく、まず説明して理解を得るようにします。
何のために資金を準備するのか」を共有し、家族の協力を得ながら進めることが大切です。
人に頼る時は返済や信頼関係を最優先に
家族・親族・知人から資金を借りる場合、信頼関係を維持し続けるための努力は怠らないようにしてください。金額の大小に関わらず、感謝と信頼を前提にした対応が必要です。
お金のことで、曖昧な口約束はトラブルのもとになります。契約書や返済計画を用意して、誠実な姿勢で関係を守ることが大切です。
自己資金以外で使える起業資金調達方法

自己資金だけで起業にかかる費用をすべてまかなうのは大変です。ここからは自己資金以外に活用できる起業資金の調達手段を紹介します。
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新しく事業をはじめる人と事業開始後おおむね7年以内の人が利用できる融資制度です。
融資限度額は、7,200万円(内運転資金4,800万円)で女性や若者、シニア、さらに廃業歴があって創業に再チャレンジする人は通常よりも有利な条件で利用できます。
信用金庫や地方銀行の創業融資
多くの起業で利用されている資金調達手段が金融機関からの融資です。金融機関は借入れ以外に日々の決済で利用するケースが多くあります。
金融機関と融資や取引きについて話すことでアドバイスが受けられることもあります。
起業資金を借りてから返済実績をつくれば信用を高まり、次の資金調達につなげやすくなるでしょう。
エンジェル投資家・ベンチャーキャピタル(VC)
融資を受けると後から返済の負担が大きくなるケースがあります。出資は株式などの資本を提供するかわりに資金の提供を受けて事業をはじめるものです。
個人で資金提供するエンジェル投資家や事業として出資するベンチャーキャピタルがよく知られています。ただし、返済不要であっても出資した側は利益を目的としています。
起業してからも出資者の意向に沿う必要があるため経営に影響するかもしれません。
補助金・助成金
国や地方自治体が提供している補助金や助成金も、起業者向けのサポートになります。
補助金や助成金は、それぞれ条件や返済の有無、スケジュールが違いますが、どれも審査を通過しなければ利用できません。
補助金は採択される人数が決まっているものもあるので、申請しても必ず受給できるとは限りません。
一方で、助成金は受給要件を満たしていて予算がなくならない限りは受給できます。
創業手帳では、経営者や起業家の方がよく使われる補助金・助成金を厳選して解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。そもそも補助金とは何か?という基礎から各補助金の最新情報まで記載していますので、ぜひご活用ください。
クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて大勢の人から資金を募る資金調達手法です。
購入型と応援型があり、購入型はリターンに商品やサービスの提供を設定したものです。
開発した商品をリターンとする手法が良く使われ、宣伝広告やテストマーケティングにも活用されています。
応援型は、基本的に見返りがない寄付でありお礼のメールやWebサイトでの経過報告が提供されており、公共性や社会的な意義がある事業によく使われています。
まとめ|お金を“つくる力”も起業の実力
自己資金がゼロでも、起業をあきらめる必要はありません。将来の起業のために今日からできることはたくさんあります。
コツコツ貯金をはじめたり、補助金や助成金を探したりできることからはじめてください。
起業のために大切なのは、資金力ではなく新しい一歩を踏み出す行動力です。どのようにすればお金をつくれるのかを考えて動き出してください。
創業手帳(冊子版)は、起業に必要なノウハウを一つの冊子にまとめた「起業のためのガイドブック」です。資金調達方法から資金繰りの基礎や、税金の知識などがこの一冊でおさえられます。
また、起業のために必要な準備としてわかりやすいのが「創業カレンダー」です。起業予定日を記入すると、その予定日を起点に前後1年間のやることがカレンダー形式で把握することができます。どちらもあわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)