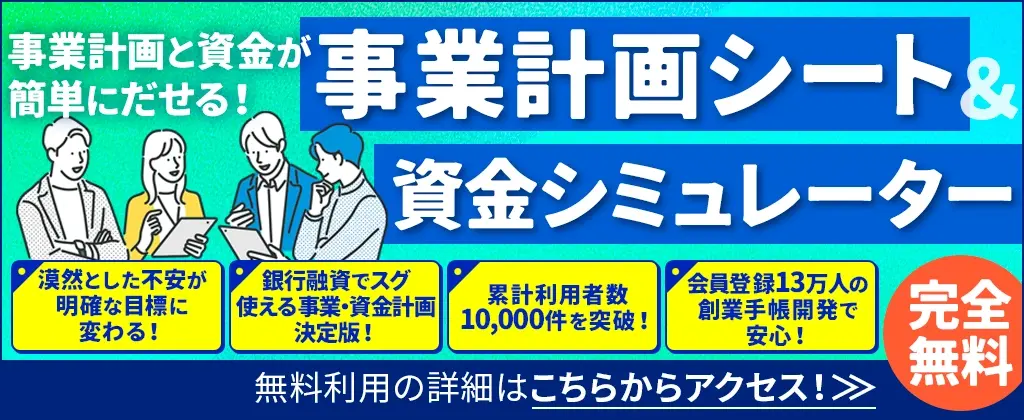費用対効果の分析方法を解説!効果を最大化するためのポイントとは
費用対効果はビジネスにおいて重要な指標

ビジネスをする上で重要な指標が費用対効果です。費用対効果の適切な分析方法や計算方法を理解することで、事業の成長につながります。
費用対効果の算出方法がわからず、感覚で計測する人がいるかもしれません。
それでは正確な効果を知ることができないため、正しい方法を理解する必要があります。
そこで今回は、費用対効果とは何なのか、費用対効果の重要性を解説するとともに、費用対効果の分析方法や計算方法、費用対効果を高めるためのポイントなどを紹介していきます。
費用対効果について理解したい人は、ぜひ参考にしてください。
費用対効果を最大化するには、感覚ではなく“数字”で把握することが欠かせません。
創業手帳が無料で提供する『事業計画シート&資金シミュレーター』を使えば、費用・売上・利益のバランスを整理し、次の一手をデータで判断できます。
実際の数値を入れてみるだけで、自社の課題と改善策が明確になります。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
費用対効果とは
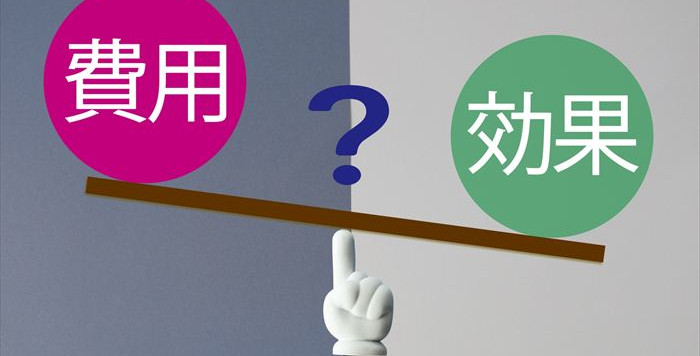
費用に対して得られる効果を費用対効果といいます。商品を作る場合、製造や販売、管理するための費用や時間的なコストがかかります。
そのコストに対して得られた効果が費用対効果です。
かけたコストに対して見合う効果が得られなければ赤字につながる可能性があるため、費用対効果の算出はビジネスにおいて重要度が高いでしょう。
似たような単語としてコストパフォーマンスがありますが、意味合いが異なります。
使ったお金に対して得られた効果を測定する目的は費用対効果もコストパフォーマンスも同じですが、視点に違いがあります。
費用対効果は企業目線での指標ですが、コストパフォーマンスは消費者目線となり、価格や費用に対しての満足度を図る指標です。
費用対効果を分析することの重要性
コストに見合う効果を得られなければ意味はありません。費用対効果を分析することがビジネスにおいて重要な理由を解説します。
投資判断の明確化は、どの事業に対してどの程度の費用をかけるべきなのか、投資判断の指標になります。
費用対効果が低ければ無駄な費用を投じることになり、利益を見込めません。しかし、費用対効果が高い事業は利益が出やすく成長する可能性も高いです。
常に費用対効果を観察すれば、問題の見直しや改善策の立案につながります。
また、リソース配分の最適化にも役立ちます。効率的な資源配分を実現できれば、限られた予算やリソースを最大限に活用して、より大きな成果を生み出すことにつながるのです。
なお、費用対効果は経営陣や取引先への説得材料にもなります。費用対効果のシミュレーション結果を提示すれば説得力を与えられます。
費用対効果の分析方法

ここからは、費用対効果の分析方法について解説していきます。
1. 目的・評価指標を設定する
費用対効果を最大化するためには、目的や評価指標を設定する必要があります。
売上増加やコスト削減、認知拡大などが当てはまりますが、「CPAを○万円以下にする」「○○円以上売上げアップを図る」など、具体的に数値目標を設定することで、効果を測定しやすくなります。
2. 費用を把握する
次に、分析対象となる費用を洗い出して把握していきます。その際には、直接費用と間接費用を分けて計算します。
直接費用とは、商品の生産に直接関わる業務で発生する費用のことです。仕入れや製造作業の工賃などが当てはまります。
一方、間接費用は特定の事業に直接関与しない共通的な費用を指し、複数のプロジェクトに共通して必要になる点が特徴です。
管理部門での人件費や事務所の光熱費、通信費などが当てはまります。
3. 効果を数値化する
次に、効果を数値化していきます。数値化するものは、売上げ・利益、KPI(CV数、顧客数) などです。
算出された数値は推定値ですが、正確に計算するためには、過去に完成させたプロジェクトの費用などと比較してください。
4. 費用対効果を計算する
効果を数値化した後には、費用対効果を計算します。費用対効果を求める計算式にはいくつか種類がありますが、基本となる計算式は以下の通りです。
「効果 ÷ 費用 」
例えば、広告費で50万円を投じて売上げが200万円増加した時の費用対効果は「200万円÷50万円=4円」となり、1円の費用で4円の効果が得られたことがわかります。
この数値が高ければ高いほど、費用対効果が高いといえます。
5. 結果を評価し改善につなげる
最後に、結果を評価し改善につなげる施策を検討していきます。分析をした結果に基づいて評価を行い、費用の削減や効果が見込める施策を考える工程です。
例えば、「社内の業務プロセスを見直して作業を削減する」という施策を行えば、人件費や時間のコストを抑えることできます。
資源の無駄遣いを防ぐためには、「在庫管理の最適化」や「エネルギー消費の削減」なども有効です。
【指標別】費用対効果を分析するための計算方法
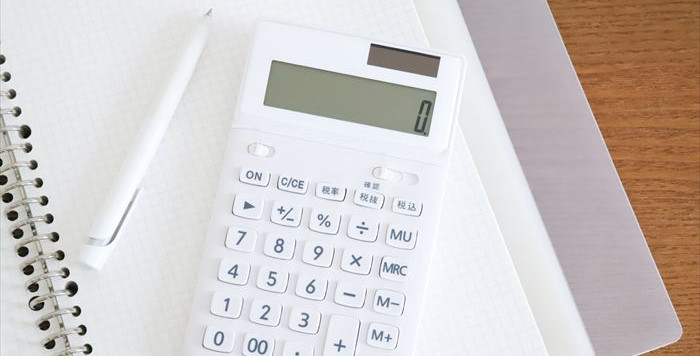
ここからは、費用対効果を分析するための計算方法について解説していきます。
ROI(投資対効果)
「Return on investment」の略語で、「投資資本利益率」や「投資利益率」とも呼ばれています。
投資費用から、どの程度の利益や効果が得られたのかを表すもので、以下の計算式を使って求められます。
「利益÷費用(投資額)×100=ROI(%)」
数値が大きいほど効果が高く、利益率も高くなります。また、金額ではなく%で示され、事業の規模に関わらず効果を比較しやすいのが特徴です。
ROAS(広告費用対効果)
「Return On Advertising Spend」の略語で、広告に対する費用効果を算出できます。
算出方法は以下の通りです。
「広告での売上げ÷広告費用×100=ROAS(%)」
数値が高いほど広告効果が高いと評価できます。複数の媒体に広告を掲載した際には、媒体ごとの効果を比べることも可能です。
ROASのみでは利益が出ているかどうかを把握できませんが、広告が売上げに対してどれほど貢献しているかを知るために役立ちます。
ROIやCLVなどの指標を組み合わせて検証することが大切です。
CPA(顧客獲得単価)
「Cost Per Acquisition」の略語で、顧客獲得単価や成果単価を示します。
1件の成果や顧客獲得のためにかけた費用を算出する指標です。成果には、購入や資料請求、問い合わせなどが当てはまります。
計算方法は以下の通りです。
「広告費÷コンバージョン数=CPA(円)」
例えば、広告費に50万円をかけ、コンバージョンが2,000人であればCPAは250円、5,000人であればCPAは100円となります。
CPAは、数値が低いほど効率が良い証明になりますが、数値が高ければ施策の見直しが必要と判断されます。
LTV(顧客生涯価値)
「Life Time Value」の略語で、1人当たりの顧客がもたらした利益を表す指標です。
顧客との取引きがスタートして終了するまでに、どの程度の利益があったのかを求められます。計算方法は以下の通りです。
「平均顧客単価×収益率×購買頻度×継続期間=LTV(円)」
例えば、月額10万円(収益率40%)でWebサイトの運用サービスを10年にわたって利用していた場合、「10万円×0.4×12×10=480万円」と計算できます。
顧客獲得のためのコストを加味する場合には、以下のような計算方法が用いられます。
「平均顧客単価×収益率×購買頻度×継続期間-(新規顧客獲得コスト+既存顧客維持コスト)」
前述したケースに当てはめて考えてみます。
新規顧客獲得コストとして広告費で100万円、既存顧客維持コストとして、定期的なフォローのための人件費で150万円使った場合、「480万円-(100万円+150万円)=230万円)です。
CPR(レスポンス獲得単価)
「Cost Per Response」の略語で、顧客からの反応1件あたりの単価を求めることができます。
レスポンスとは、無料サンプルの請求や問い合わせ、無料体験の申し込み、メールアドレスの登録などが当てはまります。
「広告費÷レスポンス数=CPR(円)」
数値が低ければ効果的な広告を実行していると判断できます。
CPO(注文獲得単価)
「Cost Per Order」の略語で、1件の注文を得るためにかかった広告の単価を求める際に活用されます。
「広告費÷注文件数=CPO(円)」
上記計算式で求められ、値が低いほど効率が良いと判断できます。広告費をかければ受注増加を狙えますが、広告費に対して売上げが適切でなければ経営を圧迫する要因です。
安価なコストで顧客を獲得できれば、広告の費用対効果は上がります。売上げと広告費のバランスを見極めるためにも活用して分析してみてください。
費用対効果を高めるためのポイント

費用対効果が予想よりも低ければ、対策を検討して実行しなければいけません。ここでは、費用対効果を高めるための具体的な方法を解説していきます。
コストを削減する
費用対効果を高めるためにはコスト削減を考えてください。業務プロセスにおける無駄を省けば、余計な手間やコストを抑えることにつながります。
業務棚卸では、効率的な業務プロセスを導入すれば生産性アップを図れます。
また、業務をマニュアル化して誰でもわかるように整えれば、人材育成費も削減が可能です。あらゆる方法を模索してコスト削減を図ってみてください。
価格設定を見直す
価格設定の見直しも費用対効果を高めるためには有効な手段です。設定した価格が低すぎれば、コストを削減したとしても利益は伸び悩みます。
そのため、商品の単価を上げて売上げの向上を狙ってみてください。単価が上がれば同じ個数を販売しても売上げの向上を目指せます。
ただし、単に値上げをしても需要がなければ売上げを作れません。市場調査を行って需要のある商品のみ値上げをするといった策が必要です。
また、値上げをしても顧客が納得できる要素を付けることも有効です。
-
- 懸賞の応募券を商品につける
- パッケージのデザインを新しくする
- アフターサービスの見直しを図る など
このように、付加価値を付ける施策の実行を検討してください。
生産性を向上させる
生産性の向上を図れば、費用対効果を高めることにつながります。そのためにも、企業は効率良く利益を上げられる仕組みづくりを考えなければいけません。
少ない作業時間や人員でも多くの商品を生み出せれば生産性はアップし、費用対効果も高まる仕組みです。
業務フローをチェックして、重複している業務がないか、必要のない業務が含まれていないか見直してみてください。
また、会議時間の短縮や社内資料を廃止することでも生産性アップにつながります。
働きやすい環境づくりにも投資してください。残業や休日出勤を減らす以外にも、福利厚生を充実させることで、従業員のモチベーションアップを図り、生産性向上につながります。
業務効率化を目指す
業務効率化を図れば生産性が上がり、無駄な作業を省くことが可能です。結果的に費用対効果を高めることに貢献します。
ITシステムやITツールを活用すれば、業務効率化につながり、労働時間や交通費の削減できます。
-
- クラウドストレージサービス
- チャットサービス
- 顧客管理ツール
- タスク管理ツール など
これらのツールをうまく活用し、業務効率化を目指してください。
ターゲットの見直しを図る
ターゲットに見合わない商品開発やターゲットに見合わない広告掲載では十分な効果を得られません。
ターゲットの見直しを図って費用対効果アップを目指してみてください。
広告配信やWeb解析ツールを活用し、どの層が多く反応しているのか、どの層が反応していないのかをデータで確認します。
年齢や地域、興味関心など、属性をもとにしてターゲットの再定義を行えばターゲットに合わせた施策につながります。
また、ペルソナが古くなっている可能性もあります。顧客のニーズやトレンドは変化が激しいため、定期的にペルソナの見直しが必要です。
最新の状況に合わせてターゲティングを行ってください。
外注を検討する
自社のみで効率的な業務ができない、人員が足りないとなれば、外注を検討してみてください。
外注費用がかかりますが、作業時間を大幅にカットできるため自社業務に集中でき、労働時間の確保にもつながります。固定費の削減ができるケースもあります。
まとめ・費用対効果を分析して持続的な事業成長を目指そう
限られたリソースを最大限活用するためにも、費用対効果はビジネスにおいて不可欠な指標です。
今回紹介したROIやCPA、LTVやCPRなどを活用し、効果的な施策の導入を進めて持続的な事業成長を目指してください。
分析によって改善の方向性が見えたら、次は“資金の動かし方”を考える段階です。
創業手帳が無料で提供する『はじめての資金調達手帳』では、融資を基本とした成長に必要な資金戦略をまとめています。
戦略的に投資判断を行いたい方におすすめです。
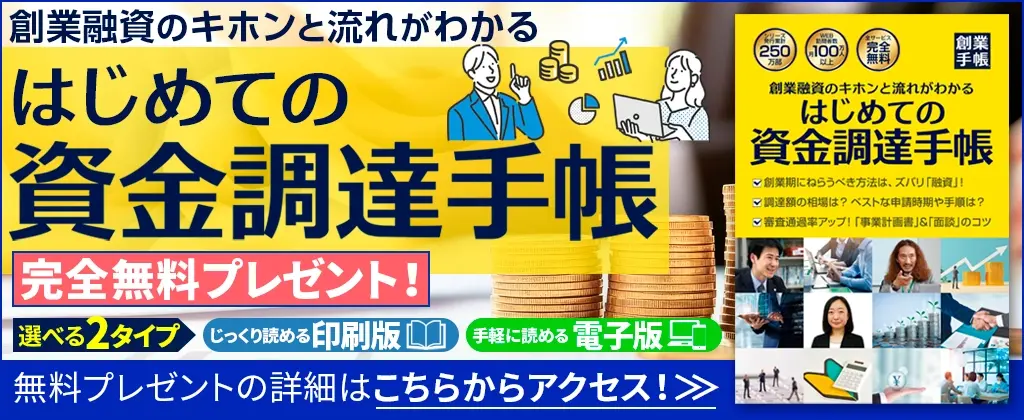
(編集:創業手帳編集部)