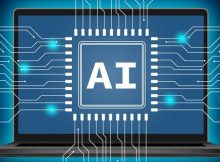中小企業こそAI活用で業務効率が10倍に?人手不足を乗り越える”実践アイデア”を紹介
人手不足に悩む中小企業こそ、AIが味方になる
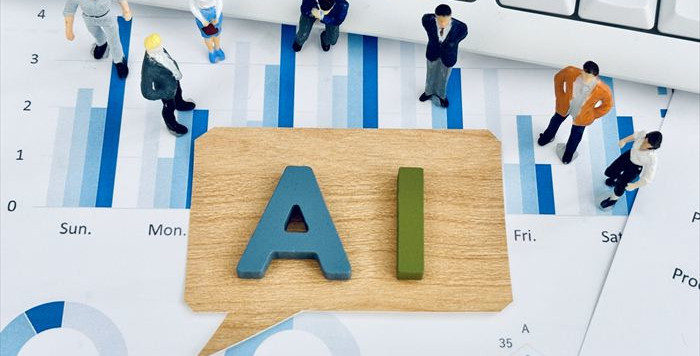
労働人口の減少によって多くの企業が人手不足に直面しています。特に中小企業の人手不足は深刻です。
中小企業は従業員ひとり当たりの業務負荷が大企業より重い傾向があり、人が少なくなると会社運営に支障をきたすケースもあります。
課題解決のために中小企業にこそ使ってほしいのがAIツールです。AIツールによって定型業務を自動化できれば、貴重な人的リソースを戦略的な業務に集中させられます。
現在のAI技術は専門知識がなくても導入できるので、人材難に苦しむ中小企業でも現実的な業務改善策として注目されています。
人手不足を補うAI導入を考えるなら、その前に様々な「生成AI」の可能性を理解しておくことが大切です。
創業手帳がまとめた 「ChatGPT生成AIガイド」 では、ビジネス現場での活用法や注意点を解説。中小企業の実務に役立つヒントが見つかります。無料でダウンロードできます。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
中小企業こそAIに向いている理由

AIを活用した業務と聞くと、大企業の業務改善であったり大型プロジェクトで導入されていたりするイメージがある人もいるかもしれません。
しかし、実際には規模が大きすぎない中小企業にこそAIの導入が革新的な効果をもたらします。
どうして中小企業がAI導入に向いているのかまとめました。
1.「時間を買う」効果が大きい
中小企業は人件費の増減が経営に直結します。少人数の組織はひとりの負担軽減が全体の生産性向上に直結しやすい構造です。
そのため、AIの導入で業務時間が短縮できれば収益に大きく影響を与えられます。
AIによる自動化で浮いた時間は、売上向上や新規事業に投入できるので費用対効果が高い投資と考えたほうがわかりやすいかもしれません。
具体的に定型業務をAIで自動化した場合の効果を試算してみてください。例えば、60分かかる議事録作成をAIで自動化した時を考えます。
AIが議事録を作成して人間がチェックするようにすれば作業時間は10分程度です。つまり50分を削減できます。
担当者の時給が3,000円で月の会議数が4回と考えます。一回の会議で削減できる費用は2,500円で月に1万円のコスト減です。
AIの月額料金が3,000円と考えればそれだけで月間に7,000円のコスト削減になります。さらに担当者にとっては200分の時間短縮が可能です。
上記はざっくりとした見積もりですが、AIが汎用性が高くてほかの業務でも活用できることを鑑みれば、その効果は大きいと考えられます。
2. 意思決定が早く、小さくはじめやすい
中小企業は経営者の判断で迅速にツール導入を決定でき、大企業のような稟議プロセスが短縮できるケースがあります。
大企業であれば、導入するために多くの部署のチェックが必要であり、導入する時のコストも大きくなりがちです。
中小企業であれば、小規模な試験導入からはじめられるため、リスクを最小限に抑えながら効果検証できます。
試験導入で効果が確認できれば即座に拡大展開が可能になり、スピード感のある業務改善が実現します。
3. 汎用AIで十分なケースが多い
中小企業の業務は一般的に定型的な業務が多く、汎用AIツールで十分に自動化や効率化が可能です。
例えば、ChatGPTやNotion AIなどは月額数千円で導入でき、多くの業務改善効果が期待できます。
カスタム開発の必要がなく、既存のSaaSツールを組み合わせるだけで実用的なシステムが構築できるため、最小限のコストだけでAI導入の効果が実感できるでしょう。
4. 従業員のスキルアップ機会が生まれる
AIツールを使えるスキルを持つ従業員がいないと導入を見送るケースもあるかもしれません。
しかし、AIツールも日常的に触れることによって、従業員のデジタルスキルが自然に向上するでしょう。
AI活用のノウハウを身につけた従業員は、会社の競争力向上に貢献する貴重な人材になると期待できます。
また、AIツールの導入によって単純作業から解放された従業員は、より創造的で付加価値の高い業務に挑戦できるようになります。
AIの導入によって従業員のスキルを底上げするチャンスが生まれるのです。
5. 顧客対応の質が向上する
AIで定型業務を自動化できれば、力を注ぐべき部分にリソースを集中できます。
例えば、店舗の定型業務をAIで自動化して顧客対応により多くの時間を割くといった方法が可能です。
さらに、AIがあることによって接客自体のクオリティ向上も望めます。今までの接客技術は人の経験や技術に依存する部分が多くありました。
AIがあれば過去の対応履歴を分析し、顧客一人ひとりに最適なサービス提供が可能になります。
迅速で正確な情報提供ができるので、顧客満足度の向上と競合他社との差別化が実現可能です。
部門別・AI活用アイデア|すぐにはじめられる例

AIの導入は、多くの部門にとって大きな変化を与えます。各部門でAI活用をはじめる際の具体的なアイデアを、導入難易度の低いものから順に紹介します。
総務・庶務
総務・庶務は、会社の円滑運営のための環境を整える仕事をしている部署です。幅広い問題に対応しているため、AIを導入して軽減される仕事が多いとされています。
例えば、会議の音声録音をAIで自動文字起こしをすれば、議事録作成時間を大幅に削減可能です。
さらに、社内規程や契約書のドラフト作成をAIに任せられるので、担当者は内容精査に集中できます。
総務・庶務が担当している問い合わせ対応のテンプレート作成や、定型的な社内アナウンス文案を自動生成可能できるので業務時間の削減効果は大きいでしょう。
経理
経理は、企業で発生する取引き、金銭授受を管理するため、日々多くの会計処理が求められます。
AIがあれば、領収書や請求書の画像をAIで読み取り、仕訳データを自動入力可能です。
AIが作業を担当することによって入力ミスや処理漏れといったヒューマンエラーを削減できます。
経理部門は、出張費や経費の管理も担当しています。AIがあれば支払い予定の確認や督促メールの下書きを自動生成できるので、金銭管理の負担は大幅に削減可能です。
経理部門が扱う膨大な情報をまとめて月次レポートの数値分析と要約をAIが行えば、経営陣向けの報告書作成を効率化できます。
営業
営業でもAIがサポートできる場面はたくさんあります。商談後のメモや議事録をAIで要約し、次回アクションの整理と共有を迅速化できれば報告業務の手間も軽減可能です。
営業の仕事には相手の感情やニーズを読み取る仕事もあるため、人間でないとできないと思われがちです。
しかし、顧客の課題に応じた提案書のたたき台をAIが作成し、営業担当者はカスタマイズに集中といった方法でより高いクオリティの提案が可能になります。
見積書作成や契約条件の確認作業もAIでサポートできるので、営業活動の時間を確保するにもAIが役立ちます。
マーケティング
企業の戦略を立案するマーケティング部門は膨大な情報を扱います。AIがあれば競合他社の情報収集と分析をAIで行い、人間はマーケティング戦略の立案に集中できます。
また、SNS投稿やブログ記事の企画案もAIが複数パターン提案することによって、コンテンツ制作の生産性も高まるかもしれません。
AIはどういったコンテンツ、タイトルが消費者に訴求できるのかといった視点での分析も可能です。
メルマガのタイトルや本文をAIが顧客属性に応じて自動生成して開封率向上を図るといった手法を採用できてアプローチの幅が広がります。
採用・人事
対面で人と接する機会が多い採用や人事の仕事でもAIが活用可能です。求人票の作成や応募者への返信メールをAIが下書きすれば、採用担当者の負担を軽減できます。
また、求人に対して応募者が多いと、採用する側の仕事も増加するでしょう。
履歴書や職務経歴書の内容をAIで分析すれば、応募者が多い時でも適性評価を効率的に実施できます。
面接は人が実施するものの面接のスケジュール調整や合否通知の文面作成をAIでサポートできるので、採用プロセスを円滑化するために役立ちます。
製造・生産管理
製造・生産管理の仕事では製造プロセスを計画通りに管理しなければいけません。AIを活用すれば生産計画を最適化でき、材料の無駄や納期遅延のリスクを削減できます。
さらに設備の稼働データをAIで分析し、メンテナンス時期の予測と故障の未然防止も可能です。
品質管理データの傾向分析もできるので、不良品の発生原因を特定し改善策を立案する時にもAIが活用できます。
顧客サービス・カスタマーサポート
顧客サービスやカスタマーサポートは電話や対面でのイメージが強くありますが、AIの導入も可能です。
よくある質問への回答をAIで自動生成すれば、顧客対応の時間短縮が短縮され品質向上にも貢献します。
チャットボットに初期対応を任せれば、24時間365日の顧客サポート体制を低コストで構築できます。
待ち時間なく好きなタイミングで問い合わせできるため、消費者の利便性向上にも貢献できる施策です。
顧客からの問い合わせ内容をデータとして分析する時にもAIが役立ちます。サービス改善のヒントや新商品のアイデアを発見するためにも活用してみてください。
在庫管理・物流
在庫管理や物流が円滑でないと、在庫不足で消費者が商品を購入できなかったり、過剰在庫を抱えてしまったりとトラブルにつながります。
過去の販売データをAIで分析すれば、適正在庫量の予測と発注業務の自動化ができ、効率良く在庫管理可能です。
在庫管理は重要な仕事であるものの、人間がずっと在庫をチェックし続けるのは困難です。
しかし、AIであれば在庫の動向を常時監視し、売れ筋商品の把握と死蔵在庫の早期発見をサポートできます。
また、商品を届ける時の配送ルートの最適化もAIの得意分野。物流コストの削減と配送時間の短縮が可能になり、現場で働く従業員の負担を減らせます。
AIは難しい・高いは本当?よくある勘違いをやさしく解説
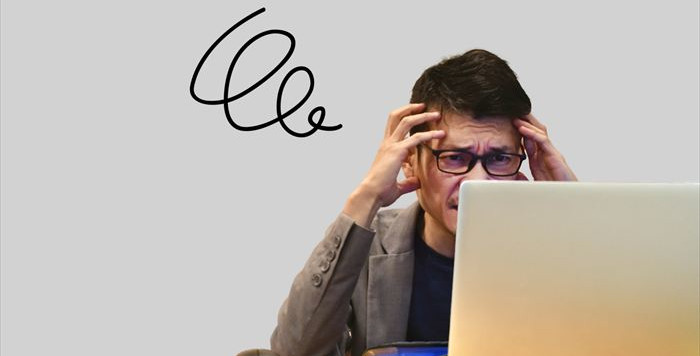
企業の中でもAIと聞くと難しくて費用がかかると思い込んでいる人がいるかもしれません。ここからは、そのようなよくある勘違いに対して解説していきます。
AIってプログラミングが必要では?
AIに対するイメージとして、「プログラミングの知識がないとわからないのでは?」と感じている人は多いかもしれません。実際にAIのシステムはプログラムで作られています。
しかし、これはあくまで開発する段階の話です。AIツールを使うのは、基本的なPC操作ができれば十分です。
多くのビジネス向けAIツールはドラッグ&ドロップで設定でき、直感的なUI設計がされているので、年代を問わず使いこなせます。
ChatGPTやClaudeなどは日本語での対話形式で使用でき、専門的なコマンド入力もいりません。
高そうで手が出ないのでは?
ChatGPTやGeminiなど主要なAIツールは、月額3,000円程度で利用可能です。無料プランでも基本機能は使えるため、まずは費用をかけずに効果を確認できます。
従業員ひとりの1時間分の人件費で1カ月間AIツールを利用できると考えれば、投資対効果が高い施策です。
今まで定型業務にかけていた人件費と比較すると格安なケースも多いので、どれだけのコストを減らせるのか実際にシミュレーションしてみてください。
うちの業種じゃ意味ないのでは?
AIは業種を問わず文書作成、データ整理、スケジュール管理など共通業務で効果を発揮します。
製造業でも販売業でもサービス業でも、事務作業の自動化により生産性向上が可能です。
中には、業界特有の専門用語や業務プロセスがあるかもしれません。しかし、AIに学習させることで対応が可能です。
どの部分であればAIに任せられるのかという視点で業務を見直してみてください。
間違った情報を出してしまうのでは?
確かにAIは事実とことなる情報を生成することがあり、これをハルシネーションと呼びます。
ハルシネーションによって誤った情報が広がれば、トラブルに発展するかもしれません。
しかし、AIの出力結果は必ず人間がチェックするといったルールを設けることで、リスクを最小限に抑えられます。
どうしても不安がある場合には初めは社内業務での利用に限定してみてください。外部への影響を気にしなくていいので、様々なAI活用を試せます。
そこから段階的に利用範囲を拡大し、信頼性を確認しながら本格運用に移行する方法が安全です。
従業員が使いこなせないのでは?
現在のAIツールは直感的な操作で使えるため、スマートフォンが使える人なら問題なく習得できます。
また、多くのAIツールは豊富な学習リソースと動画マニュアルを提供しているので、自学自習で習得できます。
社内でひとりでも使いこなせる人がいれば、その人がほかの従業員に教えることで全社的な活用が可能です。
まずはお試しとして少数の従業員が使ってみて、どのように使っていくかルールを策定してください。
セキュリティが心配では?
企業向けAIツールは厳格なセキュリティ基準を満たしている場合が多く、導入する際にはセキュリティのガイドラインを整備して対応できます。
重要な機密情報はAIに入力しないといったルールを設けることで、セキュリティリスクを管理可能です。
情報管理や機密データの取り扱いについてガイドラインを設けるとともに、社内でもAIを使う上でのリスクについて周知します。
生成AI向けのセキュリティサービスを導入する方法も検討してください。
効果が出るまで時間がかかるのでは?
多くのAI業務は既存の業務フローにそのまま組み込めるので、導入初日から効果を実感できます。
特に文書作成やデータ整理では短期間で時間短縮効果を得られるケースが多いです。
簡単な業務からはじめて、1週間程度あれば効果測定と投資対効果の確認が可能です。従業員がAIツールに慣れた後は、継続的な効率向上が期待できます。
繰り返しや手間が多い業務で使えばすぐに効果がわかるので、現場で働く従業員のフィードバックも導入の参考にしてください。
まとめ|完璧を目指さず、小さくはじめて効果を実感
AIを導入するには完璧なシステムを構築するより、ひとつの業務からはじめて徐々に範囲を拡大するほうが成功しやすいです。
中小企業の強みである意思決定の速さを活かし、試行錯誤を重ねながら最適解を見つけてください。
AIで時間を買うことで、経営者や従業員がより価値の高い業務に集中できる環境を構築できれば仕事へのモチベーションも高まります。
小さな改善からスタートして、成果を共有して拡散していくのが導入のポイントです。
AI活用の第一歩として、まずは生成AIの代表格である「ChatGPT」を知ることから始めてみませんか?
創業手帳の 「ChatGPT生成AIガイド」 では、特徴や活用方法を分かりやすく整理しています。無料でダウンロードできますのでお気軽にご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)