なぜキャッシュ不足になるのか?主な原因と14の対策を徹底解説
キャッシュ不足で黒字倒産のリスクが高まる

企業の経営において「利益が出ているのに資金繰りが苦しい」という状況は珍しくありません。
実際、帳簿上は黒字でも手元のキャッシュが足りずに支払いが滞り、倒産へと追い込まれる「黒字倒産」というケースが後を絶ちません。
なぜキャッシュ不足が起こるのか、その原因を理解することは、安定した経営基盤を築くために欠かせない第一歩です。
この記事では、キャッシュ不足に陥る主な原因と、それぞれの対策方法について解説しています。
キャッシュ不足に陥る原因とその対策方法について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
▶▶▶資金繰りの不安を減らす基本を一冊にまとめた「はじめての資金調達手帳」を無料配布中!
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
キャッシュ不足とは
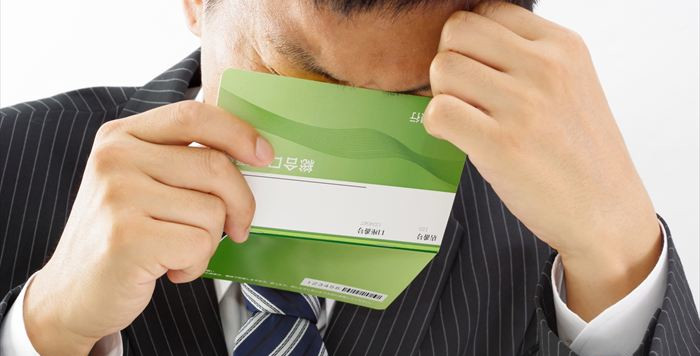
そもそもキャッシュ不足とは、簡単にいえば現金が不足している状態を指します。
現金の不足は支出が多く、現預金だけでは賄いきれない状況に陥った場合に、キャッシュ不足の状態にあるといえます。
早めに対策をしないと、冒頭でも説明したように赤字ではないのに倒産してしまう「黒字倒産」になりかねないため、注意が必要です。
▶▶▶資金繰りの不安を減らす基本を一冊にまとめた「はじめての資金調達手帳」を無料配布中!
キャッシュ不足に陥る原因&対策

キャッシュ不足に陥ってしまう原因はいくつか考えられます。それぞれの原因に応じて対策方法も変わってくるため、まずは原因を洗い出してから適切な対策を採ってください。
売上げが減少する
自社が販売している商品・サービスの売上げが減少してしまうことで、現金の不足により支出を下回ってしまうこともあります。
赤字経営になったとしてもすぐに倒産するわけではありません。
しかし、赤字状態が長く続いてしまえば手元の現金も枯渇していき、最終的に固定費などを支払うこともできず、倒産に追い込まれる可能性があります。
また、売上げ自体はそれほど減少していなくても、支出が増えて収入で賄いきれなくなれば赤字につながってしまうでしょう。
【対策1】売上げが減少した要因を洗い出す
売上げが減少したら、まずはその要因を洗い出すことが大切です。売上げが減少する要因は主に「外的要因」と「内的要因」の2つに分類できます。
外的要因には、トレンドや世間の経済状況の変化や競合他社の存在、商品イメージの悪化などが挙げられます。これらは自社の努力だけではコントロールしにくい要素です。
一方、内的要因には商品・サービスや社員などの質の低下や、新規顧客の開拓不足、客単価やリピート回数の低下などが含まれます。
これらは社内の取り組みによって改善できる可能性があります。
要因を洗い出したら、目標の再設定と方向性を明確にして改善に努めることが大切です。
【対策2】支出を見直し、不要なものは削減する
売上げの減少によるキャッシュ不足を防ぐためには、支出を見直して不要なものを削減することが大切です。
例えば、あまり効果が出ていない広告は出稿をやめて広告費を削減したり、業務フローを見直して無駄な作業や手間を減らし人件費を削減したりする方法などが挙げられます。
ただし、支出を削減しようとして自社の商品・サービスの質を低下させると、顧客離れにつながる可能性があります。
また、給与や賞与の減額を図ってしまうと、従業員のモチベーションが下がり生産性の低下につながるので注意が必要です。
回収と支払いのタイミングが合わない
掛け取引が多い業種の場合、売上金の回収と仕入れ先に支払うタイミングが合わず、バランスが崩れてしまうことでキャッシュ不足になる可能性があります。
例えば売上金の回収が2カ月後なのに対して、仕入れ先への支払いが1カ月後の場合、先に支払わなくてはならず、売上金以外から資金を捻出しなくてはなりません。
この場合、損益上は黒字となりますが、支払う時に手元の資金がなければ黒字倒産になる可能性が高いです。
【対策3】入金日・支払日を交渉する
回収と支払いのタイミングが合わないことでキャッシュ不足の状況に陥る場合、取引先と入金日・支払日について交渉する必要があります。
基本的には売上金が入金されたあとに仕入れ先などに支払うスケジュールにすれば、手元に現金が残る状況をつくりやすいです。
また、売上げが発生してから入金日まで一定の期間が空き、仕入れを急ぐ必要がない状況であれば、仕入れ日を遅らせることで支払日もずらすことが可能です。
さらに、現金ではなくクレジットカードを活用して仕入れることで、支払日が翌月または翌々月になり、キャッシュ不足を防げます。
【対策4】顧客ごとに締め日管理を行う
回収と支払いのタイミングを合わせるためにも、顧客ごとに締め日管理を行うことも重要です。
取引先ごとに掛け取引の締め日が違っている場合は、特に徹底した管理が必要となります。
月末を締め日に設定する傾向にありますが、場合によっては15日・20日頃を締め日とする場合もあります。
もし締め日が月半ばにある場合、締め日以降に取引があると翌月の請求に含めなくてはなりません。
一括管理をすると請求ミスが発生する可能性もあるため、締め日に関しては顧客ごとに管理をしたほうが良いでしょう。
売掛金の貸し倒れが発生する
掛け取引では実際に売上げたお金を回収するのに、1カ月または数カ月かかってしまいます。
業種によって異なりますが、例えば建設業や不動産業、機械・システム設計などは長期間空いて入金されるケースも少なくありません。
売掛金が入金される前に取引先が破産・倒産してしまった場合、売掛金を回収できなくなる「貸し倒れ」が発生します。
貸し倒れが発生すると、売掛金を回収できず損失が出てしまい、資金繰りの悪化もしくは倒産するリスクがあります。
【対策5】取引開始から1年未満の企業には特別な条件を設ける
取引を開始してから1年未満の企業は、信用関係がまだ十分に構築されていない場合が多いです。
そのため、取引を開始してから1年未満の企業に対しては、特別な条件を設けて掛け取引に応じることも重要な対策といえます。
例えば、1カ月あたりの取引金額に上限を設定したり、支払期日を前倒しにしたりするなどです。
このような特別な条件を設けることで、事前に回収不能となるリスクを軽減できます。
また、特別な条件を設けて一定期間以上取引を続けた際に、徐々に条件を満たせなくなった取引先が淘汰されていくため、リスクのある取引先の排除にも有効です。
【対策6】取引先の与信調査を実施する
安心して取引を行うためにも、取引先の与信調査は行ったほうが良いです。与信調査の内容は様々ですが、例えば以下の調査方法が挙げられます。
| 調査方法 | 内容 |
| 社内調査 | 過去の取引履歴や取引先を担当した自社の従業員に聞き取り調査を実施する |
| 直接調査 | 取引先を訪問または電話・FAXなどで聞き取り調査、またはアンケート調査を実施し、情報を収集する |
| 外部調査 | 登記情報など外部でも取得できる公的情報はすべて収集し、事実と相違がないか、特殊な履歴はないかをチェックする |
| 依頼調査 | 外部の調査会社に依頼し、財務情報を取得する |
在庫の抱えすぎ・滞留が発生している
在庫の抱えすぎや滞留が発生していることも、キャッシュ不足の原因として挙げられます。
在庫を大量に抱えているということは、売上げが出ないばかりか仕入れ金を回収できない状況ともいえます。
また、在庫を保管するためのスペースを確保したり、維持・管理で人手が必要だったりするため、その分コストが高くなってしまうことも要因の1つです。
特にトレンドの商品や季節に左右される商品などは売れ残りが発生しやすいため、注意が必要です。
【対策7】適正在庫を把握して維持する
在庫の抱えすぎや滞留を防ぐためには、まず適正在庫を把握することが大切です。適正在庫は欠品が出ない最小限の在庫を指します。
どのくらいの商品数を確保すれば欠品を出さずに在庫数を維持できるか、過去の売上げデータなどを元に分析し、適正在庫を見極めてください。
また、一度適正在庫を決めて運用したとしても、在庫の過剰や欠品が発生する可能性はあります。
適正在庫を維持するためにも、運用後でも在庫の過剰や欠品が発生した場合は都度適切な値を定め、適正化されてからも1年に1回は最適化を図るようにしてください。
【対策8】不良在庫を値引き販売または廃棄する
多くの不良在庫を抱えてしまった場合には、値引き販売または廃棄して在庫を少なくすることも大切です。在庫が少なくなれば管理にかかるコストの削減にもつながります。
まずは、不良在庫の品質が落ちる前に値引き販売を実施します。
ただし、値引き販売を頻繁に繰り返すと、企業やブランドのイメージダウンにつながるのであまり繰り返して行わないようにすることが大切です。
セールを行っても売り切れなかった場合は、廃棄することになります。廃棄する場所のルールに従い、正しい手続きをしてから廃棄してください。
また、廃棄する前に専門の業者へ買い取ってもらうこともできます。
廃棄だと処分するのにコストがかかってしまうものの、買取によって多少でも買取金を受け取ることが可能です。
ただし、業者が買い取ったあとはどの市場に流通するのか自社で決められないため、流通する市場によってはイメージダウンにつながる可能性もあります。
過剰な設備投資を行う
生産性や業務効率、競争力の向上などに設備投資は必要となってきますが、過剰に設備投資を行った結果、キャッシュが不足してしまうケースもあります。
例えば設備を購入すると減価償却費として数年にかけて会計処理が行われますが、実際にはまとめて支払われているため、現金が不足する状態になります。
また、設備投資をしてもすぐに効果が出るわけではなく、リターンまでに時間がかかってしまうことも要因の1つです。
他にも、設備の購入を借入金で賄った場合、毎月返済が発生することで営業キャッシュフローが圧迫し、日常の運転資金に余裕がなくなってしまいます。
【対策9】費用対効果を調査する
いくら最高級の設備に投資したとしても、それが売上げや利益、生産性などの効果に見合っていなければ意味がありません。
また、購入金額を回収できるまでの時間が長すぎることで、設備の老朽化により期待していたほどの効果が得られなくなってしまう可能性もあります。
設備はメンテナンスや修理費用などで都度コストがかかってくることから、費用対効果もきちんと調査・シミュレーションをした上で判断することが大切です。
ただし、高い効果を得られたとしてもキャッシュフローが著しく悪化してしまう場合は注意してください。
【対策10】運転資金と投資資金は分けて考える
設備の運転資金と投資資金を分けずに考えてしまうと、金融機関などから投資資金を調達する際に毎月の返済負担が大きくなり、運転資金に影響する可能性があります。
そのため、基本的に設備の運転資金と投資資金は分けて考えたほうが良いでしょう。
借入金の返済や利息負担が増える
資金繰りの悪化に悩んでいる時、借入金を利用することで一時的にキャッシュフローが改善する場合もあります。
しかし、一時的に改善されたとしても、後々借入金の返済や利息負担が増えてしまうことで、キャッシュ不足に陥る可能性が高いです。
【対策11】返済計画の見直しを行う
借入金を利用すること自体は決して悪いことではありません。しかし、無計画に利用してしまうと後々負担が大きくなっていき、キャッシュ不足に陥りやすくなります。
特に返済額が大きすぎる場合は金融機関と相談し、返済計画を見直すことが大切です。
返済計画の見直しによって返済期間を延長してもらえれば、毎月の負担も軽減されます。
ただし、返済期間が延びるとその分支払う利息が増え、総返済額が増えてしまうので注意してください。
【対策12】借り換えを検討する
現在の借入金を新しい条件の融資に置き換えることを「借り換え」と呼びます。
融資の借り換えは、現在の借入条件より低金利の融資に借り換えることで毎月の負担を軽減できたり、返済期間を延ばせたりするなど、様々なメリットがあります。
また、複数の金融機関から借入をしている場合、1つにまとめることで資金管理がしやすくなり、経営の効率化を図れることもメリットです。
ただし、借り換えによって手数料が発生したり、取引している金融機関との関係性に変化が生じたりするケースもあるため、慎重に検討するようにしましょう。
売上げが急激に増加する
キャッシュ不足に陥る原因として売上げの減少を挙げましたが、実は売上げが急激に増加することでもキャッシュ不足になる可能性があります。
売上げが急激に増加すると、その分仕入れ代金などの変動費も増えてしまいます。
掛け取引だと売上金の回収は数カ月後になってしまうことから、増えた変動費を支払うのに手元の資金が枯渇し、キャッシュ不足に陥ってしまうのです。
【対策13】キャッシュフローの最適化を図る
売上げの急激な増加により、在庫の購入や人件費などの運転資金の需要が高まり、支出が増加します。
この時、支出をするタイミングを正確に把握し、キャッシュフローを最適化させることが重要です。
例えば、取引先と支払い条件について交渉したり、売掛金を早めに回収できるよう支払日を交渉したりするなどです。
キャッシュフローの最適化を行うことで売上げの急激な増加にも素早く対応でき、安定した経営につながります。
【対策14】資金調達を行う
売上げの急激な増加に伴って運転資金も増加し、自己資金だけで賄うのが難しくなった際には、資金調達を行うのも黒字倒産を防ぐ1つの方法です。
資金調達の方法は多岐にわたりますが、まず考えたいのが日本政策金融公庫からの融資です。
日本政策金融公庫は成長初期にある企業や小規模事業者でも融資が受けやすく、民間の金融機関より低金利の融資を受けられる可能性があります。
ただし、金融機関から融資を受けるのに、審査から実際に入金されるまで1~2カ月程度の時間がかかってしまいます。
そのため、事前に売上げや支出を予測し、資金を確保したほうが良いと判断した際には早めに金融機関へ相談してください。
▶▶▶資金繰りの不安を減らす基本を一冊にまとめた「はじめての資金調達手帳」を無料配布中!
日々のキャッシュ管理で資金繰りの問題は防げる

キャッシュ不足を防ぎ資金繰りを悪化させないためには、日々のキャッシュ管理を徹底することが大切です。
毎日の取引を帳簿や現金出納帳に記録し、現金の流れを明確にする必要があります。
あとでまとめて記録しようとすると、リアルタイムで現金がどれだけあるのか把握するのが難しくなり、キャッシュ不足に陥る可能性が高いです。
また、取引だけでなく現金の出し入れの記録を正確に残しておくことで、将来的な予算の立案や税務申告でのトラブルを未然に防げるようになります。
キャッシュ不足以外にも様々な効果が期待できるため、日々のキャッシュ管理は行うようにしてください。
まとめ・キャッシュ不足にならないよう資金の動きを日々意識しよう
キャッシュ不足は、黒字倒産のような深刻なリスクを招く要因となります。
その背景には、売掛金回収の遅れや在庫過多、過剰な投資や借入金の負担など、日常の経営活動の中で見過ごされがちな原因が潜んでいます。
利益が出ているかどうかだけでなく、「今、手元にいくら資金があるのか」「近い将来どのタイミングで資金が出入りするのか」を把握することが重要です。
日々のキャッシュ管理を徹底し、健全な経営を維持することで、突然のキャッシュ不足に振り回されることなく安定した事業運営を実現できるでしょう。
キャッシュ不足の不安を減らす近道は、資金調達の“正しい型”を知ること。『はじめての資金調達手帳』は、公的融資・制度融資の基本、申請の流れや審査のポイント、信用づくりのコツまでを実務目線で整理。黒字倒産を防ぐ備えとして、今すぐ無料でチェックしてください。
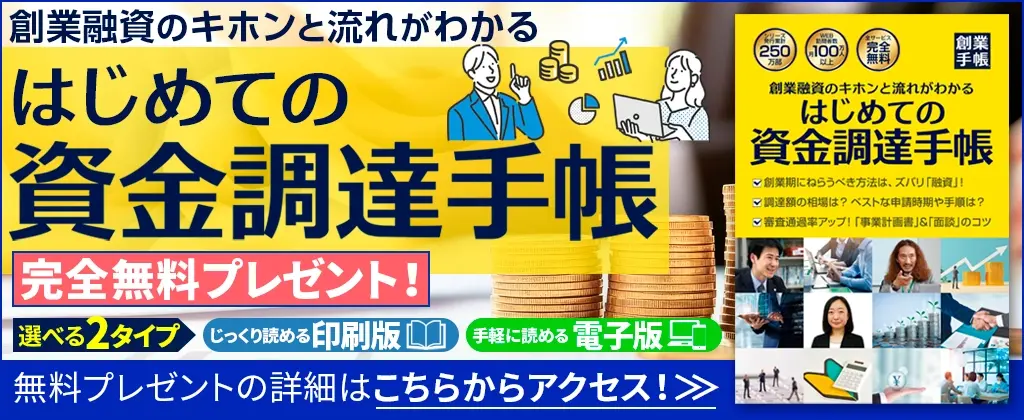
(編集:創業手帳編集部)





































