起業1年目の経理はこれで安心!勘定科目と仕訳の基礎を丁寧に解説
起業をするなら会計処理の知識も身に付けよう

起業したばかりの頃は、商品やサービスの企画・営業に集中しがちですが、実は「お金の管理」も事業を続ける上で欠かせない大切な仕事です。
特に経理の基本となる「勘定科目」や「仕訳」を理解しておくことで、日々の取引を正しく記録でき、資金繰りや決算の際に慌てることも少なくなります。
この記事では、経理初心者でもわかりやすいように、勘定科目と仕訳の基本を丁寧に解説していきます。
勘定科目と仕訳についてきちんと理解したいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
「経理って難しそう」「仕訳や勘定科目ってどう覚えればいいの?」起業したばかりの人の多くが、そんな不安を抱えています。
この記事では、会計の基礎をやさしく解説しながら、日々の取引を整理するコツを紹介します。
また、経費の分類に迷ったときに役立つ『経費チェックシート』も無料で配布中。
経理初心者の方は、ぜひ一緒にダウンロードして活用してください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
勘定科目と仕訳の基本を理解しよう

勘定科目と仕訳がそもそもどういったものなのか、基本を理解することが大切です。まずは、勘定科目と仕訳の概要について解説します。
仕訳とは?
仕訳とは、お金やモノの動きをルールに沿って記録していくことです。
事業を運営していく中で顧客や取引先などとお金やモノのやり取りが生まれますが、この取引を「借方」と「貸方」に分類し、金額や取引に当てはまる勘定科目を帳簿に記載していきます。
日々の仕訳によって、お金やモノがどこから来てどこに行ったのかを把握できるようになります。
正しく記録していくことで、事業の経営状況を客観的な数字として理解することが可能です。
勘定科目とは?
勘定科目とは、仕訳をする際に用いられる簿記の科目です。お金の出入りをよりわかりやすく分類するために用いる「見出し(ラベル)」と捉えると良いでしょう。
例えば家計簿で毎月の生活費を記録しようとしたとき、家賃・光熱費・食費・交通費といった項目に分けて記録していきます。
仕訳も同様に、取引内容に応じて決められた科目名をつけて管理します。
貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表を作成する際は、勘定科目ごとに金額をまとめ、分類にあわせて合計額を記入することになります。
取引内容を適切に勘定科目で仕訳をしていないと、正確な財務諸表を作成できなくなってしまうので注意が必要です。
【区分別】勘定科目の一覧
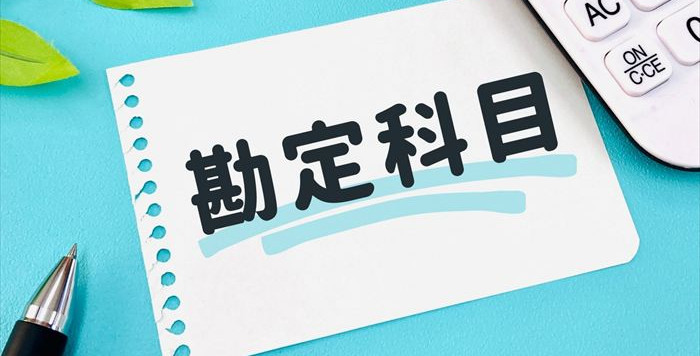
勘定科目は主に5つのグループに分類されます。ここで、それぞれの分類について解説していきます。
| 分類 | 特徴 | 主な勘定科目例 |
| 資産 | 会社が保有する財産や、将来お金になると予想されるもの | 現金、預金、売掛金、土地、ソフトウェア、開業費など |
| 負債 | 将来支払い・返済しなくてはいけないもの | 長期借入金、買掛金、未払金など |
| 純資産 | 原則返済義務がない資産(資産から負債を差し引いた残り) | 資本金、資本剰余金、利益剰余金など |
| 収益 | 会社がお金を得る原因となっているもの | 売上高、受取利息、雑収入など |
| 費用 | 会社がお金を使う原因となっているもの | 仕入、給料、地代家賃、消耗品費、水道光熱費など |
資産
資産とは、会社が保有する財産や将来的に財産・収益をもたらすと予想されるものが分類されます。資産はさらに3つの区分にグループ分けすることが可能です。
-
- 流動資産:1年以内に現金で回収されるもの(現金、預金、売掛金など)
- 固定資産:1年を超えて現金で回収されるもの(不動産、機械装置、ソフトウェアなど)
- 繰延資産:支出効果が1年以上におよび、数年間費用計上できるもの(開業費、開発費など)
貸借対照表を作成する場合、資産の勘定科目は借方(左側)に記載することになります。
負債
負債とは、会社が保有するマイナスの資産で、支払い義務を負っているものや将来的に費用または損失になると予想されているものを指します。
負債もさらに細かく2つのグループに分類することが可能です。
-
- 流動負債:1年以内に支払期限がやってくるもの(買掛金、支払手形、未払金など)
- 固定負債:1年を超えて支払期限がやってくるもの(長期借入金、社債、繰延税金負債など)
銀行からの融資や取引において未払いの金額などは、いずれ返済していかなくてはならないため、分類は負債です。
また、それ以外にも資産が減少するものは基本的に負債に該当します。
貸借対照表では貸方(右側)に記載していくことになります。
純資産
純資産とは、資産から負債を差し引いた「会社の正味の財産」を指すものです。純粋な資産となるため、返済する義務は発生しません。
純資産は主に株主資本とそれ以外(新株予約権、評価・換算差額等)に分類できます。
-
- 株主資本:株主からの出資金や留保利益などを計上するための科目(資本金、繰越利益剰余金など)
- 新株予約権:決まった金額で株式を買える権利を計上するための科目(新株予約権、ストックオプションなど)
- 評価・換算差額等:取得原価や期末の時価によって生じた評価差額などを計上する科目(有価証券評価差額金、外貨換算調整額など)
収益
収益とは、資本金取引以外の営業活動で増えた資産を指します。例えば、商品・サービスを販売して得た売上は収益に分類されます。
-
- 売上:本業によって得られた収益
- 営業外利益:本業以外で得られた収益(受取利息、雑収入など)
- 特別利益:事業と直接関係なく、例外的に発生した利益(固定資産売却益、投資有価証券売却益など)
収益が増加することで、会社の利益が上がることはもちろん、純資産の向上も期待できます。収益は損益計算書を作成する際に用いられ、費用勘定の右側に記載します。
費用
費用とは、利益を得るために使った経費を指します。主に4つの区分に分類することが可能です。
-
- 売上原価:商品・サービスを提供するのに必要な費用(仕入、製造原価など)
- 販売費および一般管理費(販管費):商品・サービスを販売するのに必要な費用や経営管理に必要な費用(広告宣伝費、給料、地代家賃など)
- 営業外費用:本業以外で発生した費用(支払利息、支払配当金、有価証券売却損など)
- 特別損失(特損):事業と直接関係なく、例外的に発生した費用(固定資産売却損、貸倒損失など)
費用は負債と異なり、収益を得るために支払ったお金が分類されるため、費用が多い=事業がうまくいっていないとは判断されません。
収益から費用を差し引き、利益を算出することで事業がうまくいったかどうかがわかります。損益計算書に記載する際は、左側に記載します。
初心者が押さえておきたい仕訳の基本パターン

実際に仕訳を行う際には、基本のパターンを覚えておくとスムーズかつ正確な会計処理につながります。ここで、各場面における仕訳例を紹介します。
商品を仕入れた場合の仕訳例
| 取引内容 | 勘定科目例 |
| 販売目的で商品を仕入れた | 仕入/現金・買掛金など |
| 製品づくりに必要な材料を仕入れた | 材料費/現金・買掛金など |
| 展示目的で商品を仕入れた | 広告宣伝費/現金・買掛金など |
主に販売することを目的として商品を仕入れた場合、「仕入」の勘定科目を用いることが多いです。
また、製品づくりに必要な原材料を仕入れた場合は、「材料費」を使うケースもあります。
見本品の配布や展示を目的に商品を仕入れた場合は、「広告宣伝費」に計上することが多いですが、仕入で一括りにしてしまっても問題ありません。
売上が発生した場合の仕訳例
| 取引内容 | 勘定科目例 |
| 商品・サービスが売れた | 現金/売上 |
| 掛売りで商品を売った | 売掛金/売上 |
| 回収した | 現金/売掛金 |
売上が発生した場合は、現金や預金の増加と売上高の計上を行うことになります。
ただし、掛売りで商品を販売した場合は、現金はあとから回収することになるため、仕訳では「売掛金」を用います。
経費を支払った場合の仕訳例
| 取引内容 | 勘定科目例 |
| 電気代・ガス代・水道代を支払った | 水道光熱費/現金など |
| 機材・機械を一時的に借りた | リース料/現金など |
| 会計ソフトを購入した | ソフトウェアまたは消耗品費/現金など |
経費を支払った場合は、それぞれの内容に合わせて適切な勘定科目を割り当てる必要があります。
例えば、事業所の電気代やガス代、水道代を支払った場合は「水道光熱費」に割り当てるのが一般的です。
ただし、リース料やソフトウェア費などは1つあたりの購入金額と使用可能期間によって費用計上できない場合があります。
費用に該当しない1つあたり10万円以上のものは「経費」ではなく「資産」の勘定科目に分類されるので、よく確認するようにしましょう。
税金を納める場合の仕訳例
| 取引内容 | 勘定科目例 |
| 収入印紙を購入した | 租税公課/現金など |
| 印鑑証明書を発行するための手数料を支払った | 租税公課/現金など |
| 源泉徴収税を従業員の給料から天引きした | 給料/預り金 |
税金や公的な費用を納める場合、基本的に「租税公課」という勘定科目が使われます。
ただし、源泉徴収税は従業員に納税義務が発生します。雇い主が代わりに納税するため、給料から天引きする際は「現金」ではなく「預り金」を用いて計上するのが基本です。
仕訳・勘定科目で注意すべきポイント

勘定科目を使って正確に仕訳を行う際には、以下のポイントも押さえておく必要があります。ここで、仕訳・勘定科目の注意点を解説します。
借方と貸方の合計が一致しているかチェックする
仕訳をする際に、借方(左側)と貸方(右側)に該当する勘定科目と金額を記載していきますが、借方と貸方の合計は必ず一致していなくてはなりません。
借方と貸方の合計金額が合わなかった場合、記入漏れまたは数字を書き間違えている可能性があるので、再度見直しを行ってください。
あとから修正しようとするとすべての取引を見直す必要が出てくるため、1つの取引を仕訳するたびに借方・貸方の合計が一致しているか確認しておくと安心です。
取引によっては借方と貸方のいずれかが2つ以上の項目になることもあります。
例えば取引先へ商品5,000円に送料1,000円を加えた合計金額で販売し、送料のみ現金で受け取って商品代金を掛けとした場合の仕訳は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 |
| 売掛金5,000円 | 売上5,000円 |
| 発送費1,000円 | 現金1,000円 |
1つの取引の中で借方と貸方に2つ以上の項目が発生していますが、最終的な合計がどちらも同じ金額になっていれば問題ありません。
事業に合った勘定科目を設定する
勘定科目は事業内容や取引の特性に合わせて自由に設定することが可能です。
一般的な勘定科目はわかりやすいので良いですが、事業に最適な勘定科目を選択することも重要となります。
例えば建設業では特有の会計処理が用いられており、「完成工事未収入金」や「未完工事支出金」「完成工事高」「完成工事原価」などの勘定科目があります。
ただし、事業に合わせた勘定科目であっても、第三者から見てその取引内容がわかるようなものにしなければなりません。
独自の勘定科目を使いすぎてしまうと、税理士や税務署が取引の内容を把握しづらくなってしまうので注意してください。
一度決めた勘定科目は継続して使う
勘定科目は基本的に一度使ったものを継続して使う必要があります。例えば以前「販売費」として計上したものを、別の取引では「営業費」に変更するなどです。
同じ取引であるにもかかわらず勘定科目を変更してしまうと、各年度で財務諸表を比較しようとしても、正確な比較ができなくなってしまいます。
会計処理のルールとして「継続性の原則」というものがあり、一度決めた会計処理の方法は毎期継続して適用しなくてはならないと定められています。
正当な理由があり、どうしても変更しなくてはいけない場合は財務諸表にその旨を記載しておいてください。
勘定科目の名称は統一させる
勘定科目の名称は統一させることも重要です。同じ社内でも部署や担当者によって勘定科目の名称が変わっていると、会計処理の際に混乱する恐れがあります。
正しく財務諸表を作成するためにも、勘定科目の名称は部署・担当者を問わず、社内で統一させたほうが良いでしょう。
仕訳作業に会計ソフトを活用するのもおすすめ

仕訳や勘定科目などは慣れてくればスムーズに記入していくことも可能ですが、慣れるまでに時間がかかってしまうものです。
特に個人事業主などは、1人で本業と経理などの事務作業をどちらもこなす必要があります。効率的かつ正確に会計処理を行うためにも、会計ソフトの活用がおすすめです。
会計ソフトは直感的な操作によって入力することも可能で、会計処理で用いられる専門用語などを知らなくても自動的に仕訳や帳票の作成を行ってくれます。
また、会計ソフトを使っているうちに徐々に用語の意味や使い方などがわかるようになります。
ソフトによってはヘルプ機能やサポートなども備わっていることから、経理初心者は積極的に会計ソフトの活用を検討してみてください。
まとめ・仕訳と勘定科目の基本を押さえて正確に会計業務を行おう
仕訳はお金の動きを記録するルールであり、勘定科目は仕訳の動きを分類するための見出し(ラベル)です。
この2つを正しく理解していれば、日々の取引を整理して事業の運営状況を数字で把握できるようになります。
最初は難しいと感じることも多いですが、慣れればスムーズに記入することも可能です。
また、会計ソフトを活用すれば計算ミスを防ぎつつ、効率的に仕訳や帳票の作成も担ってくれるので、経理初心者は特に活用を検討してみましょう。
経理を正しく行うには、「どの支出をどの勘定科目で処理するか」だけでなく、
「どこまでが経費として認められるのか」を把握しておくことも大切です。
創業手帳では、事業で使える経費を項目ごとに整理した
『経費チェックシート』を無料で配布中です。
無駄な出費を防ぎながら、経理と節税を両立したい方はぜひご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)



































