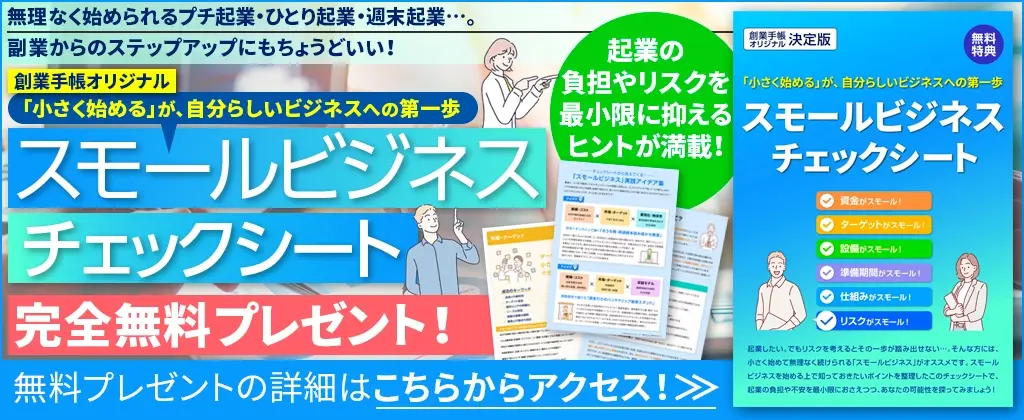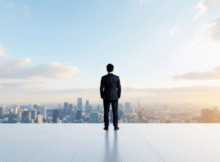定年後のプチ起業|50-60代でも無理なく始められる副業5選
自分らしく働ける!定年後のプチ起業という選択肢

「好きなことを活かして働きたい」「定年後も自分のペースで収入を得たい」――そのような50~60代に注目されているのが“プチ起業”です。
大きな投資をせずに、無理のない範囲で始められるのが特徴です。
この記事では、定年後におすすめのプチ起業5選と、失敗しないための準備・進め方を紹介します。
創業手帳の『スモールビジネス・チェックシート』では、定年後でも始めやすい小さな事業の考え方や、無理をしない続け方のポイントを整理しています。「まずは小さく試してみたい」という方は、ぜひ無料特典も活用してみてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
プチ起業が50〜60代に人気の理由

現在、50~60代でプチ起業を始める人が増えています。
人気を集めている理由として、プチ起業は本格的に起業するよりも初期費用を抑えられ、万が一失敗したとしても退職金や年金にそれほど大きな影響を与えないことが挙げられます。
また、プチ起業なら自分の好きな時間・好きなペースで働けることから、自分の体力や健康状態に合わせて無理なく働くことができるでしょう。
さらに長年培ってきた経験・スキルを活かせる分野で仕事ができるため、やりがいを感じながら収入を得られるのも、プチ起業が人気を集めている理由の1つです。
定年後のプチ起業のメリット・注意点
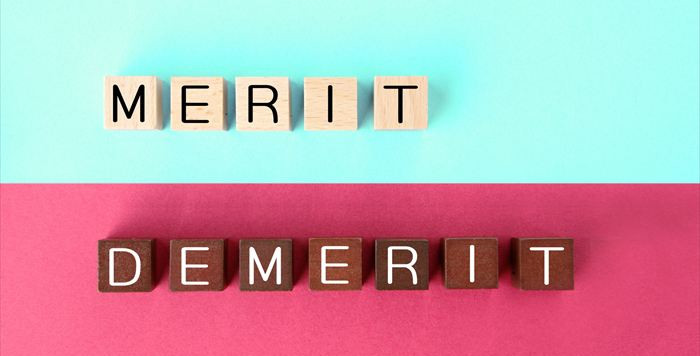
定年後にプチ起業を始めた場合、様々なメリットを得られますが、注意点やリスクも存在します。ここで、定年後にプチ起業をするメリットと注意点について解説します。
プチ起業のメリット
プチ起業と一般的な起業を比較した場合、プチ起業には様々なメリットが挙げられます。
低リスクで始められる
起業というと失敗した時のリスクが大きいイメージを持つ人もいますが、プチ起業であれば低リスクに抑えつつ事業を始められます。
失敗したとしても生活に大きな支障を与えることもなく、退職金や年金が一気に減ってしまう心配もありません。
また、起業する際には設備投資などで大きな借金を抱えることもありますが、プチ起業ならそのような設備投資や借金も不要になるため、気軽に始められます。
生きがいと社会参加の機会が得られる
定年後は好きなことに使える時間が増える一方で、暇に感じてしまう人も少なくありません。
そのような時間をプチ起業に有効活用すれば、社会とのつながりを保ちつつ生きがいを見つけることもできます。
また、これまでに培ってきた経験やスキルを活かせる仕事を始めれば、「これまでの人生で得てきたものがほかの人の役に立っている」と実感でき、自己肯定感と充実感を味わえます。
さらに、プチ起業を通して新しい出会いや交流が生まれれば、定年後に感じやすい孤独感も解消されるかもしれません。
経済的・精神的な充実感が得られる
定年を迎えて長年勤めてきた会社を辞めた場合、退職金を受け取れるものの入ってくる収入が公的年金だけになってしまいます。
これまでの収入と差があることから、「本当にこれで老後生活を快適に送れるのだろうか?」と不安に感じてしまう人もいるでしょう。
しかし、定年後にプチ起業を始めれば、年金以外の収入が得られて経済的な余裕に加え、精神的な充実感も得られるようになります。
また、好きなことを仕事にして収入を得られる喜びから、仕事に対するモチベーションも高まり、前向きな生活を送ることができます。
プチ起業の注意点・リスク
プチ起業には注意すべき点やリスクもあります。ここで、どのような注意点・リスクがあるのか確認しておいてください。
収入の不安定性
定年後のプチ起業によって年金以外の収入を得ることができますが、事業がうまくいっていない場合は収入が不安定になりがちです。
そのため、基本的には年金で生活費を賄い、プチ起業で得た収入は余裕資金として考えたほうが良いでしょう。
また、業態によっては季節や景気の影響を受け、一定の収入を得るのが難しい場合もあります。
売上が上がらない月があることも想定した上で、生活面に支障が出ない範囲で取り組むことが大切です。
体力・健康面のリスク
小規模からスタートした場合でも、老後は体力の衰えや健康状態の変化によって、体調面に影響が出てしまうことも少なくありません。
無理をし過ぎてしまうと事業を思うように続けられなくなってしまうだけでなく、医療費の負担が増えて経済的にもマイナスになる可能性があります。
また、年齢と共に集中力・判断力も低下しやすくなっています。安全面にも考慮して事業を選ぶことが重要です。
事務処理・手続きの負担
プチ起業でも事務処理や手続きなどは必要になってくるため、事務作業に関する知識も身につけておく必要があります。
特にこれまで企業に勤めていた人だと確定申告をしたことがないケースも多く、慣れない事務作業に本業よりも時間と労力を割かれる可能性が高いです。
また、法的な責任も発生することから、知識がない状態で始めてしまうとトラブルに巻き込まれる恐れもあります。
50-60代におすすめ!無理なく始められる副業・プチ起業5選

50~60代でプチ起業を始めるなら、体力や経済的にも無理なく始められるものを選ぶことが大切です。
続いては、50~60代でも無理なく始められる、おすすめの副業・プチ起業を紹介します。
1. ネットショップ・ハンドメイド販売
編み物や木工などの趣味を活かして、ハンドメイド商品を販売するネットショップの運営でプチ起業ができます。
ネットショップなら実店舗を設ける必要がないため、初期費用を抑えることができます。
しかも、全国の消費者がターゲットになることから、比較的ニッチなアイテムでも勝負していくことが可能です。
もともとハンドメイドを趣味にしていた人も、商品作りを楽しみながら収入が得られます。
また、オンライン販売のノウハウを身につけて、自分が作った商品だけでなく様々な商品を取り扱うことができれば、さらなる収入アップも期待できます。
2. シニア向け教室・講座
シニア向け教室や講座は、自分が得意な分野を活かして収入を得られる業種です。
シニア向けの教室であれば、同世代の参加者と多く交流を持つことができ、社会的なつながりを保てます。
シニア向けの中でもおすすめなのが、スマホ教室やパソコン教室、料理教室などです。
教室は自宅で開催すれば、別で教室を準備して利用代を支払う必要もありません。また、教えることで人の役に立っていると実感することもできます。
最初は月1~2回の開催からスタートし、参加者の反応を見ながら徐々に頻度を増やしていくのがおすすめです。
3. 軽飲食・キッチンカー
軽飲食やキッチンカーもおすすめの業種の1つです。
ほかの業種に比べて初期費用はかかってしまうものの、例えば、たこ焼きや焼き鳥といった簡単な調理で始められる軽飲食なら、大きな設備投資をしなくても開業できます。
また、キッチンカーなら店舗を持たなくても良いので、家賃がない分固定費を安く抑えられ、基本1人で運営することから人件費などもかかりません。
地域のお祭りやイベントに積極的に出店すれば、固定の店舗がなくても収入を得られるでしょう。
なお、軽飲食やキッチンカーで開業する場合には、食品衛生責任者の資格を取得し、保健所に届け出を提出する必要があります。
ただし、手続き自体はそれほど面倒なものではないので、飲食を始めてみたいものの予算的に大きい店舗を持つのが難しい場合は、軽飲食やキッチンカーを視野に入れてみてください。
4. 趣味を活かしたワークショップ
長年続けてきた趣味を教えるワークショップもおすすめです。自分も趣味を楽しみつつ、いろいろな人にその趣味の良さを教えながら収入を得られます。
ワークショップで使用する材料費は参加費に含められるため、少ない持ち出しでも開催することが可能です。
ワークショップにも様々な種類がありますが、例えば、ビーズやレジンなどを活用したアクセサリー作りやアロマキャンドル作り、子ども向けの工作などもおすすめです。
自宅で開催するのも良いですが、地域のカルチャーセンターや公民館と連携することで、集客の負担も軽減できます。
5. 地域サービス・代行業
草刈りや庭木の剪定、簡単な大工作業、買い物の代行サービスなどの地域サービス・代行業は、特別なスキルを持っていなくても始められるプチ起業です。
体力によって難しいものもありますが、自分で何をやるのか、どのようなことができるのか選べるので、体力に自信がない人も安心です。
現在日本国内は超高齢社会であり、なおかつ共働き世帯も増えていることから、地域密着型の地域サービスや代行業はニーズが高く、安定した収入も期待できます。
また、近所からの口コミが広がれば仕事も増え、営業活動に時間をかけなくても自然に仕事が入ってくる状況を作れます。
失敗しないためのプチ起業の準備・進め方のポイント

定年後のプチ起業で失敗しないためにも、どのような準備が必要なのか事前に知っておくことも大切です。ここで、プチ起業の準備と進め方のポイントを解説します。
アイデア選びと市場調査
まずは、どのような業種でプチ起業をするのか、アイデア選びを行います。
やってみたいことやこれまでの経験を活かせるものなど、自分に合った起業アイデアを選んでください。
また、アイデア選びに加えて市場調査も行います。対象となる市場の規模や内情を理解し、競合分析を行ってください。
競合分析をすることで差別化するにはどうすればいいか、どの顧客層にターゲットを絞り込むかなどが見えてきます。
起業アイデアが思いついたら、家族や友人などに相談し、客観的な意見・アドバイスをもらうことで成功率を高められます。
必要な資格・許認可の確認
始める業種によっては資格や許認可を取得する必要が出てきます。例えば、食品関連なら食品衛生責任者、中古品を販売するなら古物商許可が必要です。
また、教室を運営するなら知識やスキルがあることをアピールできるように、各種資格を取得したほうが良い場合もあります。
事業内容によっては開業届・営業許可なども必要です。開業届や営業許可が必要な場合は管轄の役所で確認しておくと安心です。
資格や許認可によっては取得するまでに時間がかかってしまう場合もあります。時間がかかることも見越して、早めに手続きを進めるようにしてください。
資金計画と資金調達を行う
プチ起業で失敗しないためには、綿密に資金計画を立てることも重要です。
資金計画を立てずに始めてしまうと、予算を大幅に超えてしまい生活費に影響する可能性もあります。
初期費用は必要最小限に抑え、売上が安定するようになったら設備投資を拡大していくと、段階的にアプローチできます。
どうしても設備投資が必要だったり、資金が不足したりしている場合は、公的な融資制度や補助金などを活用してください。
しかし、その分リスクは高まってしまうため、まずは小規模から自己資金でスタートさせることが大切です。
自分のペースに合わせてスタートする
プチ起業は最初からフルタイムで働き続けるよりも、まずは週1~2日から始めたほうが失敗しにくくなります。
無理をしてオーバーワークになると体調面にも影響が出る可能性があるため、週1~2日の営業でスタートしてください。
最初は健康管理や家族との時間を大切にしつつ、軌道に乗ってきたら徐々に営業日・営業時間を増やしていきましょう。
事業が継続できる仕組みを作る
定年後はいつ体調を崩してしまうかわかりません。
そのため、体調が優れない時でもバックアップできる体制を構築しておき、無理をせずに事業を継続できる仕組みを作っておくことも大切です。
無理をしなくても事業を継続できる仕組みさえ作ってしまえば、事業よりも自分の健康を第一に考えた働き方ができます。
また、将来的に事業承継や事業売却なども考えつつ、長期的に事業計画を立てることが重要です。
定年後のプチ起業でよくある質問

定年後のプチ起業に関するよくある質問について、回答していきます。プチ起業について疑問がある人もぜひチェックしてみてください。
定年後に副業やプチ起業をしても年金は減らない?
定年後に副業やプチ起業を始めた場合、年金の減額は働き方や加入している年金によって異なります。
例えば、これまで会社員として働いていた場合は厚生年金に加入していることになります。
厚生年金には「在職老齢年金制度」があり、年金の受給期間に一定額の収入を得ていると、年金の一部または全額が支給停止になってしまうので注意が必要です。
ただし、個人事業主として開業した場合、給与ではなく事業収入になることから、在職老齢年金の対象にならず、減額されずに済みます。
年金を受給しながらでも開業届は出せる?
年金を受給している人も開業届を提出し、個人事業主として事業運営ができます。
開業届を出す際に青色申告承認申請書も提出すれば、青色申告の特典として最大65万円の特別控除を受けることも可能です。
ただし、事業所得として計上する際には、継続性と営利性が認められる規模の事業を運営している必要があります。
例えば、1回だけフリマアプリを使ってハンドメイドのアクセサリーを出品し、商品が売れた場合、臨時的な収入とみなされて雑所得に区分される可能性が高いです。
プチ起業でも確定申告は必要?
確定申告は、年間の事業所得が20万円を超えた場合に必要となります。そのため、プチ起業でも事業所得によっては確定申告の準備をしなくてはなりません。
確定申告では所得金額を計算する際に、事業で使った経費もすべて把握する必要があります。
領収書やレシートなども保管しておき、確定申告で正確な金額が出せるようにしておきます。
初めての起業で確定申告などが不安な場合は、税務署が実施する無料相談会への参加や税理士に相談することも検討してみてください。
まとめ|定年後の人生をもっと豊かに、自分らしい働き方を
プチ起業は一般的な起業と比べて小規模からスタートするため、リスクを抑えつつ年金以外の収入を増やせます。
定年後の新しい生きがいとして、収入だけでなく充実感も得ることができます。
体力や健康面のリスクなどがあるものの、健康第一で楽しみながら取り組めば、人生をより豊かなものにしていくことも可能です。
自分の経験・スキルを活かしつつ、無理のない範囲でプチ起業を始めてみましょう。
定年後に「小さく始める」起業を考えている方へ。
少ない負担で続けるコツや、将来どこまで広げられるかをチェックできる『スモールビジネス・チェックシート』を創業手帳が無料でご提供しています。
(編集:創業手帳編集部)