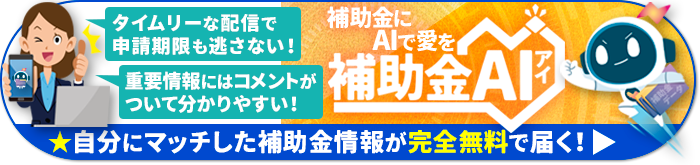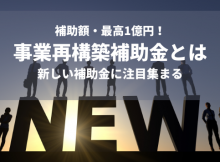シニアでも補助金はもらえる?定年後起業で使える支援制度まとめ
退職後も活用できる!シニア向け補助金制度

60歳過ぎれば引退したというのは昔の話です。退職後の長い人生で何をするかによって、人生の満足度は大きく変わります。
「60歳を過ぎても補助金は使える?」「定年後に起業したいけど、資金面が不安…」そのような方に向けて、シニアでも利用可能な起業支援制度・補助金をまとめました。
退職後の新しいチャレンジを後押しする公的支援を活用して、安心して一歩を踏み出してください。
創業手帳では、補助金・助成金の基本のしくみから、よく使われている補助金ランキングまでを掲載した『補助金ガイド』を無料でお配りしています。こちらもあわせてお読みください。
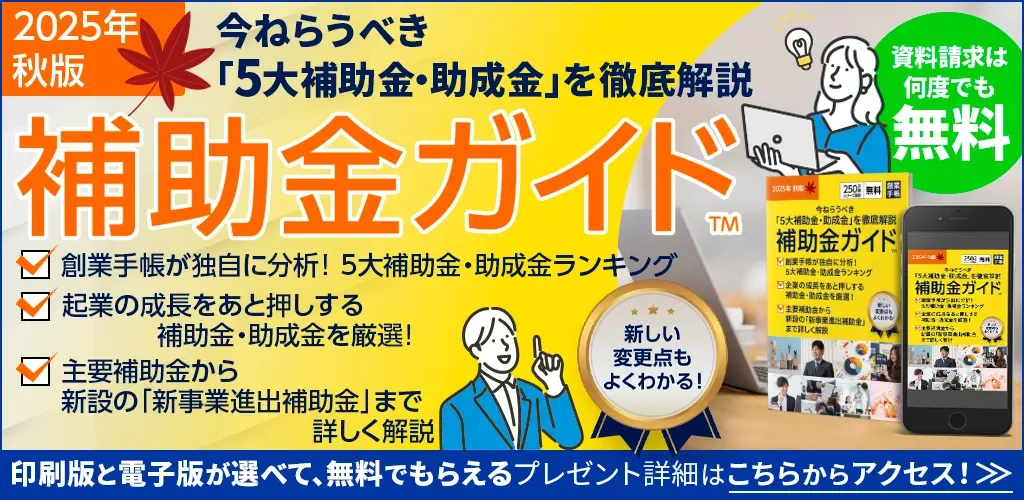
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
シニア起業でも補助金は使える?年齢制限はある?

補助金や公的なサポートは、若い世代のものでシニア起業では使えないと思い込んでいる人もいるかもしれません。
しかし、実際には多くの補助金では「年齢制限なし」で利用できます。
一般的に補助金の多くは、「創業〇年以内」「個人事業主・法人」が条件となるので年齢で制限されないことが多いです。
若年層に向けた補助金は存在しますが、一方でシニア向けの補助金といった年齢が上だからこそ有利に使える制度もあります。
以下でどのような補助金や制度を使えるのか確認してください。
シニア起業で活用できる代表的な補助金・制度一覧

シニアが起業する時に使える補助金や制度はいろいろあります。それぞれ対象者や条件が違うので事業に合ったものを選択してください。
以下では、代表的な補助金や制度を紹介しています。地方自治体が提供している制度もあるので、お住まいの自治体の精度を調べてみてください。
1. 小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、経営計画に基づいた小規模事業者の販路開拓、業務効率化などの取組みを支援するために経費の一部を補助する制度です。
通常枠と賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠があり、補助枠は2/3になります。賃金引上げ枠で赤字事業者については3/4です。
小規模事業者持続化補助金には補助上限が設定されていて、通常枠は50万円、それ以外は上限200万円となっています。
さらにインボイス特例の要件を満たす場合には、上限に50万円が上乗せされます。
補助金の対象者は、常時使用する従業員の数で決まっているため、シニアでも小規模事業者持続化補助金を利用可能です。
補助対象経費も、機械装置から広報費、ウェブサイト関連や開発費と幅広いので利用しやすいでしょう。
2. 創業・事業承継関連の自治体補助金
東京都や埼玉県など多くの自治体でシニア創業を支援する独自の補助金制度が設けられています。
地方自治体が提供している補助金制度は、その自治体の特色があらわれます。
地域密着型事業や地域課題解決につながるような事業は特に採択されやすい傾向にあるので、創業時に地域に関連した事業展開ができないか検討してみてください。
地方自治体の補助金は、市区町村の公式サイトや商工会議所で最新の募集情報が掲載されます。自分でホームページを確認するとともに、商工会議所に相談してみてください。
3. 日本政策金融公庫の融資(補助金との併用も可)
日本政策金融公庫が提供する女性・若者/シニア起業家支援資金は、女性や若年者シニアの視点を生かした事業の促進を図る中小企業者を支援する融資制度です。
対象となるのは、女性もしくは35歳未満か、55歳以上の人で新しく事業をはじめるか事業開始後おおむね7年以内の人です。
融資限度額は、直接貸付で7億2千万円、代理貸付で1億千万円になります。
融資は補助金と異なり返済義務があるものの、即座に資金調達できる点がメリットです。
起業してから資金不足に困るケースは多くあります。補助金と併用することで、より安定した資金基盤を築けます。
4. 中小企業支援センターなどの創業サポート制度
身近なビジネスの相談役として頼りになるのが都道府県に設置されている中小企業支援センターです。
中小企業支援センターでは、補助金申請書の作成支援や事業計画策定の無料サポートを受けることができます。
起業スクールや専門家派遣といった事業を実施しているため、、経営知識の習得と実践的アドバイスを得られるチャンスです。
事業をはじめたいが、専門的知識を持つ人材が必要な場合にも専門家の力を活用できます。
創業前から創業後まで継続的な伴走支援を受けられるため、初心者でも安心です。創業から海外展開、資金調達と事業の様々な場面で役立ちます。
5. ものづくり補助金(技術系事業向け)
ものづくり補助金は、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を目的とした設備投資・システム導入を行う時に受けられる補助金です。
製品・サービス高付加価値化枠とグローバル枠があり、製品・サービス高付加価値化枠は新製品新サービス開発の取組み、グローバル枠では海外事業の取組みを支援します。
ものづくり補助金も、事業所や従業員の要件はあるものの申請者の年齢は問われません。
製品・サービス高付加価値化枠は、設備投資やシステム構築、試作開発費が対象になるので技術系を専門とする人は利用を検討してみてください。
6. IT導入補助金(デジタル化支援)
IT導入補助金は、業務効率化や売上向上につながるITツール導入費用の一部が補助される制度です。
会計ソフトや顧客管理システムなど、事業運営に必要なソフトウェア購入費などが対象です。
インボイスに対応したITツールの導入に対して支援するインボイス枠やセキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠などもあります。
対象となるITツールは事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開されているもの限定です。
「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請するため、デジタル化に不安があるシニア起業家でも、専門業者のサポートを受けながら申請できます。
7. 事業再構築補助金(新分野進出向け)
事業再構築補助金は、新市場進出や業種転換など思い切った事業再構築に意欲がある中小企業等の挑戦を支援する補助金です。
成長分野進出枠(通常類型)と成長分野進出枠(GX進出類型)、コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に分けられそれぞれ違う補助上限額が設定されています。
事業再構築補助金は、事業計画を認定経営革新等支援機関の確認を受けて補助事業が終了してから3~5年で付加価値額の年平均成長率3~4%か、従業員ひとり当たり付加価値額の年平均成長率3~4%(事業類型により異なる)以上増加の達成が求められます。
枠によって対象となる事業者や条件が違うので、どれに該当するか確認してください。
補助金を活用する際の注意点

補助金はうまく活用できれば、事業を円滑にする手助けになります。しかし、注意点を把握しておかないと想定外の失敗をしてしまうかもしれません。
補助金を活用する際の注意点についてまとめました。
事前に申請しないと対象外になるケースが多い
補助金は原則として事前申請が必要であり、事業開始後の経費は対象外となる場合が多い点に注意してください。
設備購入や広告費といった経費が発生する前に、必ず補助金の申請手続きを完了しなければいけません。
補助金は申請してから採択され、入金されるまでに数カ月かかります。事業開始時期を逆算して早めの準備をしておいてください。
実績報告や書類作成が必要
補助金が採択された後も多くの行程が残されています。
実績報告書の提出や領収書の整理など、詳細な事務手続きが求められるので、必要書類を準備しておいてください。
書類作成に不安がある場合は、商工会議所や中小企業支援センターのサポートを活用できます。
専門家による申請書作成支援や実績報告のアドバイスを受けることで、手続きの負担を軽減してください。
後払いが多いため一時的な資金が必要
多くの補助金は経費を立替えた後に支給される後払い制度を採用しています。つまり、いずれ補助金が入金されるとしても、一度は自分で支払いをしなければいけません。
経費によっては高額になるため、事業開始時には自己資金または融資による資金調達が必要になります。
資金繰りを考慮して、補助金と日本政策金融公庫の融資を併用する方法も検討してみてください。
どこで情報を探せばいい?補助金探しの方法

補助金は様々な人に向けたものが用意されています。しかし、自分に合った補助金を探そうとすると難しく感じる人もいるかもしれません。
どうやって補助金を探せばいいのか紹介します。
ミラサポplus/J-Net21(公的情報サイト)
補助金を探しているのであれば、定期的にミラサポplusをチェックしてください。ミラサポplusでは、業種や地域を絞り込んで全国の補助金情報を効率的に検索できます。
また、J-Net21は中小機構が運営するサイトで、信頼性が高く最新の制度情報が随時更新されています。
起業の相談窓口として利用できる拠点も多く紹介しているので相談窓口を探している人もチェックしてみると良いでしょう。
ミラサポplusとJ-Net21はどちらも無料なので、積極的に活用してください。
自治体サイト
起業する時には、都道府県や市区町村の公式サイトを確認してください。その地域だけの創業支援補助金情報を獲得できます。
自治体の多くは、地域密着型事業や地域課題解決を目的とした事業に対して手厚い支援を用意しています。
募集時期や条件が自治体ごとに異なるため、定期的にチェックしてチャンスを逃さないようにしてください。
商工会議所
地域の商工会議所では補助金の相談から申請書作成まで、ワンストップでサポートを受けられます。
経験や実績が豊富なので、初心者にもわかりやすく制度の仕組みや申請のポイントの説明が受けられるはずです。
商工会議所では、定期的に補助金説明会や申請書作成セミナーが開催されています。同じ立場の起業家と情報交換をしたり、人脈づくりの場としても役立ちます。
地域の中小企業支援センター
地域の中小企業支援センターではシニア起業家向けの丁寧な相談対応を実施しています。
創業相談と併せて補助金の情報提供を受けることで、効率的に情報収集可能です。
補助金制度の基礎から申請方法まで、窓口でわかりやすく説明してくれるほか、創業してからも課題解決の相談に乗ってくれます。
創業手帳の「補助金AI」と「補助金ガイド」
創業手帳では、補助金を探している事業者に向けて補助金AIと補助金ガイドを提供しています。
補助AI(ほじょアイ)は希望条件を登録していると補助金情報が自動でマッチングされるシステムです。
地域別での絞込みやフリーワードマッチングもでき、今まで一件一件調べてきた補助金の情報を効率的に調べられます。
補助金ガイドは、補助金の最新情報や審査や採択後の事業報告の対策や申請の流れを開設している企業冊子で累計発行部数は、250万部を超えています。
補助AIや補助金ガイドは無料で利用できるので、まずは公式サイトをチェックしてください。
シニア起業の補助金に関するよくある質問

シニアは多くの経験や実績があるものの、補助金についてあまり知らないケースが多いでかもしれません。ここではシニア起業の補助金に関するよくある質問に回答します。
何歳まで申請できるの?
ほとんどの補助金制度では年齢の上限を設けておらず、70代や80代でも申請が可能です。
重要なのは年齢ではなく事業の実現可能性や継続性であり、シニアであっても健康状態や意欲が評価されます。
豊富な人生経験や専門知識は、審査で高く評価されます。経験や専門知識を活用して事業計画を立ててください。
会社員時代の経験は評価される?
長年の職業経験で培った専門知識や技術は、事業計画の信頼性を大幅に向上させる要素となります。
加えて、業界の人脈や取引先との関係性は、販路確保の根拠として審査で重要視される項目です。
管理職経験がある場合は、経営能力やマネジメントスキルとして評価されるので、今までの経験した職種や業種は積極的にアピールしてください。
申請が通らなかった場合の対処法は?
補助金は、申請しても審査を通過しないこともあります。もしも不採択になった場合でも審査員からのコメントが提供されるため、次回申請時への改善点が明確にできます。
同じ補助金制度でも複数回申請が可能なものが多くあるので、計画を見直して次回に再チャレンジ可能です。
ひとつの補助金がダメでもほかの制度や融資制度との組み合わせで資金調達の道筋を見つけられるので諦めずに取組み続けてください。
まとめ:シニアこそ補助金を上手に使って、無理のない起業を
補助金は年齢を問わず事業の成長を支援する制度であり、シニア起業家も積極的に活用できます。
補助金は、公募要領や申請の流れが難しく感じるかもしれません。
しかし、様々な媒体で情報収集したり、支援機関に相談したりと工夫すれば年齢に関係なく補助金を活用できます。
創業手帳などの無料ガイドで基礎知識を身につけ、計画的に起業準備を進めることが成功の鍵となるでしょう。
創業手帳では、経営者の方がよく使われている補助金・助成金を厳選して解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。補助金と助成金の違いから、補助金や助成金の最新トピックスまでわかりやすく解説。あまり補助金のことがわからない人はぜひこちらのガイドブックから補助金の勉強をスタートしてみてはいかがでしょうか。
(編集:創業手帳編集部)