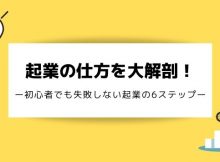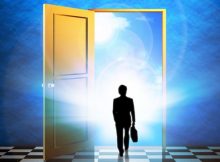開業後に後悔しやすいこと8選とその回避策|「やっておけばよかった…」を防ぐには
起業してから後悔をしないための事前準備をお教えします
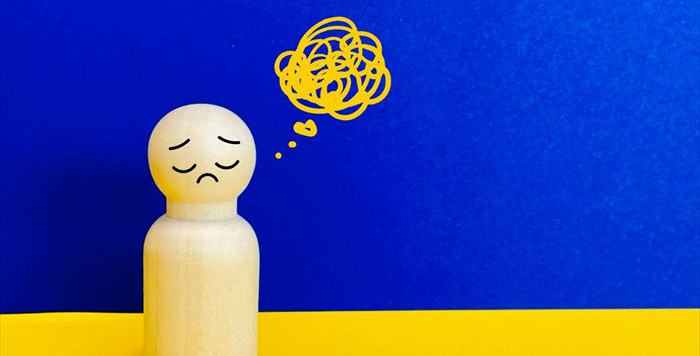
開業直後はやるべきことが多いです。準備不足のままスタートしてしまえば、起業を後悔してしまう人もいます。
そこで今回は、起業後によくある後悔の事例を時系列に紹介するとともに、それぞれの回避策も解説していきます。
これから起業を検討している人や後悔したくない人は、ぜひ参考にしてみてください。
創業手帳では、起業前の準備不足をなくすため「創業カレンダー」を無料でお配りしています。起業予定日を設定すると、その前後1年間のやることがわかるアイテムとなっています。ぜひこちらもあわせてご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
【起業の後悔1】ネーミングや屋号が安易すぎた

開業届を提出する際、屋号を記入する欄があります。必須項目ではありませんが、顧客や取引先からの信用を獲得するため、屋号名義での銀行口座の開設が可能な点が特徴です。
しかし、屋号を安易に考えることで後悔を招くケースもあります。失敗例と回避策を紹介していくので、屋号を検討する際の参考にしてください。
失敗例
屋号は会社の社名に相当するので、個人事業主であれば事業名や店舗名として使用されます。
屋号を作る際には漢字やひらがなだけではなく、カタカナやアルファベット、数字や記号を使うことが可能なので、会社名を付けるよりも自由度が高い点が特徴です。
しかし、以下のような屋号を付けてしまい後悔してしまう人もいます。
-
- インパクト重視で英語やカタカナを多用したが、読み方がわからず電話で社名を伝えるのに苦労する
- 同業他社と似た名前をつけてしまい、SEOで検索しても競合が上位に表示される
- 造語を作ったが意味が伝わらず、事業内容を説明するのに毎回時間がかかる
- SNSのアカウント名やドメインがすでに使われており、統一したブランディングができない
- 商標調査を怠り、後から商標権侵害の警告を受けて変更を余儀なくされるケース
- 発音しにくい屋号なので覚えにくい
- 長い屋号にしたため覚えにくい
- 事業がイメージしにくい抽象的な屋号にしたため、何をしている事業主なのかわかりにくくなってしまった
屋号・サービス名は変更がしづらく、ブランディングやSEOにも影響を与えるので注意してください。
回避策
ネーミングや屋号での後悔を回避するための方法を解説します。まず、類似する商標がないか、商標データベース(J-PlatPat)で類似商標の事前チェックを実施します。
SEO競合を避けるためにも、Google検索で同名・類似名の企業がないか確認することも忘れないでください。
SNSアカウント名やドメイン名の取得が可能であるかも事前に調査します。
また、覚えやすく、電話で伝えやすい音の響きかどうか実際に声に出して確認することも大切です。
第三者が覚えやすく頭に残りやすいよう、事業内容が連想できる、または親しみやすい日本語を基本とします。
家族や友人に「何の会社か想像できるか」をヒアリングしてみるのもおすすめです。
【起業の後悔2】開業届を出しただけで「やった気」になってしまった

起業するために開業届を提出しますが、それだけで満足してしまう人も中にはいるでしょう。
「やった気」になっているだけでは満足のいく収益を確保できません。失敗例や回避策を参考にして後悔を防いでください。
失敗例
開業届はあくまでも「スタートライン」であり、売上げにつながる動きがともなっていなければ形だけで終わってしまいます。
顧客獲得や売上アップ、事業の安定化といった課題は、開業届を提出しただけでは解決しないので、活動を通じて課題をクリアしていく必要があります。
開業後に考えられる失敗例は以下の通りです。
-
- 開業届提出で満足してしまい、実際の営業活動開始が3カ月遅れた
- 法的手続きは完了したが、サービス内容の詰めが甘く、初回顧客対応で失敗した
- 開業したことをSNSで報告したが、具体的に何ができるのか説明できなかった
- 名刺交換で「何をしている会社ですか?」と聞かれて、明確に答えられなかった
- 開業準備リストを作らず、必要な手続きや準備が漏れて後から慌てる
回避策
上記のような後悔をしないための回避策を紹介していきます。まず大切なのは、開業届提出前に「営業開始日」を具体的に設定することです。
逆算してスケジュールを組んでいくことで、必要な準備の洗い出しや、それに要する期間を算出できます。
また、サービス内容を30秒で説明できる「エレベーターピッチ」を事前に準備することも検討してください。
エレベーターに乗るくらいの短時間で実施するプレゼンテーションを指し、活用すれば具体的な事業内容やサービス内容を簡潔に答えられるようになります。
短期間で効果的にアピールできれば、相手の関心を高められるのでビジネスチャンスを広げることができます。
それと共に、「このようなことができます」という具体的なサービス内容を発信していきましょう。
開業後3カ月間の売上目標と行動計画を具体的に立て、開業前に必要な準備項目をチェックリスト化し、進捗管理を徹底することで必要な手続きや準備の漏れを防ぐことができます。
仮でも良いので初回顧客への提案資料やサービス説明資料を用意しておくことも大切です。
【起業の後悔3】名刺やブランドの準備が甘くて信頼を失った

名刺やブランドの準備で顧客や取引先からの信頼を失う恐れもあります。
失敗例
事業では、第一印象が「信用の土台」といえます。名刺やロゴはそのまま信頼度に直結するので、準備が甘いと後悔を招くので注意が必要です。
失敗例を具体的に上げると、以下のようになっています。
-
- 手書きの仮名刺で商談に行き、「本当に会社なの?」と不信感を持たれた
- 名刺、ロゴ、SNSアイコンがバラバラのデザインで統一感がなく、プロ感に欠けた
- 連絡先が個人のGmailアドレスのみで、法人としての信頼性が疑われた
- 会社のホームページがなく、「実在する会社なのか」と取引きを断られた
- 名刺の情報が不足しており、後から連絡を取ろうとした顧客が困惑した
回避策
信用を獲得するための方法を解説していきます。ロゴに関しては、Canvaなどの無料ツールを活用し、統一されたロゴとカラーパレットを作成してください。
ロゴの作成やSNS投稿用のデザインなど、多様な使い方ができる点が特徴です。
SNSアカウント(Facebook、X、Instagram)のプロフィール画像とヘッダーを統一することで、ブランドの具体的なイメージを訴求できるようになります。
メールアドレスに関しては、独自ドメインのメールアドレス(info@会社名.comなど)を取得することで信頼性が向上します。
名刺には最低でも「社名・代表者名・電話番号・メール・住所・ウェブサイト」を記載し、顧客の困惑を防いでください。
起業時には、簡易的でも良いのでランディングページ(LP)やホームページを作成すると、取引先からの信頼が得やすくなります。
【起業の後悔4】見積書・契約書がないまま仕事を進めてトラブルに

見積書や契約書によるトラブルが起きれば、信用問題に発展するケースもあります。悪いイメージがついてしまうと売上げにも影響を与えるので注意してください。
失敗例
仕事の基本は「契約」です。書類なしでは支払い遅延・仕様変更リスクが高まるので、以下のようなトラブルが増える可能性があります。
-
- 口約束だけで仕事を開始し、後から「そのような金額は聞いていない」と支払いを拒否された
- 作業範囲が曖昧なまま開始し、無限に修正依頼が来て採算が悪化した
- 納期や仕様を口頭でしか決めず、認識の相違からクレームに発展した
- 請求書の発行タイミングや支払い条件を決めておらず、キャッシュフローが悪化した
- 著作権や責任の所在が不明確で、トラブル時に解決に時間がかかった
回避策
口約束だとトラブルに発展する可能性が高まるので、見積書に関してはテンプレートを事前に作成し、作業内容・期間・金額を明文化するようにしてください。
契約書に関しては、基本契約書のひな形を用意して、最低限の条項(支払条件・納期・責任範囲)を盛り込みましょう。
修正回数の上限を事前に設定し、追加作業は別途見積もりとするルール化をすると共に、支払条件(月末締め翌月払いなど)と延滞金についても事前に合意を得ることが大切です。
クラウドサインなどの電子契約サービスの導入で、契約締結を効率化することも可能です。
また、著作権の帰属、機密保持、損害賠償の範囲を契約書で明確化することも忘れないようにしてください。
【起業の後悔5】集客が後手に回り、仕事が続かない

開業直後は優良顧客を作ることが重要なポイントです。顧客を集めなければ事業継続は不可能なので、仕事を続けるためにも集客力を付けることが大切です。
失敗例
起業したら、「準備→販売」ではなく「集客→販売→改善」が現代の基本です。
間違った手順で事業を進めていくと、以下のような後悔を招いてしまいます。
-
- サービス完成を待ってから集客を開始し、開業後2カ月間売上ゼロが続いた
- 「良いサービスなら自然と口コミで広がる」と思い込み、積極的な営業をしなかった
- SNSアカウントは作ったが投稿が続かず、フォロワーが増えない
- 知人への営業だけに頼り、新規開拓ルートを開拓できずに行き詰まった
- 価格設定が高すぎて問い合わせが来ず、後から値下げして混乱を招いた
回避策
開業後の売上ゼロを防ぐためにも、開業3カ月前からSNSでの情報発信を開始することで、見込み客との関係構築を図れます。
サービスが未完成でも「近日リリース予定」として事前告知すれば、興味を喚起できます。
無料相談やモニター価格での先行サービスを提供することで実績や口コミを蓄積することも可能です。
また、Google ビジネスプロフィール、各種ポータルサイトへの登録を早期実施すれば自分の事業をアピールできるほか、魅力を知ってもらうためにも役立ちます。
無料で集客できる点も強みです。
価格設定に関しては、競合他社の価格調査を行い、適正価格帯でのサービス提供を心がけてください。
紹介制度やリピート割引などの仕組みを構築し、継続的な集客導線を作ることも大切です。
【起業の後悔6】顧客管理や対応ルールを決めておらず混乱した
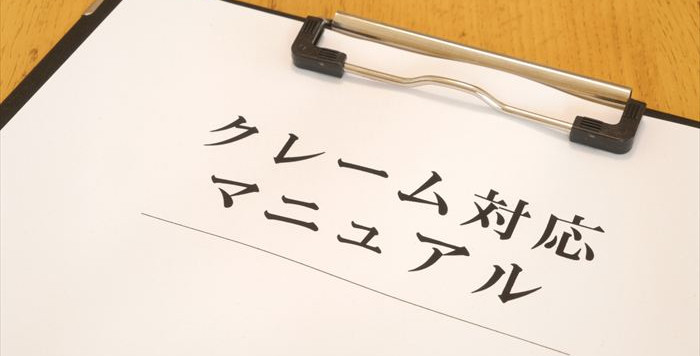
売上げや仕事を確保するためにも、多くの顧客と良好な関係性を築くことが大切です。
顧客管理や対応ルールを決めることで、顧客のニーズに合った最適なアプローチをすることにつながります。
失敗例
事業の信頼は「対応のスピードと一貫性」で決まります。以下のような失敗が起こりやすいので注意してください。
-
- 問い合わせメールの返信を忘れ、1週間後に気付いて謝罪する羽目になった
- 顧客情報をメモ帳に散在させ、過去のやり取り履歴がわからず対応に困った
- クレーム対応の手順が決まっておらず、感情的な返答で関係が悪化した
- 複数の連絡手段(メール・電話・SNS)で問い合わせが来て、対応漏れが発生した
- 納期管理ができておらず、複数案件の締切が重なって品質が低下した
回避策
GoogleスプレッドシートやAirtableといった外部ツールを活用すれば、顧客管理表を作成し、やり取り履歴を一元管理できます。
NotionやTrelloなどのタスク管理ツールを使えば、案件進捗と納期を可視化することも可能です。
問い合わせ対応は、「24時間以内返信」といったルールを設定し、自動返信メールを活用すると返信の漏れを防ぐことに役立ちます。
定型的な返信メールのテンプレートを用意すれば、対応品質の標準化も可能です。
クレーム対応については、フローチャートを作成し、冷静な対応手順を事前に決めておくことで感情的な対応を防止できます。
週次での顧客対応の振返りを実施し、改善点を継続的に洗い出すことで、スピードと一貫性のある対応につながります。
【起業の後悔7】会計処理が追いつかず、確定申告で大慌て
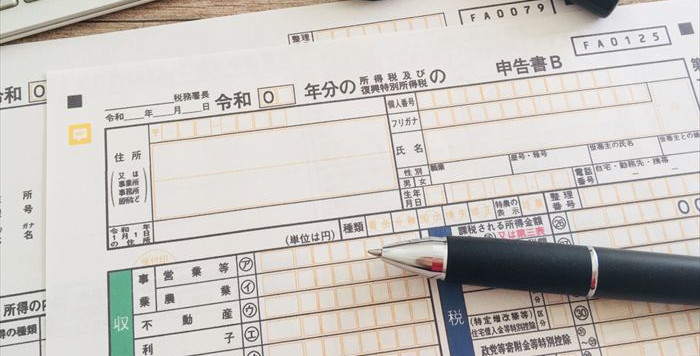
事業を営めば確定申告が義務付けられているので経理や会計業務が必須となります。
取引数が多くなれば作業量も多くなるので会計処理が追い付かずに確定申告の際に慌ててしまうケースもあります。
失敗例
面倒だからと後回しにしてしまえば、税金やキャッシュフロー、信用管理など、すべてに悪影響を及ぼしてしまいます。以下の失敗例に注意してください。
-
- レシートを財布に溜め込み、確定申告直前に仕訳作業で徹夜続きになった
- 現金とクレジットカード、銀行振込の管理がバラバラで収支が把握できない
- 経費になるものとならないものの判断ができず、税務署に問い合わせが必要になった
- 売上げの記録が曖昧で、請求漏れや二重請求のミスが発生
- 青色申告の届け出を忘れ、65万円の特別控除を受けられなかった
回避策
freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトを開業と同時に導入すると、会計業務の効率化を図れます。
銀行口座とクレジットカードを事業用に分け、自動連携で記帳を効率化することも可能です。
レシートは溜め込みすぎると仕分け作業が大変になるので、スマホアプリで即座に撮影・記録する習慣をつけると溜め込みを防げます。
毎月末に「会計の日」を設定し、1カ月分の仕訳を完了させる習慣をつけると、業務の溜め込みやミスを防ぐことに役立ちます。
また、迷った時の判断基準を明確化させるためにも、経費の種類別ガイドラインを作成してください。
そのほか、節税メリットを確保するためにも開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しましょう。
会計や確定申告についてわからないことや詳しい内容が知りたい場合は、専門家への相談も視野に入れてください。
【起業の後悔8】「知り合いだけ」で仕事を回そうとして失速した
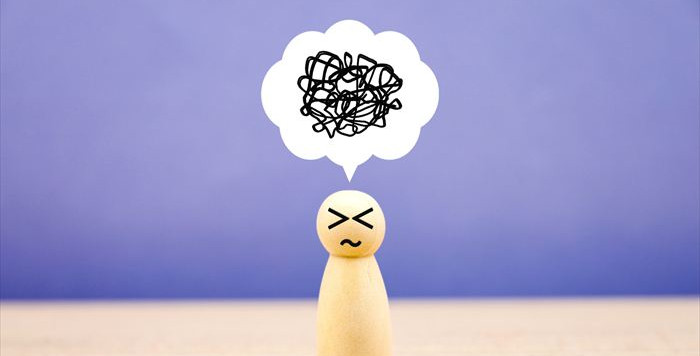
顧客がそれほど多くない起業時に、友人や知り合いを通して仕事をもらえれば、売上げを出すことにつながります。
しかし、後悔を招く要因にもなるので注意が必要です。
失敗例
友人や知り合いの「安心感」に甘えると、拡張性のないビジネスになる恐れがあります。
以下のような失敗例が考えられるので、前もって把握しておいてください。
-
- 友人からの依頼だけに頼り、3カ月目以降の案件が途切れて売上げが激減した
- 知人価格での提供が続き、適正価格での受注ができずに利益が出ない
- 紹介案件ばかりで新規開拓スキルが身につかず、営業力が向上しない
- 友人との仕事で金銭トラブルが発生し、プライベートの関係までも悪化した
- 限られた人脈の中でしか仕事ができず、事業拡大の可能性が見えない
回避策
知人案件は「実績作り」と位置づけて、3カ月程度で新規開拓にシフトを切ることを徹底してください。
ココナラ、クラウドワークスなどのプラットフォームで新規顧客開拓を同時並行するのもおすすめです。
紹介キャンペーンや口コミ制度を設け、知人ネットワークから新規顧客への導線を作る方法もあります。
業界団体やコワーキングスペースでのネットワーキングで人脈拡大を図ることも可能です。
利益が出ずに悩むケースは多いので、例え仲の良い友人であっても適正価格を提示し、「事業として持続させるため」と理解を求める必要があります。
また、知人経由の仕事でも契約書を交わし、ビジネスライクな関係を維持することを心掛けてください。
まとめ|「やっておけばよかった」は、小さな見落としから生まれる
開業直後の後悔の多くは、「気付いていれば防げた」といった内容が多いです。
完璧な準備でなくても、少しの視点とひと工夫で後悔の数を減らすことができます。今できるところから備えておきましょう。
創業手帳(冊子版)では、起業後の後悔を防ぐための情報を多数掲載しています。起業前にチェックしておけば、「やっておくべきこと」を理解できるので、事業の継続を促すためにお役立てください。
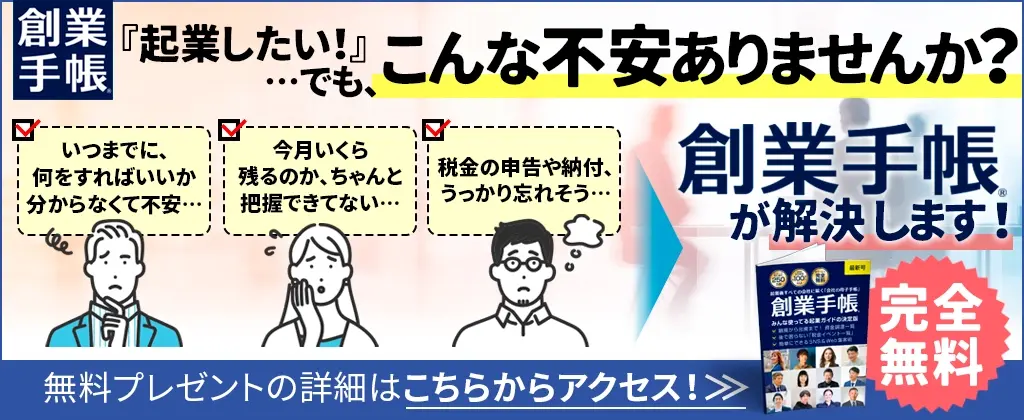
(編集:創業手帳編集部)