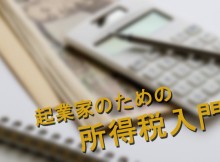やらなきゃ損!個人事業主が年末に必ず確認したい節税対策
年末は個人事業主にとって節税のラストチャンス
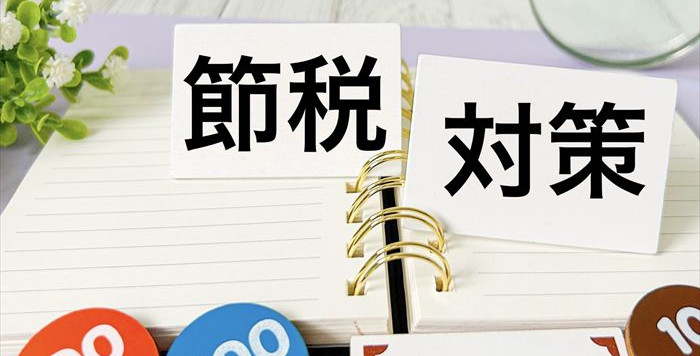
年末は1年間の所得・支出がほとんど確定するタイミングになります。そのため、当年度の税負担を抑えるために控除や経費の調整を行う個人事業主も少なくありません。
翌年の税額に直結することになるため、年末に節税対策を行うのは重要なことです。
しかし、限られた期間で進めていかなくてはならないため、事前の準備やどんな対策をすべきか確認しておく必要があります。
この記事では、個人事業主が年末までにできる節税対策の一覧と、節税対策を効率的に進めるためのポイントなどを解説します。
年末までにどんな節税対策ができるのか知っておきたい人は、ぜひ参考にしてください。
▶▶▶知らぬ間の損を防ぐ!『税金チェックシート』で今すぐ確認
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主が年末に節税を考えるべき理由

そもそも個人事業主はなぜ年末に節税対策について考えたほうが良いのでしょうか。まずは年末に節税を考えるべき理由を3つ紹介します。
所得確定のタイミングで節税効果が最大化できる
個人事業主の所得税は、1月~12月に得た収入から必要経費を差し引き、さらに所得控除や税額控除などが適用され、その年に納める所得税が決定します。
つまり、年末に1年間の所得がほとんど確定することになります。このタイミングで経費や控除の調整を行うことで、税負担を直接軽減させることが可能です。
必要経費の前倒しや控除の活用を年末に行うと、翌年の税額にも影響を与えられます。
正確に所得を把握する必要はありますが、節税効果の最大化を狙うためにも年末に節税対策を取り入れたほうが良いでしょう。
税務上の締切が近いため迅速な対応が必要
年明けから確定申告や控除申請の期限が迫ってくることから、年末頃から必要書類や商標などを揃えておく必要があります。
確定申告の期間は例年2月16日~3月15日の1カ月間になりますが、インボイスを発行している適格事業者は、さらに消費税の申告も1月1日~3月31日までに行わなくてはなりません。
1年間の所得や支出を整理する必要があり、人によってはかなりの手間と時間がかかってしまう場合もあります。
また、締切間際になると焦ってミスをしてしまい、書類の不備が見つかる可能性もあります。
迅速かつ正確に対応するためにも、年明けではなく年末から準備を進めておいたほうが良いです。
限られた期間で実行できる具体策がある
消耗品の購入や広告費の活用、共済・iDeCo・ふるさと納税などは年内までに利用することで節税効果が得られます。
例えばふるさと納税の場合、12月31日までに利用した金額が当年度の所得税還付、翌年度の住民税控除の対象になります。
年末までに行動することで翌年の事業資金も効率的に確保できることから、積極的に活用するのがおすすめです。
▶▶▶知らぬ間の損を防ぐ!『税金チェックシート』で今すぐ確認
年末までにできる節税対策一覧
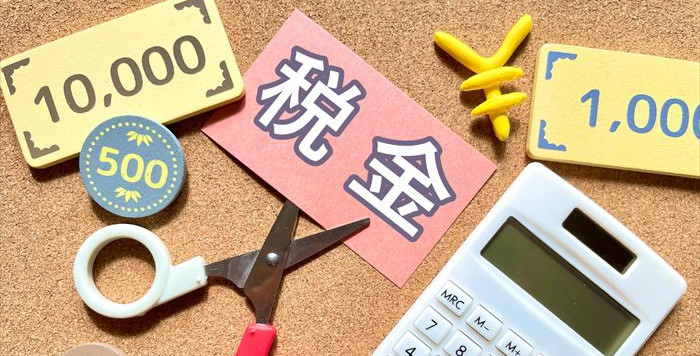
年末までにできる節税対策にも様々な種類があります。ここで主な対策方法を解説します。
| 節税対策 | ポイント | 年末までに行う理由 |
|---|---|---|
| 必要経費の前倒し | 「短期前払費用の特例」を活用して経費計上 | 当年度の所得を減らし税負担を軽くする |
| 減価償却資産購入 | 30万円未満は全額経費計上 | 年末購入で節税効果を最大化できる |
| 青色申告控除 | 帳簿・書類を整備して65万円控除 | 年内に準備を完了すると控除対象になる |
| 小規模企業共済 | 掛金は全額所得控除 | 年末までに支払いで当年分の節税に反映 |
| iDeCo掛金 | 所得控除対象、上限を確認 | 年末に設定・支払うことで節税可能 |
| ふるさと納税 | 自己負担2,000円で控除 | 年末までに寄附を完了すると当年控除適用 |
| 医療費・保険控除 | 支払証明書を整理、控除上限を確認 | 年末に整理して正確に申告できる |
| 赤字繰越控除 | 前年度赤字を翌年に繰り越す | 年末に帳簿整理で翌年以降の税負担軽減 |
1.必要経費の前倒し支出
基本的に経費を前倒しで支払った場合、一時的に資産に計上し、提供を受けた分のみ経費にできる仕組みです。
しかし、短期前払費用の特例を活用すると、前倒しで支払った費用が以下の条件を満たしている場合、資産に計上しなくても支払い時に必要経費として計上できるようになります。
-
- 支払い日から1年以内に役務の提供を受ける
- 実際に事業年度末までに費用を支払っている
- 継続して役務の提供を受けている
- 継続して同じように経理処理をしている
例えば家賃や駐車場代、保険料、サーバーの利用料など、毎年契約を更新して同じように経費処理するものであることが重要です。
2.減価償却資産の購入
10万円以上の固定資産を購入すると、耐用年数に合わせて減価償却をすることになります。
例えば定額法で求める場合、20万円の固定資産(耐用年数5年)を購入した場合、年間で経費にできるのは4万円までとなります。
取得価額20万円×定額法の償却率0.2=4万円
つまり、経費にできるまで時間がかかってしまうことになります。
しかし、青色申告の個人事業主であれば「少額減価償却資産の特例」により、10万円以上30万円未満の減価償却資産は、取得したその年に全額経費として計上することが可能です。
事業年度ごとの上限は300万円までになりますが、まとめて経費計上することで大きな節税効果が期待できます。
3.青色申告特別控除の活用
個人事業主の確定申告は白色申告と青色申告の2種類に分かれますが、青色申告のほうが特別控除の適用により、節税効果が大きくなります。
青色申告特別控除は、所得金額から一定額を差し引ける控除です。最大65万円の控除が受けられますが、適用されるには以下の要件をすべて満たさなくてはなりません。
1.事業所得または事業規模の不動産所得がある
2.1の所得に関する取引に対して複式簿記で記帳している
3.2に基づいて作成した青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)を添付し、確定申告をしている
4.確定申告の期限を守っている
5.現金主義による所得計算の特例は利用していない
6.e-Taxで確定申告、または仕訳帳・総勘定元帳などを電子帳簿保存法で定められた「優良な電子帳簿」として保存している
65万円控除を受けるには確定申告の期限を守り、決算書もきちんと準備しておく必要があるため、年末から準備を進めたほうが良いです。
電子申告や会計ソフトなどを活用すると、青色申告に必要な記帳作業も効率的に行えるのでおすすめです。
4.小規模企業共済の掛金
小規模企業共済は、中小機構が運営する制度で、個人事業主や小規模企業の経営者・役員のための積み立てによる退職金制度です。
小規模企業共済を活用することで、廃業時にまとまった金額を受け取れるようになっています。
この小規模企業共済の掛金は毎月1,000円~7万円の範囲内です。500円単位で自由に設定でき、加入後に増額・減額することが可能です。
掛金は全額課税対象所得から控除できることから、当年度の経費を調整しつつ退職金を準備することもできます。
掛金を増やしたい場合、随時申し込みが可能となっていますが、増額後の金額請求は翌々月からになります。
当年度の所得控除対象として申告したい場合は、早めの申し込みが必要です。
5.iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金
iDeCoとは、毎月掛金を積み立てて運用し、資産を形成する年金制度です。
老後の資産形成を目的とした年金制度ということで原則60歳になるまで受給できないものの、掛金は全額所得控除の対象になるため、税負担を軽減できます。
ただし、掛金の上限額は職業によって異なるため、自分の職業に合った金額を年末までに設定しておくことが大切です。
個人事業主は会社員とは異なり、厚生年金に加入できません。国民年金に加入しているものの、厚生年金と比べて受給額は低くなっています。
そのため、節税対策も兼ねて将来受け取れる年金を増やしておきたい人には、iDeCoの活用がおすすめです。
6.ふるさと納税
ふるさと納税は、自分が住んでいる自治体以外の地方自治体に寄附を行い、寄附額から2,000円引いた金額分の所得税・住民税が控除される制度です。
ふるさと納税の場合、手元に残る資金が増えるわけではないため、実質税金を前払いしているだけになりますが、2,000円支払えば返礼品として様々な日用品・飲食料などを手に入れられます。
12月31日までに寄附を完了させると、当年分の所得税の控除が適用されます。
個人事業主の場合、ワンストップ特例制度は活用できないため、確定申告が必要です。
また、収入が変動しやすい個人事業主は上限額が把握しづらいため、上限額を超えないように注意してください。
7.所得控除
所得控除は、所得の合計金額から各種控除の合計額を差し引き、課税所得を減らせる制度です。
課税所得を減らすことができれば、その分納める所得税も少なくなります。
所得控除はすべての人に適用される「基礎控除」をはじめ、様々な控除があります。
-
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 社会保険料控除
- 医療費控除
- 勤労学生控除
- ひとり親控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 障害者控除
- 寄附金控除(ふるさと納税を含む)
- 地震保険料控除
- 生命保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 雑損控除
例えば医療費控除は、個人事業主本人と生計を一にする配偶者やその他の家族のために支払った医療費も含めて、1年間に支払った医療費が10万円(または所得金額の5%)を超える場合に、その超えた金額が控除対象となります。
支払った医療費が50万円で、保険金などで補填される金額が20万円だった場合、(50万円-20万円)-10万円=20万円が控除額として適用されます。
ただし、その年の所得金額が200万円未満だった場合、「10万円」ではなく「所得金額の5%」を差し引いた金額が控除対象となるため、注意してください。
8.赤字の繰越控除の整理
青色申告の個人事業主は特別控除を受けられるだけでなく、赤字を翌年以降の3年間繰り越せる制度も活用できます。
繰越控除を利用するには、帳簿整理を年末までに完了させることが重要です。
例えば今年の事業所得で赤字が80万円だった場合、翌年の事業所得の黒字が100万円であれば、翌年は100万円-80万円=20万円が課税対象となり、大きな節税効果をもたらす場合もあります。
繰越控除を活用するためには正確な帳簿と書類を準備しておく必要があるため、年末から早めに準備を進めておきましょう。
▶▶▶知らぬ間の損を防ぐ!『税金チェックシート』で今すぐ確認
節税対策を効果的に進めるためのポイント

個人事業主が年末に節税対策を効果的に進めていくためには、以下3つのポイントを押さえることが大切です。
支出の調整は無理なく行う
事業の運営に支障が出ない範囲で支出を前倒しすると、節税効果が得やすくなります。
突発的に大きな支出があると、キャッシュフローにも大きく影響してくることから、年度末まで計画的に支出を分散させる必要があります。
複数の節税対策を組み合わせる際にも、支出額が増えすぎて負担が大きくなりすぎないように、優先順位をつけて調整するのがおすすめです。
経費は事業関連で明確にする
事業に関連する支出のみ経費として計上することで、税務署から指摘を受けたり、否認されたりするリスクを回避できます。
プライベートの支出と混在する経費は帳簿上で分けて管理しなくてはなりません。
領収書・請求書などの書類を整理し、経費の用途を明確に示せる状態にした上で保管することが大切です。
証憑の保管を徹底する
領収書や請求書などの証憑を整理・保管することで、税務署から確認の連絡が来た際にすぐ対応できるようになります。
電子データの保存も可能で、スキャナーや会計ソフトなどを活用すれば効率的な管理も可能です。
書類を保管する期間は原則7年間になるため、長期的に管理体制を整えておけば節税対策時の信頼性も高まります。
▶▶▶知らぬ間の損を防ぐ!『税金チェックシート』で今すぐ確認
税理士に相談すべきケース

個人事業主で年末に節税対策をしようと考えた際に、自分一人では判断できなかったり、不安に感じたりすることもあるでしょう。
そのような時は税理士に相談することも検討してください。ここでは、どのようなケースで税理士に相談すべきか解説します。
所得が増えて節税策が複雑な場合
前年度よりも事業がうまくいき、所得が一気に増えた場合、節税対策として複数の控除や共済、保険制度などを組み合わせようと考える人も多いです。
しかし、いきなり増やそうとすると手続きに手間取ったり、支出が増えてキャッシュフローに影響したりする可能性もあります。
そのため、所得が増えて節税対策が複雑になってきたと感じたら、税理士に相談するのがおすすめです。
特に年間売上が1,000万円を超えると経理業務が増えて煩雑化し、納税額も大幅にアップするため、税理士に相談したほうが良いです。
税理士に相談すれば複雑な計算から書類の作成まで、専門家からアドバイスを受けられます。年末の駆け込み対応も、税理士に相談すれば効率的かつ確実に実行できます。
帳簿整理や経費計上に不安がある場合
節税対策によっては帳簿の整理などが必要になりますが、ここで不安を感じたら税理士に相談することで税務リスクを回避できます。
例えば適切な証憑の管理方法や経費計上のルールが曖昧な状態で進めてしまった場合、不備が見られて税務署から指摘される可能性があります。
不安な部分はそのままにせず、税理士などのプロからアドバイスをもらうことで正確な処理が可能です。
特に年末の経費前倒しや減価償却資産の計上で不安に感じた際には、専門家からアドバイスを受けましょう。
投資や新規設備購入など複雑なケース
新規設備の購入や投資など、税務上の判断が複雑で難しいケースでも税理士に相談すべきです。
税理士に相談することで単に節税効果を得られるだけでなく、事業資金・キャッシュフローへの影響も考慮したアドバイスがもらえます。
税務申告の直前でも相談に応じてもらえる場合があるため、判断が難しい複雑なケースの際は税理士に相談してください。
▶▶▶知らぬ間の損を防ぐ!『税金チェックシート』で今すぐ確認
まとめ|年末の一手で税負担を軽減しよう
個人事業主は年末に節税対策を行うことで、当年度や翌年分の税負担を軽減できる可能性があります。
年末まで計画的に経費の前倒しや共済、iDeCo、ふるさと納税などを活用すれば、確かな節税効果が得られます。
証憑の整理・管理を徹底し、税理士からも適切なアドバイスを受けながら、年末に向けて節税対策に取り組んでみましょう。
税金は「知らないだけ」で損をしてしまうケースが少なくありません。創業手帳が起業家相談や専門家取材をもとに作成した無料の『税金チェックシート』では、見落としがちな節税ポイントを一覧で整理できます。納税時に慌てないためにも、今のうちに基本を押さえておきましょう。

(編集:創業手帳編集部)