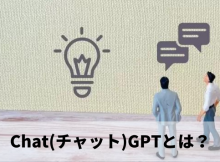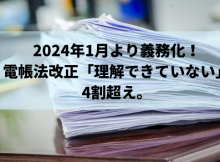約束手形・小切手廃止の理由は?企業が取るべき代替策・対応を解説
約束手形・小切手が2026年度末で廃止に

企業間取引きで利用されてきた約束手形や小切手は2026年度末で廃止される予定です。
紙の手形や小切手がなくなることにより、決済手段を新しくしなければいけない企業もあるかもしれません。
しかし、約束手形・小切手の廃止によってコストや事務負担の軽減といったメリットもあります。
さらに、廃止となるのはあくまで紙の約束手形や小切手であり、電子記録債権(でんさい)は利用できます。
どういった代替手段があるのか、自社で廃止に対してどのような対応をしなければならないのか確認しておきましょう。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
約束手形・小切手廃止の背景

約束手形などの手形や小切手は、長い歴史を持つ決済手段で多くの企業が利用してきました。
古くから現金の代わりとして企業間で使われてきたものの、2025年現在は廃止に向けて進んでいます。
紙の約束手形や小切手が廃止されて電子化することで、事務負担やコスト、リスクの低減も期待されています。
ここでは、そもそもなぜ約束手形などの手形と小切手を廃止するのか、その背景について説明していきましょう。
支払いに関する問題点
約束手形と小切手を使う上での問題点として、支払い手段としての使い勝手の悪さやリスクの高さが挙げられます。
約束手形と小切手は、現金化するまでにかかる時間が長く、支払期限前に現金化しようとすれば割引料が発生します。
商品やサービスを提供して支払いを受ける側としては、現金化が遅いことで資金繰りが悪化してしまう点が課題です。
さらに紙の現物であることから紛失や盗難にも注意しなければいけません。
また、約束手形と小切手のように対面や郵送で現物の紙をやり取りする取引きは現在の経済に合わなくなりつつあります。
郵送料や印紙税がかかることや紛失、盗難のリスクがあることから、ほかの資金調達手段を選ぶ企業も増えています。
事実として約束手形の発行残高は減少傾向にあり、1990年代の約束手形の残高107兆円をピークに、近年は25兆円程まで減少しました。
こうした現状を踏まえて2021年2月に政府は2026年末までに約束手形の利用廃止に向けた方針を決定しています。
これらの移行は政府だけでなく産業界、金融界が連携して電子化に向け取組むものです。
中小企業庁や一般社団法人全国銀行協会などからも、約束手形の利用廃止についての案内文が出されています。
現金での支払いや電子記録債権の移行の推奨
約束手形と小切手は2026年度末に廃止が予定されています。ただし、廃止になるのはあくまで紙媒体の約束手形と小切手です。
電子化されているもの(電子記録債権 通称でんさい)は引き続き使うことができます。
でんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称・でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。
紙ではなく電子化されているため、現物の紛失や盗難のリスクはなくなります。
また、Web上で管理できるため、事務手続きが簡便で、支払期日には自動入金される仕組みです。
現在、国の方針として約束手形と小切手の廃止に伴って、でんさいの利用が推奨されています。
約束手当・小切手廃止までのスケジュール

約束手形と小切手は利用廃止に向けて進んでいます。そのため、現在約束手形と小切手を決済に使っている企業は、対応が求められます。
2021年に政府が公表した「成長戦略実行計画」には、5年後の約束手形の利用廃止と小切手の全面電子化が盛り込まれました。
2021年の7月には、一般社団法人が全国銀行協会も電子交換所における約束手形と小切手の交換枚数をゼロにする目標を定めています。
これ以降、大手銀行も手形や小切手の利用停止に向けて動き出しました。新規顧客の手形発行停止や2027年4月以降を期日とする手形と小切手の取立受付停止を公表しています。
政府・産業界・金融界が一丸となり、手形や小切手の機能を2026年度末までに全て電子化することを目指して歩みを進めています。
大手銀行では、インターネットバンキングやでんさいネットのように代替となる商品も案内されるようになりました。
約束手形や小切手の廃止をきっかけとして、電子的な決済手段を活用しはじめる企業もあるようです。
紙の手形、小切手廃止を契機として電子化への流れが加速し、より高い利便性の決済手段の導入が進められています。
紙の約束手形・小切手廃止で得られる企業側のメリット

約束手形・小切手を廃止することによって、決済の問題が解消されます。約束手形・小切手廃止によって企業にどのようなメリットがあるのか紹介します。
郵送や管理の負担・コストを軽減できる
紙の約束手形や小切手は、支払側と受取側で現物の紙をやり取りすることになります。
現物の紙を押印して郵送したり、受け取ってから保管、管理する手間は決して少なくありません。手形帳に記入したり銀行に持って行ったりするための事務作業も発生します。
さらに決済時には支払い側の企業は手形、受取側の企業は領収書に収入印紙を貼らなければいけません。
紙の手形からでんさいに移行することでこれらの収入印紙は不要となり、企業のコストを軽減できます。
受け取り側の資金繰りの負担が解消される
企業にとって資金繰りがスムーズかどうかは死活問題です。現金やでんさいであれば、支払いを受ける企業は早期に現金化できるので、資金をほかの事業資金に活用できます。
一方で、紙の手形は現金化するまで3~4カ月かかります。
一般的に売上の入金より経費の支出が先にあるので、手形を受け取った企業は現金化するまでの間は資金繰りが圧迫されてしまうのです。
特に製造業や建設業の下請け企業は、支払いの額面も大きく、入金されるまで資金繰りが悪化して支払いができなくなるリスクへの対処が課題でした。
電子化によってスピーディーに現金化できれば資金繰りの不安が減って、より効率的に資金を活用できます。
盗難や紛失のリスクがなくなる
現物の紙である約束手形や小切手は、紛失や盗難のリスクがありました。支払企業も受取企業も盗難などされることがないように金庫などで保管します。
約束手形や小切手を受け取った側は保管に注意するだけでなく支払期日を失念しないように注意が必要です。
しかし、どれだけ管理に注意しても火事や災害で約束手形や小切手がなくなってしまうかもしれません。
紙の約束手形や小切手は、数字や内容を書き換えられたり、偽造されたりといったトラブルのリスクもあります。
一方で、現金振り込みやでんさいであれば、紛失や盗難は発生しません。より安心して取引きに集中できるようになります。
約束手形・小切手の廃止で企業が取るべき対応

約束手形や小切手が廃止になれば、今までと決済手段を変えなければならない企業も少なくありません。どういった対応をすればいいのか紹介します。
代替となる決済手段への移行を進める
約束手形や小切手が廃止になった時に、まず考えなければならないのが代わりの決済手段をどうするかです。
今まで約束手形や小切手で決済してきた場合にはほかの決済手段に移行しなければいけません。約束手形や小切手の代替になる決済手段は主に以下のものです。
①振込
個人でも法人でもよく使われている決済手段で定期的な支払いであれば口座振替もできる。
②でんさい
でんさいネットが取り扱う電子記録債権で手形や小切手の代替決済として推奨されている。
③クレジットカード決済
個人取引きや小規模事業者であればクレジットカード決済で対応できるケースもある。
④デビットカード
即時決済が可能でクレジットカードを使いたくない場合に使われている。
⑤電子マネー
少額決済が手軽に可能になる。
取引先と代替手段の協議をする
決済手段の移行は自社だけでなく取引先とも協議が必要です。約束手形や小切手を頻繁に使っている取引先があれば、早めにどうするか話し合ってください。
自社内でほかにどういった決済手段があるのか、取引きの性質に合う決済手段はどれかあらかじめ検討しておくと、話し合いもスムーズです。
社内教育や顧客への周知に取り組む
決済手段の移行に際して社内教育や顧客への周知も必要です。
従業員に対しては、約束手形や小切手が廃止になることや新しい決済手段の導入について研修の機会を設けてください。
特に決済業務に携わる部門では、ミスが起きないように徹底して教育を行います。また、約束手形や小切手で支払う顧客がいる場合には事前に決済手段の移行を通知します。
小売業やサービス業のように多数の顧客に周知する場合には、Webサイトやポスターで告知したり、請求書に記載したり効果的な方法を選択してください。
代替案として推奨される「でんさい(電子記録債権)」とは

約束手形や小切手の代替案としてでんさいへの移行が推奨されています。もともと約束手形や小切手の課題を解決する目的で新しく作られたのがでんさいです。
でんさいであれば電子的記録により債権を発行、管理できます。
紙媒体の約束手形とでんさいの違いは、紙媒体と電子媒体のどちらでやり取りするかです。
紙媒体であれば、必要事項を記載して相手に交付した時点で債権が発生し、裏書きすることで債権譲渡が可能です。
支払いを受けるには、銀行に提出して口座に振り込んでもらわなければいけません。
でんさいの場合には、電子債権記録機関の記録原簿へ「発生記録」を行うことで債権が発生し、譲渡時には「譲渡記録」を行います。
支払いも期日になると支払側から受取側に振り込まれる仕組みです。
受取側のメリット
でんさいを導入すると、受取側は紛失や盗難のリスクに対応できます。
約束手形や小切手のように現物ではないので、郵送が遅れたり間違ったものを渡されたりするケースも避けられます。
受取側の事務処理コストが大幅に軽減される点もメリットです。でんさいは、支払期日になれば自動入金されるので取り立ても不要です。
さらに、Web上で管理できるので現物を保管する手間もありません。
でんさいは、決済結果の記録によって支払いを確認できるため、当事者間の合意があれば領収書を不要にできます。
領収書を発行する場合でもでんさい支払いであることを記入すれば非課税となるので、収入印紙などのコストが大幅に削減可能です。
でんさいは分割も可能であり、例えば100万円の債権のうち50万円を分割譲渡するといった方法もあります。
必要な資金分だけ分割できるので資金繰りにより柔軟に対応できます。
支払側のメリット
でんさいは、支払い側にも多くのメリットがあります。支払側は今までの手形の用紙代や手形に必要となる印紙代を削減可能です。
現物がなくなったことで郵送することもなくなり、郵送費用も発生しなくなります。
加えて、現物を管理することがなくなり手形の記入や押印の手間も削減可能です。現物ではないので、押印間違いや記入ミスも発生しません。
でんさい(電子記録債権)の利用方法

今まででんさいを利用してこなかった企業もあるかもしれません。ここからはでんさいを利用するための手続きについて解説しています。
でんさいの利用は取引金融機関に相談
でんさいネットでは、「参加金融機関一覧」を掲載しているので、初めにでんさいの窓口となる金融機関を選びます。
自社と取引先の金融機関が違う場合でも、でんさいに参加している金融機関であれば取引きに利用可能です。
金融機関を選んででんさいの利用を申し込みます。申し込みに関わる書類や手続きはその金融機関に問い合わせてください。
申し込み後に審査を受けて通過すれば、利用契約に進みます。「利用者番号」が通知され、でんさいネットを利用できるようになります。
でんさい対応のシステムを利用する前に押さえておきたいポイント
債権や債務管理システム、会計システムを利用している場合には、でんさいに対応しているかどうかもチェックしてください。
経理業務を効率化するために押さえておきたいポイントについてまとめました。
自動仕訳処理や一括で入金・支払管理ができる
でんさいに対応した会計システムでは、でんさいデータから自動で仕訳をしたり、一括で入金、支払管理が可能です。
債権の発生から割引、譲渡、決済までその都度会計処理すると手間がかかります。
使用している会計ソフトがでんさいのデータと連携して自動処理できるか確認しておいてください。
紙の手形も一元管理できる
約束手形や小切手が完全に廃止されるまでは、でんさいと紙の手形の両方が発生することがあります。
でんさいと紙の手形を一元管理する会計システムであれば、それぞれを別に管理する手間が発生しません。
管理業務を効率化するためにもどういった決済方法に対応しているのか、紙の手形もまとめて管理できるかチェックしてください。
適正にデータを保存できる
でんさいの記録は、債権が消滅した日から5年間(消滅していない債権の場合は支払期日または最後の電子記録がされた日から10年間)の保存が必要です。
でんさいネットでも保存されますが、自社システムで保存したい場合には、保存がいつまで可能か確認しておくようにしてください。
まとめ・約束手形・小切手が廃止する前に対応しよう
約束手形や為替手形、小切手が廃止の方向で進み、多くの企業に選択が迫られています。
どの決済手段に移行するか検討しなければならないものの、移行をきっかけとして決済手段の効率化や資金繰りの改善が可能です。
でんさいは、紙の手形にあった課題を克服した金銭債権として、大きな期待が寄せられています。
自社でどのように利用できるか、決済を移行することで会計処理がどうなるかもシミュレーションしてみてください。
創業手帳(冊子版)は、企業を取り巻く環境変化に対応するための記事を多数掲載しています。会計や税務の疑問解決にも創業手帳をお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)