運転資金が不足する要因とは?必要な資金の計算方法や資金調達方法を解説
事業を継続するためには運転資金が必要

運転資金とは、事業を安定して継続するための資金です。
会社経営などの事業を行っている場合、業績が好調だったり、利益が出ていたりすれば問題ないと考えるかもしれません。
しかし、運転資金は会社を運営するために必要な資金なので、不足してしまえば経営難に陥ってしまう可能性もあります。
この記事では、事業を維持するための運転資金が不足する理由やリスク、資金不足のための対策に加えて資金調達方法などについて解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
運転資金が不足する要因

なぜ、運転資金が不足してしまうのでしょうか。ここでは、不足の要因として考えられるのは以下のとおりです
キャッシュフロー管理の不足
運転資金不足になる原因の一つに、キャッシュフローの管理不足が考えられます。
キャッシュフローは、資金の流れを意味するもので流出と流入を含めた総合的な資金の動きのことです。
キャッシュフローの管理ができていないと、経営にどれくらいの資金がかかっているのか、いくら収入を得ているのかが把握できていないということになり、運転資金が不足してしまう可能性があります。
事業活動している以上、日々キャッシュの動きがあります。
売掛金の入金、人件費の支払い、仕入費用などは日々の業務に欠かせないものであり、キャッシュフローが適切に管理されていないと支払う現金の確保ができず、結果的に黒字倒産という事態が起こりかねません。
運転資金不足にならないためには、キャッシュフローの管理を適切に行ってください。
売上の減少・増加によるズレ
売上が急激に増加や減少した場合も、運転資金が不足する可能性があります。
売上が増えるなら問題ないと考えるかもしれませんが、結果的に仕事が忙しくなるため人件費や仕入費が増えてしまうでしょう。
増えた費用をすぐ賄う運転資金があれば問題ありませんが、実際には売上の計上と売掛金の入金がされるタイミングにはタイムラグが生じるため、対応できない可能性もあります。
一方で売上が減少した場合は、入金額が少なくなるので各種支払い時に資金不足に陥るかもしれません。
このような急激な売上の減少や増加にも対応できる運転資金がないと、安定した事業継続も難しくなります。
取引先の倒産・入金遅延
取引先の急な倒産や経営不振によって本来入金される予定日にお金が入らない場合、この出来事をきっかけに運転資金不足を起こす可能性があります。
経営をしている以上、取引先が倒産してしまう可能性やリスクを常に考えて、これらのあおりを受けないように運転資金を残しておかなければなりません。
ここで、運転資金が不足していると取引先倒産による入金遅延で資金難に陥った結果、自社も倒産してしまう可能性もあるので注意してください。
事業の拡大
事業を大きくできるチャンスが到来した時、思い切って拡大を選択しようと決めるかもしれません。
確かに事業拡大によって売上の増加は期待できますが、運転資金も増加することを忘れてしまったり、計算が甘かったりすると運転資金不足に陥ってしまいます。
仕入、在庫、固定費、人件費などはそれぞれ事業の拡大に伴って増加します。運転資金においても十分な計算をしなければリスクは避けられないので注意してください。
在庫の増加
運転資金が不足する理由として、在庫の増加も関係してきます。
ITビジネスが普及したことで在庫を持たないケースもありますが、在庫が必要なビジネスであれば常に管理やチェックを怠らないように意識してください。
在庫管理の失敗などで増えてしまった場合、過剰在庫が資金の固定化を引き起こして運転資金不足を招く可能性があります。
さらに、過剰在庫が保管所の圧迫を招くようならスペースの新たな確保や管理費用もかかってくるため、運転資金不足になりやすいです。
売掛金の割引
売掛金は、現金になるまでに時間がかかります。このことを知らずにいると、現金になるまでの期間中に運転資金が不足しやすく、事業が不安定になってしまうかもしれません。
何としても運転資金が必要となった場合には、売掛金を割引いて満期前に現金化(ファクタリングや手形割引)できますが、その分の手数料がかかってしまいます。
この方法であれば、満期まで待たずに資金調達がスムーズにできる一方で、満期前に現金化したことで手数料が引かれた金額しか得られません。
1回や2回であれば良いかもしれませんが、何度も売掛金の満期前に現金化してしまえば自転車操業状態に陥って次第に運転資金そのものが不足してしまいます。
運転資金の不足によるリスク

運転資金の不足は、企業に想像以上のリスクがかかることを忘れてはいけません。
特に注意したいリスクとして、以下のことが考えられます。
-
- 事業拡大のチャンスを逃す
- 支払いの遅延によって取引先からの信用が低下する
- 従業員の給与支払いが遅れることで起こる人材流出
- 金融機関からの追加借入が困難になる
最も深刻なのは、資金繰りが一度悪くなってしまうと取引先や金融機関からの信用を失ってしまい、さらなる資金繰りが難しくなることです。
このような状態に陥った場合は、売上が順調になっていたとしても一時的な資金不足で経営が困難になっていく可能性があります。
運転資金不足によるリスクは大きいので、日頃から事業継続に必要な運転資金を管理できるようにしましょう。
事業継続に必要な運転資金

事業継続に必要な運転資金を知るには、どのような方法があるのでしょうか。ここでは、運転資金の計算方法や目安、不足時の調達方法について解説します。
運転資金の計算方法
運転資金の計算に必要なのが、「売上債権」「棚卸資産」「仕入債務」です。これらを計算した時に、経常運転資金がわかります。
経常運転資金とは、家賃、人件費、仕入代金など運営時に必要な資金のことです。運転資金と言われたら「経常運転資金」を指すことがほとんどです。
経常運転資金は、売掛金入金までの資金不足を補うために活用され、事業の継続に欠かせないものとなります。
「売上債権」は、商品を提供したもののまだ回収できていない売上代金です。
「棚卸資産」は販売していない商品在庫、「仕入債務」は仕入費用でまだ支払い終わっていない代金を意味します。運転資金の計算方法は、以下のとおりです。
売上債権+棚卸資産-仕入債務=経常運転資金
運転資金の目安
このような方法で計算した時、運転資金はどれくらいを目安に用意したら良いでしょうか。
必要とされる運転資金の目安は約3カ月~6カ月分とされていますが、事業内容や業種によって変わってきます。
例えば、小売店や飲食店では仕入をしてから売上回収までの期間が比較的短いため、運転資金が少額でも問題ありません。
これは、商品が売れればその場で代金を支払ってもらえるため、まとまった金額を用意する必要がないからです。
一方の製造業や不動産業などの場合は、資金投資後に回収するまでの期間が数カ月~年単位で必要になるケースもあるので、その期間の資金繰りが必要になります。
事業内容に合わせて余裕のある運転資金を用意してください。
運転資金が不足した際の資金調達方法

運転資金計画の甘さや取引先の急な倒産などにより、予定していた資金調達がスムーズにできなくなった場合は早急に運転資金不足を解消しなければなりません。
ここでは、万が一運転資金が不足した際の資金調達方法について解説します。
銀行による融資を活用する
運転資金が足りなくなった場合は、銀行による融資の活用がおすすめです。
都市銀行、地方銀行、信用金庫などで運転資金調達が可能で、比較的金利が低くてまとまった金額の借入がしやすいです。
融資には銀行独自の審査基準を用いたプロパー融資と、信用保証協会の保証が付いている保証協会付き融資があります。
プロパー融資の場合、銀行によっては審査基準を厳しくしている所もあるので、赤字経営の場合は難しい可能性が高いです。
保証協会付き融資は、審査は通りやすいものの保証費用の支払いが必要です。
他にも都市銀行は大手企業中心で、地方銀行や信用金庫は中小企業や個人事業主に適しています。
ビジネスローンを活用する
ビジネスローンは、事業資金の融資に特化しているローンです。個人事業主と法人の代表者のみ申し込みができます。
これまでの銀行融資に比べて柔軟な審査基準で、スピードのある融資ができるので運転資金以外にもつなぎ資金、仕入資金、設備投資などの事業目的でも利用できるのが特徴です。
原則、無担保、無保証人での申し込みが可能で不動産を持たない事業者でも利用しやすいです。
取り扱っているのは銀行、信用金庫・組合、消費者金融などがあり、最短で審査を完了させて融資を得られるものもあります。
ただし、高金利での貸付もあるので必要な額だけ借りてスムーズな返済ができる場合のみがおすすめです。
日本政策金融公庫からの融資を活用する
日本政策金融公庫は、政府系の金融機関で民間金融機関です。
中小企業や個人事業主の支援を目的にしていて、一般の貸付に加えて新企業育成貸付や企業活力強化貸付などの制度も設けています。
融資についての相談もしやすく、条件を満たしていれば無担保で借りられるだけでなく、返済についての据え置き期間もあるので負担がかかりにくいです。
ただし、申し込みから審査完了してから融資までの時間がかかりやすく、提出書類も多い傾向です。即日融資が難しいので利用希望の際は早めに相談してください。
補助金・助成金を活用する
運転資金不足の際には、地方自治体や国の補助金や助成金の活用もできます。
これらの補助金や助成金には「ものづくり補助金」「事業承継・M&A補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」などがあります。
それぞれの補助金において特定の条件が決められているので満たした場合のみ補助が受けられる仕組みです。
補助金や助成金を受けられる場合、返済の必要があるのでその分の資金繰りは不要ですが、審査期間が早くて1カ月~4カ月程度と、補助金や助成金が出るまでの時間がかかります。
幅広い種類がありますが、早急な資金繰りには向いていません。
ファクタリングを活用する
ファクタリングは、資金調達方法のひとつで売掛金支払期限の前に現金化できるのが特徴です。
企業間の売掛金は、入金までに1カ月~2カ月程度の時間がかかってしまうため、売上があっても資金繰りが滞りがちという場合におすすめの方法です。
ファクタリングの仕組みは、保有している売掛債権などを期日の前に売却して現金化する方法です。借入と違い、信用情報などに影響を及ぼす心配がありません。
しかし、ファクタリング事業者によっては手数料が高額になりがちなので、急な運転資金不足が起こった時のみの利用に留めましょう。
運転資金の不足を防ぐための対策

運転資金不足を起こしてしまうと、そこから資金繰りのペースが狂うことがあります。良いペースで運転資金不足を起こさないために、以下の対策を取ってみてください。
資金繰り表を作成する
安定した資金繰りを行う場合は、資金繰り表の作成がおすすめです。
資金繰り表があれば現金の収入と支出を記載して書き込み、日々の収支と支出を計算して現金の不足が予測できます。
この表の作成によって、売上が入金されたり経費が必要なタイミングが把握できたりするので、その先の支出に向けて資金準備がしやすくなります。
コストを見直す
運転資金の不足を防ぐには、コストの見直しも必要になります。コスト削減が期待できる経費は、固定費、変動費、人件費、赤字事業です。
これらの中で最も効果が期待できるのは変動費と人件費で、仕入原価や残業代などは支出に対して割合も大きいです。
ただし、人件費に関しては従業員のモチベーション低下や集団退職などのリスクを伴う可能性もあります。
本当に必要なコストや価格、費用などを見直して必要最低限なもの以外の削減を意識してみましょう。
不要な資産を売却する
運転資金の不足が起こった際には、資産売却もひとつの手段です。使用していない遊休資産について確認し、売却すれば一時的なキャッシュが得られます。
特に資産維持にコストがかかっていた場合は、その分のコストカットもが可能です。
ただし、売却するのは不要な資産に限ったものとし、必要な資産売却によって事業の縮小や休止などが起こってしまいます。
資産によっては買い手がすぐに現れるわけでもありません。事前に税理士など専門家の意見を聞いてみると良いでしょう。
まとめ・自社に合った方法で運転資金不足の解消を目指そう
事業継続には運転資金が欠かせません。万が一、運転資金が不足してしまった場合はどのような理由で不足しているのか確認が必要です。
運転資金不足にはリスクがあり、安定した事業継続には日頃から管理できる体制が求められます。
自社の事業に適した方法で、運転資金不足を解消できるように目指してください。
自社の運転資金がどのくらい不足しているのかを把握するには、具体的な数値の整理が欠かせません。
『資金シミュレーター』を使えば、売上・仕入・人件費などを入力するだけで、今後の資金繰りを可視化できます。
無料で利用できるので、まずは現在の資金状況を数値で確認してみてください。
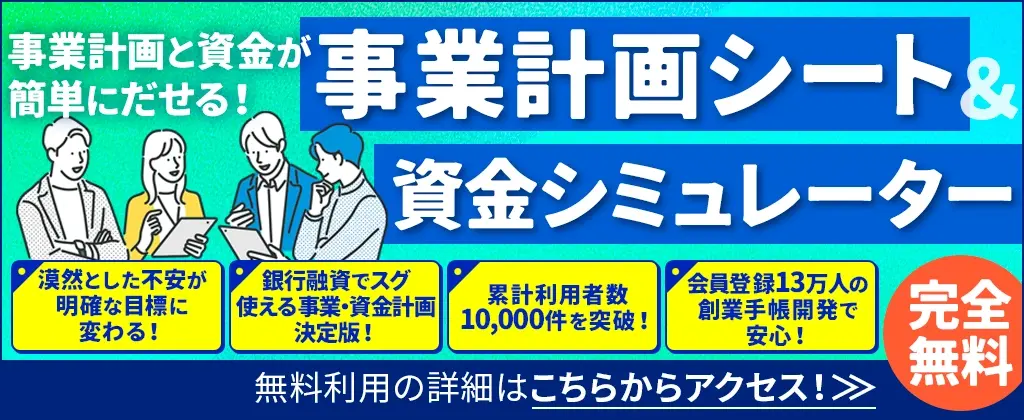
(編集:創業手帳編集部)




































