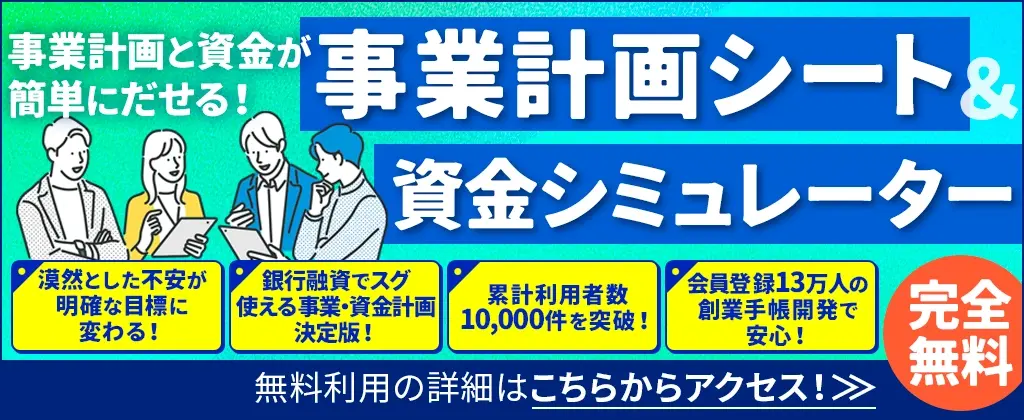【経営者必見】厳しい資金繰りの改善方法を解説!資金難に陥る企業の特徴も紹介
安定した資金繰りで事業を成長させよう

「なぜ毎月末に資金不足が発生するのだろうか」
「どうすれば安定した資金繰りを実現できるのか」
経営者の多くは上記のような悩みを抱えているのではないでしょうか。資金繰りの悪化は経営危機に直結するため、正確な資金管理の把握が欠かせません。
厳しい資金繰りの企業であっても早期に改善策を実施すれば、資金繰りを安定させることができます。
この記事では、資金難に陥りやすい企業に共通する特徴を紹介し、資金繰りを改善するための具体的なコツも解説します。
資金繰りの安定化を図りたい方は、是非参考にしてみてください。記事を読み終えると、資金繰り管理の重要性が理解でき、最初の一歩として資金繰り表の作成に取りかかることができます。
創業手帳では、会員登録された方は無料で使える「資金シミュレーター」を公開。ご自身の事業について、現在どのくらいの資金があり、どのくらい足りないのかが一目瞭然です。また印刷すればそのまま金融機関に出せる資金繰り表が作成できます。あわせてご利用ください。
この記事の目次
資金繰りが厳しくなる企業に共通する7つの特徴とは?

資金繰りが悪化しやすい企業には、同じ原因で資金不足に陥るケースが多く見られます。資金が底をつく前に早期発見できるよう、厳しい資金繰りに陥りやすい企業の特徴を理解しましょう。
資金繰りを管理していない
資金繰りが厳しくなる企業で最も多い原因は、資金繰りを管理していないことです。起業から営業として奔走した経営者の場合、数字の管理に苦手意識を持つ傾向があります。
長い間、数字の管理を避けた「どんぶり勘定」で経営してきた結果、細かい収支を把握する習慣が身についていません。
感覚的な経営判断では、会社の規模が小さいほど、気づいた時には資金繰りが逼迫している傾向が多くあります。
日本・東京商工会議所の調査によると、売上1,000万円以下の企業では約90%が経理事務担当者が1人のみで、さらに約80%では経理専任の従業員がいない状況です。
このように多くの中小企業では、経営者自身や営業担当者が経理業務を兼務している状況です。本業の忙しさから経理業務が後回しになり、資金繰り管理が疎かになりやすい環境と言えるでしょう。
※参考:日本・東京商工会議所 中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査 結果
資金繰りの実態を把握できていない
経営者が資金の流れを正確に理解していないケースも多く見られます。その原因のひとつは経営者が資金繰り表を確認して、資金を把握するための仕組みが整っていないためです。具体的には以下のケースです。
- 経理担当者がおらず経理業務が後回し
- 経理担当者がいても帳簿づけのみ
- 資金繰り表を形式的に作成して保存するだけ
月次で資金の流れが見えていない状態が続くと、資金繰りの深刻な問題に気づくのが遅れてしまいます。
定期的に資金繰り表から実態を把握する習慣をつけることが、企業の安定につながるでしょう。
収入と支出のバランスが悪い
資金繰りの安定には収入と支出のバランスが欠かせません。しかし、資金繰りが厳しくなる企業では、バランスが崩れているケースが多く見られます。
手元に十分な余裕資金がない中で、収入よりも支出のタイミングが先に来ると、資金不足につながりかねません。
例えば、不要な経費の積み重ねは、手元の資金を徐々に減らす要因です。また、根拠のない売上見込みで判断して先行投資を決めてしまうと、支払い直前の資金繰りに困ってしまいます。
収入と支出のタイミングやバランスを常に意識することが、資金繰りの安定につながるでしょう。
財務諸表の作成が遅い
財務諸表の作成が遅れている企業は、資金繰りが悪化するリスクが高まります。最新の財務内容を把握できていない状態は、資金不足を事前に察知できず、対策が遅れかねません。
日本・東京商工会議所の調査によると、売上1,000万円以下の企業では約30%、1,000万円超~5,000万円以下でも約20%が毎月の帳簿を作成できていません。帳簿作成が遅れると、併せて財務諸表作成の遅れにつながります。
例えば、3か月前の帳簿しかない状態では、直近の資金繰りを把握できません。売上が維持できていても、作成していない間の大きな支払いを見落として資金不足になるケースもありえます。
支払い直前に資金不足がわかっても、対策が間に合わない可能性があります。早めに資金状況を把握できるように資金繰り表の作成は重要です。
※参考:日本・東京商工会議所 中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査 結果
売上が増加しているのに手元の現金が増えていない

売上が順調に推移しているにもかかわらず、資金繰りが悪化するケースは少なくありません。売上が増えるにつれて、仕入れなどの支出も増えるため、入金が支払いに追いつかず、一時的に資金繰りが苦しくなりかねません。
この状況は「黒字倒産」と呼ばれる典型例です。以下の表は、入金と支払いのタイミングが1ヶ月ズレている企業が売上、仕入とともに1.5倍に増えたケースです。
| 時期 | 仕入 | 売上 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 前月 | 100万円 | 120万円 | +20万円 |
| 売上増加の月 | 150万円 | 120万円 | −30万円 |
| 翌月 | 150万円 | 180万円 | +30万円 |
資金繰り表で入出金のタイミングを見える化できれば、財務知識がなくてもリスクを察知できます。
お金の動きが資金繰りにあっていない
業種に適した資金繰り計画を立てないと、厳しい状況に陥りやすくなります。業種ごとに仕入れから売上回収までの期間が違うためです。
例えば、仕入れの支払期間が30日、売上の回収期間が60日であれば、回収期間−支払期間=30日間の資金を補う必要があります。
自社の資金サイクルを意識せずに取引条件を決めた結果、資金繰りを悪化させているケースが少なくありません。自社の業種に合った資金の流れで取引条件を決定することが資金繰りの安定に重要です。
資金調達に取り組めていない
事業を拡大するうえで、必要に応じた資金調達を計画的に行うことが重要です。売上増加や一時的な資金に対応するための資金など資金調達は欠かせません。
しかし、数字管理が苦手な経営者は必要なタイミングに資金調達できず、資金繰りが悪化して初めて金融機関に相談するケースが多く見られます。
計画的な資金調達には、自社の事業計画や財務状況を整理し、金融機関と日頃から良好な関係の構築が大切です。経営者は、資金繰りを把握して自社の経営へ積極的に取り組む姿勢が求められるでしょう。
厳しい資金繰りを改善する7つの改善策

資金繰りが厳しい状態から適切な対策を講じていけば立て直しは可能です。ここでは、資金繰りを安定させるための具体的な7つのコツを解説します。
1.資金繰り表を作成して月次管理する
資金繰り改善の第一歩は、資金繰り表を作成して「見える化」することです。資金繰りの問題がどこにあるのかを把握せずに対策はできません。
資金繰り表とは、将来の収入と支出を予測し、月ごとの資金の流れを一覧にしたものであり、資金が不足する時期や金額が事前に把握可能です。
例えば、3か月先に大きな支払いが控えていることが分かれば、それまでに資金を準備する計画を立てられます。また、資金繰り表を継続的に作成することで、季節変動や取引先ごとの入金パターンなども見えてきます。
資金繰り表を毎月作成してチェックする習慣が正確な資金繰りの把握につながるでしょう。
2.資金繰り悪化の原因を調べる
資金繰り改善には原因の特定が欠かせません。表面的な対策では一時的な改善にとどまるため、根本的な原因を見極める必要があります。
資金繰り表からの分析で考えられる主な要因と対応は、以下のとおりです。
| 要因 | 対応 |
|---|---|
| 売上代金の回収遅延 | 特定の取引先から入金が遅れているなら取引条件を見直す |
| 売上減少 | ・季節変動がある場合は、閑散期に備えておく ・単純な受注減少であれば、新規先へのアプローチ |
| 経費増加 | 内容を確認して、削減できないか精査 |
分析により経営上の問題点を探ることが可能です。原因が特定できれば的確な対策を考えられるでしょう。
3.経費を削減する

資金繰りを改善するためには、経費削減が効果的です。支出を抑えれば、直接的に手元資金の流出を防ぐことができます。
経費削減では固定費と変動費を分けて考えることが重要です。主な内容は、以下のとおりです。
| 費用 | 主な項目 | 対策 |
|---|---|---|
| 固定費 | 人件費や家賃 | 役員報酬の削減、オフィス縮小 |
| 変動費 | 材料費や消耗品費、手数料 | 発注を見直し、購入内容の精査 |
固定費は毎月一定額が発生する経費であるため、見直しにより大きな効果が得られます。一方、変動費は業務量に応じて変動する経費であり、効果は大きくありませんが取り組みやすい項目です。
経費削減を進める際は、必要な投資まで削減するのではなく、無駄を省く姿勢で取り組むといいでしょう。
4.在庫量を適正に調整する
過剰な在庫は資金繰りを圧迫します。仕入れ時に支払ったものの、売れ残ったままでは資金を回収できません。
在庫を適正化するには現状把握が必須です。販売頻度や在庫の回転率を分析し、長く売れ残っている商品は値下げしてでも現金化しましょう。
過剰在庫は金融機関から「不良在庫」と判断され、融資審査に悪影響を及ぼします。適正な在庫量にすることは資金繰り改善と将来の資金調達につながるでしょう。
5.受取期間と支払期間のギャップを改善する
資金繰りで重要なポイントは、入金と支払いのギャップを大きくしないことです。支払いが先に来ると、回収による入金まで資金を別に確保する必要があります。
例えば、仕入代金の支払いが30日後、売上代金の入金が60日後となると、30日分のギャップが発生して資金を別に用意する必要が生じます。このギャップが大きいほど必要な資金が増大して資金繰り負担を増加します。
取引先と交渉して取引条件を見直すことが有効な改善策です。入金を早め、支払いを遅くできるとギャップが縮まって資金繰りを安定させられるでしょう。
6.不要な資産を売却して資金化する
事業に活用されていない資産である遊休資産は、売却できると資金繰りの改善に有効です。遊休資産の売却は維持コストを削減でき、また売却代金により負債を減少できます。
活用できていない土地が遊休資産の一つとして挙げられます。売却することで、得られるメリットは以下のとおりです。
- 固定資産税や維持管理費のコスト削減
- 借入金の返済や未払金の決済による財務内容改善
資産売却を検討する際は、将来必要となる可能性のある資産まで売却してしまわないように資産を見極めましょう。
7.金融機関や専門家などへ相談する
自社の取り組みだけで資金繰りの改善が難しい場合は、金融機関や専門家への相談も検討すると有効です。
金融機関は多くの企業を見てきた経験や知識から、業種ごとの特性や資金繰り改善のためのアドバイス、融資取引での返済条件の変更などの支援を期待できます。
また、中小企業診断士や税理士などの専門家も、さまざまな面から経営改善のための有益なアドバイスを提供してくれます。
現状を正確に伝えることが重要になるため、資金繰り表をはじめとした財務資料を準備して相談しましょう。
会社の資金繰りショートを避ける際の間違った対処法

資金繰りショートとは、支払日に必要な資金が足りなくなる状態です。このような状況は取引先や金融機関との信頼関係を損ない、会社経営に大きな打撃を与えかねません。
資金難を回避する「間違った対処法」は、一時的に対応できても将来の経営をさらに圧迫します。ここでは、避けるべき対応策について解説します。
取引先へ交渉せずに支払いを遅延する
連絡もなく支払いを遅らせることは避けるべき対処法のひとつです。取引先からの信頼が一気になくなります。
長期的な取引で信頼関係を構築した企業であれば、事前の相談で支払期日を延長してくれる可能性があります。逆に相談なく支払いを遅延すると、今後の取引を失いかねません。
資金繰り改善には取引先との良好な関係維持も不可欠です。支払いが困難になりそうな際には、資金繰り表を提示しながら具体的に支払える日を説明すると、説得力が高まるでしょう。
消費者金融などから借り入れする
比較的審査が通りやすい消費者金融などからの借入も避けるべき対処法です。消費者金融などの借入金利は一般的に高くなります。
高い金利での借り入れは返済負担を大きくし、資金繰りを悪化させます。資金ショートを回避できても、再び資金ショートの状況に直面するでしょう。
緊急時の資金調達手段として魅力的な解決策に映りますが、根本的な解決にはつながりません。
税金や社会保険料を滞納する
資金難に陥った際、税金や社会保険料の支払いを後回しにすることも間違った選択です。納税は法律上の義務であり、支払いの滞納は資産の差し押さえ対応につながります。
取引しているわけでもなく、売上に影響ないように思うかもしれません。しかし、滞納が続くと延滞税などで支払いが増え、最後には資産の差し押さえ措置をとられます。
また銀行取引にも悪影響があり、税金の滞納は融資審査に落ちる要因となり、銀行口座の差し押さえは資金難が露呈して信用不安につながるでしょう。
まとめ・資金繰りを見える化して安定した経営を確立しよう

資金繰りが厳しい企業には資金の流れを把握していないことや、収支バランスの悪さ、財務情報の見える化ができていないなどの共通点があります。
資金繰りを改善する第一歩は資金繰り表を作成して現状を正確に把握することです。主な改善策として具体的な7つのコツを紹介しました。すぐにできる対策から時間をかけた対策まであるため、できるものから取り組んでいくことが大切です。
また、一時的な解決を図って間違った対処法を選択しないように注意する必要があります。抜本的な解決にはならず、すぐに同じような危機に直面するでしょう。
毎月資金繰り表を作成することで資金の流れを把握でき、適切な資金管理と経営判断ができるようになり、資金繰りの安定化につながるでしょう。
資金繰り改善に活用できる「キャッシュフロー改善」チェックシートは資金調達手帳に掲載されています。資金調達だけでなく、資金管理に必要な財務資料の内容や作成方法を学べ、実務に役立つツールも好評ですので、ぜひご利用ください。
(編集:創業手帳編集部)