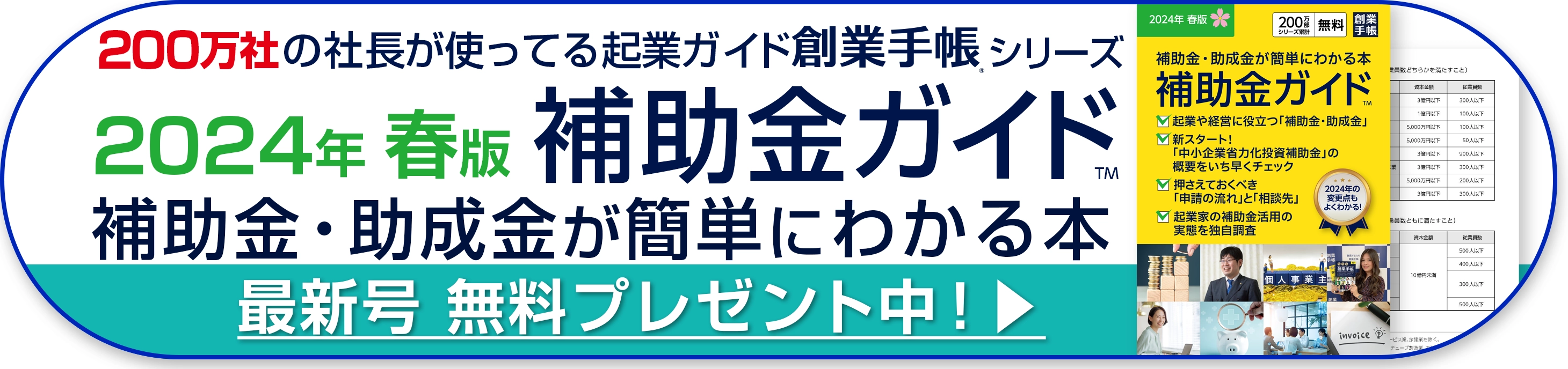定年後再雇用とは?労働条件や契約の流れ、助成金などをわかりやすく解説
定年後の再雇用は企業側にメリットあり!

少子高齢化社会の日本において、すでに労働力を確保するのが難しく、人手不足に陥っている企業も少なくありません。
しかし、高年齢者雇用安定法による定年後の再雇用制度を活用すれば、高年齢者の雇用を継続することも可能です。
そこで今回は、定年後の再雇用制度に関する概要から労働条件、契約の流れなどを解説します。
定年後再雇用で使える助成金なども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
また、シニア人材の活用だけでなく、育児支援、社員のスキルアップなどにも使える「雇用で差がつく助成金10選」を無料配布しています。社労士が厳選した助成金の支給額・助成率、スケジュールなどを確認できます。ぜひこの機会にご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
定年後の再雇用制度とは
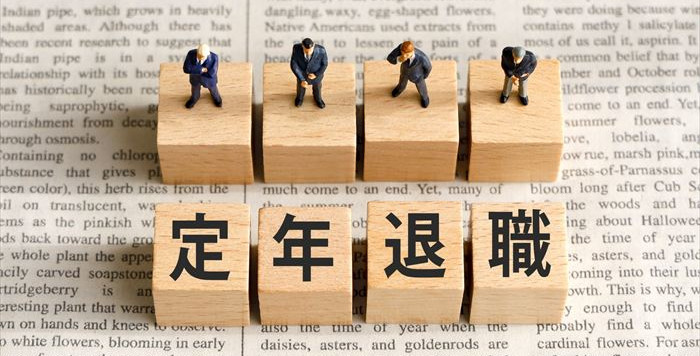
定年後の再雇用制度とは、定年を迎えた従業員が一度退職し、再度同じ会社で新しく雇用契約を結び直す制度を指します。
ここで、定年後の再雇用制度に関する概要や導入背景、再就職・勤務延長制度との違いについて解説します。
定年後再雇用の概要
定年後再雇用制度では定年を迎えた従業員と再度雇用契約を結び直すことになるため、従来と異なる雇用契約で採用されることになります。
例えば、これまでは正社員として長年勤めてきた人が、定年後の再雇用制度によって労働時間が短くなったり職務内容が限定されたりするなど、柔軟に設定することが可能です。
再雇用期間は企業ごとに異なるものの、高年齢者雇用安定法に則り、従業員が希望する場合はその従業員を65歳まで雇用する義務が会社にあります。
そのため、会社側は少なくとも65歳まで再雇用できる制度を整えておく必要があります。
定年後再雇用の導入背景
定年後の再雇用制度が導入された背景として、少子高齢化やその影響による労働力不足が挙げられます。
また、定年退職年齢と年金受給開始年齢にギャップがあることで定年後も働くことを希望する高齢者が増えていることから、定年後の再雇用制度が導入されました。
高年齢者が活躍できる環境の整備を目指す「高年齢者雇用安定法」では、70歳までの就業機会の確保について企業側に求めています。
「高年齢者就業確保措置」と呼ばれる具体的な措置について、以下のように会社側に実施が求められています。
-
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
①事業主が自ら行う社会貢献事業
②事業主が委託・出資(資金提供)などを行う団体による社会貢献事業
なお、これまでは労使協定によって継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は経過措置が認められていました。
しかし、2025年4月1日から以下いずれかの措置を講じなくてはいけなくなりました。
-
- 定年制の廃止
- 65歳までの定年引上げ
- 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
再就職や勤務延長制度との違い
定年後の再雇用制度と似ているものとして、「再就職」や「勤務延長制度」などがあります。
定年後の再就職は、定年を迎えた高年齢者がハローワークやシルバー人材センターなどを活用し、これまで働いていた会社とは別の就職先を見つけることをいいます。
自分が希望する会社から求人が出ていれば、そこで働ける可能性があるというメリットもあるでしょう。
しかし、そもそもシニアで募集される職種は限られており、必ずしも希望する職種で働けるわけではない点に注意が必要です。
勤務延長制度とは、定年を迎えた従業員が退職せず、これまでと同じ雇用形態で働き続ける制度です。
再雇用制度とは異なり、以前の労働条件が継続されるため給与が大きく減ってしまうリスクも回避できます。
ただし、企業側からすると高年齢者が職場に長く留まることで、若手社員の成長や昇進のチャンスが潰されてしまい、若い世代の離職率増加につながる可能性もあります。
定年後の再雇用制度導入のメリット

定年後の再雇用制度を取り入れることで、企業側はどのようなメリットを得られるのでしょうか。
まず挙げられるのは、ベテランがこれまで培ってきた知識・経験を活かせるという点です。
ベテランが次々に定年退職となると、現場で活かせる知識や経験が少なくなりますが、再雇用制度によって引き続き仕事に活かせるようになります。
少子高齢化によって若い労働力が減少傾向にあることから、若い人材を確保できない企業は再雇用制度を導入することで人手不足をカバーできる点もメリットです。
また、定年退職にともなって新しい人材を雇用した場合、教育費用などでコストがかかってしまいます。
しかし、再雇用制度を導入すれば採用・教育にかかるコストも削減できます。
このように、企業は定年後の再雇用制度を導入することで、様々なメリットを得られるようになるでしょう。
定年後再雇用における労働条件

定年後の再雇用制度を導入する場合、労働条件はどのように設定すれば良いのか迷ってしまう人もいるかもしれません。
そこで、あくまでも目安となりますが、定年後再雇用の労働条件についても解説します。
仕事内容
再雇用制度を導入する場合、高年齢者がこれまでと異なる業種に就くことは認められていません。
これは過去の判例でも、もともとデスクワークをしていた事務職が、再雇用後に清掃員として再雇用するのは違憲だと判決が出されています。
ただし、仕事内容は変わっていても業種が同じであれば問題ありません。また、業種が同じ仕事でも定年前より責任が軽くなるケースも多いです。
雇用形態
雇用形態は再雇用契約の内容によって異なっており、定年後もフルタイムで働く人もいれば、嘱託・パートなどの雇用形態に変更する人もいます。
労働政策研究・研修機構(JILPT)による『60代の雇用・生活調査』(2020年)では、60代の雇用形態について「パート・アルバイト」が最も多い40.7%でした。
次いで「正社員」の21.4%、「嘱託」15.2%、「契約社員」14.4%になることがわかっています。
契約更新期間
企業が取り入れている再雇用制度では、1年ごとに契約を更新する有期雇用の契約社員または嘱託社員として再雇用されるケースが多いです。
しかし、場合によっては半年ごと、2年ごとに設定する企業もあります。
更新条件には健康状態や業績の評価など、明確な基準を設定しておくことが大切です。また、上限期間については最長で雇用できる期間を設定するのが望ましいでしょう。
給与・賞与・各種手当
再雇用後の給与水準は、雇用形態や仕事内容などに合わせて異なる設定になる場合が多いです。
例えば、これまで正社員として働いてきた人を嘱託社員として再雇用した場合、これまで受け取っていた給与水準から下がってしまう場合が多いです。
賞与は会社によって支給する場合と支給しない場合に分かれますが、もし支給する場合はいつ支給するのか、算定基準をどうするか明確にしておきましょう。
各種手当は仕事内容や責任の変更によって見直す必要が出てきます。
例えば、これまでは役職手当がついていた人は、再雇用によって役職・職責が変わり、手当がなくなる可能性が高いです。
退職金
再雇用制度は定年退職をしてから再び同じ企業で働くことになるため、基本的には定年退職をした時点で退職金が支払われます。
しかし、再雇用規約期間が終了する時点で退職金を支払う場合は、請求権の時効に関するトラブルにつながる恐れもあります。
そのため、企業と対象となる従業員との間で明確に支払い時期を確認しておくことが大切です。
有給休暇
労働基準法では再雇用した従業員に対しても、有給休暇の取得は適用されます。
定年退職をした日と再雇用した日に空白期間がない場合、継続して就業しているとみなされるため、有給休暇も定年前の勤続年数を通算した日数を取得できます。
なお、これは雇用形態が変わっても同様に適用されるものです。
例えば、正社員から再雇用後にアルバイトへ変わったとしても、以前の勤続年数を通算した日数で取得できるケースが多いです。
社会保険
定年後の再雇用制度で新たに雇用契約を結び直すことになったとしても、社会保険の加入に関してはリセットされません。
基本的には再雇用となった場合でも雇用は継続しているとみなされるため、被保険者年数も定年前からの通算年数が適用されます。
ただし、加入条件や保険料の負担に関しては、労働条件によって変化するので注意が必要です。
例えば、再雇用契約で1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が、ほかの従業員の4分の3未満になる場合、社会保険の被保険者資格が失われることになります。
定年後再雇用契約する際の流れ

実際に企業で定年後再雇用制度を導入する場合、再雇用契約を締結させる際の流れはどのように行われるのでしょうか。
ここで、定年後再雇用契約をする際の流れについて紹介します。
1.対象者に通達して意思確認を行う
定年後に再雇用するかどうかは企業側が勝手に決められるわけではありません。
まずは再雇用制度の対象になる定年退職予定の人に対して、再雇用制度の内容と運用方法について事前に通達・説明を行う必要があります。
対象者に文書などで通達したら、個別の説明会を設けて丁寧に説明し、疑問点をなくしていきます。
十分に説明する時間を設けた上で、再雇用を希望するかどうか意思確認をすることが重要です。
2.対象者と面談で雇用条件を確認する
再雇用を希望する対象者に対して個別での面談を実施し、再雇用後の働き方に関する希望を聞きながら、賃金や雇用形態など雇用条件の確認をしてもらいます。
雇用条件に関しては特に後々トラブルが発生しないよう、きちんと説明することが大切です。
3.再雇用契約を締結する
再雇用後の雇用条件で合意を得られたら、書面で再雇用契約を締結します。また、会社の退職規定に則って定年達成時に退職金を支払う場合は、その準備も進めておきます。
再雇用者の仕事内容や役割、就業場所については、関係部署への周知を徹底させることも重要です。
さらに、再雇用者に対しても改めて研修を実施し、再雇用における就業時のルールなどを認知してもらいます。
4.社会保険の手続きを行う
再雇用後に所定労働時間が減少し、社会保険の適用範囲外になった場合は健康保険と厚生年金保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
また、社会保険の適用範囲内だったとしても、賃金が低下して社会保険の標準報酬月額が下がってしまう場合には、同日得喪(資格喪失届と資格取得届を同時に提出すること)の手続きが必要です。
定年後再雇用を成功させるためのポイント

企業が再雇用制度の導入で成功するためには、以下の3つのポイントを押さえておくことも大切です。
就業規則を整備する
再雇用制度を導入する場合、まずは就業規則にその旨を記載し、これまでの規則内容と変更しなくてはいけない箇所があれば改定する必要があります。
通常の規則改定と同じく、労働組合または労働者代表からの意見も取り入れつつ、改定後の就業規則を所轄の労働基準監督署に変更届と共に提出します。
従業員の健康状態を把握する
定年後の再雇用制度で対象となるのは、基本的に65歳以上の高年齢者です。
高年齢者になると若者に比べて視力や聴力、筋力などが低下してくる傾向にあるため、労働災害が発生する危険性も伴います。
トラブルが発生してからでは遅いため、企業側はあらかじめ従業員の健康状態について把握することも重要となってきます。
例えば、定期健康診断にプラスして健康に関するアンケート調査を社内で実施し、事業者と従業員本人が健康状態を客観的に把握できる体制を構築するのもおすすめです。
給付金や助成金を活用する
国は高年齢者の雇用を促進させることを目的に、再雇用制度を含む継続雇用制度の導入支援に活用できる給付金・助成金を設けています。
・高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険の被保険者だった期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則60歳以降の賃金が、60歳時点と比べて75%未満に減少した状態でも働き続ける場合に支給される給付金です。
2025年4月1日以降で60歳に達した日を迎えた人は、60歳以上65歳未満における賃金が60歳時点の賃金と比べて64%減少した場合、各月の賃金の10%相当額となります。
そして64%超75%未満減少した場合は、その低下率に応じて各月の賃金の10%相当額未満が支給されます。
・65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金は、65歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用基盤を整備することを目的に実施している助成金制度です。
主に3つのコースがあり、それぞれ助成内容と助成額が異なります。
| コース | 対象 | 助成額 |
| 65歳超継続雇用促進コース | 定年引上げや定年制度の廃止、継続雇用制度を導入する事業主が対象 | 当該措置の内容や定年の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて10万円~160万円を支給 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者の雇用管理制度を整備する事業主が対象 | 雇用管理制度の導入などで使った経費(上限50万円)に対して、60%(中小企業以外は45%)の助成率を乗じた額を支給 |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業者が対象。その人数(上限10人)に応じて助成 | 対象者1人につき30万円(中小企業以外は23万円) |
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障がい者などの就職困難者を、ハローワークなどの紹介を活用し、継続して雇用する労働者(雇用保険被保険者または高年齢被保険者)として雇い入れた事業者に対し、助成される制度です。
支給される金額は、雇い入れた労働者の類型と企業規模によって異なります。
例えば、短時間労働者以外の高年齢者(60歳以上)の場合、1人あたり60万円(中小企業以外は50万円)が支給されます。
短期労働者で高年齢者の場合は1人あたり40万円(中小企業以外は30万円)です。
まとめ・定年後再雇用は人材の確保に有効
少子高齢化が進行する中で、徐々に若者を採用するのが難しくなってきています。
このような状況で人手不足を解消していくためにも、定年後の再雇用制度を導入するのがおすすめです。
助成金などもうまく活用しながら、人材の確保を目指して定年後の再雇用制度を導入してみましょう。
また、シニア人材活用にも使える助成金を掲載した「雇用で差がつく助成金10選」は以下のバナーから無料でもらえます。
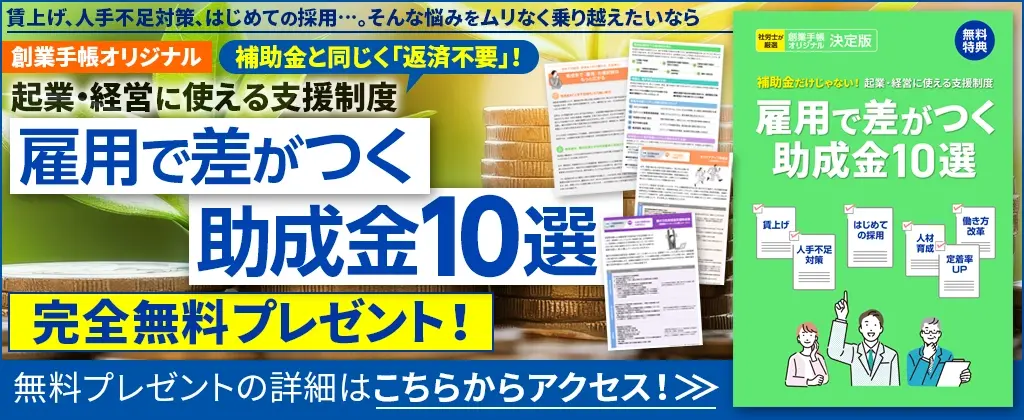
創業手帳別冊版「補助金ガイド」では、経営者の方々がよく使われている補助金・助成金を厳選してわかりやすく解説しています。ぜひこちらもあわせてお読みください。

(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。