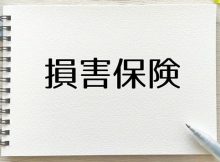「傷病手当金」と「傷病手当」は何が違う?特徴や申請する流れも解説!
「傷病手当金」と「傷病手当」は似た言葉でも目的が異なる
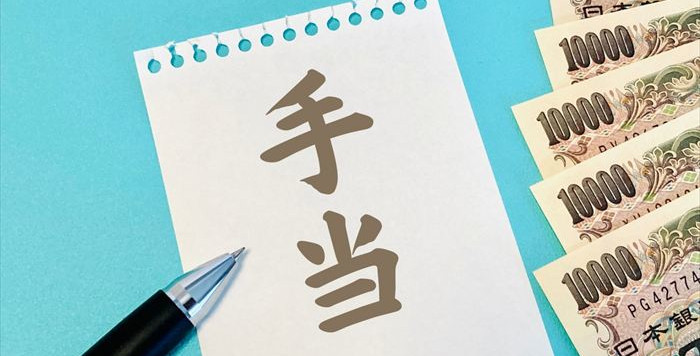
仕事や日常生活の中で病気やけがによって働けなくなった時、収入の不安を少しでも軽減する制度が「傷病手当金」や「傷病手当」です。
一見すると似た制度に思えますが、実はそれぞれ支給の目的や制度の仕組みが異なります。
この記事では、「傷病手当金」と「傷病手当」の違いをわかりやすく解説するとともに、それぞれの特徴や申請の流れについても詳しく解説します。
自分や家族が制度を利用する可能性がある人は、今回の記事を通して正しい知識を身に付けてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
傷病手当金と傷病手当の違い
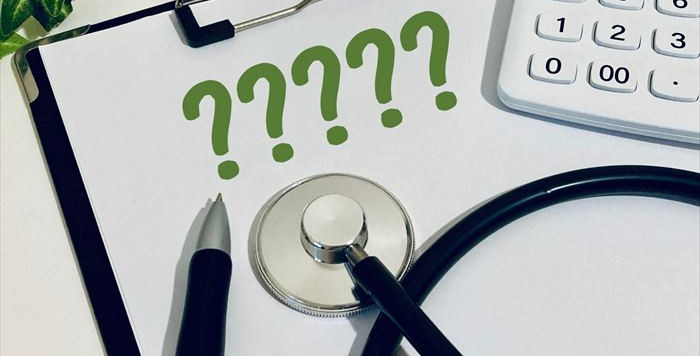
傷病手当金と傷病手当は似た言葉でも保険の種類から目的、利用できる人まで異なっています。ここで、具体的な3つの違いについて解説します。
| 傷病手当金 | 傷病手当 | |
|---|---|---|
| 保険の種類 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 目的 | 在職中に病気やけがで働けなくなった人の給与の一部を補うことが目的 | 失業中に病気やけがの影響で求職活動ができない人の生活費を支援することが目的 |
| 利用できる人 | 健康保険に加入しており、業務外の病気・けがで働けなくなった人 | ハローワークで求職の申し込みをした人 |
保険の種類
傷病手当金と傷病手当の大きな違いとして、保険の種類が異なる点が挙げられます。傷病手当金は健康保険に該当する制度ですが、傷病手当は雇用保険に該当する制度です。
日本は国民皆保険制度によって、国民全員が何らかの公的医療保険に加入する義務があります。
傷病手当金は主に健康保険組合と全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する医療保険を組み合わせた健康保険に該当するものです。
そのため、国民健康保険に加入している場合は傷病手当金を利用できません。
目的
保険の種類が違っていることから、目的も大きく異なります。
例えば傷病手当金は健康保険に加入している人が利用できるため、在職中に病気やけがで働けなくなってしまった際の給与補償を目的としています。
一方、傷病手当は失業中に病気やけがをしてしまい、働けなくなった人を対象としているため、その人の生活費を支援することが大きな目的です。
病気やけがをしていてもすべての人が傷病手当を受け取れるわけではないため、注意してください。
利用できる人
詳しい支給条件などは後ほどそれぞれの項目で解説しますが、傷病手当金を利用できる人は主に健康保険に加入していて、業務外の病気・けがで働けなくなった人になります。
仕事中や通勤中に発生した病気やけがは労災保険の対象となり、傷病手当金は原則支給されません。
傷病手当は目的でも紹介したように、失業中に病気やけがをして働けなくなった人を対象としています。
そのため、ハローワークで求職の申し込みをしており、失業手当の受給資格を持っている人が利用できます。
傷病手当金と傷病手当は利用できる人が異なっているため、同時に2つの制度を利用することはできません。
傷病手当金とは?
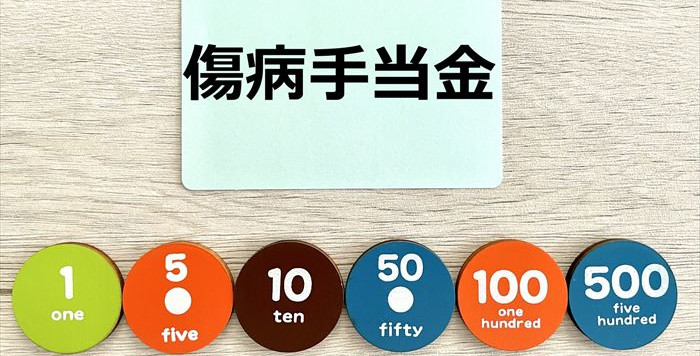
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外で発生した病気・けがを理由に療養が必要となった際に、被保険者とその家族の生活を守るために支給される手当金です。
会社を休んでいることで十分な報酬を得られない場合に支給されます。
傷病手当金が支給される条件
傷病手当金が支給されるには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
-
- 業務外の病気やけがであること
- これまで担当していた仕事ができない状況にあること
- 仕事を休んだ期間に給与の支払いがないこと
- 連続した3日間の待機期間を含め、4日以上仕事を休まなくてはならないこと
業務内で発生した病気やけがは労災保険の対象なので、傷病手当金は支給されません。
病気やけがの療養でこれまで担当していた仕事ができない状況にある場合、条件を満たしていることになります。
例えば、療養後にこれまで担当していた仕事ができず部署異動や業務内容を変更して勤務を続けた場合、リハビリ出勤で給与の支払いがなされていなければ「勤務ができていない」と判断され、傷病手当金の対象になる可能性があります。
また、所得補償を目的とする制度なので、休んでいる期間中に事業主から給与が支払われた場合は傷病手当金の対象外になってしまうのです。
ただし、給与が支払われていても傷病手当金より給与が少なかった場合は、差額分が支払われます。
傷病手当金で支給される金額
傷病手当金で支給される金額は、以下の計算式によって求められます。
1日あたりの支給金額=支給開始日から以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
支給開始日は最初に給付が支給される日を指しています。
例えば12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額が30万円だった場合、30万円÷30日×(2/3)=6,667円が1日あたりの支給金額です。
ただし、12カ月間は継続したものでなければなりません。加入期間が12カ月間に満たない場合、以下のいずれか低い金額を使って計算することになります。
-
- 支給開始日が属する月より以前の直近の継続した各月の標準報酬月額
- 標準報酬月額の平均値(支給開始日が2025年4月1日以降の場合は32万円)
傷病手当金の受給期間
傷病手当金は病気やけがで仕事を休んでから最初の待機3日間を除き、4日目から支給されます。連続で3日間休まないと支給されないので注意が必要です。
受給期間は休業4日目の支給開始日から、通算して1年6カ月目まで支給されます。
以前までは途中で4日目以降に出勤して給与支払いがあった場合、その期間も1年6カ月の中に含まれてしまっていました。
しかし、2022年1月1日から支給期間が通算化され、途中で出勤している場合でもその期間を除いて欠勤した期間だけで1年6カ月目まで支給されるようになりました。
支給停止・調整されるケース
傷病手当金の支給対象だった場合でも、途中で支給が停止になったり、調整を受けたりするケースがあります。
例えば障害厚生年金や障害手当金を受けることが決まった場合です。傷病手当金を受ける期間がまだ残っていたとしても支給されなくなってしまいます。
ただし、障害厚生年金の金額の360分の1が傷病手当金の1日あたりの支給金額より低かった場合、その差額分は支給されます。
また、労災保険から休業補償給付を受けたことがあり、同一の病気やけがで働けなくなった場合は傷病手当金が支給されません。
資格喪失後に傷病手当金を継続給付していて、老齢年金を受けている場合も支給されないので注意してください。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合、傷病手当金が出産手当金よりも多ければ、その差額分の支給となります。
傷病手当とは?

傷病手当は、離職後にハローワークで求職の申し込みを行った場合に受けられる手当です。
もともと求職期間は雇用保険の基本手当(失業手当)が支給されるものですが、この期間中に病気やけがの影響で働く意思はあるのに求職活動ができない状態にあると、傷病手当が支給されることになります。
そのため、雇用保険の基本手当と傷病手当を両方同時に受け取ることはできません。
ただし、病気やけがが治り、医師から就労可能と診断書で判断された場合、そのまま求職活動を行うと傷病手当から基本手当に切り替わり、支給を受けられるようになります。
傷病手当が支給される条件
雇用保険の傷病手当が支給されるには、まず基本手当の受給資格がある上で、傷病手当が支給される条件も満たしていないといけません。
基本手当は以下の条件をすべて満たしている必要があります。
-
- 離職している(正当な理由による退職・解雇など)
- 管轄のハローワークで求職の申し込みをしている
- 働く意思と能力はあるものの、失業状態にある
- 積極的に求職活動を行っている
- 離職日以前の2年間雇用保険に加入しており、その期間が12カ月以上ある(特定受給資格者の場合は6カ月)
さらに、傷病手当を受け取るためには、以下の条件をすべて満たさなくてはなりません。
-
- 働けない状態を除き、基本手当の受給資格を持っている
- ハローワークで求職の申し込みをしてから病気やけがが発生した
- 病気やけがで15日以上働けない状態が続いている
- 医師の診断書(傷病証明書)を提出できる
- ハローワークに傷病手当の申請をしている
傷病手当で支給される金額
傷病手当の金額は原則基本手当の金額と同じで、離職日前6カ月間に支払われた給料の平均を計算し、金額が決定されます。具体的な計算式は以下のとおりです。
1日あたりの支給金額(基本手当日額)=賃金日額×給付率(45~80%)
賃金日額は離職日前6カ月間の賃金総額(賞与を除く)÷180日で計算します。例えば月収30万円を受け取っていた場合、30万円×6カ月÷180日=1万円になります。
給付率は賃金日額が低いほど最大80%が適用され、高所得者は45%が適用されます。離職理由によって給付率の変更は見られません。
今回80%で計算した場合、賃金日額1万円×給付率80%=8,000円になります。ただし、賃金日額と基本手当日額は離職時の年齢によって上限額が異なります。
| 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 | |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,130円 | 7,065円 |
| 30~44歳 | 15,690円 | 7,845円 |
| 45~59歳 | 17,270円 | 8,635円 |
| 60~64歳 | 16,490円 | 7,420円 |
上記で計算した8,000円は、45~59歳ならそのまま支給されますが、それ以外の年齢だと上限額までとなるので注意してください。
傷病手当の受給期間
傷病手当の受給期間は、基本手当の所定給付日数から基本手当が支給された日数を差し引くと、傷病手当の上限日数が把握できます。
基本手当の所定給付日数は、離職日の翌日から原則1年以内です。ただし、離職理由や雇用保険の被保険者だった期間によって90日から最大360日まで変動します。
例えば自己都合で退職した場合、年齢ではなく被保険者期間によって所定給付日数が決まっています。
| 雇用保険の被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 |
| 10年以上20年未満 | 150日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合による退職や倒産、家族の介護などでやむを得ず退職した場合などは、年齢と被保険者期間に応じて期間が異なっています。
| 年齢/被保険者期間 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
傷病手当金と傷病手当の申請の違い
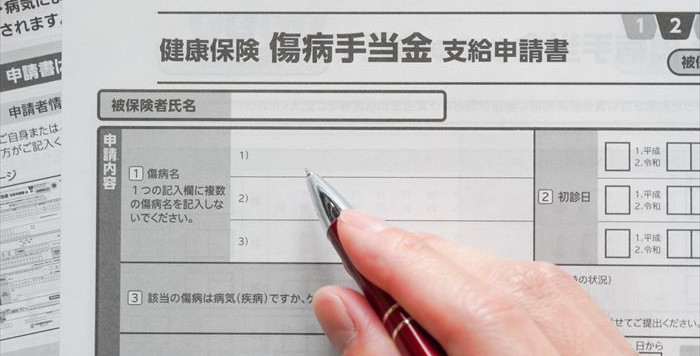
傷病手当金と傷病手当は申請方法も異なります。ここで、それぞれの申請方法について確認しておいてください。
傷病手当金の申請方法
- 傷病手当金の申請方法
-
- 1.申請書の取り寄せ・記入を行う
- 2.主治医に書類を記入してもらう
- 3.全国健康保険協会または健康保険組合に申請する
- 4.申請書類を提出する
傷病手当金の申請をする際に、勤務先による手続きと被保険者本人の手続きが必要です。
勤務先は被保険者が申請期間中に出勤した日数や出勤していない日に支払った賃金を記入します。
一方、被保険者本人は被保険者用の支給申請書を記入し、主治医に療養担当者記入用紙への記入をお願いします。
申請書は加入している健康保険のホームページからダウンロード可能です。
就労ができなくなったと認められた期間を過ぎてから、申請する必要があります。
さらに申請期限は手当金を受給できる日の翌日から2年以内までなので、忘れずに申請手続きをしてください。
傷病手当の申請方法
- 傷病手当金の申請方法
-
- 1.傷病手当支給申請書を入手して記入する
- 2.ハローワークに提出する
傷病手当支給申請書はハローワークに置かれており、基本情報と就職活動ができない理由、療養期間などを記載する必要があります。
また、医師の証明欄も設けられているため、担当医に記入と押印を依頼してください。
記入ミスや証明欄が未記入だと申請が受理されない可能性もあるので、不備がないかチェックしてから提出するようにしましょう。
傷病手当金と傷病手当に関するよくある質問

最後に、傷病手当金と傷病手当に関するよくある質問を紹介します。
傷病手当金は有給休暇を取った日にも支払われる?
傷病手当金の条件として、休業期間中に給与が支払われていないことが含まれています。
有給休暇は賃金が発生する休暇になるため、給料が発生しており傷病手当金の条件を満たさないことになります。
そのため、原則有給休暇と傷病手当金を併用することはできません。ただし、有給取得による給与金額が傷病手当金よりも少なかった場合、その差額分が支給されます。
傷病手当金と失業保険(基本手当)は同時に受け取れますか?
傷病手当金と失業保険は、原則同時に受給することはできません。しかし、一定の条件を満たすことで切り替えや調整が可能になります。条件は以下のとおりです。
-
- 傷病手当金と失業保険の両方の条件を満たしている
- 先に傷病手当金を受給している
- 失業保険の延長手続きを行っている
傷病手当金を受け取ってから失業保険の延長手続きを行った場合、病状が回復するまで傷病手当金を受け取り、回復次第失業保険に切り替えることが可能です。
会社を退職してからも傷病手当金は受け取れますか?
退職後も条件さえ満たしていれば、最長1年6カ月間は受給できるようになります。条件は以下のとおりになります。
-
- 退職日までに1年以上継続して健康保険に加入している
- 退職日の前日までに連続3日以上欠勤し、退職日当日も休業している
- 退職日と同じ傷病で引き続き働けない状態にある
- 傷病手当金の支給開始日から休職日を通算し、1年6カ月以内の範囲である
- 退職後も働けない状態が続いている
なお、支給対象になる日の翌日から数えて、2年以内であれば退職後でも傷病手当金を申請することは可能です。
アルバイト・パートでも傷病手当金や傷病手当を受け取れますか?
アルバイトやパートなどの雇用形態でも、傷病手当金を受け取ることは可能です。ただし、勤務先の保険加入状況によって異なります。
例えば家族や配偶者の被扶養者でパートをしている場合、被保険者として認められないため傷病手当金を受け取れません。
また、被扶養者ではなくても勤務先の健康保険ではなく国民健康保険に加入している場合は支給対象外です。
失業手当の受給中に病気やけがで働けなくなったらどうなりますか?
ハローワークで「傷病手当(傷病手当支給申請)」を行うと、受給期間の延長が可能になります。
失業手当の受給中に病気やけがで働けなくなった場合、ハローワークで傷病手当を申請し、就業できない期間が30日以上になると、失業手当の受給期間を最大4年以内であれば延長することが可能です。
傷病手当を受けている間、失業手当はどうなりますか?
原則、傷病手当を受け取っている期間に失業手当も受け取ることはできません。傷病手当が支給されたら失業手当は一時的に停止されることになります。
停止した失業手当は、回復して働ける状態になったら受給再開手続きを行うことで、失業手当を復活させることが可能です。
まとめ・傷病手当金と傷病手当の違いを理解してうまく活用しよう
傷病手当金は健康保険、傷病手当は雇用保険と、保険の種類から異なっています。
万が一働けなくなってしまった場合でも、自分の状況に合わせて傷病手当金や傷病手当を活用することで、金銭的な負担を少しでも軽減させることが可能です。
傷病手当金と傷病手当の違いを理解して、適切に手当を受けられるようにしてください。
創業手帳(冊子版)では、経営者も知っておきたい社会保険に関する情報も数多く掲載しています。ほかにも、労働環境の整備に役立つ知識・ノウハウも紹介しているので、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)