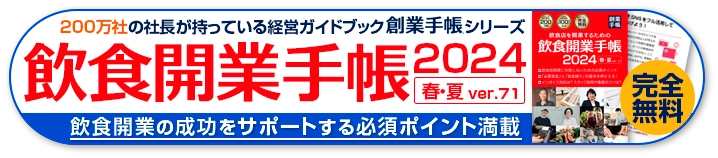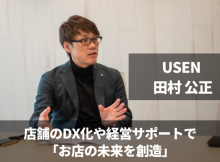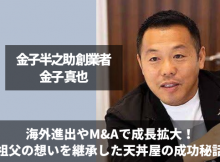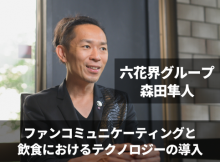サイゼリヤ元社長 堀埜 一成|失敗しても自分が辞めればいい。そう思ったら社長業を心から楽しめた
理念以外は全て変える。サイゼリヤ2代目社長の外食業の常識を超えた成長戦略とは
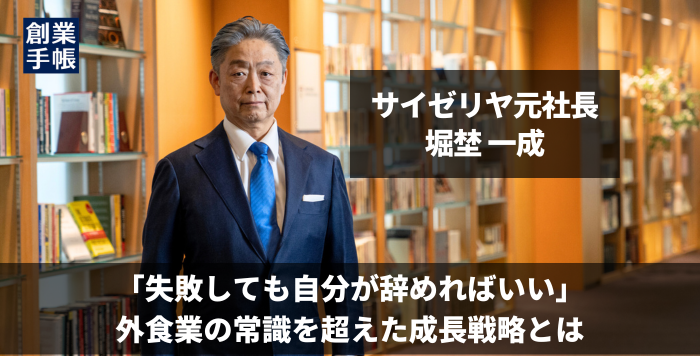
気軽にイタリアンが楽しめる人気レストランチェーン「サイゼリヤ」は圧倒的な安さと美味しさから多くの方に利用されています。2009年から13年間、株式会社サイゼリヤの代表取締役社長を務めたのが堀埜一成さんです。
創業者からバトンを受けた堀埜さんは、社長就任後さまざまな改革を実行。その結果、サイゼリヤは国内外あわせて1,500店舗以上となり、同社も大企業へ成長しました。
「社長を任命された直後は大きなプレッシャーを感じました。でもお客様に必要とされる会社である限り、失敗しても自分が辞めれば会社は残る。そう気づいてからは社長業を心から楽しめました」と語る堀埜さん。今回は堀埜さんがどうサイゼリヤを成長させたのか、創業手帳代表の大久保がインタビューしました。

株式会社サイゼリヤ 元代表取締役社長
1957年富山県生まれ。京都大学農学部、京都大学大学院農学研究科修了。1981年味の素に入社、1998年には同社発酵技術研究所研究室長を務める。
サイゼリヤ創業者の正垣泰彦氏より生産技術者として口説かれ、2000年株式会社サイゼリヤに入社、同年取締役に就任。2009年同社代表取締役社長に就任。食堂業と農業の産業化を自らのミッションとし、13年の在任期間で急速成長後の基盤づくり、成熟期の技術開発など独自の感性で会社の進化をけん引する。2022年に代表取締役を退任。

創業手帳 株式会社 ファウンダー
大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
社長を任命された後、重すぎする責任に圧倒されプレジデントブルーに

大久保:著書「サイゼリヤ元社長が教える 年間客数2億人の経営術」を拝読して、外食業以外の方も読むべき素晴らしい内容だと感じ、今回インタビューの機会をいただきました。
著書にもありましたが、あらためてサイゼリヤの社長に就任した経緯を教えていただけますか?
堀埜:2000年に味の素からサイゼリヤに移った時から、いずれは社長になるという話でした。
社長になる数年前に数人が集められ、当時社長だった正垣会長(編集部注:サイゼリヤ創業者の正垣泰彦氏)から「ここにいる全員が社長候補だから、それぞれ事業部を持って運営してくれ。その中から次の社長を選ぶ」と言われました。
僕は100店舗ぐらいを担当して運営や経営を行った後、変革推進部という新しい部署を作らせてもらいました。これは全てのオペレーションを変える必要があると感じたからなんです。
それから半年ぐらい経った1月に正垣会長に呼び出され、「4月から社長な」と言われました。本来なら嬉しいところですが、全く喜びはなく自分でも驚きました。
なぜかというと、1万人近くいる従業員とその家族も含めた人生を、全て社長となる僕が背負うということを実感したからです。結婚前に不安になることをマリッジブルーと言いますが、僕の場合はプレジデントブルーという感じですね。社長就任までの3か月くらいはその状態が続きました。
大久保:確かに、重すぎる責任ですよね。どのように克服されたのでしょうか?
堀埜:正垣会長にずっと言われていた「この会社を潰していいからな」という言葉を思い出したのがきっかけです。最初に言われたときは冗談だと思いましたが、プレジデントブルーになっている間、真意がわかってきました。
会社が潰れても僕が社長を辞めれば済む、ということなんですよね。会社が正しいことをしていてお客様から必要とされていれば、会社は必ず生き残る。万が一でもクビになるのは社長だけで、全員が路頭に迷うことはない。
そういう意味だと気づいて「よし、社長になるぞ」という気持ちになれました。社長として多くのチャレンジができたのも、会長の言葉によってプレジデントブルーを克服できたからだと思っています。
大久保:なるほど。社長に就任後、「原価を計算せず売値を決める」などサイゼリヤの独特な経営に驚いたそうですね。こうした経営を引き継ぐのは、大変だったのではないでしょうか。
堀埜:そこはポジティブでした。社長交代会見の時も、正垣会長の隣で僕は「理念以外は全部変えます」と宣言したんですよ。
理念は創業者のものですから、変えられない。でも他のことは全て変えるつもりで僕は社長になりました。それが認められないなら社長をやる気はないですよ、という宣言でもあったんです。
それを聞いて正垣会長は隣で笑っていました。正垣会長は、本気で僕に任せてくれていたんですよね。会長の支えがなかったら、今の私はいません。
原料を作るところからお客様に渡るまで、あらゆることを改革した

大久保:社長就任後に堀埜さんが取り組んだ改革について、伺えますか?
堀埜:僕は企業の持つ能力を「技能」から「技術」に変えたかった。「技術」というのは文字を通じて伝えられるものです。飲食業では「俺の後ろ姿を見て学べ」ということが多いですよね。そういう「技能」ではなく、マニュアルや報告書を見て学べる「技術」にしたかったんです。
当時のサイゼリヤは、報告書を書く時間があれば働けという雰囲気でした。日報は一応ありましたが、数字を書くだけで反省がないので次につながらない。それを全て変えようと思い、とにかく報告書の作成と報告会をしました。これは味の素にいた頃ずっとやってきたことです。
大久保:著書の中で「レストラン版ユニクロを目指した」いうフレーズが印象的でした。あらためて堀埜さんがどんなイメージを持っていたのか、教えていただけますか?
堀埜:ユニクロというのは、バーティカルマーチャンダイズ(材料段階から消費者に渡るまでの商品化計画を一貫して取り組む)の考え方という意味です。サイゼリヤでも、外食業ながら本気で工場を作ろうと思いました。 もともと僕は工場技術者で、そこは得意な分野でしたから。
ユニクロは素材開発にメーカーが関わっているそうなので、厳密に言うと自社完結ではありません。でもサイゼリヤでは、原料を作るところから全て自分たちでやろうと考えました。
大久保:やはり全て自社で行うことが、サイゼリヤの低価格につながっているわけですね。
堀埜:その通りです。チェーンストア化しようとする時、コストリーダーシップ戦略を取らなければなりません。そのためにはコストを下げ続ける必要があります。原価だけではダメで、店舗のオペレーションまで含めた全てのコストを下げ続ける必要があります。
原料を作るところからお客様に渡るまでのコストをコントロールしなければ、低価格は維持できません。そこで、原料から販売までのバリューチェーンの全てを自社でコントロールできるようにしました。
大久保:外食産業はセントラルキッチンを持つところが多いですが、サイゼリヤは少し違う工場を持っているとお聞きしました。どのようなところが違うのでしょうか?
堀埜:どちらも、店舗で使用する製品を作るのですが、セントラルキッチンは店舗で行っていることをそのまま大型にしたものです。そうではなく、僕はプラントで使われる大型機器を使用して製品を作る工場を作ろうとしました。例えると、湯沸かし器のように水道から直接配管を通りお湯になって出てくるようなものです。
僕が社長就任後に立ち上げた工場でも、まず鍋を絶対に使わないように指示しました。鍋は蒸気が出るのですごくエネルギーのロスになりますが、プラントなら蒸気は出ません。つまりエネルギーのロスがないわけです。
さらに鍋ではなく配管ですから上にも伸ばせるので、3次元で扱えます。つまり工場の製造機器の占める面積が小さくて済むわけです。その分、空調費用を大幅におさえられます。
ファンを増やすのではなく「サポーター」を増やしたかった

大久保:従業員の性善説に基づく、という考え方もすごくユニークですよね。
堀埜:確かに珍しいですね。サイゼリヤではもともと店舗にノルマがありませんでした。ノルマがないから、例えばサラダを盛るときも多めにする。お客様から「量が少ない」と言われたくないですから。一方で本部としては、一定量以上は盛れないような食器にするわけです。
店舗では賞味期限が切れた食材はすぐ廃棄しますが、これもノルマがないからできることです。廃棄が多い場合、改善すべきなのは店舗ではなく本部です。自動発注システムを作っている部門に、もっと精度を上げてくれと指示を出すわけです。
店舗でやることは絞りこみ、あとは本部が仕組みを作って維持する。その分店舗には、従業員とお客様を見ていただくわけです。
店長は、従業員を楽しく働かせることがミッションなんですよ。お客様の前に、まず従業員を見ます。従業員に不満があれば、お客様が喜ぶはずがありませんから。お客様は不特定多数ですし、いろいろな考えがあるのでコントロールできないけれど、従業員はターゲットがはっきりしているのでコントロールできるという考えです。
従業員をケアした上で、お客様を見てもらう。現場には「君たちは1人でも多くのサポーターを増やすことが使命」と伝えていました。サポーターは単なるファンと違って、何か変なことをすると叱ってくれる。サッカーでも、サポーターはそういう存在ですよね。
そういう意味では、お客様も従業員も経営者もサイゼリヤというブランドのサポーターです。これが僕の打ち出した「サポーター思想」という考え方です。
大久保:その思想によってスタッフも定着するし、熱心なお客様もつくという、目に見えない競争力になっている気がします。
堀埜:そうですね。社長になった時の話にもありましたが、「正しいことをする」ということをいつも考えていました。
2011年に東日本大震災が起こった時も、1週間以内に店を再開させました。あれだけ余震が続くと、精神的に参ってしまうことが多い。そこで店を再開させるという目標を作ったわけです。
また自社の出店基準に満たない地域にも店を出して、準備ができたら仮設住宅に住む方々を招待しました。とはいえそういう方々を利用したくなかったので、メディアには黙っていました。仮設住宅に住む方を招待した時に「マスコミはどこ?」ってよく聞かれましたね。
当時は被災エリアから撤退した外食チェーンもありましたが、サイゼリヤはそういうところにあえて出店しました。やはりあたたかくて新鮮なものを食べてほしいという想いからです。
この時のお客様は、その後サイゼリヤのサポーターになってくださいました。またこれをきっかけに、素晴らしいシステムエンジニアがサイゼリヤに入社してくれたんですよ。
他社が撤退する中、サイゼリヤが中国で成功できた理由

大久保:中国進出についても興味深いですよね。海外で成功したポイントについて伺えますか?
堀埜:成功した理由は簡単です。「うまくいくまでやめない」それだけなんです。実は上海で5店舗出した時点では赤字で、どうしようかなと思っていました。その時に正垣会長が価格をそれまでの半額以下にしたところ、毎日100人ぐらい並ぶようになりました。
上海でのモデルが出来上がってから、さらに店舗数は増えていきました。黒字になったのは11店舗くらいまで増やした時で、累積赤字が消えたのはおそらく20店舗ぐらいです。
他社の日本のレストランチェーンも中国へ進出したのですが、彼らの多くは撤退してしまいました。それは店舗数が少なかったからだと思います。中国では、少ない店舗で黒字になるのは無理なんです。店舗を出したら必ず模倣店が出てきてしまうので。
サイゼリヤは10~20店舗になって、ようやく利益が出るモデルにしました。そこまで行くと、真似できなくなります。実際サイゼリヤも、上海でうまく行き始めたら模倣店がたくさん出ました。でも途中からついていけなくなって、模倣店は必ず値上げしていきましたね。
実は彼らが市場を広げてくれたことになるんですよね。結果的には、サイゼリヤにとってプラスに働いたと思っています。
あとは「日本を売りにしない」ということを徹底しました。しっかり味とサービスで顧客を呼びたいと思ったからです。今ではSNSなどでサイゼリヤが日本企業だと広まってきましたが、当時中国ではそれを知らない人も多かったようです。
大久保:日本だけではなくて、世界にサポーターがいるわけですね。
堀埜:僕は世界中の美味しいものを食べてきました。そういう中で繁盛している店には共通点があることに気づいたんです。
「美味しいから食べて」というスタンスの店は人が行列している。 一方で儲けようとしているところは繁盛していない。これは飲食業にとって、世界共通のポイントだと思います。
大久保:広告やマーケティングも必要かもしれませんが、そういうものでは作れないものが大事ということですね。
仕事を変えた直後はネガティブになるけれど、そのうち「今が一番楽しい」と思えてくる

大久保:2022年にサイゼリヤの社長を退任された堀埜さんですが、現在どのような活動をされているのでしょうか。
堀埜:主に執筆と講演ですね。まだ退任して間もないので、自分がサイゼリヤでやってきたことの記憶がフレッシュなんです。そういう状態で執筆や講演をしていくうちに、整理されてまとまっていく感じがしています。
講演の多くは中国向けなんですよ。研修で日本に来た中国の方たち向けに講演することもありますし、僕が中国へ行って講演をすることもあります。
大久保:今回出版された著書もすごく読みやすく、異業種の私が読んでも非常に役立つものでした。
堀埜:いろいろな理論を応用してはいますが、僕の場合必ず自分の使いやすい方に変えています。特に飲食業はローテクですから、一般的な理論は先端産業の話なのでそのままでは使えません。実際に「あれ、実は使えないぞ」ということもありました。そういう意味では、実践して成功も失敗も経験しているのは特徴ですね。
大久保:なるほど。さらにスパッとさわやかに仕事を切り替えたというところも、堀埜さんの大きな特徴かもしれません。
堀埜:実を言うと、仕事を変えた直後はいつもすごく嫌なんです。でもしばらく経つと今やっていることが一番楽しいと思えてくる。必ずそういうポジティブな気持ちになっていくんです。
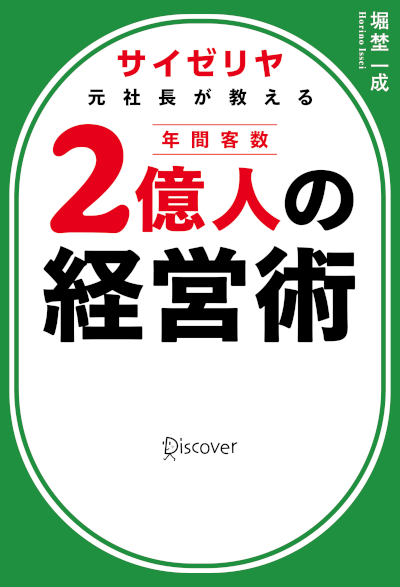 「サイゼリヤ元社長が教える 年間客数2億人の経営術」堀埜一成(ディスカヴァー・トゥエンティワン社)
「サイゼリヤ元社長が教える 年間客数2億人の経営術」堀埜一成(ディスカヴァー・トゥエンティワン社)
なぜサイゼリヤが圧倒的な安さと美味しさを実現できるのか。カリスマ創業者から指名され2代目社長として同社の急速拡大に貢献、コロナ禍にも揺るがない組織基盤をつくりあげた著者がサイゼリヤを経営していた13年間を総括。成功の舞台裏を余すことなく語り下ろす。
(取材協力:
株式会社サイゼリヤ 元代表取締役社長 堀埜一成)
(編集: 創業手帳編集部)