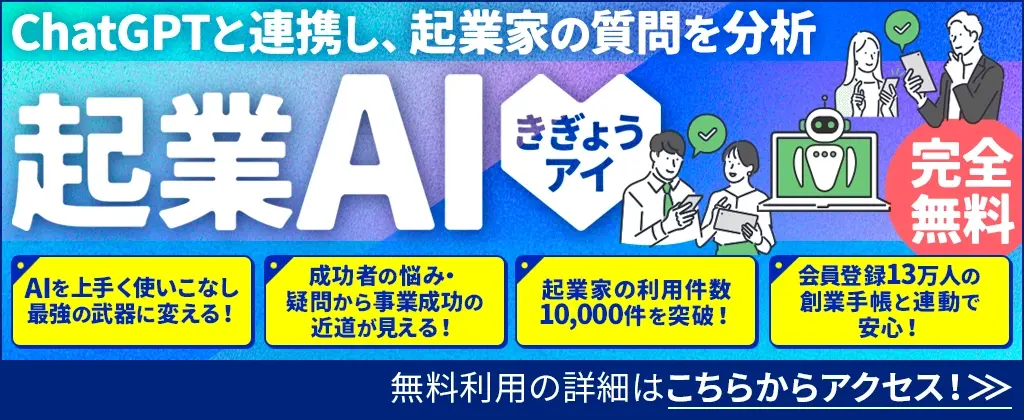高齢者向けビジネスとは?シニア市場の特徴や起業のコツを解説
高齢者向けビジネスの種類は多種多様

人口に占める高齢者の割合は増加傾向になり、高齢者向けビジネスには多くの企業が参入しています。
高齢者向けビジネスは多岐にわたっていて、健康や医療、介護に関わるものだけではありません。
趣味やライフスタイルに関わるものや子世代に関係するものまで豊富にあります。
高齢者向けのビジネスを成功させるには、高齢者の多種多様なニーズをくみ取って適切な商品やサービスを提供することが必要です。
どういった種類のビジネスがあるのか、高齢者向けのビジネスを成功するために押さえておきたいポイントを紹介します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
高齢者向けビジネスの市場規模

ビジネスをはじめる時に、必ず考えておきたいのが誰に向けたビジネスなのかという点です。
日本の総人口が減少する中で、2024年の総務省の調査によると65歳以上人口は3625万人と過去最多であり総人口に占める割合は 29.3%と過去最高を記録しています。
総人口に占める65歳以上人口の割合を比較すると日本は世界で最も高くなっており、今後も消費市場での存在感も増していくと考えられます。
人口比率が増す高齢者向けの商品やサービスは、成長が期待されるビジネスです。
みずほコーポレート銀行産業調査部の調査では高齢者向けビジネスの市場規模は、2007年は62.9兆円であったのに対し、2025年の予想市場規模は101.3兆円まで増加するとしています。
医療や介護、生活産業のどの分野も成長が予想され、中でも目覚ましいのが介護分野です。
医療や介護以外でも、食品や趣味、介護用品といった生活全般の充実に貢献する高齢者向けビジネスはこれから大きな成長が期待できます。
市場規模が拡大する中で高齢者層にリーチし続けることが、ビジネスの成功のカギを握っています。
高齢者向けビジネスの特徴

高齢者向けのビジネスは、ただ既存のビジネスを高齢者向けにしただけではありません。
ここでは、高齢者向けビジネスの特徴についてまとめています。
シニア層のニーズ
高齢者向けのビジネスとは、シニア層をターゲットにしたビジネスをいいます。つまり、成功するためにはシニア層のニーズやライフスタイルへの理解が欠かせません。
現代のシニアの特徴として挙げられるのが、質が高い生活へのニーズです。
健康の維持や安全の暮らし、快適さは基本的な要求としてその中で自分らしい生活を希望しています。
こういったニーズに対応する商品、サービスとして挙げられるのが、品質にこだわった健康食品や日常的な介護用品、心身を活性化させるレクリエーションアイテムといったものです。
具体的な業種としては、在宅介護サービスやフィットネスセンター、健康関連商品が挙げられます。
加えてシニア特有の課題を解決するアイテムとしては、見守りサービスや健康管理ツールが代表的です。
これらのツールはシニアの日常の不安を取り除いて本人とその家族に安心感をもたらします。
生活の質向上や精神的充実感の獲得によってシニアの生活満足度が高まることで、将来的に企業やシニア市場の成長も期待できます。
アクティブシニアの増加
高齢者の中でもアクティブシニアと呼ばれる世代は、年代に縛られることなく積極的に交流、活動に取組みます。
家族やコミュニティとのつながりを大切にしていて、日常でもより自分らしく快適な生活を求めているのです。
アクティブシニアは趣味や娯楽にお金を使うほか、新しい体験や学びへの関心も強い点が特徴です。
退職後の生活を充実させるために、旅行や趣味、学習をはじめる高齢者が多くビジネスチャンスが眠っています。
また、アクティブシニアはインターネットなどのITツールも活用していることもポイントです。
情報収集もインターネットが広く使われている点も企業は留意しなければいけません。
高齢者向けビジネスの種類

高齢者向けのビジネスは、一般に医療と介護、生活産業の3つに分けられていました。しかし、高齢者向けのビジネスはより多様になり種類も増えています。
どういった種類のビジネスがあるのか紹介します。
介護系
介護系に分類されるビジネスには、居住系介護やデイサービス、在宅介護などがあります。
自宅で安心して生活できるような訪問介護のほか、補助具などの介護用品、福祉用品などが代表的。介護系は常に一定の需要があるため、長期的に安定した利益が期待できます。
医療・医薬品系
高齢者が抱える問題としてまず挙げられるのが健康面です。健康面での問題に対応するための医療や医薬産業は拡大を続けています。
高齢者向けの医療機器や症状に応じた医薬品、健康管理を提供するヘルスケアサービスが提供されています。
住宅系
介護施設ときくと老人ホームがイメージされがちですが、実際にはより細かく分類されます。
居宅に介護福祉士やホームヘルパーが訪問する居宅サービスは、利用者が自立した生活を送れるようにする目的で生活援助を提供しています。
老人ホームでの日常生活の介助やリハビリは施設サービスに分類され、利用者は24時間体制で見守り介護を受けることが可能です。
趣味・娯楽系
高齢者向けの趣味・娯楽と聞くと、囲碁やゲートボールがイメージする人もいるかもしれません。しかし、実際には囲碁やゲートボールを含むもののより多様化が進んでいます。
園芸や俳句、料理のサービスも需要が高まっています。
趣味・娯楽に触れることで脳の活性化や交流が期待でき、楽しく日常生活送るために欠かせない分野です。
宅配・配食系
宅配や配食サービスは高齢者向けのサービスとして注目されています。
配食サービスにより、高齢者は日々の調理の負担を減らしながらも栄養バランスを保つことが可能です。
宅配、配食系のビジネスは料理による災リスクが減らせる上、宅配時に安否の確認ができるので、本人だけでなくその家族にも支持されています。
代行サービス
高齢者向けの代行サービスもニーズが高まっています。家事代行サービスは、高齢になるにつれて大変になる炊事や洗濯、掃除をサポートするビジネスです。
車の運転が難しい高齢者に対して送迎をする運転代行も需要があります。
これらの代行サービスは、状況に合わせたプランを提供するなど高齢者のニーズに柔軟に対応可能です。
日常生活のサポートして高齢者が安心して暮らせるように普及が期待されています。
フィットネス系
健康維持やケガからの回復のためにリハビリをする高齢者はたくさんいます。
生活の質を高めるためにフィットネスジムで鍛えたいと考えている高齢者も多く、スポーツやフィットネス市場が注目されるようになりました。
また、体の不調を訴える高齢者に向けたリハビリプログラムや整体サービスも需要が期待されます。
これらのサービスは、単発ではなく習慣として継続することが前提なので長期的な収入が見込めます。
高齢者向けビジネスをはじめるメリット

高齢者向けのビジネスは、様々な業種の企業が参入しています。高齢者向けのビジネスをはじめるメリットについて紹介します。
市場規模が拡大している
高齢者向けのビジネスは、現在まで安定して市場規模が拡大しています。現在の日本は、人口減少が予想されています。
多くの市場が縮小する中で、高齢者向けのビジネスはこれまで以上の伸びが期待できる領域です。
長期的に安定した収益が期待できる市場として多くの企業が参入しています。
幅広い業種で参入しやすい
高齢者向けのビジネスは、幅広い業種のビジネスモデルが存在します。
介護サービスやバリアフリーのほかにも、代行や配食、趣味の分野まで多種多様な分野が高齢者向けのビジネスとして参入可能です。
食品や家具、レジャーといった幅広い異業種から参入しやすい市場です。
収益性が見込める
高齢者向けのビジネスは、内容によって国からの介護報酬や補助金を受給できます。そのため、安定した収益が期待できる点がメリットです。
さらに現在の高齢者は貯蓄額が多いため、より収益性が見込めます。
お金に余裕がない世代をターゲットにするよりもより余裕がある世代を対象にすることで高い収益性が見込めるでしょう。
社会貢献につながる
高齢者向けのビジネスは、高齢者の生活の質向上や不安の解消を目的としています。
年を重ねることで、生活の困難さや孤独を感じる人は珍しくありません。高齢者向けのビジネスはサービスを提供することで社会貢献につながるビジネスです。
高齢者向けビジネスにおける注意点

高齢者向けのビジネスは、市場規模も大きく社会貢献が叶う事業です。しかし、メリットばかりを見ていると想定外の事態が発生することもあります。
ここでは高齢者向けのビジネスにおける注意点を紹介します。
介護保険制度の見直しで状況が変化しやすい
介護に関わるビジネスは、ほかの一般事業とは収益構造が異なります。介護保険制度適用のサービスを提供している事業所は、介護報酬が収入の大部分を占めています。
この収益構造は利用者数を確保すれば安定しているように思われがちです。しかし、介護保険制度は国の財政状況や高齢者の割合といった状況に合わせて見直しが行われます。
保険で補われているサービスの利用者負担が大きくなってしまえば利用者が使いにくくなってしまいます。
つまり、見直しによって、介護報酬の単価が引き下げれば収益に直接影響するのです。
近年は社会保障費の削減によって減算も見込まれている一方で、需要が高まっているケアについては介護報酬が引き上げとなっているケースもあります。
良い影響と悪い影響があるという点に注意しなければいけません。
既存のサービスが好まれやすい
革新的なアイデアで新しい市場を開拓したいと考える人もいるかもしれません。
しかし、高齢者向けの市場では新しいサービスは受け入れられにくく既存のサービスや環境を維持しようとします。
これは今まで積み重ねてきた信頼や関係性を重んじるためです。
同じサービスを10年間利用してきたのに急に新しいサービスに乗り換えると、また使い慣れていないものに慣れるところからスタートしなければいけません。
現状のサービスに多少の不満があっても、同じものを使い続けていたほうが負担が少ないと判断されてしまいます。
高齢者に認知されるまで時間がかかる
ビジネスとして成功するためには、多くの人に活用されなければいけません。しかし、高齢者から商品やサービスを認知されるまでに時間がかかってしまうことがあります。
若者世代への情報発信であれば、SNSを活用して数日で情報が拡散されます。これは若者世代は情報に対して敏感であることが理由です。
しかし、高齢者はSNSの普及率も比較的低く、情報を届けにくい世代です。
せっかく良い商品やサービスを発信したとしても、認知されなければ利用されることもありません。高齢者にどうやって認知してもらうかが高齢者ビジネスの課題といえます。
高齢者向けビジネスをはじめるコツ

高齢者向けビジネスは、既存のビジネスを単純に高齢者向けにするだけでは不十分です。ここでは、高齢者向けビジネスをはじめる時に知っておきたいコツを紹介します。
ターゲット層を明確にする
高齢者向けビジネスは、高齢者とひとくくりにするのではなく属性や年齢に合わせた商品開発が求められます。
健康志向が強い70代向けのアイテムや高齢者特有の生活課題に着目したサービスのようにできるだけターゲットを絞り込むようにしてください。
同じシニア層でも年齢や属性で興味関心やライフスタイルが異なるため、ターゲットを広範囲にしすぎれば需要に合わなくなるかもしれません。
ターゲットを明確にして需要やニーズに合わせた商品を提供してください。
高齢者に馴染みのある商材・サービスを選ぶ
高齢者は、生活に根差した、なじみがあるものを選択する傾向があります。
まったく異なる商品やサービスであっても高齢者が知っている商品やサービスを含めると抵抗感が少なくなります。
最新機能を搭載した製品でも見た目や操作には、親しみやすさを持たせて直感的に操作できるようにしてください。
また、懐かしい雰囲気のデザインや味わいを導入することで高齢者の共感につながります。
高齢者にすでに認知されているサービスや商品にはどのようなものがあるのか、事前に把握しておくことが大切です。
アナログとデジタルの両方を活用してマーケティングをする
高齢者は、アナログな機器を好むといわれているものの、近年ではインターネットやデジタルな手法も利用が広がっています。
高齢者にアピールする時には、アナログとデジタルの両方を活用してマーケティングしてください。
チラシやポスターといったアナログな手段と、メールマガジンやSNS、オンラインショッピングといったデジタルの手法を組み合わせることでターゲットにもれなくアプローチできます。
高齢者の中でSNSの利用者は限られているので、どういった宣伝方法がサービスに合っているのかを考える必要があります。
子どもや孫世代にもアプローチを広げる
高齢者向けビジネスだから単純に高齢者にアプローチすればいいわけではありません。その子どもや孫世代に届くアプローチやマーケティングが必要です。
多くの家庭では、購買の決定やサービスの利用に子どもや孫世代が関わっています。子どもや孫が気に入るサービスや高齢者にとっても魅力的です。
具体的には、高齢者の安全を確保するための商品の品質や安全性、アフターケアがあります。
子ども、孫世代に向けて商品の魅力や使用感をアピールするのであればSNSも有効な手段です。
子どもや孫の世代の信頼を勝ち取ることが高齢者向けビジネスの成功には欠かせません。
まとめ・高齢者の多様なニーズに応えられるビジネスで成功を目指そう
高齢者のニーズは千差万別です。健康増進や介護、住宅など高齢者向けサービスは多くの可能性を秘めています。
高齢者の消費動向や資産、健康状態やライフステージによってもニーズは異なるはずです。
高齢者にどういったニーズがあるのかを把握して適切な戦略を立てることが成功のカギを握っています。
高齢者の健康的で充実した生活を実現するために何ができるかを考えてみてください。
ビジネスのアイデアの壁打ちには創業手帳が無料で提供している「起業AI」をご活用ください。創業手帳が独自に起業家からの質問1万件を分析し、ChatGPTと連携させたサービスです。起業家のよくある質問を分析してスムーズに壁打ちしてくれます。
またビジネスアイデアが固まったら、「創業カレンダー」を使って起業までの準備をしっかり固めるとよいでしょう。全て無料でお使いいただけます。
(編集:創業手帳編集部)