個人事業主が定額減税に対応する方法は?やるべきことをわかりやすく解説
個人事業主が定額減税を受けるパターンは2つ
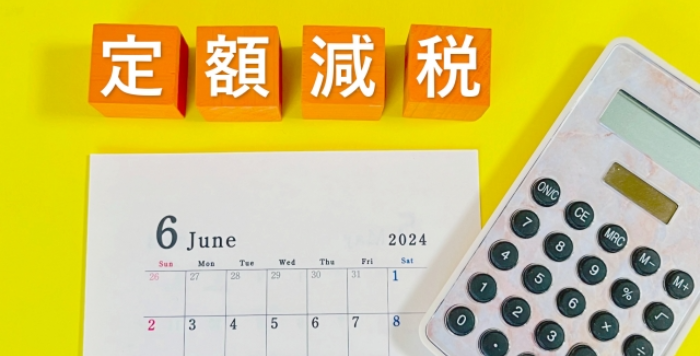
●個人事業主が知っておきたい定額減税の概要
●個人事業主が減税を受けるための2つのパターン(確定申告と予定納税)
●扶養家族や従業員がいる場合の対応方法
●減税金額や控除の手順
●控除しきれない金額はどうなるのか
2024年6月より、政府による定額減税が行われます。定額減税は、昨今の物価高騰により国民の生活が苦しくなっていることを背景に、国民の負担軽減を目的に行われる措置です。
給与所得者の場合は特段自分で対応しなくても定額減税を受けられますが、個人事業主の方は対応が異なります。また、実際に定額減税の恩恵を受けられるタイミングも異なる点は押さえておきましょう。
こちらの記事では、個人事業主が定額減税を受けるにあたって対応すべきことを解説します。具体的に何をすべきか、正確に理解できていない方に役立つ内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください。
創業手帳では、様々ある税金についていつ支払えばいいのかを予め把握しておけるための「税金カレンダー」をご用意致しました。個人事業主向けと法人用と分かれていて、法人用については自身の会社の決算月の設定によって使い分けられるようにそれぞれカレンダーをご用意。税金の支払い忘れによる余計な支出を増やさないためにも、是非こちらをご活用ください。無料でご利用いただけます。
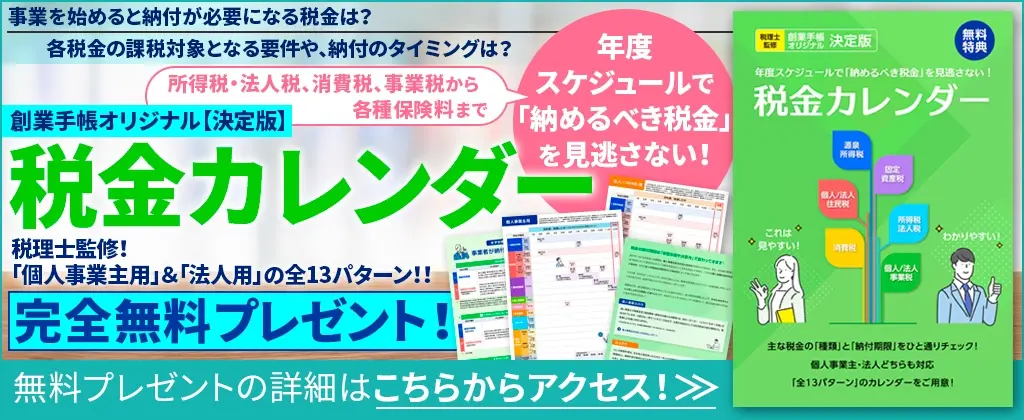
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
定額減税とは

定額減税とは、令和6年分の所得税を控除する措置です。昨今の物価上昇の影響で国民生活の負担が重くなっている事態を受け、定額で減税を行う仕組みとなっています。
対象者
定額減税の対象となる方は「令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
高額所得者を除き、多くの方が対象になることがわかります。働き方は関係なく、給与所得者はもちろん、年金受給者や事業所得者なども対象です。
減税される金額
減税される金額は納税者本人および扶養家族一人につき、所得税が3万円・住民税が1万円となっています。
例えば、扶養家族が3人いる場合、受けられる定額減税は以下のとおりです。
| 所得税 | 3万円×4人=12万円 |
| 住民税 | 1万円×4人=4万円 |
| 合計 | 16万円 |
物価の上昇に伴って家計が苦しいと感じている世帯にとって、ありがたい施策といえるでしょう。
扶養家族の範囲
定額減税は、納税者本人だけでなく扶養家族(同一生計配偶者や扶養親族)も含まれます。定額減税の対象となる扶養家族は「合計所得が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)の居住者」です。
つまり、専業主婦や学生など所得税と住民税を納税していない扶養家族も、定額減税の対象となります。
ただし、専従者給与を支払っている家族は扶養家族に該当せず、支払う給与から定額減税を処理を行う必要があります。
税法上の扶養控除と定額減税の扶養家族は対象範囲が異なる点に注意
税法上の扶養控除と、今回行われる定額減税の扶養家族は対象範囲が異なります。混同しがちなポイントなので、間違えないように注意しましょう。
例えば、16歳未満の子は所得税における扶養控除を受けられません。しかし、定額減税は16歳未満の子も対象となります。
基本的に、合計所得が48万円以下(年収103万円以下)の扶養家族に関しては定額控除の対象になる、と理解しておきましょう。
なお、令和6年度中に誕生した子どもは所得税の定額減税の対象になりますが、住民税の定額減税は対象外です。これは、所得税と住民税の計算方法の違いによるものです。
所得税の減税については、令和6年1月1日から令和6年12月31日の期間における所得を基に計算した税額から控除されます。一方で、住民税の減税については令和5年1月1日~令和5年12月31日の期間における所得を基に計算した税額から控除されます。
つまり、税額を計算する対象期間が、所得税と住民税では1年間のズレがあるのです。扶養家族の人数について、所得税については令和6年12月31日時点、住民税については令和5年12月31日時点で判断します。そのため、令和6年中に子どもが生まれた場合は所得税のみ定額減税を受けられます。
個人事業主が定額減税を受ける方法

個人事業主が定額減税を受ける方法は、確定申告で控除を受ける方法と予定納税額で控除を受ける2パターンにわかれます。
以下で、それぞれどのような流れで進むか解説します。
所得税について
所得税の減税は、年間の所得税が15万円以上あるかどうかによりパターンが分かれます。
パターン1:令和6年分の確定申告で控除を受ける
個人事業主の方は、原則として令和6年分の確定申告を行った際に、所得税額から定額控除の額が控除されます。
つまり、実際に定額控除の恩恵を受けられるのは令和7年2月以降となります。給与所得者は令和6年6月以降に定額控除の恩恵を受けられますが、個人事業主はタイミングが異なる点に注意しましょう。
個人事業主が定額減税を受ける際の確定申告のやり方や、注意点などは以下の記事を参考にしてください。
より確定申告について知りたい方へ『確定申告ガイド』をご用意しています。基本的な流れだけでなく、定額減税や経費処理の方法についても触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

パターン2:令和6年の第1期の予定納税額で控除を受ける
予定納税の対象となっている個人事業主の場合は、確定申告を待たずに定額控除が受けられます。令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)より、本人分に係る定額控除分が自動的に控除される仕組みです。
第1期分予定納税額(7月)で控除しきれなかった場合は、第2期分予定納税額(11月)から控除されます。第2期分予定納税額で控除しきれなかった分がある場合は、確定申告で還付を受けられます。
基本的に、予定納税から控除される場合は特段個人事業主が対応することなく、定額減税の恩恵を受けられます。すでに控除されたあとの金額で税務署から通知が届くため、内容を確認してみてください。
住民税について
住民税に関しては、令和6年度第1期分の納付額から直接控除されます。つまり、特段対応することなく定額控除の恩恵を受けられます。
住民税決定通知書に減税額が記載されているため、通知書が届いたら確認してみてください。なお、第1期分で控除しきれない金額がある場合は第2期以降で控除されます。
扶養家族がいる場合

定額減税は、納税者本人だけでなく扶養家族も対象です。扶養家族分の定額減税を受ける場合も、確定申告をする場合と予定納税から控除される場合で異なります。
以下で、それぞれどのような対応が求められるか解説します。
パターン1:確定申告で控除を受ける
確定申告で定額控除を受ける場合は、確定申告書に扶養家族を記載します。確定申告を通じて定額減税が反映され、最終的な税額に落とし込まれる仕組みです。
定額減税の対象となる扶養家族は、令和6年12月31日現在で納税者本人と生計を一にしており、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の配偶者や親族です。
もし合計所得金額が48万円を超えている親族がいる場合、本人が勤務先を通じて定額減税を受けることになります。
パターン2:予定納税で控除を受ける
予定納税から定額控除を受ける場合、扶養家族に関する定額控除を受けるためには予定納税額の減額申請が必要です。「予定納税額の減額申請書」を令和6年7月31日までに提出すれば、予定納税額から扶養家族分が控除されます。
第1期分予定納税額から控除しきれなかった金額がある場合は、控除しきれない金額に関しては第2期分予定納税額(11月)から控除されます。
詳細な手続き方法に関しては、今後国税庁のホームページで更新される予定となっています。
予定納税の減額申請手順
予定納税の減額申請を行う際の手順は、以下のとおりです。
- 国税庁のホームページから「予定納税額の減額申請書」をダウンロードする
- 減額申請書に必要事項を記載する
- 減額申請書と添付書類を税務署へ提出する
予定納税額の減額申請書には、自分の情報や予定納税額を記載します。また、「申告納税見積額等の計算書」で計算した減額後の金額を記載します。
予定納税額の減額申請書には、年間の所得や控除額などを記載しなければなりません。当該年度の数値を見積もったうえで計算しなければならず、作成にあたって手間がかかる点は否めません。
予定納税の段階で扶養家族分の控除を受けない場合、また予定納税で減額申請を忘れた場合でも、確定申告で定額控除を受けられます。そのため、扶養家族分の定額減税を急がない場合は、「予定納税額の減額申請書」を出さなくても問題ありません。
控除しきれない金額について
所得税でも住民税でも定額控除で控除しきれない金額がある場合は、別途支給(調整給付)されます。
例えば、扶養家族が3人いる場合、所得税で受けられる定額控除は12万円です。控除できる所得税額が10万円の場合、税額控除が2万円分余ってしまいます。
この場合、2万円は後日に別途支給される仕組みとなっています。調整給付は、令和6年夏以降に行われる「当初給付」と、令和7年以降の「不足額給付」の2回に分けて行われる予定です。
調整給付の時期や申請方法に関しては、今後国税庁や自治体のホームページで公表される予定となっています。
雇用している従業員、または家族従業員がいる場合
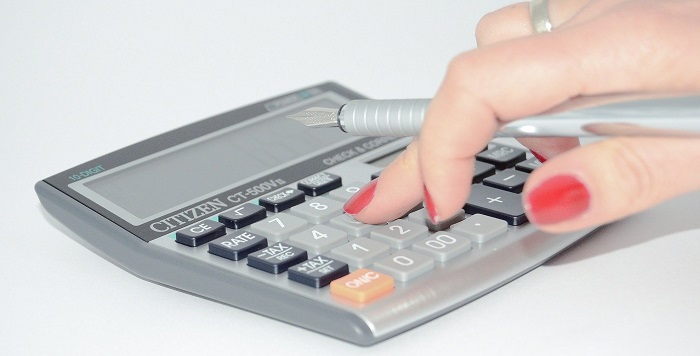
雇用している従業員がいる、または家族従業員がいる個人事業主の方は、従業員分の定額減税を行う必要があります。令和6年6月以降より、定額減税を考慮したうえで給料を支給する必要がある点を押さえておきましょう。
例えば、以下のようなケースで考えてみましょう(従業員に扶養家族がいないケース)。
- 令和6年6月の源泉所得税:8,000円
- 令和6年7月の源泉所得税:8,000円
- 令和6年8月の源泉所得税:8,000円
- 令和6年9月の源泉所得税:8,000円
所得税の定額減税は3万円でした。そのため、従業員に対して給料を支払う際には、源泉所得税について以下のような処理を行う必要があります。
- 令和6年6月の源泉所得税:8,000円→0円
- 令和6年7月の源泉所得税:8,000円→0円
- 令和6年8月の源泉所得税:8,000円→0円
- 令和6年9月の源泉所得税:8,000円→2,000円
上記のように、3万円を控除するまで毎月の源泉所得税から差し引く処理を行います。年末調整でまとめて3万円を一括調整することはできません。そのため、令和6年6月以降の所得税から都度控除する必要があります。
なお、住民税に関しては令和6年6月分は一律0円とする仕組みになっています。その後の詳細な計算は市区町村が行うため、事業主が計算をする必要はありません。つまり、令和6年7月以降の住民税の天引きに関しては通常通り行えばよい、ということです。
家族従業員に対して専従者給与を支払っている場合も、基本的には令和6年6月以降における毎月の所得税から控除します。
しかし、そもそもの専従者給与が低額の場合や毎月の源泉所得税が0円というケースが有り得るでしょう。年末までに3万円を控除しきれなかった場合、年末調整を通じて還付する流れとなります。
雇用している従業員に対しても家族従業員に対しても、給与明細を渡す際には「定額減税額:〇〇円」のように記載しましょう。また、税務署や市区町村に源泉徴収票を提出する際にも、摘要欄に「定額減税額:〇〇円」と記載する必要があります。
まとめ:個人事業主は確定申告か予定納税で定額減税を受けよう
個人事業主が定額減税を受ける流れは、給与所得者と異なります。確定申告をしたうえで減税を受けるか、予定納税から控除されるかの2パターンにわかれます。
定額減税は扶養家族も対象となるため、忘れずに申請しましょう。最新情報は、国税庁や自治体のホームページなどで確認してみてください。
創業手帳では、事業主が知っておくべき税制度や節税方法に関する情報を提供しています。資金繰りを改善するうえで税制度の理解は欠かせないため、「税金カレンダー」もあわせてご活用ください。
確定申告に悩んでいる方、基本だけでなく定額減税・年末調整も解説した『確定申告ガイド』や『副業確定申告ガイド』もおすすめです。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。



































