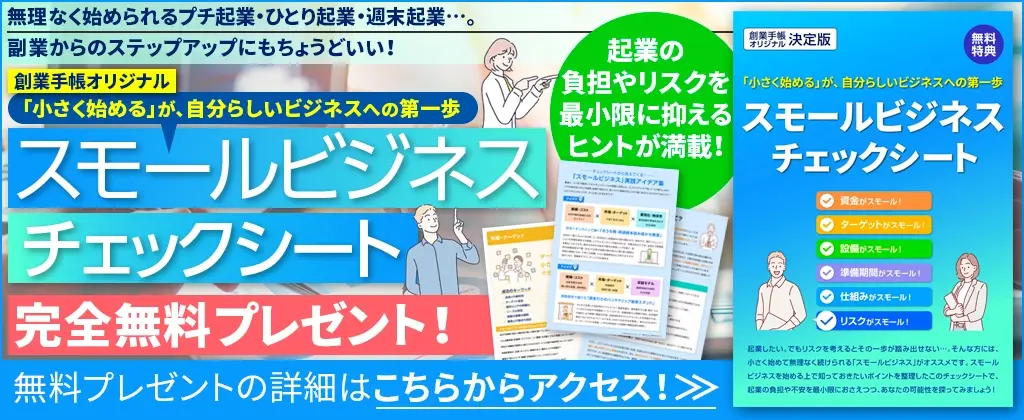スモールビジネスのリスクとは?失敗例から学ぶ5つの注意点と回避策
スモールビジネスの「低リスク」には落とし穴がある

スモールビジネスは、少人数や小資本で始めるビジネスです。
一般的には、従業員数5人以下の事業を指していますが、個人事業主でも該当するため「低リスクでチャレンジできる」「小さく始められる」という印象を抱く人もいるでしょう。
しかし、スモールビジネスだからと油断していると収益化の遅れや資金管理の甘さにより、予想以上の損失を被るリスクがあることを忘れてはいけません。
スタートしてから予想外の事態に困惑しないように、事前にリスクを理解し、適切な備えをすれば安心してスモールビジネスが始められます。
この記事では、スモールビジネスで見落としがちなリスクに加えて、失敗例から学ぶ5つの注意点と回避策について解説します。
「小さく始めれば大丈夫」と思っていても、思わぬリスクが潜んでいるのがスモールビジネスです。
創業手帳の『スモールビジネス・チェックシート』は、リスクと向き合いながら持続的に収益を作るためのヒントをまとめています。事前の準備に役立つ無料特典です。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
スモールビジネスに潜む主なリスク5つ

様々なメリットのあるスモールビジネスですが、実はこのビジネスならではのリスクも存在しています。ここでは、スモールビジネスに潜んでいるリスクについて解説します。
1. 収益化までの期間が読めない
スモールビジネスは、少人数や個人事業主としてスタートするビジネスです。
起業したばかりの時は、知名度ゼロからのスタートとなるため、安定した集客までの時間がかかりやすい傾向があります。
また、商品やサービスを提供しているからといって、最初から好調なスタートができるわけではないことを理解しておいてください。
まだ、他社との信頼関係も構築されていない状態なので市場に浸透していくまでに数カ月から数年という時間がかかり、どれくらいの期間で収益化が安定していくかもわかりません。
これらの理由から収益化できるまでの期間が読めないので、事前に売上が上がらない期間の生活費や事業経費を十分に見込んでおかなければ、資金が枯渇するリスクが高まります。
2. 事業と生活費の区別がつかなくなる
スモールビジネスは個人や少人数で行っていく事業であり、収益化までの時間もはっきり判断できません。そのため、売上が不安定な期間が長く続く可能性もあります。
売上が不安定な時期になると、事業が安定するように資金を補填しなければいけないと考えます。
そこで生活費で赤字を補填したり、事業に回したりしてしまうと事業と生活費の区別がわからず金銭感覚が曖昧になる可能性が高いです。
特に個人事業主は、個人用と事業用の口座を分けずに運用するケースが多くなり、その結果損益の把握が困難になるケースもあります。
事業と生活費の区別をきちんとつけていないと、税務上の問題も起こりやすくなるだけではありません。
確定申告の際に経費の区分が混乱しやすくなり、その結果大きなミスにつながる可能性が高いです。
3.十分な準備資金がないまま始めてしまう過小資本でのスタート
スモールビジネスは、規模が小さいため比較的始めやすいビジネスです。
ビジネス資金がいらない、少しで良いという意味ではなく、ある程度の準備資金や事業資金は必要となります。
しかし「とにかくお金をかけずに」という発想でビジネスを開始してしまうと、必要な投資を省いてしまい、結果的に品質や集客力が低下して成長できません。
事業を開始して多くの集客を得たいなら最低限の広告費や設備投資が必要ですが、これらの資金をケチってしまえば競合他社に品質面で劣りやすく、顧客獲得が困難になります。
スモールビジネスでは、まったく資金がいらないわけではありません。
きちんとした資金計画を立ててからスタートしなければ、事業拡大のタイミングで資金不足に陥るリスクが高まります。
4. 孤立と判断ミス
スモールビジネスには少人数や個人でも立ち上げられるので、起業に関してのハードルが低くなります。
その一方で気軽に相談できる環境が整っていない傾向になりやすく、特に個人で立ち上げた場合は第三者の客観的な視点からの情報が入りにくい環境になりやすいです。
自分で考えても答えが出ない場合、誰かに相談したくてもできる環境がなければ頼れるのは自分だけになってしまいます。
その結果、独りよがりな判断をしやすく、市場ニーズとズレた商品開発や価格設定をしてしまうなどの判断ミスも起こりやすいです。
また、相談相手がいないことで精神的に大きな負担もかかりやすくなり、いざという時に冷静な経営判断ができなくなる可能性もあります。
5. 拡大時の壁に直面する
スモールビジネスをスタートして将来的に拡大することを目指した場合、これまでと同じ品質で同じ生産性を維持するという点について考えなければなりません。
しかし、個人のスキルや時間に依存しているビジネスモデルでは、一定の収益を超えてしまうとこれ以上の成長が難しくなります。
拡大時に戦略やノウハウの共有、マニュアル作成など何かしらの拡大戦略を決めていないと、「稼げるが忙しい」という状態から抜け出せずに収入アップも期待できません。
さらなる人材の確保や外注体制などについても、しっかり取組みや体制づくりを行わないと、せっかくの事業拡大チャンスを逃してしまう可能性があります。
スモールビジネスの失敗しやすいパターンと事例

スモールビジネスでは、スピード感を持って市場の動向に反応できる特徴がありますが、その一方で戦略を間違えたことで失敗しやすくなるケースもあります。
ここでは、スモールビジネスの失敗しやすいパターンと事例を紹介します。
ケース1:在庫を抱えすぎて資金が回らない
スモールビジネスを副業の延長と考えてしまう人も少なくありません。
しかし、スモールビジネスは個人や少人数で運営する事業であり、副業のように本業を持たずに自己実現できるのが特徴です。
これらを同じような認識で始めてしまった場合、売れると思い込んで大量の在庫を仕入れた結果、資金難に陥るケースもあります。
また、インターネットでの物販などでは季節商品やトレンドアイテムなどを大量に入荷しても売りやすい傾向にあります。
しかし、タイミングが少しずれてしまうだけで売れ残りや損失を出すケースも多いです。
正確な売れ行きを予測することなく、一時的な思い付きや流行で在庫投資を増やしてしまうと資金難に陥るだけでなく、キャッシュフローが悪化して事業継続が困難になるので注意してください。
ケース2:SNSに頼りすぎて売上が不安定
スモールビジネスで失敗しやすいのは、SNS頼りになりすぎることです。
SNSをチェックすれば流行などがわかりやすく、お金をかけにくいスモールビジネスでは費用のかからないSNSに頼りたくなるものです。
確かに、SNSでインフルエンサーになって成功している人も存在しているので頼ること自体は悪くありません。
しかし、SNSのアルゴリズムを変更したことで突然リーチが減少し、それまでの集客手法が通用しなくなるケースも存在します。
また、インフルエンサーが注目して紹介してくれたことをきっかけに売上が上がると好調だと感じやすいのですが、このような売上の上昇は一時的なものがほとんどです。
ここで、継続的な集客がなければ結果的に急激な売上減少に陥ってしまいます。
ほかにも、流行が生まれやすいSNSの運用やチェックなどに時間をかけすぎてしまうと、商品開発や顧客対応が疎かになることもあります。
その結果品質低下で顧客離れが起きる可能性もあるので注意してください。
ケース3:価格設定ミスで利益が出ない
スモールビジネスで、多くの人に利用してもらって顧客にしたいと考えた時、多くの集客が得られるようにと価格を競合他社より安く設定しすぎることがあります。
「安さで勝負」という戦略もありますが、安易に参入すると価格競争に巻き込まれて利益率が極端に低くなりやすいだけでなく、原価や人件費を考慮すると赤字になる可能性が高いです。
価格の安さばかりに注目してしまうと、時給換算した時に最低賃金を下回る収益しか得られず、労働に見合わない事業を続けることになります。
このような状態が続くと、利益が出ないのに労働をしなければならず、結果的に事業が継続できなくなってしまいます。
スモールビジネスのリスクを抑えるために準備すべきこと

少しでもスモールビジネスのリスクを抑えるためには、事前にどのような準備が必要でしょうか。ここでは、リスクを最小限にするために準備したいことを紹介します。
1. 生活費を含めた”最低限必要な資金”を確保する
スモールビジネスを開始する前に、最低限必要な資金を確保しておくことが大切です。
目安は、事業を開始した時から収益化までの期間を想定して算出します。数カ月分の生活費、運転資金を事前に確保しておくと安心です。
また、安定した売上が出るまでの期間の固定費として、家賃や光熱費、通信費などを明確に計算して資金計画を立ててください。
固定費についても用意しておかなければ、生活することができません。
緊急事態が起こっても対応できるようにあらかじめ予備の資金も含めておき、想定よりも多めの資金を準備するのがおすすめです。
2. 商品やサービスは”小さくテスト”してから本格化
スモールビジネスをスタートする際には、いきなり大きな投資をするのではなく最小限のコストから始めて、市場の反応を確認してから本格的に展開していきます。
テストする目的は、ビジネスの成功率を高めるために必要なことです。ここで、需要を正しく確認せずに販売してしまうと大きな失敗をする可能性があります。
少量の在庫から始めて、限定的なサービスを提供することで顧客のニーズや需要が確認できます。
この結果をもとに商品の改良、サービスの見直し、価格の調整をしていけば成功率が高まるとともに本格参入できるタイミングもわかりやすいです。
3.収支の見える化と定期的な振り返りで、PDCAを回す
リスクを抑えるためには、収支の見える化として「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Act(改善)」を行います。
現状の把握と課題を知り、PDCAを回すことで具体的な計画にできるだけでなく、内容を明確に把握できます。
そのために取り組みたいのは、売上、経費、利益を日次または週次で記録して数字で事業状況を把握できる仕組みづくりです。
このような仕組みづくりで、数字で事業の振り返りがしやすく計画と実績の差異を分析して改善点が見つけやすくなります。
これらのサイクルを習慣にすれば、数字で判断して決定できるので事業の安定化が期待できます。
4. 信頼できる第三者の意見を取り入れる
スモールビジネスには、個人事業主も含まれます。そのため、経営における判断はすべて自分で行うことになります。
しかし起業したばかりで不安な時は、誰かに相談したいものの誰に相談すべきか、信頼できる意見は何かと考えることも少なくありません。
このような時は、同業者や経営者と定期的な情報交換をすることで、客観的な視点からアドバイスを受ける機会がつくれます。
ほかにも、商工会議所や起業支援機関の相談サービスがあるので、上手に利用して専門家からの助言を得ることも可能です。
家族や友人の意見やアドバイスに頼らず、すでにビジネス経験のある人からの意見を真摯(しんし)に受け入れる姿勢でいると、ためになることを教えてもらえます。
5. 無理のないスモールスタートで段階的に広げる
スモールビジネスは、できるだけ無理のないスモールスタートを意識してください。
最初から起業するよりも、副業からスタートして安定した流れや収益が得られることを確認してから本業にして独立すると、段階的に広げていくことができます。
1人でできる範囲や規模から始めていき、安定した収益が得られるようになったら設備や人員を徐々に拡大していきます。
無理せず、身の丈に合った事業規模を維持できるように意識し、急激な拡大などで管理不能な状態や資金不足にならないように心がけてください。
安心してスモールビジネスをスタートするためのサポート策

初めてでも安心してスモールビジネスをスタートするには、どのようなサポートがあるか知っておくことも大切です。
ここでは、スモールビジネスをサポートしてくれる内容について解説します。
自治体や公的機関の相談窓口を活用する
スモールビジネスについて相談したい場合は、最も身近で創業後も関係がある可能性の高い地域の商工会議所で受け付けています。
地域の小規模事業者の強い味方であり、経営や補助金、支援制度などに加えて一般的な相談も可能です。
また、経営の相談に関しては日本政策金融公庫でもできます。創業融資に強みがあり、一般の経営相談窓口も行っているので創業準備や間もない時期を中心に対応してくれます。
ほかにも中小企業基盤整備機構では、創業期、成長期、成熟期に分類して適したサポート体制を整えているので、どの時期でも相談できるのが特徴です。
これらの相談窓口を積極的に活用してみてください。
無料で学べる起業講座や支援プログラムを活用する
スモールビジネスのサポートとして、無料で学べる起業講座や支援プログラムを活用するのもおすすめです。
商工会議所や商工会が開催している起業セミナーもあり、ここでは事業計画書の作成方法や資金調達の基礎知識が学べます。
中小企業庁の「創業スクール」でスモールビジネスに関連する内容も公開されていますが、ほかにもオンライン学習プラットフォームなどの活用で、起業に関する講座が学習できます。
これらの活用によって、自分で学びたい内容が学べるでしょう。
仲間づくりと情報収集にはコミュニティを活用
スモールビジネスでは、同じ環境の仲間をつくると有益な情報を知るきっかけも生まれます。
同じ志を持つ起業家が集まるコミュニティなどの参加で、情報交換や相互支援ができます。
お互いの関係性を良好にするきっかけも生まれ、ビジネスについての相談もしやすくなるでしょう。
業界別の勉強会や交流会にも積極的に参加し、先輩起業家からの実体験に基づくアドバイスを得たり、SNSやオンラインコミュニティも活用すれば、地域を超えた起業家ネットワークの構築ができたりします。
まとめ:リスクはある。でも、準備と知識で回避できる
スモールビジネスに限らず、どのようなビジネスであってもリスクはついてきます。
しかし、「事前に知っておくこと」と「備えること」を意識すれば、回避や対処ができる可能性が高くなるでしょう。
特にスモールビジネスの場合、小さい規模からのスタートなので万が一失敗してもやり直ししやすいです。
できるだけリスクを被らないように、事前に正しくリスクについて理解しておき、安心してビジネスの一歩を踏み出せるようにしてください。
リスクを理解したうえで挑戦すれば、スモールビジネスは大きな可能性を秘めています。
創業手帳の『スモールビジネス・チェックシート』には、リスクを最小限に抑えつつ収益を生み出すための工夫が詰まっています。安心して一歩を踏み出すためにご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)