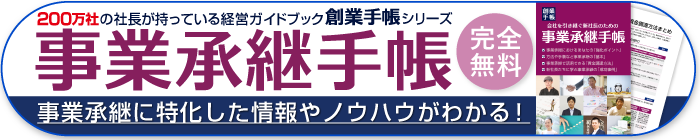ゼロから作らない起業|個人が会社を買って始める「M&A起業」のススメ
M&A起業は個人でも実現可能な起業手段

M&A起業は「一部の富裕層だけ」に限った話ではなく、一般的な会社員でも実現可能な起業手段です。
多くの人がM&A起業なんて個人には無理と思いがちですが、実際には数百万円台から始められる案件が豊富にあります。
個人事業主やサラリーマンでも会社を買って、起業が可能です。
本記事では、会社を買ってM&A起業する具体的な方法とそこから成功するために押さえておきたいポイントを実践的に解説します。
会社を買って起業する方法は魅力的ですが、目的や状況によって適したM&A手法は異なります。
『中小企業のためのM&Aガイド』 では、目的別のM&Aパターン・業種ごとの傾向・成功のコツまで一冊で整理。リスクや税金の注意点、相談先の比較もわかりやすくまとめています。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
なぜ今、会社を買って起業する人が増えているのか

会社を買って起業する人が増えている背景には、昨今の後継者不足問題があります。
中小企業庁の『中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題』によると後継者不足により廃業危機にある中小企業が全国で約127万社存在し、日本企業全体の3分の1が後継者未定の状態です。
さらに、コロナ禍で事業承継のニーズは高まり、個人向けの小規模M&A市場の拡大が予想されています。
もちろん事業承継型のM&Aには、買う側にも多くのメリットがあります。
会社を買う側は、事業承継によりゼロから事業を立ち上げるリスクを避けながら、既存の顧客基盤と収益構造を活用できるでしょう。
個人でも会社は買える?M&A起業の現実

そもそも会社を買収する、M&Aをするといった言葉はニュースで聞くことはあっても、法人同士の話だけだと思われがちです。
しかし、法人だけでなく個人でも会社買収は可能であり、実際に年間数千件の個人M&Aが成立しています。
地方の小規模事業であれば、300万円から1,000万円程度あれば買収できる案件もあるので、決して個人でまったく手が届かないものではありません。
すぐに資金を用意できない場合でも、日本政策金融公庫の創業融資や事業承継・引継ぎ補助金といった各種制度があるため、資金調達のハードルが下がっています。
終身雇用が当たり前だった時代が終わり、個人が将来を考えて起業を視野に入れるようになりました。
M&A起業もキャリアパスの選択肢のひとつとして検討されるようになったのです。
どんな会社を買えばいい?選び方のポイント

M&A起業が広がっているといっても、実際にどのような会社を買えばいいのか見当がつきにくいかもしれません。会社選びは買収後の成功を左右する最重要ポイントです。
ここでは、会社選びのポイントとして以下の3つを紹介していきます。これらの観点から慎重に検討してみてください。
自分の経験やスキルが活かせる事業か
M&A起業は、どのような会社を買ってもいいわけではありません。買う会社に迷った場合には、自分の経験・スキルを活用できる会社を選んでください。
これまでの職歴や専門知識を活用できる業界を選ぶことで、買収後の事業運営が成功しやすくなります。
また、すでに人脈やスキルがあるので、新しい切り口から既存の事業を広げることもできます。
もちろん、まったく未経験の分野でも、興味と学習意欲があれば挑戦可能です。
しかし、どうしても実際に事業に着手しなければわからないことも多いので、最初の1年は苦労することは覚悟しておいてください。
会社を選ぶ時には、営業、管理、技術など自分の得意分野を活かせるポジションが事業内に存在するかも確認します。
営業や技術など自分の得意分野があれば、未経験であってもスキルを活用できるでしょう。
黒字か赤字かではなく「再現性」に注目
買おうとしている会社は利益が出ているのか、赤字になっていないかは必ずチェックしてください。
赤字だから購入を避けるべきとは言い切れません。赤字か黒字かではなく、どうしてその状態になったのか、その再現性に注目してください。
赤字企業であっても改善の余地があり、立て直しが可能な構造的要因を持つ事業であれば成長の可能性があります。
過去3年の売上推移と利益率を分析し、業績悪化の原因が一時的か構造的なものであるかを判断します。
安定した収益、持続可能な経営基盤を築くためにデータビジネスモデルや戦略の有効性を評価しなければいけません。
また、競合他社の状況や市場の成長性も調べるべき項目です。事業の将来性を客観的に評価するとともに、必要に応じて専門家にも相談してみてください。
従業員や顧客との関係性もチェック
会社を買ってから従業員や顧客との関係が維持できないと、人手不足や売上低下につながってしまうかもしれません。
M&A起業する時には、その会社の従業員の年齢構成や勤続年数、離職率を確認し、組織の安定性を必ず把握してください。
さらに、主要顧客との取引年数や契約条件を調査し、売上の継続性、持続可能性を判断する必要があります。
前経営者と従業員・顧客の関係が良好で、引き継ぎ後も協力が得られる環境かどうかを見極めるようにしてください。
会社を買ってからも引き継いだ関係性を友好に保つためには、買収した時にこれからの経営方針や従業員の待遇について説明することも大切です。
個人が会社を買うまでのステップ

個人で会社を買うのは、突拍子もないことではありません。以下の流れで進めていけば、個人でも安全にM&A起業を実現可能です。
どのような内容で進めていけばいいのか注意点とともにまとめたので参考にしてみてください。
希望条件の整理(予算、地域、業種など)
会社を買うためには、まず予算や地域、業種といった希望条件を整理します。買収予算は自己資金と借入可能額を合わせて現実的な上限を設定します。
地域によってはM&A起業案件自体がそう多くはないかもしれません。居住地から通勤可能な範囲、または移住を前提として地域を決めておきます。
業種はこれまでの経験や興味のある分野から選んでください。業種を広げすぎると探しにくいので、運営可能な業種を3つ程度に絞り込むようにします。
希望条件を満たす会社が見つからないケースもあるかもしれません。そのため、条件に優先順位を付けて本当に譲れない条件だけ満たす企業を探すことも大切です。
M&A仲介サイトなどで買収先を探す
条件を整理したら、インターネットでM&Aマッチングサイトを使って会社を探してみましょう。
売りに出されている会社の一覧を見て、希望に合う会社がない時にも定期的に案件をチェックするようにしてみてください。
また、事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的機関を利用する方法もあります。事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置した公的相談窓口で各都道府県に窓口があります。
起業家と後継者不足の会社を引き合わせる後継者人材バンクがあるので、気になる人は登録を検討してみてください。
売買交渉を申し入れる
自分の希望条件に合う会社が見つかった時には、売買交渉の申し入れをします。売買交渉の申し入れとは、「会社を買いたい」という意思を売り手に伝えることです。
マッチングサイトで見つけた場合には、マッチングサイトからメッセージを送付できます。
仲介会社を利用している場合には、仲介会社に意思を伝えてコンタクトを取りましょう。
売買交渉で話し合うのは買収価格だけでなく、引き継ぎ期間などの条件も含みます。今後の契約にも関わる部分なので、丁寧に交渉するようにしてください。
秘密保持契約の締結
売買交渉の申し入れでは、秘密保持契約の締結が必要です。秘密保持契約とは、M&Aの判断材料として売り手が提示した会社の情報を外部に漏らさないと約束する契約です。
M&Aが成立するまでには、会社の機密情報に触れることもあります。情報漏洩のリスクに対応するための手段として秘密保持契約が用いられています。
秘密保持契約を締結してから、会社や事業の機密情報が記載された資料を閲覧できるようになるのです。
デューデリジェンスを行う
デューデリジェンスとは、買い手が専門家に依頼して売り手の企業や事業の情報を収集、分析する手続きです。
買い手は、デューデリジェンスによって企業価値を評価をするための情報や今後支障になる要素を把握します。
デューデリジェンスでは、財務や税務、法務、労務といったあらゆる方向性から調査します。
未払金になっている給与や債務保証といった帳簿に記載されていない債務を引き継いでしまうリスクがあるため、必ず信頼できる専門家に依頼してください。
専門家は税理士や公認会計士、弁護士などが一般的ですが、マッチングサービスで用意されているデューデリジェンスを利用できるケースもあります。
最終契約の締結
デューデリジェンスの結果を踏まえて最終条件の交渉を行ってから、最終契約を結びます。
最終契約を締結した後は、事業譲渡の手続きや株式譲渡、代金の受け渡しを行うクロージングの段階です。最終契約書には会社の譲渡の内容や売買価格などが含まれます。
最終契約書には法的拘束力があり、定められた事項が遵守されない時には損害賠償を求めることも可能です。
補償の期間や上限額が定められているかについても確認してください。
個人のM&A起業に活用できる支援制度・融資

個人がM&A起業する場合、どうしても資金の問題が発生してしまいます。資金調達の不安を解消するために公的支援制度の活用も検討しましょう。
どのような制度を利用できるのかまとめたので参考にしてみてください。
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金は、事業承継を契機にした新しい取り組みを支援する制度です。
その内容に応じて枠が設けられていて事業承継促進枠と専門家活用枠、廃業・再チャレンジ枠、PMI推進枠があります。
事業承継・M&A補助金は、常時募集しているわけではなく公募期間が決まっています。
公式サイトで申請受付期間や交付決定時期、事業実施期間のスケジュールをチェックしてください。
新規開業・スタートアップ支援資金
新規開業・スタートアップ支援資金は、女性や若者、シニア、廃業歴がある人など幅広い対象の起業を支援しています。
融資限度額は、7,200万円(うち運転資金4,800万円)なので、多くの資金準備が必要な場合にも適しています。
経営者保証免除特例制度や創業支援貸付利率特例制度など併用できる制度もあるので、条件をみて積極的に活用してください。
都道府県の後継者バンクや支援機関
各都道府県の事業引継ぎ支援センターでは、事業承継のために無料相談やマッチング支援を提供しています。
さらに地域の商工会議所や信用金庫でも事業承継に関する相談窓口を設置し、案件紹介を行っています。
都道府県では、地域密着型の事業承継支援を行っていることがあるので、地元の優良案件に出会うためにも利用できる機関がないか調べてみてください。
注意点と失敗しないためのポイント

M&A起業にはリスクもあるため不安に感じる人も多いかもしれません。成功させるためには、以下の3つのリスクを事前に把握し適切な対策を講じてください。
財務・契約面は専門家にチェックしてもらう
M&A起業では必ず税理士や公認会計士に依頼し、簿外債務や隠れた負債がないか財務諸表を詳しく調査してください。
契約書の内容も専門家でないと難しい部分が多くあるので、司法書士や弁護士にチェックしてもらい、法的リスクや不利な条項がないか確認しましょう。
専門家への報酬は数十万円かかるため負担に感じるかもしれません。
しかし、買収後のトラブルを防ぐための必要投資です。専門家を探す時にはM&Aについての実績があるかどうかも確認しておいてください。
「買った後どうするか」の戦略を立てる
M&A起業は買ったらゴールではなく、新しいスタートです。今までの事業を現状維持するだけでは競合に負けるため、買収後3年間の具体的な改善計画を立てるようにします。
売上向上やコスト削減、新サービス展開など、企業を成長させるための戦略を明確にしておきます。
計画実行のための人材確保や設備投資の資金も、買収時に併せて準備しておくようにしてください。
時間をかけて信頼関係構築を行う
買った企業には、長年働いてきた従業員や付き合いがある取引先が存在しています。前経営者に慣れ親しんだ従業員は新経営者に対して警戒心を持つかもしれません。
焦らず時間をかけて信頼関係構築を目指してください。
また、M&A起業をしたからといって急激な人事変更や給与カットは避けて、まずは現状を理解することから始めましょう。
関係構築には時間がかかります。定期的な面談や懇親会を通じて、従業員一人ひとりとのコミュニケーションを重視してください。
まとめ|「買って始める起業」は現実的な選択肢
M&A起業は個人でも十分に実現可能で、ゼロから起業するよりもリスクを抑えられる点がメリットです。
近年、後継者不足により売却を希望する優良企業が増えており、買い手にとって有利な環境が整っています。
起業時の支障となりやすい資金の問題も公的支援制度が利用できます。相談窓口などのサポート機関もあるので、資金面での不安を解消しながら挑戦してみてください。
後継者不在の会社を引き継ぐ、新規事業として買収する──
M&Aにはさまざまな活用パターンがあります。
『中小企業のためのM&Aガイド』 では、スキーム別の解説や業種ごとの傾向、成功事例をまとめてチェック可能。これからM&Aを検討する方に最適な入門書です。無料でダウンロードできます。
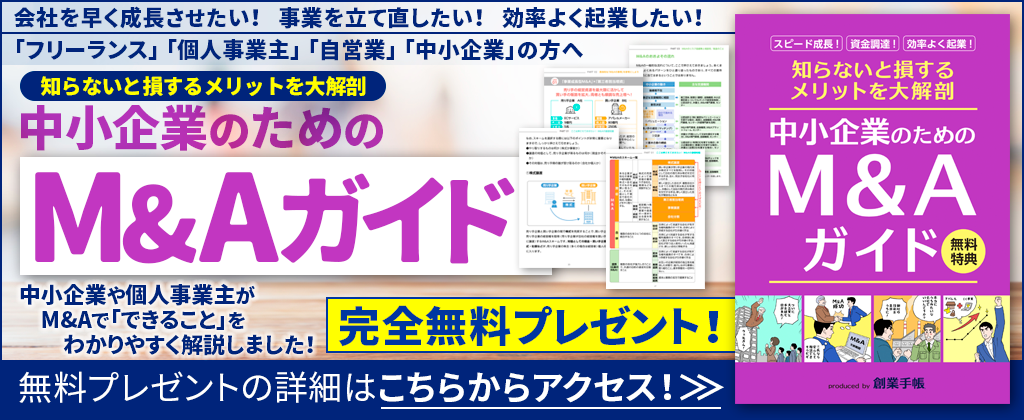
(編集:創業手帳編集部)