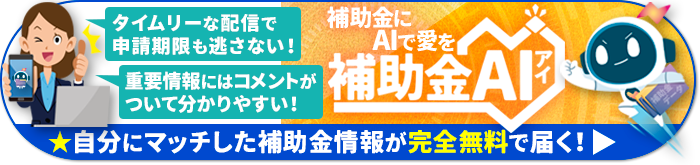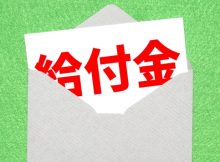新商品・新サービスの開発に使える補助金・助成金の種類!メリットや注意点も解説
新商品開発時には費用負担を軽減できる補助金制度を活用しよう

新商品の開発や新サービスの導入を目指そうとしても、予算が足りずに悩んでいる企業担当者もいるかもしれません。
予算が足りない場合、融資の活用も検討されますが返済する必要があるため躊躇してしまいます。
そのような時には補助金や助成金制度がおすすめです。制度を活用すれば、商品開発にかかるコストを抑えることができます。
そこで今回は、新商品・新サービスの開発に使える補助金・助成金を紹介するとともに、活用時の注意点やメリットを解説していきます。
新商品、新サービスの開発を検討している企業や補助金や助成金の活用を考えている企業は、ぜひ参考にしてみてください。
創業手帳では、経営者の方がよく使っている補助金をランキング形式で紹介した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。こちらもあわせてご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
【全国】新商品・新サービスの開発に使える補助金・助成金
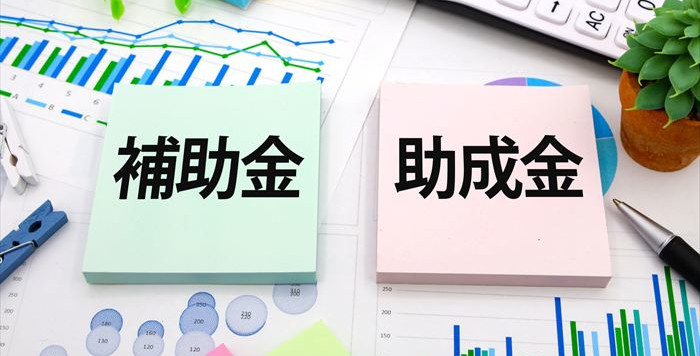
まずは、全国を対象に国が用意している新商品・新サービスの開発に使える補助金・助成金を紹介していきます。
対象者や補助額など、それぞれの特徴を知り、活用できる制度であるか確認するために役立ててください。
ものづくり補助金
中小企業や小規模事業者が生産性向上のために革新的なサービスの開発や試作品の開発、生産プロセスの改善を実施するための設備投資を支援するための補助金制度がものづくり補助金です。
具体的な対象経費としては、設備投資費をはじめ、システム構築費、外注費、試作品開発費などが当てはまります。
補助率は企業規模によって違いがあります。
中小企業は1/2、小規模事業者・再生事業者は2/3となり、最低賃金の引き上げに取り組む事業者に対しては補助率を2/3に引き上げる仕組みです。補助上限額は以下の通りです。
| 従業員の規模 | 補助上限額 |
| 5人以下 | 750万円 |
| 6~20人 | 1,000万円 |
| 21~50人 | 1,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 |
また、大幅な賃上げをすると従業員規模に応じて100万円~1,000万円補助上限額が上乗せされます。
以下の要件をすべて満たせるよう、3~5年の事業計画を策定して実行しなければいけません。
・付加価値額
年平均成長率3.0%以上増加
・1人当たりの給与支給総額
都道府県の最低賃金の直近5年で、年平均成長率以上もしくは2.0%以上の増加
・事業所内最低賃金
各都道府県の最低賃金30円以上アップする
・従業員の仕事、子育て両立支援
従業員21人以上の場合は、一般事業主行動計画の策定と公表を実施
小規模事業者持続化補助金
販路拡大や業務効率化を目指す小規模事業者や個人事業主を支援する補助制度が小規模事業者持続化補助金です。
補助事業にかかる製造装置の購入や新サービスを紹介するためのチラシの作成、看板の設置、販路開拓のための旅費、新商品の試作品開発にかかる経費などが、対象となる経費です。
補助率、補助上限額は以下の通りです。
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
| 補助上限 | 50万円 |
| インボイス特例 | 50万円の上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 150万円の上乗せ |
| 上記特例をともに満たしている事業者 | 200万円の上乗せ |
インボイス特例とは、免税事業者から適格請求書発行事業者へと転換する小規模事業者です。
賃金引上げ特例は、補助事業を実施する期間において事業場内最低賃金を申請時よりも50円以上増加させた事業者となります。
【地方自治体】新商品・新サービスの開発に使える補助金・助成金

自治体でも、企業向けに新商品や新サービスの開発時に使える補助金や助成金制度を提供しています。ピックアップして紹介していきます。
【東京都】新製品・新技術開発助成事業
東京都内の中小企業者の技術力の強化や新分野開拓を促進するため、実用化の見込みがある新製品や新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成する制度が新製品・新技術開発助成事業です。
原材料や副資材費、委託・外注費、専門家指導費、機械装置・工具器具費などが助成対象経費となります。
また、以下が対象者です。
-
- 東京都内の本店または支店で実質的な事業活動をしている中小企業者
- 東京都内で創業を具体的に計画している個人
助成率は、助成対象と認められる経費の1/2以内で、賃上げ計画を策定して実施した場合には3/4以内にアップします。
助成限度額は、2,500万円です。
申請する場合、国が提供している電子申請システムの「Jグランツ」で受け付けています。
GビズIDプライムアカウントの取得が必要になるので、あらかじめ登録しておくとスムーズな申請につながります。
【大阪府】新事業展開テイクオフ支援事業
大阪府内で新事業展開にチャレンジをする中小企業に対して提供しているのが新事業展開テイクオフ支援事業です。100万円を上限として、対象経費の1/2以内の補助です。
また、建設業や運輸業、宿泊業・飲食サービス業での人手不足の解消にかかる経費に対しては、50万円を上乗せしてくれます。
ただし、制度を活用するためには大阪府が指定しているセミナーを1回以上受講する必要があります。
大阪産業局が主催するセミナーや商工会・商工会議所が主催するセミナーがあるので、事業に役立つ内容を選別し、知識向上につなげるためにもあらかじめ確認しておいてください。
【京都府】チャレンジ・バイ(京都府新商品・サービス販売促進支援制度)
京都府が実施しているのが、中小企業を対象にした新商品・サービス開発のためのチャレンジ・バイ(京都府新商品・サービス販売促進支援制度)です。
府内にある中小企業が手掛けた新商品や新サービスを京都府が認定・公表・PRし、府庁での率先購入や販路開拓をサポートする制度です。
認定の対象となる商品やサービスは、販売や提供をスタートしてから5年以内のもので、次に適合するものとなります。
-
- 独自性がある
- 有用性がある
- 生産、提供の確実性がある
また併せて、病院や介護施設、研究機関などが商品を購入する場合の補助も実施しています。
補助上限額は、チャレンジ・バイ認定商品・サービスと一般商品・サービスの差額の1/2以内となっており、100万円が上限です。
【宮城県】地域資源活用推進整備事業
農林漁業者が生産した農林水産物などの地域資源を活用し、新商品や新サービスの開発を通じて農山漁村の「なりわい」づくりの促進を目的に、新たな取り組みを実施する際に必要となる機器や器具などの導入費用を補助する制度が宮城県による地域資源活用推進整備事業です。
加工品を製造するための機械や器具の購入、原料保管器具の購入、配管や配電工事に必要な経費などが主な対象経費になります。対象者は以下の通りです。
-
- 宮城県内に本店がある農林漁業の法人
- 農林漁業者の組織団体
- 農林漁業を営んでいる個人
- 上記いずれかと連携する中小企業者
補助率は1/2以内で下限額は30万円、上限は200万円となります。
【新潟県】県産食品新市場開拓支援事業
県産の農林水産物や米粉などの消費・需要拡大を図ることを目的に、新商品の開発や販路拡大に要する経費の一部を補助する制度が新潟県による県産食品新市場開拓支援事業です。
新潟県内に本社や事業所を有している食品製造事業者、県内の食品関連事業者のほか、知事が認めた企業または団体が対象となります。
県産の原材料確保のための活動や商品開発、メニュー開発活動、マーケティング活動などが対象経費となります。補助率は、補助対象経費の1/2以内です。
新商品・新サービス開発に使える補助金・助成金を活用する際の注意点

補助金や助成金を活用する際には注意点があります。スムーズに申請するため、対象となるためにも、あらかじめ確認しておきましょう。
開発内容が審査基準に適合している必要がある
補助金や助成金は、申請をすれば必ず受け取れるわけではありません。
補助金の多くは「革新性」「市場性」「生産性向上」などの要素が求められ、単なる改良では対象外となる場合があります。
例えば、ものづくり補助金では「革新性」が重要視されています。新商品であれば何でも良いとはなりません。
世の中にありふれている商品や古い設備を更新するための申請では採択されない可能性が高いです。
そのため、業種内での先進、地域内での先進など、相対的な視点による革新性を示す必要があります。
事業計画の完成度が採択を左右する
補助金の申請には、開発の狙いや成果、費用対効果などを明確に記した事業計画書が必要です。不備があると不採択の原因になるので注意してください。
事業計画が採択されるためには、審査項目を満たしている必要があります。
審査項目に関しては、公募要領に記載されているケースが多いので必ず確認するようにしてください。不安があれば専門家のアドバイスを聞くのもおすすめです。
開発前に申請・交付決定が必要なケースが多い
補助金の多くは「事前着手NG」です。そのため、申請前に開発を始めたり、開発に必要な製品を購入したりすれば補助対象外になってしまいます。
これは、補助金が「新しく取り組む事業」に対する支援が対象であるからといえます。
申請前に開発を始めてしまえば、すでに開始された事業と新事業との整合性がとれなくなる可能性があるため、原則として事前着手は認められていません。
前払い金や手付金の支払いに関しても着手行為とみなされる可能性があるので注意してください。
開発費用は自己資金で一時立て替える必要がある
補助金は「後払い」が原則です。事業が実際に行われたのか事務局が確認してから交付される仕組みです。
そのため、開発にかかる費用を一時的に自己資金でまかなえる準備が必要になります。
補助金の申請から入金まで、1年程度かかるケースもあるため、ある程度の資金を確保してから開発を始める必要があります。
成果や経費の報告義務がある
開発後には実績報告書の提出が求められます。例えば、ものづくり補助金は補助事業終了後、5年間にわたって合計6回の事業化状況報告が必要です。
万が一報告を怠った場合は、ペナルティとして返還を求められる可能性があるので必ず提出するようにしてください。
スムーズに提出するためにも、実施状況や経費の使途を証明する書類を日頃から整理しておく必要があります。
補助金・助成金を使うメリット

最後に、補助金や助成金を活用するメリットを紹介していきます。
返済不要で開発資金を確保できる
新商品の開発や新サービスの提供に向けての資金を確保する場合、融資を思い浮かべる人は多いはずです。しかし、融資となれば返済が大きな負担となってしまいます。
多く借りればその分返済する額も多くなるので、場合によっては赤字が続くケースも考えられます。
補助金や助成金は融資とは異なり、返済の必要がありません。
受給するまでには期間を要するため、実際にかかった経費は一時的に立て替える必要がありますが、返済の必要性がないので負担を抑えられる点が大きな魅力です。
販路開拓や業績拡大の後押しになる
補助金や助成金を活用すれば、断念した新規事業も行えるようになります。返済が必要ないので、新事業に挑戦するリスクを抑えられるでしょう。
また、展示会出展・広告・EC構築など、開発後の販売活動も補助対象となる制度が多く、より多くの人たちに商品を提供できるので、成果に直結しやすくなります。
公的支援による信頼性向上にもつながる
前述したように、補助金や助成金の申請時には多くの場合で事業計画書の提出を求められます。
その際には事業計画に関するアドバイスを受けられるケースがあるので、採択された事実が「第三者の評価」として信用力を高め、取引先や金融機関からの評価向上につながる場合もあります。
資金調達のための融資を検討している企業にとっては大きなメリットとなります。
まとめ・事業に合った補助金・助成金を選んで期限内に申請しよう
新商品・新サービスの開発に使える補助金・助成金制度は、全国で使える制度もあれば、自治体が独自に設けている制度もあります。
そして活用すれば開発資金を確保し、販路開拓や業績拡大の後押しとなるメリットを得られます。
ただし、活用するには審査や要件があり、開発内容が審査基準に適合していなければ対象外となってしまうため、対象内であるかあらかじめ確認することが大切です。
また、申請には期限が設けられているので、期限内に申請するためにも条件を確認するだけではなく、申請に必要な書類についてもチェックしておきましょう。
事前に用意をしておけばスムーズな申請が可能です。
創業手帳では、地方自治体からの補助金・助成金情報を見逃さないためのサービス「補助金AI」を無料で提供しています。ご登録いただいた都道府県の補助金・助成金情報を月2回配信。たくさんある中の情報が探しやすくなります。ぜひこちらもあわせてご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)
創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。