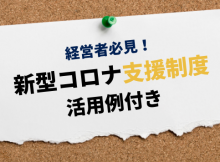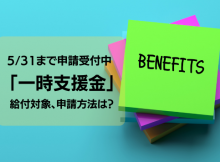個人事業主が病気になったらどうなる?知っておきたい給付金制度について解説
個人事業主は万が一に備えることが重要!

会社員とは異なり、個人事業主は病気やケガで仕事ができなくなった場合のリスクが大きいものです。
有給休暇や傷病手当金などは原則として利用できないため、生活への影響は深刻です。
特に、長期間の療養が必要になった時には、収入減や医療費の負担が重なり、事業の継続が困難になることもあります。
万が一の事態に備えて、給付金や保険などの制度を理解しておくことが大切です。
この記事では、個人事業主が病気になった時に受け取れる可能性のある給付金制度について詳しく解説します。
創業手帳では、自分に合った給付金(補助金・助成金)が配信される「補助金AI(無料)」や補助金を基本から分かりやすく解説した「補助金ガイド(無料)」も提供中です。ぜひこの機会にあわせてご利用ください!


 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人事業主が病気で働けなくなった時のリスク

個人事業主が病気で働けなくなった場合には、以下のリスクがあります。
-
- 傷病手当金・雇用保険がない
- 収入ストップによる生活費への影響
会社員は会社の健康保険に加入していますが、個人事業主は国民健康保険に加入しています。
国民健康保険は医療費を一部補助してくれる健康保険制度ではあるものの、会社の健康保険とは異なり傷病手当金を受け取ることができません。
また、病気になり事業の運営が難しくなった場合に、次の仕事を探すまでの生活資金や職業訓練を受ける費用の一部支給といった雇用保険の保障が受けられないことも、デメリットです。
収入がストップした状態が続けば、貯金が底をつく可能性もあり、生活費にも多大な影響を及ぼします。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主も活用できる!病気になった時の給付金制度

個人事業主は、傷病手当金や雇用保険による保障は受けられないものの、病気になった時に利用できる制度が用意されています。
ここからは、個人事業主が利用できる給付金制度について解説していきます。
労災保険の特別加入
労災保険は労働者を守るための制度で、仕事中や通勤中に発生した事故や職業病になった場合に治療費や休業補償、障害補償などを受けられる保険です。
個人事業主は労働者ではなく事業主にあたることから、原則として労災保険に加入できません。
しかし、労災保険の特別加入によって、一部の業種・職種に該当する個人事業主も労災保険に加入できます。
また、これまでは中小事業主や一人親方(運送事業や土木・建築事業など)、特定作業従事者(芸能関係、介護作業従事者など)、海外派遣者などが対象となっていました。
しかし、2024年11月からは起業などから業務委託を受けているフリーランスも特別加入できるようになっています。
対象範囲が広がったことで、労災保険の特別加入がしやすくなったため、加入を検討してみてください。
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心と体の障害を軽減または取り除くための治療にかかった費用を軽減するための制度です。
精神疾患を罹患し精神病院に通院している人や、更生医療を受けている人などが対象となります。
自立支援医療制度は、所得に応じて1カ月あたりの負担上限額が決まっています。
| 所得区分 | 精神通院医療・更生医療 | 重度かつ継続 |
| 生活保護 | 0円 | |
| 市町村民税非課税(本人の年収80万円以下) | 2,500円 | |
| 市町村民税非課税(上記以外) | 5,000円 | |
| 市町村民税所得割33,000円未満(年収約290万円~400万円未満) | 総医療費の1割または高額医療費の自己負担限度額 | 5,000円 |
| 市町村民税所得割33,000円以上235,000円未満(年収約400万円~833万円) | 1万円 | |
| 市町村民税所得割235,000円以上(年収約833万円以上) | 対象外 | 2万円 |
障害基礎年金
障害基礎年金とは、国民年金に加入している間に障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合に支給される年金です。
障害基礎年金を受けるには、初診日の前日時点で次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
-
- 初診日のある月の前々月まで公的年金の加入期間の3分の2以上、保険料が納付または免除されている
- 初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間で保険料を未納していない
会社員や公務員は障害基礎年金に加えて障害厚生年金も支給対象となりますが、個人事業主の場合は障害基礎年金のみが対象です。
また、会社員・公務員だと障害等級が3級であれば障害年金を受給できますが、個人事業主は障害等級が1級または2級でなければ受給できません。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主が給付金以外の備えとして使える保険・制度

労災保険の特別加入や自立支援医療制度、障害基礎年金などの給付金制度は用意されていますが、生活費や医療費を賄えるかどうか不安に感じる人もいるでしょう。
ここからは、給付金以外の備えとして使える保険や制度についても紹介します。
医療保険
医療保険は、病気やケガになった際の治療費や入院・手術にかかる費用をカバーできる保険です。
国民健康保険では、病気やケガの治療費が1~3割の自己負担額に抑えられますが、公的医療保険の対象外となった場合は全額自己負担になります。
例えば、入院時の食事療養費や差額のベッド代、先進医療にかかる費用などは公的医療保険の対象外です。
一方、民間の医療保険に加入しておけば、入院や手術にかかる費用を賄うことが可能です。
受け取りが可能な給付金は保険商品の種類や契約内容で異なるものの、基本的には医療費負担を補うものであり、収入を補償するための保険ではないので注意してください。
就業不能保険
就業不能保険とは、病気やケガが原因で長期間にわたり働けなくなってしまい、収入が減少した時のために備える保険です。
働けなくなってから60日間の待機期間があり、その後給付金を受け取ることができます。
就業不能保険に加入していれば、傷病手当金を受給できなくても収入がゼロになることはありません。
また、退院後の在宅療養にかかる費用や生活費、医療保険では賄いきれなかった不足金額も、就業不能保険からカバーすることが可能です。
ただし、医師からの指示ではなく、自分で決めた在宅療養は対象外となります。
所得補償保険
所得補償保険は、病気やケガなどが原因で万が一働けなくなってしまった際に、所得を保障するための保険です。
就業不能保険と同じく、収入の減少リスクに備えるための保険ですが、基本的には生命保険会社が就業不能保険、損害保険会社が所得補償保険として提供しています。
また、就業不能保険は60歳や70歳までと長期にわたって給付金を受け取ることが可能ですが、所得補償保険は1~5年間と比較的短めに設定されていることが大きな特徴です。
就業不能保険であれば、保障金額が契約前の年収によって上限が決まります。
しかし、所得補償保険の場合には、契約前1年間の所得に対して50~70%を上限に設定することになります。
個人年金保険
個人年金保険は、老後の生活資金に備えるために活用できる私的年金のひとつです。公的年金を補完するためのものであり、保険期間・年金額などは各商品によって異なります。
加入するタイミングで年金を受け取る年齢を選ぶことができ、万が一保険料払込期間に死亡した際には死亡保険金を受け取れます。
なお、個人年金保険には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
・終身年金
年金受取人の被保険者が生存している場合、一生涯年金が受け取れます。ただし、被保険者が死亡すると年金の支払いが終了し、遺族が年金を引き継ぐことはできません。
・有期年金
年金受取人の被保険者が生存している場合、契約時に決められた一定期間年金が受け取れます。ただし、遺族が年金を引き継ぐことができません。
・確定年金
年金受取人の被保険者の生死に問わず、契約時に定めた一定期間年金が支払われます。
受取期間に被保険者が死亡してしまった場合でも、遺族は受取期間が終了するまで年金を受け取ることが可能です。
小規模企業共済
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主が将来の備えとして活用できる制度です。
小規模企業共済によって掛金を積み立てておくことで、退職金として受け取れます。毎月の掛金は1,000~7万円まで500円単位で設定でき、加入後に増減させることも可能です。
また、全額課税対象所得から控除でき、節税効果が得られることもメリットといえます。
なお、共済金を受け取る場合、一括と分割のいずれかを選択することが可能です。
一括で受け取る場合は退職所得扱いになりますが、年金のように分割で受け取る場合には雑所得扱いになります。
いずれも事業所得に比べれば税負担は大きく軽減できます。
ただし、掛金納付月数が240カ月(20年)未満で任意解約をすると、受け取れる共済金が掛金の合計金額を下回ってしまい、元本割れを起こしてしまうので注意が必要です。
所得税・住民税の納税猶予
期限内に所得税・住民税を納めるのが困難な場合は、国税または市区町村の猶予制度を活用してください。
国税の猶予制度は、納税により事業継続や生活が困難になってしまう場合や、災害などの被害に遭った場合に、税務署へ申請することで原則1年以内は納税が猶予されます。
住民税の納税猶予は、市区町村に申請することで認めてもらえる場合があります。猶予期間は国税と同じく原則として1年以内です。
住民税で納税猶予を受けられるのは、以下に該当する人になります。
-
- 震災や風水害、火災、盗難などの被害を受けた人
- 病気やケガをしてしまった人
- 事業の廃止または休止をした人
- 事業で著しい損失を受けた人 など
納税猶予を利用するためには、役所で相談することが大切です。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
給付金を受け取るまでの期間は?

給付金制度は、申請から支給されるまでに数カ月かかることを想定しておくことが大切です。
障害基礎年金の場合は審査に3カ月程度、審査に通っても実際に受給されるまで1カ月半近くかかる場合もあり、申請から4~5カ月後に支給される可能性もあります。
また、労災保険の特別加入でも、給付されるまでに1カ月以上かかってしまうケースもあります。
病気で働けなくなった時にすぐ使えるお金が支給されるわけではないため、空白期間の生活資金をどのように確保するかが重要です。
生活費をカバーする手段として、就業不能保険や所得補償保険、小規模企業共済の貸付制度など民間の備えが必要となります。
公的給付と民間の備えをうまく活用しつつ、早めに準備することが大切です。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主が病気で働けなくなる前に備えるべきこと

いつ、どこで病気になってしまうかはわかりません。そのため、個人事業主であれば、働けなくなる前に備えておくことが大切です。
ここで、個人事業主が病気で働けなくなる前に備えるべきことを紹介します。
事業と生活の両方を補えるだけの資金を確保しておく
病気で働けなくなった時のために、事業面に加えて生活資金も補えるだけの資金を確保しておくことが重要です。
働けなくなると事業をストップせざるを得ない状況に陥り、仕事ができない状態が続けば収入はゼロです。
また、運転資金がなくなれば、事業の継続が困難になります。数カ月~1年分程度は、事業の運転資金を確保しておくと安心です。
なお、事業の運転資金に加え、生活費も確保しておかないといけません。
会社員であれば生活費の半年程度が目安となりますが、公的保障が手薄な個人事業主は1~2年分は用意しておいてください。
経営状況や今後の手続きに関して家族・専門家と連携しておく
働けなくなった場合でも、経営状況をすぐに把握できたり、給付金の申請・手続きなどをすぐ行えるようにしたりするために、事前に家族や専門家と連携しておいてください。
例えば、税理士と連携を取っておけば、税務申告を代行してもらったり、所得税・住民税の猶予制度を利用したい場合に相談したりできます。
また、家族と連携が取れていれば、自分が仕事をできなくても家族に事業を引き継いでもらうことも可能です。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
個人事業主が病気で働けなくなった場合の確定申告

個人事業主が病気になり働けなくなると収入がゼロになってしまうことから、「確定申告は不要」と考える人もいるでしょう。
年間所得が48万円以下の場合や副業分の所得が20万円以下なら、確定申告を行う必要はありません。
しかし、病気などが原因で売上げがなかったとしても、確定申告をすることで損益通算や純損失の繰り越し・繰り戻しなどを利用できます。
住民税を申告していなければ国民健康保険料が高くなったり各種証明書の発行ができなくなったりするため、確定申告するほうが良いかもしれません。
 【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
【完全無料】シリーズ累計250万部「みんなが使ってる起業ガイドの決定版」『創業手帳』
まとめ・病気で働けなくなった時のために早めの備えが大切!
個人事業主は病気で働けなくなった場合、会社員や公務員よりも公的保障が手薄なため、すぐに収入が減ってしまう可能性が高いです。
傷病手当金や障害厚生年金などの制度が利用できない分、運転資金・生活資金の貯金や保険などを取り入れることで、リスクにも備えられます。
いつ病気になるかわからないので、リスクには早めに備えておくことが大切です。
創業手帳では、一人一人のニーズに合わせた補助金・助成金情報を配信する「補助金AI(無料)」サービスや、補助金に関する基礎知識をやさしく説明する「補助金ガイド(無料)」を無料提供しています。このチャンスにぜひ活用してみてください!


(編集:創業手帳編集部)