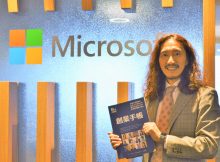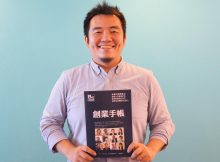AIQ 渡辺 求|SNSデータのAIプロファイリングで本質を見える化
ミュージシャン志望からAI起業家へ

「まさか自分が起業するなんて思ってもいなかった」そう語るのは、47歳でAIQ(アイキュー)株式会社(以下、AIQ)を立ち上げた渡辺 求さん。
ミュージシャンを目指した学生時代、大企業での安定したキャリア、ベンチャーでのスピード感ある経営。そのすべての経験が、起業という決断につながっていきました。
今回の記事では、人生後半に差しかかる中、自分の「好き」と本気で向き合った渡辺さんの挑戦と、そこに込めた想いを創業手帳の大久保が聞きました。

AIQ株式会社 代表取締役社長 CEO兼COO
カシオ計算機、バンダイナムコエンターテイメントの新規事業開発責任者を経て、テクミラホールディングス(旧ネオス) 常務取締役、インミミック(ソニーミュージックエンターテインメントと旧ネオスの合同会社)代表を兼務し、ガラケーからスマホに向けた携帯電話の進化をデバイス開発、サービス開発、テクノロジー開発のすべての角度から新規ビジネスを創出。それらの経験をもとに、生成AIの進化を見据えたAIソリューションの社会実装を実現。2019年に取締役、2021年に代表取締役に就任。ForbesJAPAN2025年1月号「日本の起業家名鑑400」に選出。

創業手帳 株式会社 ファウンダー
大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
限界を感じた先に見えた新しい道。メーカーから通信業界への転身

大久保:昔から起業を志していましたか?
渡辺:私たちの世代は終身雇用が中心で、いかにいい会社に入って、定年まで働くかという意識の人ばかりでした。なので、まさか自分が起業するなんて思ってもいませんでした。
私は昔ミュージシャンを志していまして、学生時代にはライブハウスで演奏をしていました。途中でプロになるのは難しそうだと気づきましたが、それでも何かしら音楽に関わる仕事がしたいと思ったのです。そこで、当時から電子楽器を作っているカシオ計算機に就職し、3年目に大きな転機がありました。
当時の私は積極的に意見が言えない性格だったのですが、正反対に自分の意見を言う同期がいまして、彼がどんどん自分の意見を言って、やりたいことを叶えている姿を見ていたのです。
自分の意見を言わないと思いは叶えられないと思い、積極的に意見を発信する性格へ変わっていきました。
大久保:性格を変えるほどの転機を経て、バンダイナムコエンターテインメント(以下BNEI)に転職されていますね。当時は起業どころか転職も稀だったと思いますが、なぜ決断したのでしょうか。
渡辺:メーカーでモノづくりの奥深さを実感することができた一方で、より大きな変化や新たな価値創造に興味が沸いてきたのです。
さらに、技術的な進歩が大きい領域で新しい挑戦がしたいと思い、退職を申し出ましたが、部署異動を提案されたのです。そこで、当時最先端技術だったポケベルやPHSを扱う通信機器の部門に配置換えをお願いし、異動後にはKDDIに出向することになりました。KDDIでは、同じ通信事業でもインフラを整備する企業であるKDDIとデバイスを作る企業のカシオ計算機では、大きな違いがあると気づきました。
インフラ側の企業では、若い人たちにどんどん権限を渡して、自分よりも若い人が活躍している姿が印象的でした。
大久保:その後、BNEIへの転職を決めた具体的なきっかけをお聞かせください。
渡辺:KDDIに出向している時に、KDDIの方とBNEIの方と3人で食事をする機会がありました。そこで当時の自分の思いを語ったところ、BNEIへの転職を勧めていただき、転職することを決心しました。
大久保:BNEIのどこに惹かれたのですか?
渡辺:KDDIに出向している時に少しアメリカで仕事をしていたのですが、1年くらいで日本に帰らないといけなくなりました。ですが、私はもっとアメリカで働きたかったのです。
そのようなタイミングで、BNEIには日本で作ったデジタルコンテンツを欧米向けに輸出する新規事業を立ち上げる計画があり、その責任者を探していました。ある種のヘッドハンティングでBNEIに転職することになりました。
大久保:BNEIで新規事業の責任者をしてみていかがでしたか?
渡辺:私は欧米の担当だったので、1ヶ月の半分くらいはアメリカかヨーロッパのどちらかにいるという働き方が新鮮でした。さらに、BNEIは現地に販売会社があり、私の部下にも多くの外国人がつきました。
文化が違う土地で、文化が違う人と一緒に働く経験は、私の視野を大きく広げるきっかけになったと感じています。
また、将来的に起業したいと考えているなら、まずは社内で新規事業を立ち上げることがいい経験になると思いました。特に最近は社員のことを大事にする企業が増えたので、新規事業や社内起業をしやすくなってきていると思います。
ベンチャー企業への転身で見えた、大企業との決定的な違い

大久保:BNEIの後にもいくつか転職されていますよね?
渡辺:BNEIの次はボーダフォンに転職、その後BNEIでお世話になった役員の方とのご縁もあって、「ネオス(現テクミラホールディングス)」にジョインしました。私を誘ってくれたBNEIの役員の方が、アメリカのベンチャーキャピタルから出資を受けて起業した会社です。
ネオスでは常務取締役として経営にも参画し、上場まで達成できたことは、とてもいい経験となりました。
大久保:ベンチャー企業と大企業ではどのような違いを感じましたか?
渡辺:例えば契約書1つでも、大企業の場合は法務部に任せればチェックと締結までを進めてくれますが、ベンチャー企業の場合は全て自分でしないといけません。
大企業では他の部署に任せていたことを全て自分でするので、業務範囲はガラッと変わり、色々な気づきがありましたね。
「社長にしか見えない景色がある」その一言が起業の原点に

大久保:その後、どのような経緯で起業することになりましたか?
渡辺:前職のベンチャー企業でも色々な新規事業を提案していたのですが、最終的に判断するのは社長です。その社長に「渡辺くんも社長になればわかる。社長にしか見えない景色がある」と言われたのが衝撃的で、初めて「社長をしてみたい」と強く思いました。
今私が経営しているAIQのサービスであるプロファイリングも、実は前職で何度も提案していた事業でした。
しかし、当時は事業化が叶わず、だったら自分で起業しようと思い、AIQを創業しました。
当時、私の提案が承認されていたら、AIQを起業していないかもしれないので、全ての物事がうまくいけばいいということではないですね。
大久保:当初から起業したかったわけではないですが、リスクを取らないとやりたいことをできないので、結果的に起業したという流れですね。
渡辺:まさにその通りです。新規事業を立案するくらいなので、その分野に関しては社内で一番詳しくなります。しかし、組織の中では上司の許可がないと進められません。
組織に所属すると、その分野に詳しくない上司に却下されることも起きるかもしれないですよね。そうなったら納得できないだろうな、と思いました。だったら自分でリスクを取って、自分が決済者になるしかないと思ったのです。
一から作らずあるものを活かす。AIQの合理的な戦略思考

大久保:今やられているAIによるプロファイリング技術を活用した事業は、どのようなきっかけで注目し始めましたか?
渡辺:AIQの共同創業者の髙松がネオス時代の私の部下で、会社を辞めると言っていました。当時から彼はとても優秀だったので、このまま離れるのは勿体無いと思い、彼に何かやりたいことはないの?と聞くと、ディープラーニングに興味があると言ってました。
だったら一緒に起業しようと話すようになり、AIの分野で起業することになりました。
大久保:AIの中でも、プロファイリングに注目したのはなぜですか?
渡辺:私は47歳で起業しているのですが、当時から「人生100年時代」と言われ始めていました。起業するということは、残りの50年を同じ分野の仕事をすることになるかもしれないので、せっかくなら今まで気づいていない「自分が好きなこと」を見つけたいと思いました。
でも、自分が好きなことは、自分が一番気づかなかったりしますよね。そこで、AIを使ったプロファイリングに注目するようになりました。
先輩が身につけている物に興味を持つように、普段は身近なところから派生して自分の好きなことが見つかるものですが、SNSが普及した現代では、インターネット上でもうまくマッチングできるのでは?と考えました。
大久保:具体的にはどのような仕組みでプロファイリングをしていますか?
渡辺:SNS上では検索履歴や視聴したコンテンツにより、おすすめコンテンツが表示されますよね?その技術を応用し構築しました。
大久保:多くの起業家は全て自社で作ることを考えがちですが、今あるSNSに蓄積された情報に注目したのはなぜですか?
渡辺:自分でプラットフォームを作り、情報を貯めることも考えたのですが、膨大な時間と資金がかかると感じたのです。
すでにSNSに多くの情報が蓄積されており、ルール内であれば誰でも自由に使えるので、その情報の宝箱を使わない手はないと思い、今の形に辿り着きました。
手段はどうであれ、辿り着く目的は同じなので、合理的な判断ができたと思っています。
信頼とアライアンスが導いたプロダクトの拡大戦略

大久保:完成したプロダクトを広めるために、どんなことを工夫しましたか?
渡辺:プロダクトが完成してからは、私個人の人脈も活用しつつ、関係企業を増やしながら進めるアライアンス型を意識しました。
KDDIにいた時に、全部自社で完結させるのではなく、色々な協力会社とアライアンスを組む経験をしていたのです。アライアンス型で進めた方が、物事を早く効率的に進められますし、レバレッジも大きいです。
今ビジネスの中心にあるGAFAM(※1)も、言ってしまえばアライアンスの塊ですよね。どんなに小さな企業でも、アライアンスを意識して動くとスムーズに進められるかもしれません。
大久保:アライアンス先を探したり、うまく提携したりするには、何が大事になりましか?
渡辺:アライアンスを成功させるために一番大事なことは「信頼」です。
何が要因で信頼につながるかは人それぞれですが、「この人なら信頼できる」「この人と働いてみたい」と思ってもらえる自分の強みを探すことが大切です。
大久保:今後の展望を教えてください。
渡辺:企業には人手不足や人材教育など、様々な課題がありますが、それをプロファイリング技術を活用したデジタルクローンで解決したいと考えています。
現在AIQでは、起業のきっかけにもなったプロファイリング技術を含む、独自の「HUMANISE AI」を軸に、さまざまな企業の課題解決に取り組んでいます。
SNSなどのデータから人の「個性」を読み解くこの技術は、マーケティング戦略やデジタルクローンの活用、高度な顧客理解に基づくDXの支援といったかたちで、幅広く応用が進んでいます。
今後も、共感や信頼をベースにしたアライアンスを大切にしながら、より良い社会づくりにつながる取り組みを広げていけたらと思っています。
※1:GAFAM・・・Google、Apple、Facebook(現Meta)、Amazon、Microsoftの頭文字を取った呼称で、世界を代表する巨大IT企業5社を指す
(取材協力:
AIQ株式会社 代表取締役社長 CEO兼COO 渡辺 求)
(編集: 創業手帳編集部)