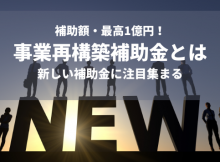【育休支援】育休中の「肩代わり」にも支援あり!両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」とは?
育休中の業務を支える従業員を支援し、よりよい職場環境を作ろう

2024年1月より、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」が新設されています。この助成金には、育児休業を取得する従業員がいるとき、業務負担が増えた従業員へ報いるという目的があります。
業務量が増える従業員が報われる仕組みが設けられたことで、当該従業員はモチベーションを保つことができ、また育児休業をする従業員は肩身が狭い思いをせずに済みます。
育児休業を取得中、あるいは取得を予定している従業員を雇用している事業主の方は、両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」を有効活用しましょう。
創業手帳では、その他経営でよく使われている補助金・助成金に厳選して解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。こちらもあわせてお読みください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」とは

まずは、両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」の内容について見ていきましょう。
制度の趣旨
政府は少子化に歯止めをかけるために、育児休業給付金の支給率を高めたり、新たに「出生後休業支援給付金」を創設したりして、子育て世帯への経済的支援を拡充しています。
しかし、従業員が育児休業を取得することで、他の従業員の業務負担が重くなってしまいます。
「育休中等業務代替支援コース」は、育児休業や育児短時間勤務制度を利用する従業員がいる場合に、その間の業務を埋める従業員に過度な負担がかからないようにするための体制整備を支援することを目的として新設されました。
業務の代替体制を整えることで、特定の従業員に業務が偏る事態を防げます。また、助成金の活用により育児休業を取りやすい職場環境を作り、休業取得が原因の離職を防止することも期待されています。
対象となる事業主
助成金の対象となるのは、以下の対策をした「中小企業事業主」です。
- 育児休業を取得した労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等を行う
- 育児短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等を行う
- 育児休業を取得した労働者の代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む。)を行う
なお、中小企業事業主の定義は、業種によって以下のように定められています。
| 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 | |
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「資本金の額または出資の総額」と「常時雇用する労働者の数」の、いずれかを満たせば対象となります。
コースの種類
「育休中等業務代替支援コース」は「手当支給等」と「新規雇用(育児休業)」に大別されます。それぞれの内容を見ていきましょう。
手当支給等
育児休業
「手当支給等」の中でも、「育児休業」は育児休業を取得した従業員の業務を代替する従業員に対して手当の支給を行ったとき、対象となります。
短時間勤務
「手当支給等」の中でも、「短時間勤務」は育児のための短時間勤務制度を利用する従業員の業務を代替する従業員に対して手当の支給を行ったとき、対象となります。
新規雇用(育児休業)
「新規雇用(育児休業)」は、育児休業取得者の業務を代替する従業員(育児休業代替職員)を確保したとき、対象となります。なお、代替職員は派遣労働者を受け入れた場合も含みます。
支給要件
続いて、それぞれの支給要件について確認しましょう。
手当支給等
育児休業
「手当支給等」の「育児休業」に該当するための要件は、以下のとおりです。
- 対象労働者(育児休業取得者)の業務を、事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させていること
- 業務の見直し・効率化のための取組を実施していること
- 代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること
- 対象労働者に7日以上の育児休業を取得させたこと
- 対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
なお、対象労働者の育児休業期間が1カ月以上である場合には、さらに以下の取り組みも求められます。
- 育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること
- 育児休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させたこと
- 対象労働者を原職等に復帰した日から支給申請日までの3カ月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
簡単にまとめると、従業員に7日以上の育児休業を取得させることと、代替業務を担当する従業員の賃上げが求められています。また、育児休業から復帰した従業員について、そのまま雇用を継続することも求められます。
短時間勤務
「手当支給等」の「短時間勤務」に該当するための要件は、以下のとおりです。
- 3歳未満の子を養育する労働者が、育児のための短時間勤務制度を1カ月以上利用したこと
- 育児のための短時間勤務制度利用者の業務を、事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させていること
- 業務の見直し・効率化のための取組を実施していること
- 代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること
- 対象制度利用者を、短時間勤務制度の利用開始日及び支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること
- 対象労働者の短時間勤務制度利用開始前に育児のための短時間勤務制度などを労働協約または就業規則に定めていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
「短時間勤務」においても、代替業務を担当する従業員の賃上げが欠かせません。
新規雇用(育児休業)
新規雇用(育児休業)の支給要件は、以下のとおりです。
- 対象労働者(育児休業取得者)の代替要員を、新たな雇い入れまたは新たな派遣受入れにより確保したこと
- 対象労働者に7日以上の育児休業を取得させたこと
- 対象育児休業取得者を育児休業の開始日及び職場復帰後、支給申請日までの間において、雇用保険被保険者として雇用していたこと
- 対象労働者の育児休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
なお、対象労働者の育児休業期間が1カ月以上である場合には、さらに以下の取り組みが求められます。
- 育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること
- 育児休業終了後、対象労働者を原則として原職等に復帰させたこと
- 対象労働者を原職等に復帰した日から支給申請日までの3カ月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること
支給額
それぞれのコースにおいて、支給額を見ていきましょう。
手当支給等
育児休業
「手当支給等」の「育児休業」では、以下の金額が助成されます。
| 業務体制整備経費 | 5万円(育児休業期間1カ月未満の場合は2万円) |
| 業務代替手当 | 業務代替者に支給した手当の総額の3/4 (プラチナくるみん認定事業主は4/5) |
なお、業務代替手当の上限額は毎月10万円、支給対象期間は代替期間12カ月分です。
短時間勤務
「手当支給等」の「短時間勤務」では、以下の金額が助成されます。
| 業務体制整備経費 | 2万円 |
| 業務代替手当 | 業務代替者に支給した手当の総額の3/4 |
なお、業務代替手当の上限額は1カ月ごとに3万円、支給対象期間は子が3歳に到達する日の属する月までです。
新規雇用(育児休業)
「新規雇用(育児休業)」は、新たに雇用した代替職員の代替期間に応じて、助成額が定められています。
| 業務代替期間 | 支給額(通常) | 支給額(プラチナくるみん認定事業主の場合) |
| 7日以上14日未満 | 9万円 | 11万円 |
| 14日以上1カ月未満 | 13万5,000円 | 16万5,000円 |
| 1カ月以上3カ月未満 | 27万円 | 33万円 |
| 3カ月以上6カ月未満 | 45万円 | 55万円 |
| 6カ月以上 | 67万5,000円 | 82万5,000円 |
なお、育児休業を取得した従業員が有期雇用労働者で、以下の要件に該当する場合は支給額に10万円が加算されます。
- 業務代替期間が1カ月以上である
- 育児休業開始日前の6カ月間において、期間の定めのない労働者として雇用されていない
このように、育児休業の取得によって穴が開いてしまった業務体制をカバーする仕組みを整備することにより、経費や手当の一部について助成を受けられる制度となっています。
両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」を活用するメリット

「育休中等業務代替支援コース」の活用により、育児休業を取得する従業員やカバーする従業員、事業主の三者にメリットがもたらされます。
具体的なメリットについて、詳しく見ていきましょう。
育児休業をする従業員のメリット
安心して育児休業を取得できる
育児休業を取得する従業員は、多かれ少なかれ「周囲に迷惑をかけてしまう」という不安を感じてしまうものです。「育休中等業務代替支援コース」により、自分の業務をカバーしてくれた従業員が報われる仕組みが整備されるため、肩身が狭い思いをせずに済むでしょう。
業務の穴埋めがきちんと行われるため、仕事の引き継ぎや同僚への負担増に関する懸念を軽減でき、安心して育児休業を取得できます。
スムーズに職場復帰できる
育児休業中、自分の担当業務は既存の従業員や新規雇用の代替要員で補填するため、業務が滞る心配はありません。育児休業取得者は、「復帰後に仕事が溜まっているのではないか?」という不安を感じずに済むでしょう。
長期の休業から復帰するとき、「ちゃんと復帰できるかどうか」という不安を抱える従業員がいるかもしれません。引継ぎ体制や復帰後の体制をきちんと整備し、従業員の不安を軽減することで、長期的な勤続にもつながるでしょう。
育児休業をカバーする従業員のメリット
経済的な報酬を得られモチベーションが向上する
育児休業中の従業員の業務を代替する従業員には、給与のベースアップや追加の手当(業務代替手当など)が支給されます。業務負担が重くなったことに対して経済的な報酬を得られるため、「貢献が評価されている」と感じ、モチベーションがアップするでしょう。
ベースアップや手当がないと、「業務量が増えただけで、実質的に損をしている」と感じてしまい、モチベーションが低下してしまいます。
生産性の停滞やモチベーションの低下を防ぐためにも、業務量が増えてしまった従業員に対して、経済的なインセンティブを付与することは効果的です。
業務体制が維持され過重な負担を回避できる
助成金を受給するための要件に「業務の見直し・効率化のための取組を実施していること」が設けられています。
つまり、育児休業を取得する従業員の業務がしっかりと代替される仕組みが整備されるため、現場では業務体制が維持されます。業務が適切に分散され、特定の従業員に過重な負担がかかる事態は起きないため、安心して業務にあたれるでしょう。
業務体制の整備を事前に計画し、労使間で話し合うことで、代替を担当する従業員は新たな業務にとりかかる準備を進められます。
事業主のメリット
経済的負担を軽減できる
事業主は助成金を活用することにより、給与の増額や手当の支給、新規雇用に伴って発生する費用負担を軽減できます。人件費の増加を抑えられ、資金繰りにもよい影響をもたらしてくれるでしょう。
複数のコースがあるため、業務の穴埋めをする従業員がいる場合は手当支給等(育児休業)、追加で従業員を雇用する場合は新規雇用(育児休業)を活用すればよいでしょう。穴埋めの方法に応じて、柔軟に活用できる点は「育休中等業務代替支援コース」のメリットです。
人材配置や業務の生産性を維持できる
育児休業期間中の業務配分を適切に分配し、また必要に応じて代替職員を雇用することで、人材配置や業務の生産性を維持できます。「仕事が早いあの人に任せてしまおう」という属人的な業務体制ではなく、職場全体でカバーすることにより、従業員の納得感も得やすくなるでしょう。
特定の従業員に業務負担が偏らない体制がしっかり整っていることで、働きやすい環境が整備されます。その結果、各従業員のモチベーションと生産性を維持できるでしょう。
企業イメージの向上と人材確保につながる
従業員が「育児休業を取得しやすい」と感じられる環境の整備につながれば、育児休業取得の促進にもつながります。政府は少子化対策の一環で、男性の育児休業取得率の向上を目指しています。
企業全体で育児休業取得率を上昇させれば、企業イメージの向上につながるでしょう。また、「従業員を大切にしている企業」「従業員のワークライフバランスを大切にする企業」という印象を対外的にアピールできれば、人材確保や人材定着にも寄与します。
特に、昨今は就職先・転職先を探すにあたって「ワークライフバランスを実現できるか」という点を重視する求職者が増えています。安心して育児休業を取得でき、長期的にキャリア形成を図れる安心感があれば、優れた従業員の長期的な勤続にもつながるでしょう。
支給申請の流れ

実際に助成金を申請する際の流れは、以下のとおりです。
| 手当支給等(育児休業) |
|
| 手当支給等(短時間勤務) |
|
| 新規雇用(育児休業) |
|
申請にあたって必要な書類は、利用するコースによって異なります。詳細は厚生労働省の資料に掲載されているため、確認しておくとよいでしょう。
両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」の注意事項
育休中等業務代替支援コースの利用にあたって、いくつか注意すべき点があります。詳細な支給ルールを確認しておきましょう。
1.支給人数・年数の上限がある
「育休中等業務代替支援コース」の支給人数・年数は、「手当支給等(育児休業)」「手当支給等(短時間勤務)」「新規雇用(育児休業)」を全てあわせて、以下の上限が設けられています。
- 育児休業取得者と制度利用者の合計で1年度10人まで
- 初回の対象者が出てから5年間
同じ年度内において5人以上の育児休業が発生した場合、全員分に関して助成対象とならない可能性があります。
2.2024(令和6)年1月1日以降に育児休業や時短勤務を開始した従業員がいるときに対象となる
「手当支給等(育児休業)」「新規雇用(育児休業)」の対象となるのは、2024(令和6)年1月1日以降に育児休業(産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産後休業)を開始している場合です。
「手当支給等(短時間勤務)」に関しては、2024(令和6)年1月1日以降に育児のための短時間勤務制度利用を開始している場合が対象です。
3.手当支給等と新規雇用は併給はできない
同一従業員の同一の子に係る育児休業について、「手当支給等(育児休業)」「新規雇用(育児休業)」は併用できません。いずれか一方かつ1回のみ対象となります。
また、同一の子にかかわる短時間勤務について、「手当支給等(短時間勤務)」を利用できるのも1回のみです。
4.業務を代替する人は複数でも可
業務を代替する従業員数に、特段制限はありません。複数の従業員で穴埋めをカバーする形でも、助成対象となります。
ただし、該当者それぞれが支給要件を満たす必要があります。
5.代わりに雇う人が業務委託の場合は対象外
育児休業を取得する人の業務を、業務委託で穴埋めをする場合は「育休中等業務代替支援コース」の対象外です。
あくまでも、直接雇用か派遣で雇い入れる場合が対象です。
まとめ:「育休中等業務代替支援コース」を活用してすべての従業員の満足度を高めよう
快適に働ける環境を整備するために、従業員が安心して育児休業を取得できるように支援しましょう。また、休業中の業務をカバーする従業員のモチベーションを維持することも効果的です。
育児休業を取得中の従業員、これから取得予定の従業員がいる場合、両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」を活用するとよいでしょう。カバーする従業員のモチベーションアップや、育児休業を取得する従業員のスムーズな復帰をサポートするためにも、効果的な制度です。
創業手帳が発行している「補助金ガイド」では、中小企業の人材確保・人材定着につながるお役立ち情報を提供しています。また、自社に合った補助金の最新情報が自動でタイムリーに届く「補助金AI」も無料でご利用いただけます。
企業経営に役立つ情報を随時提供しておりますので、ぜひお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)