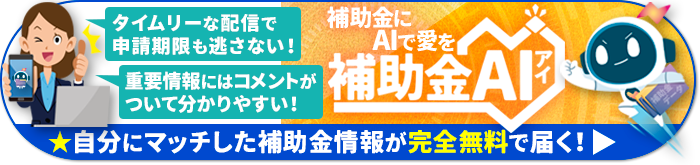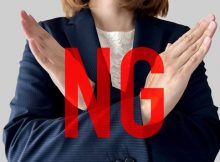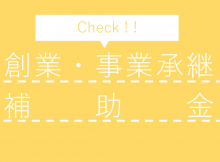収益納付とは?基礎知識から2025年度に収益納付が撤廃される補助金制度まで解説
補助金申請をする前に「収益納付」について知っておこう

事業でさらなる成長や規模の拡大を目指すために、補助金制度が活用されることも多いです。
補助金制度を利用することで対象となる経費が一部補助され、自己負担額を抑えつつ事業の成長を目指すことができます。
補助金制度は一般的に返済が不要となりますが、実は一定の利益が発生してしまうと「収益納付」により一部補助金を返納しなくてはなりません。
今回は収益納付とはどのようなものか、対象範囲や計算方法などの基礎知識を解説します。
さらに、2025年度に収益納付が撤廃される補助金制度についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
創業手帳では起業家・経営者の方がよく使われている補助金助成金を厳選して解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。こちらもあわせてご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
収益納付とは?利益がでたら一部補助金を返納すること
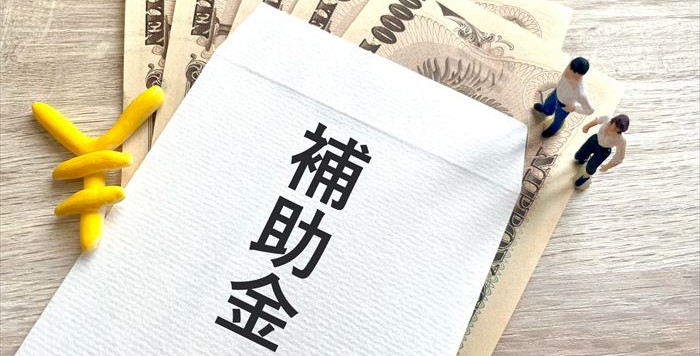
収益納付とは、補助金事業において自己負担額を超える利益が発生した際に、その一部を返納することです。
補助金を受けたことで得られた効果が事業者の利益となった際に、その利益の一部を返納することで国の支出が適切だったことを証明するために設けられています。
税金などの貴重な財源から支出された補助金だからこそ、原則返済は不要となるものの、利益が発生したら相応の返還が必要だという考え方です。
そのため、多くの補助事業では毎年報告を行い、どれくらいの利益がでたのかを報告する義務があります。
収益納付の対象になるケース・ならないケース

補助金を受けてその後の事業で利益がでた場合、収益納付の対象になるケースもありますが、そうでないケースも存在します。
どのようなケースだと収益納付の対象になるのか解説します。
収益納付になるケース
収益納付の対象になるのは、補助金を使ったことで直接的に発生した利益がある場合です。例えば以下のようなケースが該当します。
・設備導入による収益
補助金を活用して新しく生産設備を導入し、その設備を使って生産された商品によって利益がでた場合、収益納付の対象になります。
・ECサイト構築による収益
補助金を活用してECサイトを構築したり、既存のサイトに新たな決済機能などを追加したりした場合、構築によって販売数が増加したら収益納付の対象になります。
・移動販売による収益
補助金を活用して移動販売用の車を購入し、移動販売事業を行った結果、利益がでたら収益納付の対象になります。
・展示会・イベント参加による収益
補助金を活用して展示会やイベントに出展し、そこで商品を販売して利益がでた場合は収益納付の対象です。
収益納付にならないケース
収益納付は補助金を使って直接的な利益が発生した際に対象となりますが、逆に間接的に利益が発生した場合には対象外となります。例えば以下のようなケースです。
-
- 補助金を使い、自社サイト(ECサイト以外)を作成した結果、利益となった
- 補助金を使い、広告・チラシを作成して利益になった
- 補助金を使って店舗を改装し、その後の運営で利益がでた
- 補助金を使って商品生産に直接関わらない設備を導入し、利益につながった
自社サイトや広告・チラシ、店舗の改装などは顧客数を増やす効果はあるものの、直接利益がでているわけではないので、収益納付の対象になりません。
また、商品生産に関わらない業務効率化を向上させる設備なども、収益納付の対象外です。
収益納付の計算方法

収益納付は補助金を受けて得られた利益に基づき、どれくらい返納すべきかが決まります。
計算する際には補助金対象の事業にかかった経費から、受け取った補助金額を差し引き、自己負担額を算出してください。
この自己負担額がその年の利益を超えていた場合には、収益納付が発生し、一部返納することになります。
つまり、補助金を使った事業で営業利益がでたら納付が求められることになります。自己負担額の範囲内に利益が収まれば、収益納付は不要です。
なお、事業計画の途中で赤字になってしまった場合、前の年に返納した収益納付が戻ってくることもありません。
例えば1年目は赤字、2年目は経費を上回る利益がでて、3年目に再び赤字となってしまった場合、1年目と3年目は赤字のため収益納付は不要です。
2年目は収益納付を行う必要があります。しかし、2年目に返納した分の収益納付は3年目が赤字になったとしても還付されないので、注意してください。
収益納付の計算例
補助金事業で生産用の機械設備を新たに導入した場合、収益納付額はどのように計算すれば良いのでしょうか。条件は以下のとおりです。
補助金額:300万円
補助事業にかかった金額:700万円
事業によって得られた営業利益:500万円
収益納付額の計算式は、(本年度収益額-控除額)×(補助金確定額÷本年度までの補助事業にかかる支出額)になります。
控除額は事業者が自己負担した分の経費で、補助金確定額は受け取った補助金額の総額です。上記の条件を当てはめると以下のようになります。
(500万円-(700万円-300万円))×(300万円÷700万円)
=100万円×0.42
=42万円
つまり、この条件だと42万円を返納することになります。
2025年4月に収益納付が撤廃される補助金制度
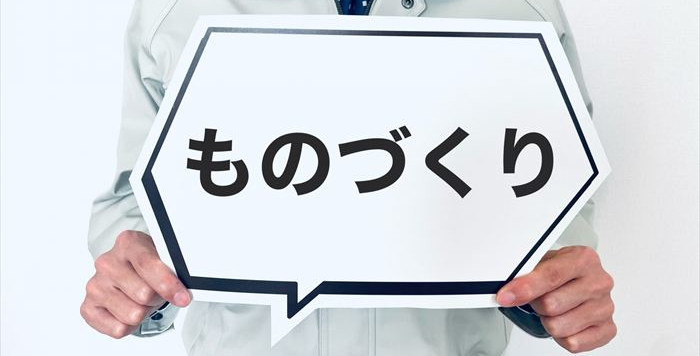
ここまで補助金制度の収益納付について紹介してきましたが、2025年4月から収益納付が撤廃される補助金制度があります。
収益納付が撤廃される補助金制度は、「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」です。
新事業進出補助金は新しい制度になりますが、事業再構築補助金の後継制度であり、以前は収益納付がありました。各補助金制度の概要は以下のとおりです。
| ものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠) | 新事業進出補助金 | |
| 目的 | 新製品・新サービスの開発による高付加価値化 | 企業の成長・拡大に向け、新市場・新たな高付加価値事業への進出にかかる設備投資 |
| 補助上限額 | 750万円~2,500万円 | 従業員数20人以下:2,500万円 従業員数21~50人:4,000万円 従業員数51~100人:5,500万円 従業員数101人以上:7,000万円 |
| 補助率 | 中小企業1/2、小規模・再生2/3 | 1/2 |
| 対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、原材料費など | 建物費、構築物費、機械装置・システム構築費など |
| 注意点 | 賃上げ要件を満たさないと補助金返還義務が発生 | 1人あたり給与支給総額の年平均成長率と事業所内最低賃金の基本要件が未達の場合、補助金返還が求められる |
| 補足 | 大幅な賃上げにより補助上限額を100万円~1,000万円上乗せが可能 | 大幅な賃上げにより補助上限額を500万円~2,000万円上乗せが可能 |
いずれの制度も収益納付は撤廃となります。
注意点としてものづくり補助金の場合は賃上げ要件、新事業進出補助金は1人あたり給与支給総額の年平均成長率と事業所内最低賃金の基本要件が未達成の場合、補助金返還が求められるので注意が必要です。
過去の採択事業者は収益納付が必要
収益納付が撤廃されるものづくり補助金と新事業進出補助金ですが、2025年以前に採択された事業者に関しては引き続き収益納付が必要と考えられます。
明確に「過去の採択事業者は引き続き収益納付が必要」と発表されているわけではありません。
しかし、過去の採択事業者はすでに収益納付が発生しており、国庫に返還した収益納付を事業者に再び返還することは考えにくいでしょう。
収益納付が撤廃される理由

ものづくり補助金などはもともと収益納付が求められていましたが、中小企業庁が発表した令和6年度補正予算に基づくものづくり補助金の概要において、「収益納付は求めない」と記載されました。
収益納付が撤廃される理由として、中小企業庁のイノベーションチームは「中小企業の成長を加速させるため」であることを説明しています。
収益納付は営業利益に基づいて、その分の補助金を返納する制度です。
営業利益がでたにも関わらず、補助金を返納しなくてはならないため、企業は事業拡大や次の成長戦略にその利益が使えなくなってしまいます。
せっかく補助金を受けて勢いづいた中小企業の成長をストップさせてしまう恐れがあることから、中小企業庁のイノベーションチームは財務当局と調整し、収益納付を求めない形になったと考えられます。
収益納付の撤廃で起こり得る影響・メリット

収益納付が撤廃されることにより、様々な影響がでると考えられます。例えば、補助金を受けた企業は収益納付による返還を気にせず、事業に集中できる点です。
また、収益納付によって補助金を返納しなくてはならないことから、補助金制度の利用を躊躇する企業もあったと考えられます。
しかし、収益納付が撤廃されたことで、これまで躊躇していた企業も補助金活用のハードルが下がり、申請者が増える可能性も高いです。
さらに、収益納付が撤廃されれば補助金を使って得た利益をすべて自社のために使えることから、企業の経営戦略もより柔軟なものになり、資金繰りが改善したり新しい事業投資を促進できたりします。
企業側はもちろん、国側にとっても中小企業の経営が改善されることで経済活動も活発になるなどのメリットが期待できます。
収益納付の対策方法
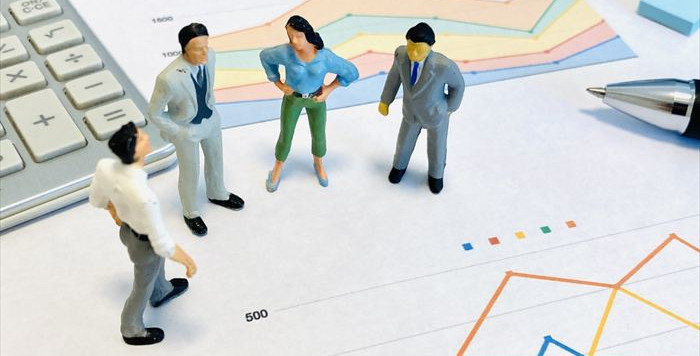
ものづくり補助金や新事業進出補助金の収益納付は2025年4月から撤廃されます。
しかし、その他の補助金制度にはまだ収益納付があったり、すでにものづくり補助金などに採択された事業者は収益納付による返納が必要だったりします。
そこで、経営者が行える収益納付への対策方法についても解説していきましょう。
計上する売上・経費を精査する
ものづくり補助金や新事業進出補助金の前身となる事業再構築補助金といった、国が実施する大型の補助金制度の場合、計上する収益や経費を精査することで収益納付の返納額を減らしたり、収益納付自体を回避できたりします。
収益納付の対象となるのは、会社全体の売上げや経費ではなく、補助金制度を活用した事業のみが対象です。
そのため、事業化状況報告書を作成して収益納付の発生が考えられる場合には、補助金制度を活用した事業と関係ない事業の売上が含まれていないか、経費の計上漏れがないか精査することが大切です。
補助事業期間を短縮させる
多くの補助金制度は事業計画期間を3~5年に設定しています。
例えば、ものづくり補助金や事業再構築補助金は補助金を受けてから3~5年間で事業計画を実施し、毎年事業化状況報告を行うことが義務付けられています。
事業計画を5年に設定した場合、収益納付の算定期間も5年間になるため、収益納付を行う可能性が高まるでしょう。
そのため、極力収益納付をしなくても良い状況にするためには、事業期間を短縮して計画することがポイントです。
ただし、事業期間を短縮した結果、計画の時点で十分な収益が見込めないと判断されてしまった場合、そもそも不採択となる可能性が高いです。
収益納付の対策を講じる目的で不自然な事業計画にならないよう、注意してください。
専門家に相談する
収益納付の発生が見込まれる場合には、中小企業診断士などの専門家に相談するのもひとつの方法です。
補助金制度に詳しい中小企業診断士などに相談すると、補助金事業とは関係ない売上げが含まれていないか、算定に含められる経費がないかなどをプロの視点から見直してもらえます。
自分で確認するよりも確実にチェックしてもらえるため、本来返納する必要のない収益納付も回避することができます。
また、相談先によっては事業化状況報告書の作成を代行してもらうことも可能です。
事業化状況報告書の作成が不安な人は、専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
まとめ・収益納付の撤廃は事業者にとってメリットが大きい!
収益納付は補助金制度において、利益がでた際に返納することを指します。
補助金制度を活用した企業にとっては、せっかく利益がでても収益納付によって一部返納しなくてはならないため、補助金制度の申請自体を躊躇していた人もいるかもしれません。
しかし、2025年4月からものづくり補助金や事業再構築補助金の後継となる新事業進出補助金で収益納付が撤廃されたため、申請のハードルは低くなったといえます。
事業者にとって収益納付が撤廃されたことで、でた利益を事業拡大や次の投資に使えるようになるなどメリットも大きいため、補助金をうまく活用して利益を上げていきましょう。
創業手帳では起業家・経営者の方がよく使われている補助金助成金を厳選して解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。3ヶ月に1度内容を更新し最新情報をお届け。こちらもあわせてご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)