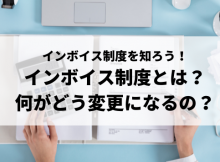インボイス制度2年目で2割特例はどうなる?確定申告の注意点も含めわかりやすく解説
2割特例で確定申告も安心!インボイス制度2年目のポイント解説

今年も確定申告の季節がやってきました。インボイス制度に登録している方の中には、「インボイス制度2年目は、1年目とどう違うのだろう」と悩まれている方もいるかもしれません。
そこで本記事では、インボイス制度に登録して2年目の方が確定申告する際に知っておきたいことをまとめてご説明します。
創業手帳では確定申告の基本をまとめた「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。所得税についてはもちろん、消費税の申告についても掲載。2割特例を始めとした、3種類の計算方法についてもわかりやすく解説しています。あわせてご利用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
インボイスの2割特例をわかりやすく解説。計算方法も

インボイス制度における2割特例についてご説明します。
2割特例とは、事業者の消費税納税額を簡易的に計算できる制度です。通常の計算方法ではなく、売上にかかる消費税額の20%を納付することで済む特例措置となっています。
例えば、売上が税抜き100万円(税込み110万円)だったとすれば、売上にかかる消費税額は10万円なので、2割特例で支払うべき税額は10万円の2割で2万円のみです。
この制度が創設された主な背景には、インボイス発行事業者登録の低調な普及率があります。インボイスを発行するためには、事業者は必ず消費税の課税事業者になることが求められます。この要件により、多くの事業者は「課税事業者としてインボイス制度にも登録し消費税を納付する」か「免税事業者のままインボイス制度に登録しない」かの選択を迫られることになりました。
特に個人事業主の間では、確定申告の事務負担増大や新たな納税義務の発生を懸念し、インボイス発行事業者への登録を見送る動きが広がっていました。2割特例は、こうした事業者の負担を軽減し、インボイス制度への参加を促進するために導入されたものです。
2割特例の適用期間はいつまで?個人事業主と法人で違いも
2割特例制度の適用期間は、事業形態によって異なります。個人事業主と法人では、それぞれ異なる期間が設定されているため、各事業形態に応じた適用期間について詳しく見ていきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、会計期間は暦年(1月1日から12月31日まで)に統一されています。これに合わせて、2割特例の適用期間も全ての個人事業主に対して同一の期間が設定されています。
具体的には、必要な要件を満たしている個人事業主であれば、2023年10月から2026年12月末までの3年3カ月間、この特例措置を利用することができます。

引用:国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
ただし、注意すべき重要な点があります。適用期間中であっても、年間売上高が1,000万円を超過するなど、定められた要件を満たさなくなった場合は、その時点で特例の適用が終了します。そのため、事業規模の変動には特に注意を払う必要があります。
法人企業の場合
法人企業における2割特例の適用期間は、各社の決算月に応じて異なる特徴があります。適用期間の長さは決算月によって大きく変動し、その違いは事業運営に重要な影響を及ぼす可能性があります。
特に注意すべきは、9月決算企業の状況です。これらの企業は最長でも3年間しか特例を利用できないため、他の決算月の企業と比べて相対的に不利な立場に置かれています。
一方、8月決算企業にとっては最も有利な制度設計となっており、最長で3年11カ月という長期間にわたって特例を活用することができます。この決算月による適用期間の違いは、個人事業主の一律な適用期間とは大きく異なる特徴です。

引用:国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
重要な点として、法人企業の2割特例は2026年9月30日を含む事業年度をもって終了することが定められています。この終了時期は全ての法人企業に共通する期限となります。
2割特例の対象者とは?対象外となるケースも解説
インボイス制度の2割特例の対象者については、明確な要件が定められています。
この特例を利用できるのは、インボイス制度の開始を機に、それまでの免税事業者から新たにインボイス発行事業者(課税事業者)に移行した事業者です。具体的には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、そしてインボイス発行事業者として登録していることが条件となります。
インボイス発行事業者への登録は、事業者の任意選択となっています。しかし、この選択は取引関係に大きな影響を及ぼす可能性があります。登録しない場合、適格請求書(インボイス)を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなり、結果として取引先の納税額が増加することになります。
なお、独占禁止法により、取引先にインボイス発行事業者への登録を強制することは禁止されています。ただし、この制度が今後の取引形態や取引関係に実質的な影響を与えることは避けられない状況といえます。
2割特例には対象外となるケースが存在します。特例を利用できない事業者として、以下のような状況が定められています。
・基準期間もしくは特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
・基準期間と特定期間の課税売上高は1,000万円以下でも、課税事業者選択届出書を提出して2023年10月1日以前から課税事業者になっている場合
・課税期間を短縮している場合
ただし、2つ目の条件については重要な例外規定があります。2023年10月1日が属する課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出した場合は、2割特例の適用対象となります。
この制度の本質は、インボイス制度への登録を契機として課税事業者に転換する事業者の負担を軽減することにあります。そのため、制度適用の可否は、この目的に沿って判断されることになります。
開業2年目、2割特例や消費税の免税はどうなる?適用条件を解説
開業2年目における消費税の取り扱いについて、2割特例の適用条件と消費税の免税条件は、個人事業主にとって重要なポイントです。それぞれ詳しく解説します。
開業2年目で2割特例は適用されるのか?
2割特例は、インボイス制度の開始に伴い、免税事業者から新たにインボイス発行事業者(課税事業者)に移行した事業者を対象とした制度です。
適用条件
・基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
・インボイス発行事業者として登録していること
・2023年10月1日から2026年9月30日までの期間に、免税事業者からインボイス制度に新規登録し、課税事業者に移行した事業者であること
これらの条件を満たせば、開業2年目であっても2割特例を適用できます。
また特例の適用開始時期は、インボイス制度への登録を完了した事業年度からとなります。
開業2年目は消費税は免税されるのか?
会社設立時における消費税の納税義務については、特別な免除規定が設けられています。新設法人の場合、通常は設立から2期目までの期間について、消費税の納税が免除されます。
さらに、まず個人事業主として開業し2年間の消費税免除を受けた後、法人化して追加で2期分の免除を受けるという方法があります。この場合、最長で4年間にわたって消費税の納税義務を免除することが可能となります。
しかしながら、この免除規定には一定の制限があり、特定の要件に該当する場合には免除を受けることができません。そのため、事業計画を立てる際には、これらの要件について十分な確認が必要です。
また免税事業者のままではインボイスの発行ができず、取引できる企業が限られてしまう可能性もあります。
免税事業者のままでいるメリット・デメリットをきちんと把握しておきましょう。
インボイス登録をやめたらどうなる?
インボイス制度の登録をやめる場合、以下の2つのポイントに注意が必要です。
いつまでにやめたらいい?
インボイス制度の登録を失効させるためには、所定の期日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
2025年からインボイスを失効させたいなら2024年12月17日までに届出の提出が必要でした。もし、2025年度でインボイスを失効させたいなら、2025年12月17日までに届出の提出が必要です。
この期限を過ぎてしまうと、翌年度の確定申告までインボイス制度の登録が継続されることになります。
一度登録をやめたらどうなる?
インボイス制度の登録を取り消して再度登録する場合、「2年縛り」と呼ばれる制限が発生する場合があります。
2年縛りとは、免税事業者から課税事業者に移行する際、「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみを提出し、「課税事業者選択届出書」を提出しなかった場合に適用されるルールです。一度インボイス制度を取り消して再登録する場合、2年間の継続義務が発生します。
この規定の実際の適用例を見てみましょう。2024年12月末でインボイス制度の登録を取り消した事業者が2025年に再度登録する場合、2027年12月末まではインボイス制度から離脱することができません。さらに具体的な例として、2025年1月3日に再登録した場合、2025年1月3日から2027年12月31日まで、すなわち2年11ヶ月29日間の消費税納税義務が継続します。
ただし、例外的に2023年10月の制度開始時に免税事業者から課税事業者に移行した場合は、この2年縛りは適用されません。そのため、将来的に課税事業者やインボイス制度への再登録を予定していない事業者は、現時点で登録を取り消すことも選択肢として考えられます。
インボイス制度の登録を続けるメリット

インボイス制度の取り消しを考えている方に向けて、あらためてインボイス制度に登録し続けるメリットをご紹介します。
課税事業者の場合、2割特例で消費税の負担が軽減する
インボイス制度における2割特例は、課税事業者の税負担を大幅に軽減する効果があります。通常の消費税率と比較して低い税率で計算・納税できるため、特にインボイス未登録事業者との取引においても、税負担を抑えることが可能となります。
この軽減措置は、企業の財務面に複数のメリットをもたらします。税負担の軽減は直接的な資金繰りの改善につながり、経営の安定性を高めることができます。また、手元資金の確保が容易になることで、事業運営における柔軟性も向上します。
BtoBの場合、顧客から好印象を持ってもらいやすい
インボイス制度に登録した小規模事業者の多くが、BtoBビジネスをしている事業者でしょう。顧客にストレスを与えずに事業を続けるためには、インボイス制度に登録するという選択肢を取る方がベターだからです。
インボイス制度の登録を続けるデメリット
インボイス制度の取り消しを考えている方に向けて、インボイス制度に登録し続けるデメリットをご紹介します。
余計に消費税を払っている
従来までであれば、売上1000万円以下の個人事業主は消費税を免税されていました。しかし、インボイス制度が開始されたことで、売上1000万円以下の事業者であっても、取引先への考慮などから課税事業者になった事業者が増えました。課税事業者でなければ、インボイス制度事業者になれないためです。
つまり、インボイス制度に登録しなければ消費税を納税しなくて済んだにもかかわらず、インボイス制度に登録したことで消費税を余計に支払っているのです。
業務が複雑になる
インボイス制度における2割特例の導入は、事業者の実務面に新たな課題をもたらします。通常の課税取引と2割特例対象の取引を適切に区分して管理する必要が生じるため、税額計算の複雑化や請求書作成業務の煩雑化が避けられません。
このような実務の複雑化に伴い、税務処理の正確性がより一層重要になります。税額計算や申告において誤りが発生した場合、税務上のペナルティが課される可能性があるためです。そのため、事業者は従来以上に慎重な税務管理体制を構築し、正確な処理を徹底することが求められます。
インボイス制度の2年目も2割特例を活用しましょう

インボイス制度2年目の方に向けて、2割特例の適用条件や計算方法、注意点などについて解説しました。2割特例は、インボイス制度開始に伴う負担を軽減するための有効な手段です。ぜひ本記事を参考に、2割特例を賢く活用して、確定申告をスムーズに乗り切ってください。
インボイス制度や確定申告について、さらに詳しい情報を知りたい場合は、国税庁のWebサイトや税務署の相談窓口をご利用ください。
創業手帳では確定申告の基本をまとめた「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。所得税についてはもちろん、消費税の申告についても掲載。2割特例を始めとした、3種類の計算方法についてもわかりやすく解説しています。あわせてご利用ください。

(編集:創業手帳編集部)