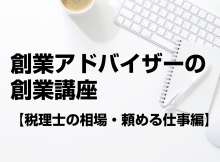倒産と破産の違いは?意味や手続きの流れなどをわかりやすく解説
倒産と破産の違いを理解しよう

会社が経営破綻した場合、倒産や破産を検討することが必要です。倒産と破産はよく混同されますが、正確には意味合いが異なります。
そこで今回は、会社の倒産と破産の違いや破産を選択するメリット・デメリット、手続きの流れ、そのほかの倒産手続きの種類などについて紹介します。
いざ経営破綻になった時、スムーズな決断や必要な手続きを済ませるための備えとして参考にしてください。
この記事の目次
会社の倒産と破産の違いとは?

経営破綻の際によく登場する倒産や破産という言葉は、それぞれ明確な違いが存在します。
まずは、倒産と破産のそれぞれの意味から具体的な違いを紹介します。
倒産とは
倒産に法的な定義は存在しませんが、一般的な意味は業績の悪化などで負債の返済が困難になり、事業活動が困難になった状態です。
銀行との取引停止処分を受けたり、代表が倒産を認めたり(内整理)、裁判所で各種倒産手続きを行ったりすれば倒産とみなされます。
倒産は、清算型と再建型の2種類に分けられます。清算型は破産や特別清算によって、会社を消滅させる倒産方法です。
再建型は、会社更生法や民事再生法によって事業を続けながら債務弁済をしていく倒産方法となります。
破産とは
破産は倒産とは異なり、法律で明確に定義されています。
その意味は、すべての財産を債務の返済に充てて、返済しきれなかった部分を帳消しにして会社を消滅させることです。
つまり、破産は会社を倒産させる手続きのひとつです。
債務超過で事業の継続が困難になった場合、破産手続きを行うことで負債が免除されます。
保有している財産や事業はすべて清算され、破産管財人が債権者に向けて公平に会社の財産・事業を分配する仕組みとなっています。
会社の倒産で破産手続きをするメリット

会社の倒産方法は複数ありますが、破産手続きを選択することには以下のメリットがあります。
債務の消滅で資金繰りの悩みがなくなる
破産手続きを行うと、返済しきれない債務が消滅します。今まで返済をするために資金繰りに悩んでいた会社は、その悩みから解放されることが大きなメリットです。
再建型の倒産手続きの場合、会社の業績を回復させながら弁済していく必要があるため、資金繰りに悩まされる可能性があります。
しかし、破産手続きは清算型となり、会社の財産や事業を清算した上で会社を消滅させることを前提としているため、今後資金繰りに悩む必要がなくなります。
債権者への対応が不要になる
破産手続きは裁判所を介して行う手続きであるため、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士は債権者に受任通達を送り、それ以降の督促は弁護士が窓口になります。
会社の経営者が債権者に対して対応する必要がなくなるので、精神的な負担を軽減できます。
また、破産が法的な手続きであるため、債権者から納得を得られやすいこともメリットです。
裁判所によって選任された破産管財者が公平に財産を分配するため、債権者が一方的に不利になることがありません。
代表者個人の債務が免除される
会社の債務に対して、代表者本人が連帯保証人になっているケースがほとんどです。その場合、会社が債務を支払えないと債権者は代表者に返済を求めることができます。
しかし、破産手続きでは代表者も同時に破産申し立てをするケースが一般的です。
会社を消滅させ、さらに代表者の連帯保証も免責されるので、債務を弁済する必要がなくなります。その結果、代表者本人は会社が倒産しても経済的な再建を目指せます。
従業員や取引先などへの迷惑を最小限に抑えられる
破産手続きは、従業員や取引先などの関係者に対する迷惑を最小限に抑えられるメリットがあります。
例えば、会社が給与を支払えない状況でも未払賃金立替払制度を利用できるため、従業員は給与の一部を受け取ることが可能です。
速やかに破産手続きをすれば、取引先側の不良債権が増えるのを押さえられます。
そして、取引先は早期に貸倒れ処理ができるため、リスクに備えた適切な経営判断がしやすくなります。
会社の倒産で破産手続きをするデメリット

破産手続きには多数のメリットがある一方で、デメリットがあることを理解しておく必要があります。そのデメリットは以下のとおりです。
法人格の消滅で事業を継続できない
破産手続きは法人格を消滅させることを前提にした倒産方法となります。そのため、手続きが完了すれば事業を継続することができません。
改めて同じ商売を行う場合、一から会社を興す必要があります。
会社を継続して債権の負担を軽減させたいのであれば、再建型の倒産手続きを検討することが求められます。清算型の破産手続きを選択する際は、慎重に検討してください。
連帯保証人の個人資産も失われる
会社の債務の連帯保証人が取引先や取引先の代表者・役員など、当該会社の代表者以外となっているケースがあります。
その場合、破産手続きによって連帯保証人の個人資産は失われてしまう可能性があるので注意が必要です。
破産によって会社に返済を要求できないと、債権者は連帯保証人に弁済が求められるので、迷惑をかけることになります。
また、連帯保証人も会社と一緒に破産の申し立てを行うと、個人資産の一部を売却処分しなければならず、資産を失うことになります。
代表者に対する信用度が低下する
破産手続きを行った代表者は、信用情報機関に7年間ほど、破産したことが登録されます。
事故情報となるため、住宅ローンなど借入れが困難になったり、クレジットカードを新規作成したりすることができなくなります。
また、破産した事実は従業員や取引先などの関係者に通達しなければなりません。
債務を完済できず会社が消滅することから、会社や代表者に対して世間からの信用は大きく低下してしまいます。
破産後、新しく会社を設立しても信用回復にはかなりの時間と労力がかかり、なかなか事業が軌道に乗らないかもしれません。
破産手続きの流れ

会社の破産手続きは、以下の流れで行われます。具体的な流れを紹介します。
1.破産申し立て
破産手続きが複雑なので、弁護士に依頼するのが一般的です。破産手続きに詳しい弁護士に相談し、申し立ての準備を進めてください。
手続きの際には会社の全部事項証明書や賃借対照表・損益計算書など数多くの書類が必要です。弁護士に確認しながら必要な書類を用意してください。
法人の破産手続きの場合、くれぐれも混乱を招かないためにも迅速かつ内密に進めていくことが大切です。
債権者に対しては弁護士が受任通知を行うため、返済の督促を止めてくれます。
また、破産手続きの前に全従業員の解雇が必要です。説明会を行い、倒産や解雇の事実、給与や社会保険の手続きなどに関する説明を行ってください。
2.破産手続き開始・破産管財人の決定
弁護士が破産手続き開始申立書など作成して、裁判所に提出します。申し立てが認められると官報に破産開始の決定が掲載され、手続きを進める破産管財人が決まります。
破産管財人は会社と無関係の弁護士から選出され、法律に従って調査や債権者への配当などの業務を行う人です。
清算手続きをすべて代行してくれるので、代表者が勝手に処分したり、債権者が財産の差し押さえ・強制執行したりすることができなくなります。
3.会社の財産の換価
財産の換価とは、債権者に債務を返すために会社の資産を現金化することです。
破産手続きを行うと、破産法第34条によって会社の財産のすべては破産財団に属することが定められています。
個人の破産手続きでは、破産後も所有できる財産を認める自由財産制度が存在します。しかし、法人の場合はないので、破産開始後は勝手に財産を処分できません。
破産財団に属した財産は、破産管財人を通じて換価処分されます。
4.債権者集会で説明
破産手続きの開始決定から2~3カ月後に債権者集会が開かれます。
この場では、破産に至った経緯や今後の手続きなどについて確認や説明が行われ、さらに裁判所が必要な決定を行います。
実際に債権者が集まるケースは少なく、裁判官・破産管財人、会社の代表者、会社の代理人弁護士で行われるのが一般的です。
また、集会の回数は通常1回ですが、2回以上にわたって開催されるケースもあります。
5.債権者に資金を配当
換価処分によって得た資金は、税金、社会保険料、未払い賃金などに充てられます。また、余った資金は債権者に対して債務の額に合わせて配当されます。
ただし、資金がほとんど残らない場合は配当自体行われません。
また、配当される場合、抵当権が設定された債権を持つ債権者が優先されるため、ほとんど配当を得られないケースもあるでしょう。
支払いや配当が完了すると破産手続きの完了です。これによって会社と事業は消滅し、債務から解放されます。
破産以外の倒産の手続き

倒産の手続きは複数あるため、破産が妥当とは限りません。ほかにも民事再生・会社更生・特別清算の3つがあるので、それぞれの特徴を紹介します。
民事再生
民事再生は、債権者の同意を得て債務の一部を圧縮し、完済を目指す手続きです。こちらは再建型の倒産手続きとなるため、会社を存続しながら債務の返済を目指せます。
会社と消滅させたくない時や債務の圧縮によって対処できる場合に適しています。
民事再生であれば債務の額を大幅に圧縮でき、また弁済期間も最長10年まで延長可能です。
また、民事再生の申し立てが金融機関に通知されると、口座に入っている預金で債務を相殺させることが禁じられるため、再建に必要な資金を確保できます。
監督委員の設置が必要となりますが、経営陣を一新させず、経営権を維持させることもメリットです。
会社更生
会社更生は、株式会社のみが利用できる会社更生法に基づいた裁判手続きです。債務を圧縮すると同時に新しいスポンサーを得て、再建していきます。
具体的には裁判所が更生管財人を選定し、その管財人主導のもと、更生計画が策定・遂行されます。
更生計画では担保権者や株主の権利を制約でき、合併や増減資などの組織編成も簡易的に行えるのが特徴です。
しかし、株式がすべて無価値となってしまうため、新しいスポンサーが株主となり、特別な事情がない限り代表取締役が交代するのが通常です。
この性質から単独オーナーや同族経営が多い中小企業では、あまり選ばれない倒産手続きになります。
特別清算
特別清算は、破産手続きと同じく裁判所を通じて清算を行う手続きです。会社法に基づいて行われる手続きであるため、利用できるのは株式会社のみとなっています。
また、破産手続きに比べて比較的簡易的に会社の清算ができます。
破産との大きな違いは、手続きを進める人物です。破産手続きでは、裁判所によっては破産管財人が選任され、手続きを行います。
一方、特別清算は代表者が特別清算人となり、主体的に手続きを進めることが可能です。
ただし、債権者の同意を得ないとできないので、破産よりもハードルが高くなるかもしれません。
倒産・破産のよくある質問に回答します

ここからは会社の倒産・破産に関するよくある質問をピックアップして紹介します。
債務整理と破産の違いは何ですか?
債務整理は、再建を整理する方法の総称です。つまり、債務が消滅する破産は債務整理のひとつといえます。
債務整理というと、一般的には任意整理を連想するケースが多いです。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行い、債務の減額を求める方法になります。
それに対して、破産は裁判所を介して債務の全額を免除してもらうことが可能です。
債務超過で返済しきれない場合、債務の負担から解放されるなら法人格はなくなりますが、破産が有効といえます。
株式会社は会社更生ができますが、小規模事業者でも利用できる再生手続きはありますか?
小規模事業者は個人再生という形で債務整理が可能です。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
小規模個人再生は、裁判所の認可を受けて再建を5分の1から10分の1に減額して、原則3年間で返済するように再生計画を立てるという手続きです。
給与所得者再生も裁判所を介して債務を大幅に減らせる手続きですが、小規模個人再生のほうが減額率は高い傾向にあります。
どちらが適しているかはケースバイケースであるため、司法書士や弁護士などの専門家と相談して検討するのがおすすめです。
破産した場合、店舗兼住宅や事務所兼住宅はどうなりますか?
自分が所有する店舗兼自宅や事務所兼自宅は、破産手続きにおいて処分の対象となってしまいます。
そのため、破産手続きが開始する前に転居先や資金を確保し、準備しておかなければなりません。
なお、賃貸住宅であれば自分が所有する不動産ではないため、引き続き住み続けることが可能です。
ただし、滞納している家賃も破産手続きに含めている場合、その家賃も免責の対象となるため退去が必要です。
破産した場合、賃貸物件は契約できますか?
破産した場合でも新たに賃貸物件を契約することは可能なため、転居できないというはありません。
ただし、破産後は7年程信用情報機関に事故情報が記録されます。
そのため、家賃の支払いをクレジットカードにする際や信販系の家賃保証会社を利用する場合、審査を通過できないために入居できない可能性があります。
特に家賃保証会社の審査に落ちた場合、連帯保証人を確保する必要があります。
まとめ・会社の倒産・破産の悩みは専門家への相談がおすすめ
会社の倒産方法は複数あり、破産はそのひとつです。破産手続きをすれば、超過した債務が免責されるので借金から解放されます。
しかし、会社の継続できなくなること、従業員や取引先などに迷惑をかけるので社会的信用が下がるといったリスクがあります。
破産が妥当な選択なのか判断したり、スムーズに手続きを行ったりするために弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
創業手帳(冊子版)では、企業のノウハウから倒産や債務整理など経営者が知っておくべき情報をお届けしています。創業期のサポートにご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)