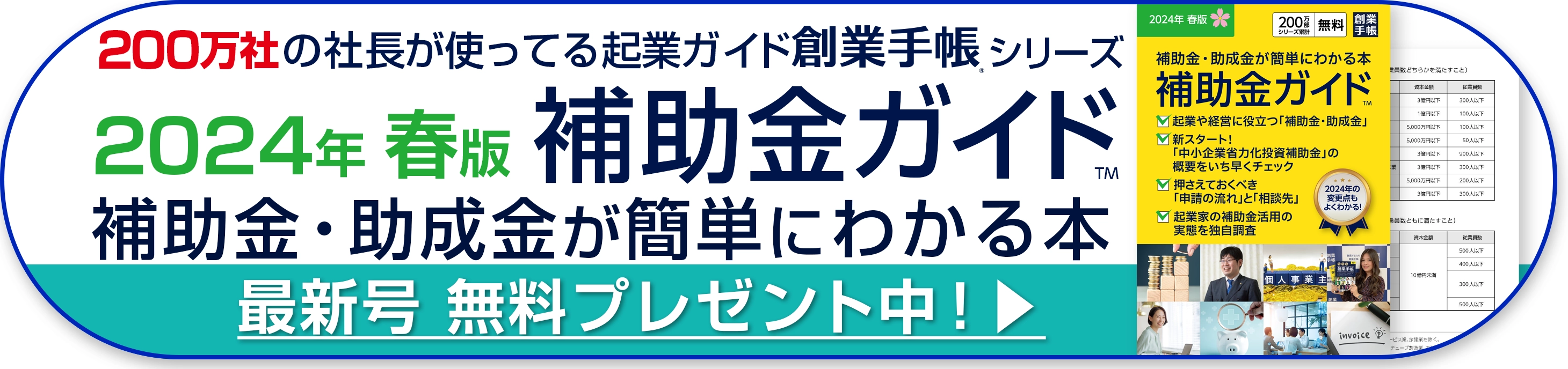観光農園の成功事例は?ブルーベリー観光農園などのメリット・デメリットをご紹介
観光農園とは?成功事例や農林水産省の定義、使える補助金、メリット・デメリット・課題などご紹介

昨今、起業・創業を考えている方にじわじわと人気が出てきている業態が、観光農園です。観光農園は観光ビジネスと農業のメリット両取りができるとして、起業家たちの間で話題になっているのです。本記事では、観光農園ビジネスの成功事例やメリット・デメリット、使える補助金などをまとめてご紹介します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
観光農園とは?農林水産省の定義も解説
観光農園とは、一般の人々が訪れて果物や野菜の収穫体験ができる農園のことです。
日本では「フルーツ狩り」や「収穫体験」という形で親しまれています。
季節ごとに異なる作物(イチゴ、ブドウ、リンゴ、サツマイモなど)を自分の手で収穫して楽しむことができ、多くの場合はその場で食べたり持ち帰ったりすることが可能です。
観光農園は家族連れや観光客に人気のレジャースポットであると同時に、農業体験を通じた食育の場としても機能しています。
また、農家にとっては副収入源となるだけでなく、都市部の人々が農業や食の生産過程に触れる貴重な機会を提供する場でもあり、地域の観光資源としても重要な役割を果たしています。
ちなみに、観光農園とは何か、その定義は農林水産省のホームページを見ると以下のように解説されています。
「観光農園とは、農業経営体が観光客等の第三者に、ほ場において自ら 生産した農産物の収穫等一部の農作業を体験又はほ場を鑑賞させ、 料金を得る事業をいう。」
引用:農林水産省
観光農園の市場規模は?
観光農園・貸し農園そのものの市場規模に関するデータはありませんが、農林水産省が行っている「6次産業化総合調査」によると、2018年度の農業生産関連事業による年間総販売金額は2兆1,040億円で、このうち観光農園は403億円となっています。
また観光農園では、事業体数は減少傾向となっていますが、年間販売金額は2014年度以降増加傾向にあります。
このデータから、個々の観光農園の経営効率が向上していることが推測され、少数の事業者がより大きな市場シェアを獲得していると考えられます。
これは農業体験型観光に対する消費者需要の高まりを反映していると同時に、経営規模の拡大や多角化によって収益性を高めている成功事例が増えていることを示唆しています。
観光農園の成功事例。ブルーベリー観光農園で成功した事例など

ブルーベリー観光農園
元デンソー社員の畔柳茂樹氏は、45歳で独立しブルーベリー観光農園「ブルーベリーファームおかざき」を開設しました。年間わずか60日の営業で年収2000万円を達成し、サラリーマン時代の収入を大幅に上回る成功を収めています。
畔柳氏によると、ブルーベリー観光農園の最大の特徴は、通常農業の最大の課題となる「収穫の手間」を、お客様に体験型レジャーとして提供することで逆に付加価値に変えている点です。女性や家族連れを中心に人気があり、農園側は収穫の人件費がかからず、お客様は通常高価なブルーベリーを安く、楽しみながら食べられるという双方にメリットがあります。
ブルーベリー栽培の特長としては、病虫害に強く育てやすい点、一度植えれば毎年収穫できる点、肥料や水やりも自動化できる点が挙げられています。このため農業未経験者でも比較的簡単に始められるとのことです。
畔柳氏は、サラリーマン時代のストレスから解放され、対人関係のストレスが少なく、収入が増え、定年がない点を起業の大きなメリットとして挙げています。また、自分の商品が直接お客様に喜ばれる実感がモチベーションになるとも語っています。
ブルーベリー観光農園を始めるには、まず郊外の集客しやすい立地を確保し、公的融資などで資金調達をすることが重要です。栽培設備は養液栽培システムを導入すれば資材業者がすべて請け負ってくれます。収穫は2年目以降になるため、最初は週末の副業として始めることもできます。集客にはホームページやGoogleマップの設定、Instagramでの発信が効果的だとアドバイスしています。
農業は未開拓市場であり、環境面でも魅力があることから、畔柳氏は起業の選択肢として農業、特にブルーベリー観光農園をおすすめされています。
畔柳さんのブルーベリー観光農園の成功の秘訣をもっと詳しく知りたいかたは、こちらの「ブルーベリーガイド」もぜひあわせてお読みください。
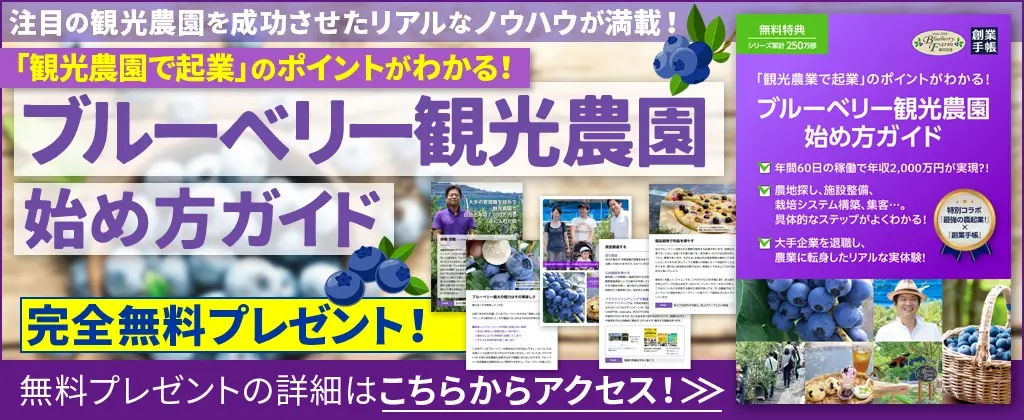
平田観光農園
広島県三次市の平田観光農園も独自の成功を収めています。中山間地域という立地にもかかわらず、年間16万人もの来園者を集め、そのうち約4,000人(2.5%)が外国人観光客という驚異的な実績を上げています。
平田観光農園の成功の秘訣は、日本最多となる150種類もの果物を栽培していることです。これにより香港人が好む大粒のイチゴやブドウ、東南アジアの人々が珍しいと感じるリンゴなど、各国の訪問客の好みに合わせた果物体験を提供できます。
また、国内外の商談会に積極的に参加し、旅行会社に地元の魅力をPRしていることも重要な戦略です。特に四国のお遍路と広島を組み合わせたルートが人気を集めており、都市圏だけでなく地方の観光ルートを開拓したい旅行会社のニーズとマッチしています。
平田観光農園が単なる果物狩り体験を超えているのは、フルーツピザ作り、月一のアウトドア体験、動物とのふれあい広場、ダッチオーブン料理など、多様な体験プログラムを提供している点です。加えて、海外からの農業研修生を受け入れており、帰国した研修生たちによるSNSでの情報発信が新たな来園者獲得につながっています。
現状では海外からのインバウンド客の受け入れは利益率の面では課題があるものの、長期的には農産物や加工品の輸出につながる投資だと考えられています。「巨大キノコ」などの話題性で度々メディアに取り上げられる平田観光農園の戦略は、立地条件に恵まれない農園が海外からの観光客を取り込むための参考となるでしょう。
観光農園はメリットたくさん!起業におすすめな理由

観光農園が人気な理由は、そのメリットからです。以下では、観光農園のビジネスとしてのメリットをご紹介します。
収益の多様化と安定化
観光農園における収益の多様化と安定化は、単一の収入源に頼らない経営戦略の核心です。基本となる入園料・収穫体験料に加え、収穫した果物などを直接販売することも可能です。
さらに収穫物を活用したジャムやドライフルーツなどの加工品販売は、保存性を高めつつ季節外でも継続的な収入を確保できる手段となります。
自家製農産物を使ったカフェやレストランの併設は、滞在時間と客単価の向上に貢献するでしょう。
平田観光農園のようなフルーツピザ作りやダッチオーブン料理などの多様な体験プログラムは、天候不順時や収穫期以外の集客力維持に効果的です。
季節ごとのイベント開催や地域特産品も扱う直売所の運営、ECサイトを通じた全国展開なども収益源の拡大につながります。
安定化の面では、平田観光農園の150種の果物栽培のような品種の多様化、早生種から晩生種までの栽培による営業期間の延長、リピーター確保のための会員制度や予約システムの導入が効果的です。
また気象リスクへの対応として雨天対応施設の整備やハウス栽培の導入、さらに畔柳氏のような観光農園とセミナー事業の組み合わせなど複合的な経営戦略も、従来の農業が抱える季節性や市場価格変動のリスクを軽減し、持続可能な農業経営の実現に貢献します。
人件費削減
観光農園における収穫の人件費削減は、このビジネスモデルの最も革新的な側面の一つです。通常の農業では、特に果物や野菜の収穫作業は非常に労働集約的で、人件費が全体のコストの大きな部分を占めています。
ブルーベリーなどの小さな果実は一つひとつ手で摘む必要があり、畔柳氏のインタビューでも述べられているように「ブルーベリー農業の唯一にして最大のデメリットと言えるのが、収穫の手間がかかる点」です。これが市場でブルーベリーの価格が高くなる主な理由の一つでもあります。
観光農園では、この「収穫の手間」を逆転の発想で「体験価値」に変換しています。お客様自身が収穫作業を行い、その体験に対して料金を支払うという仕組みです。つまり、最大のコスト要因だった収穫作業が、収益を生み出す体験商品に変わるのです。
他のビジネス展開の可能性の多様さ
観光農園におけるオフシーズン活用の可能性は、年間を通した安定経営の鍵となります。収穫期が限られる農業の特性上、オフシーズンをいかに有効活用するかが収益性向上の重要な戦略です。
まず加工品製造と販売が基本的な活用法です。旬の時期に収穫した果物や野菜を使ってジャム、ドライフルーツ、ピクルス、果実酒などを製造し、オフシーズンに販売することで商品の寿命を延ばします。畔柳氏もブルーベリーの収穫期以外にジャムなどの加工品販売を行っています。
カフェやレストランの通年営業も効果的です。収穫期には新鮮な農産物、オフシーズンには保存加工した自家製品を使ったメニューを提供できます。季節ごとの限定メニューはリピーター獲得にも貢献します。
教育プログラムの展開も注目されています。学校の課外活動や企業研修、食育ワークショップなど、農業知識を伝える場として施設を活用できます。平田観光農園のようにフルーツピザ作りや料理体験のプログラムは年間を通して実施可能です。
農園の景観や施設を活かしたイベント開催も魅力的です。季節の花々を楽しむフラワーガーデン、紅葉狩り、クリスマスマーケット、雪景色を楽しむ冬のイベントなど、収穫以外の自然の魅力を提供できます。結婚式や撮影会場としての貸し出しも考えられます。
オンラインでの展開も重要な戦略です。畔柳氏のように農業セミナーをオンラインで開催したり、SNSを通じて農園の日常や農産物の成長過程を発信することで、オフシーズンでもファンとの関係を維持できます。
温室やハウス栽培の導入により、通常の収穫期を延長したり、オフシーズンにも一部の農産物を生産することも可能です。イチゴなどは季節外れの栽培で高単価販売の機会が得られます。
観光農園のデメリット・課題は何?

観光農園にはもちろん、ビジネス業態としてのデメリット・課題も存在します。以下でご紹介します。
季節・天候への依存
観光農園は収穫期に大きく依存しており、営業期間が限られます。悪天候は来場者数に直接影響し、台風や長雨などで収穫期のピーク時に営業できないと年間収益が大きく落ち込む可能性があります。また天候不順による収穫不良は体験品質にも影響します。
初期投資と維持コストの高さ
土地の取得や整備、栽培設備の導入、駐車場やトイレなどの来客用施設整備には多額の投資が必要です。農園の美観維持や安全確保のための定期的なメンテナンスコストも発生します。
集客の難しさと競合
立地条件が集客に大きく影響します。中山間地域など交通アクセスが悪い場所では、平田観光農園のような特別な魅力がないと集客が難しくなります。また、観光農園の増加により競合も激しくなっています。
食品安全と責任問題
お客様が直接収穫・飲食する場であるため、農薬管理や安全性確保に細心の注意を払う必要があります。事故や食中毒などのリスク管理も重要な課題です。
観光農園が使える補助金は?
観光農園事業は「事業再構築補助金」の補助対象となっていました。現在まで多数の採択事例が確認されています。しかし、「事業再構築補助金」は募集が終了してしまいました。
そして、その後継となる補助金と見られているのが、「新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進事業)」です。令和7年から新に始まる「新事業進出補助金」は、中小企業が既存事業とは異なる分野へ前向きに挑戦し、新市場開拓や高付加価値事業への進出を支援する制度で最終的には賃上げにつなげることを目的としています。
公募開始は2025年4月からの予定であり、多くの事業者から注目を集めています。補助率は事業費の1/2、最大9,000万円という高額な補助が受けられるのが特徴です。
この補助金は単なる農業事業ではなく「新しい市場への進出」や「付加価値の向上」を重視しているため、観光農園の新規展開は補助対象となる可能性が高いと考えられます。実際に、本補助金の前身である「事業再構築補助金」においても観光農園は補助対象として認められていました。
この補助金を活用することで、収穫体験だけでなく、農産物を活用した加工品の製造・販売や飲食サービスの提供など、観光農園の収益多様化と付加価値創出を効率的に実現できます。これにより年間を通した安定経営の基盤を少ない自己負担で構築することが可能になります。
他にも、以下のような補助金の活用事例があります。
・福島県「鏡石町新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした農産物直売所等の対策費用の補助」
・兵庫県「まちなか農園開設支援事業」
・佐賀県「さが農村ビジネス総合支援事業」
観光農園で起業し、成功しましょう

以上、観光農園の成功事例やメリット・デメリット、使える補助金などをご紹介しました。
創業手帳では、観光農園の開業でも使える補助金・助成金について解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。こちらもあわせてお読みください。

(編集:創業手帳編集部)