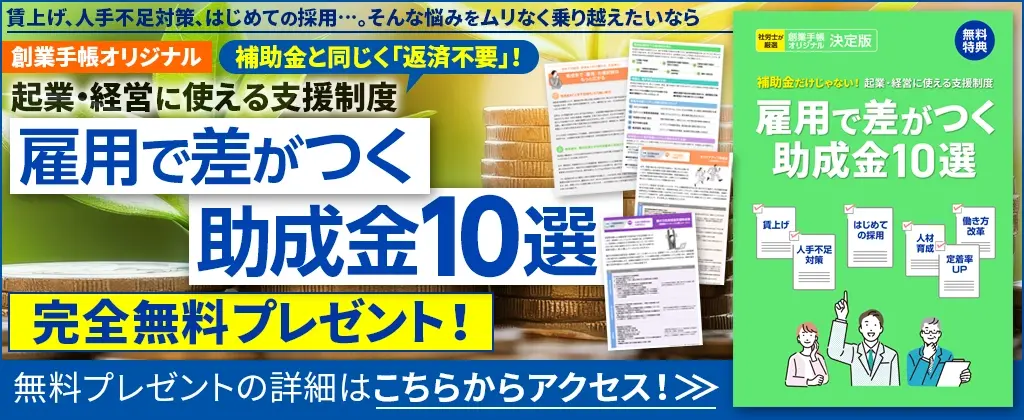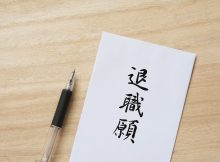リベンジ退職とは?攻撃的な離職の兆候&企業の防止策を解説
リベンジ退職で企業が深刻なダメージを負う可能性がある

「会社を辞めたい」と感じたことがある人もいるでしょう。
本来なら退職手続きを済ませる人も多くいるかもしれませんが、中には「リベンジ退職」といい、会社や上司への不満を仕返ししてから退職するケースもあります。
Z世代を中心に会社への仕返しを行うリベンジ退職が広まっていますが、企業側は深刻なダメージを受ける可能性が高いです。
今回は、リベンジ退職の特徴と一般的な退職との違いをはじめ、リベンジ退職の兆候やリベンジ退職によって企業が受ける影響について解説します。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
「リベンジ退職」とは?通常の退職との違い

「リベンジ退職」は、職場の環境や上司、待遇などに対して、意図的に損害を与えたり業務を停滞させたりして退職することです。
リベンジ退職は企業に対するネガティブな感情がむき出しの状態で、報復という意味合いが強くなります。ここでは、リベンジ退職の詳しい内容を解説します。
一般的な退職(転職・キャリアアップ型)との違い
一般的な退職の場合、退職の通知期間である1カ月以上前には退職や転職の意向を会社側に示さなければなりません。
上司や同僚との関係性が良好であれば、滞りなく退職に向けて準備することができます。
一方、リベンジ退職は、感情的・報復的な動機で行動に出る点が最大の特徴です。
退職通知を突発的にすることが多く、会社を辞める前日に通知するケースもあります。業務に関する引き継ぎが一切できず、企業と断絶に近い形です。
リベンジ退職の具体例
リベンジ退職の具体例は以下のとおりです。
-
- 突然退職の意思を示して話を聞かない
- 上司に「あなたのせいだ」といってそのまま辞める
- 業務の引き継ぎを拒否して困らせる
- 企業の機密情報を持ち出してしまう
- 企業の悪口をSNSで発信する
- 繁忙期に退職する
- 同僚や顧客を引き抜く
このように、企業に対してのネガティブな感情が報復として現れることがほとんどです。
リベンジ退職は業務への支障、意図的な業務の引き継ぎをせずに困らせる、企業ブランドのイメージ低下、引き抜きによる直接的なダメージといったことが起こるため、企業にとってプラスになることはありません。
リベンジ退職が起きてしまう背景

ここからは、リベンジ退職が起こる背景をみていきます。
労働環境・条件への期待とギャップ
リベンジ退職が起こる背景には、労働環境や条件に対する期待やギャップがあります。
期待していた労働条件や労働環境ではなかったり、成果に対する評価がと不十分だったりすることが原因として考えられます。
理想と現実がマッチしていないケースは珍しくありません。そのため、従業員が何かしらのギャップを感じながら働いていることもあります。
ギャップの大きさは企業に対する不満を大きくさせる傾向があり、リベンジ退職を起こしやすいとされています。
コミュニケーション不足による意識のズレ
リベンジ退職は、コミュニケーション不足によっても起こりやすくなります。
上司や部下、同僚とのコミュニケーション必要不可欠ですが、円滑なコミュニケーションを取りにくい環境では小さなズレが大きくなってしまう可能性が高いです。
その結果、職場や上司に対する不満が生まれやすくなります。
職場の人間関係には立場の違いから価値観が異なったり、意識のズレが生じたりしやすいです。
これらが積み重なった時、蓄積された不満が爆発してリベンジ退職の原因になることがあります。
評価制度・人事対応への不満
従業員に対する評価は、リベンジ退職を起こす可能性を秘めています。
企業のために一生懸命働いて成績や結果を残してきたものの、それが適正に評価されていない場合は不満と同時に失望感を抱きやすいです。
わかりやすい評価制度を公表していない企業がほとんどであり、結果的にリベンジ退職が起こりやすくなります。
働き方に対する意識の変化
「ひとつの会社に長く勤務するのが美徳」という風潮がありましたが、現代ではこのような考え方は薄れていき、自分の目標やスキルアップなどを視野にした転職が当たり前になりました。
また、フリーランスとして働くことも注目されていて、企業への所属にこだわらない人も増えています。
今までは、このような働き方が浸透していたため、退職時にもできるだけ迷惑をかけないように時期を調整したり、退職の意思を企業側のタイミングで報告したりしていました。
しかし、転職先や今までお世話になった企業に迷惑がかかるという意識が薄れてきた結果、受けた理不尽さを退職で晴らすという考えも出てきたのです。
リベンジ退職を示す兆候とは?一般的な退職との違い

リベンジ退職の兆候として、「強い感情」「周囲への影響」が現れます。ここでは、リベンジ退職の兆候について解説します。
強い不満や不信感をあらわにする
会社に対して強い不満や不信感を持っている人は、それをあらわにすることが多いです。
強い不満や不信感の理由は、長時間労働による燃え尽き、成長機会の不足、評価制度の不透明さや不公平感、職場でのいじめやパワハラなどです。
単に不満を抱えているわけでなく、感情的になるとSNSなどに発信することもあります。
SNSは個人での発信が簡単にできるため、不満が多いと頻繁に書き込むかもしれません。このような様子が見られた場合は、リベンジ退職の兆候と捉えられます。
周囲との断絶・孤立傾向が高まる
リベンジ退職の兆候として、周囲とのコミュニケーションを避けたり雑談に入らなくなったりする様子がみられます。
孤立した行動は、退職の決意が決まるまで周囲に気づかれないようにしている可能性も考えられます。
特に、今まで積極的にコミュニケーションを取っていた人が周囲との関係を希薄にしている場合には、リベンジ退職を考えている可能性が高いです。
会社への「仕返し」と受け取れる言動がある
リベンジ退職の兆候として、会社への仕返しと感じる行動が増えます。
遅刻や早退、無断欠勤など、勤務態度が今までと変わるだけでなく、業務に対して真剣に取組まないことも増えます。
企業に対してダメージを与える行動がみられる場合は、リベンジ退職の可能性が高まっています。
退職後の行動に“報復性”や“計画性”がある
退職後の転職先が企業の競合相手や同業の場合は、報復性や計画性があるかもしれません。
競合会社に転職した場合、企業のノウハウや知識が流通してしまうことも考えられます。
また、退職してから企業について暴露系の投稿をするなど、次の一手を考えている場合もあります。
リベンジ退職による企業側の影響

ここからは、リベンジ退職による企業側の影響を紹介します。
業務の混乱・突発的な人材流出
リベンジ退職が起こってしまった場合、業務の混乱が起こる可能性が高いです。
2025年1月、大手企業の元社員が損害賠償を求められた裁判がありました。
元社員は最終出社日前日に勤務先の共有サーバー内に業務で必要なデータを含んだフォルダを退職日に削除するようにプログラムしていたのです。
企業側がファイル消失に気が付いた時はすでに復元可能期間を経過しており復旧できなかったため、無駄な人件費や時間が生じました。
元社員の男性には賠償金支払いが命じられました。大きな業務混乱を招いた事例です。
専門性が高い業務を担当していた社員が引き継ぎ期間を設けずに退職したり、わざと引き継ぎ資料を作らなかったりした場合、企業側には大きな影響が出てしまいます。
従業員のモチベーション低下・不安の連鎖
リベンジ退職が起こると、同じような不満や不安を抱えた従業員から会社に対しての不信感が高まりやすいです。
負の連鎖状態になってしまうと、企業組織自体のモチベーション低下や生産性の悪化などが起こり得ます。
採用・育成コストの増大
リベンジ退職をきっかけに他の従業員が退職すれば、欠員補充や新規採用に関わる採用コストや育成コストが必要です。
退職する人数が多いほど費用がかさむため、企業の財務状態は悪化しやすくなります。
また、採用活動を強化したり教育研修を実施したりすれば、さらに費用がかかります。なお、派遣会社を通じて人材を紹介してもらう場合にも手数料の支払いが必要です。
機密漏洩や顧客離れのリスク
リベンジ退職した元社員が、のちにSNSなどで企業の内部情報を書き込んだり、顧客リストなどを流したりする可能性があります。
機密情報の漏洩などが起これば経済的な損害があるだけでなく、内容によっては顧客離れを起こす可能性も高いです。
また、顧客情報を持ち出された場合には、売上に損害を受けやすくなります。
SNSなどでの悪評拡散・信用毀損
リベンジ退職をした従業員がいる場合、SNSなどで悪い噂や評判が拡散されるかもしれません。
従業員が企業側に対して不満を抱えていた場合、高い確率でこのような事態が想定されます。
SNSで悪い噂や評判が拡散されれば、企業やブランドに対するイメージも低下します。一度広まった悪評による影響が長く続いてしまうことも考えられます。
リベンジ退職を防ぐには?企業が行うべき具体策

リベンジ退職は気が付かないうちに起こる可能性もあります。ここからは、企業側が取るべき対策について解説します。
1on1を“安心して話せる場”にする仕組みづくりを実施
リベンジ退職が起こるきっかけは、企業側と従業員の間にできた認識の違いや不公平感です。
従業員と不安・不満・意識のズレをなくして心理的な負担を軽減させるためには、「1on1ミーティング」を取り入れてみてください。
ただの形式的な面談ではなく、上司や先輩が新入社員の不安や悩みに寄り添えるように行うことで、信頼関係を築きやすくなります。
「本音で話したら評価が下がるかもしれない」「どうせ改善されないだろうから意味がない」と考える社員が多くいますが、このような不安や不満はリベンジ退職を生みます。
定期的に安心して話せる仕組みを作ったり、第三者相談窓口の設置をしたりするなど、発言が評価に響かない社内環境作りが大切です。
一方的に感じさせない評価制度作り
リベンジ退職が起こるきっかけとして、評価制度の曖昧さが挙げられます。
評価制度を公表していても、適正な判断がされているのか不安に感じている従業員は一定数います。
会社や上司が認識している評価基準と従業員が評価してほしい成果がズレると、従業員はきちんと評価されていないと感じ、モチベーションの低下を招きます。
できるだけ評価基準を明確にする仕組みが重要です。
また、結果だけではなく過程も評価することで、従業員の様々な努力を評価できます。
上司に限らず同僚からの評価も判断材料にすることで、適正な評価につながりやすいでしょう。
キャリア支援・柔軟な働き方の導入
リベンジ退職を防ぐためには、キャリア支援のサポートや柔軟な働き方の導入など、企業側が新たな制度を取り入れることも必要です。
従業員の中には、単純に給与を得るためだけに働いているだけでなく、キャリアを築きたいと考えている人もいます。
キャリア開発支援が形式的な研修制度のみであれば、従業員は不満を抱えやすいです。
企業側は従業員それぞれのキャリア志向を汲み取ったり、能力が向上するような支援をしたりすることで、企業の持続的な発展や従業員のキャリア形成が実現します。
リベンジ退職が起きた時の対応とリスク管理

ここからは、リベンジ退職に対して企業が取るべき対応と、リスク管理について解説します。
退職後の法的リスクと専門家への相談
リベンジ退職では、退職者がSNS上で会社の内部情報を暴露したり、名誉を毀損する発言をしたりするケースも見られます。
感情的に反応するのではなく、まずは専門家へ相談してください。
投稿のスクリーンショットや情報漏洩に関する痕跡を記録した上で、弁護士や社労士に対応の可否を判断してもらいます。
なお、必要であれば名誉毀損や不正競争防止法違反などの法的措置を検討することも視野に入れてください。
社内・社外への影響を最小限に抑える
リベンジ退職が発生した際には、周囲の社員や取引先にも動揺が広がることがあります。
まずは、社内向けに事実を冷静かつ簡潔に共有し、「適切に対応している」という安心感を伝えることが大切です。
また、社外には不用意な情報発信を避けつつ、信用不安につながらないよう、担当変更やフォロー体制の強化を速やかに実施してください。
平静かつ迅速に動く姿勢が自社の信頼を守るための最善策です。
まとめ・リベンジ退職を未然に防ぐ組織を目指そう
リベンジ退職は、企業の体質や上司などに対する不満から、組織にダメージを与えて退職することです。
企業にとってもマイナスになる可能性は高いといえます。
リベンジ退職を減らすためには、企業側が職場環境の改善や公平な評価制度、キャリア開発支援などを行うことが大切です。
社員の定着や働きやすい職場づくりを進めるうえで、国の助成金制度を活用するのも一つの有効な手段です。
創業手帳では、人材の採用・定着・育成に役立つ制度を厳選した「雇用で差がつく助成金10選」を無料で配布中。
正社員化や職場環境改善、シニア・育児支援など、目的別に探しやすくまとめています。人が辞めない職場づくりの第一歩として、ぜひご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)