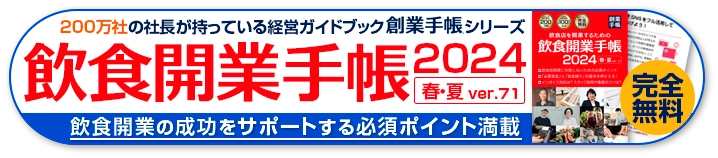飲食店の新メニューを開発する流れやポイントを徹底解説!
新メニュー開発を集客につなげよう

飲食店で新メニュー開発を行う場合、ただ目新しいメニューを考えるだけでなく、集客を意識して考えることも大切です。
しかし、集客だけを意識したメニューでは一時的な売上げは期待できても将来的な集客まで見込めるかわかりません。
そこで知っておきたいのがメニュー開発の基本から開発手順、メリットなどです。
この記事では、飲食店におけるメニュー開発の重要性に加えて手順やポイント、工夫などを解説します。新メニュー開発を検討している人はぜひ参考にしてください。
創業手帳が発行している『飲食開業手帳』では、 メニュー戦略に加え、資金計画・人材確保・制度対応など、開業に必要な知識やノウハウ を1冊にまとめています。開業準備や経営に不安を感じている方は、無料でお配りしていますのでぜひあわせてご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
飲食店におけるメニュー開発の重要性・メリット

飲食店では、メニュー開発についてどのように考えているのでしょうか。ここでは、メニュー開発の重要性に加えてメリットを紹介します。
新規顧客獲得につながる
メニュー開発は、飲食店独自の料理や飲み物などを企画、設計、改良していく流れです。
大きく分類すると「定番メニュー」と、イベントや季節に応じて提供する「期間限定メニュー」があり、安定した人気のあるメニューと新しさや限定感を提供できます。
単純に新しい料理やメニューを増やしていくのではなく、飲食店のコンセプトに合った商品を生み出すことで顧客満足度の向上も期待できます。
メニュー開発を行うことは、今まで通っていた常連客に対して飽きのこないメニューや新たな発見として楽しさを提供でき、新規のお客様に対しては新しさをアピールできるでしょう。
ここで、お店の存在は知っていたものの定番メニューを魅力的に感じなかった層に対しても訴求できます。
お客様にいつもの安心感を提供できると共に、新たな発見を加えることでリピーター率の向上も期待できます。
今までアプローチしていなかった客層からの注目も期待できるため、新規顧客獲得のチャンスも増えるでしょう。
既存顧客を飽きさせない
新メニュー開発を定期的に行うことで、既存顧客を飽きさせる心配も少なくなります。
その季節やイベントに応じたメニューを提供できれば、既存のお客様に楽しんでもらえるだけでなく、そこで人気になった場合は定番メニューにすることも可能です。
お客様の反応を見ながら新メニュー開発することで、お客様を飽きさせずにより常連になってくれる可能性も高いです。
また、新メニュー開発の際にお客様からの意見を取り入れた場合は、「意見を反映してもらえた」と特別に感じてもらえるので、より支持されやすい店舗になります。
収益性の最適化が図れる
メニュー開発によって、収益性の最適化を図ることができます。
新メニュー開発の際に現時点でのメニューの原価率、作業効率などの観点で分析し、改善すべき点や見直す余地のあるメニューを見つけなければなりません。
人気があっても利益率の低いメニュー、調理時間の手間や時間がかかるなど回転率が低いメニューを確認し、これらの改良や効率化のための作業について考えます。
ここで利益や作業効率などについて考え、高利益と低価格のバランスを保って配置すれば客単価の向上も期待できます。
飲食店の新メニューを開発する際の手順

飲食店で新メニューを開発する際には、以下の手順で行っていきます。この手順に沿って新メニューについて考えてみてください。
1.市場調査や既存メニューの分析を行う
飲食店で新メニューを考える際には、コンセプトや市場の調査がポイントです。
最初に顧客ターゲット層、競合の情報、ニーズ、立地の特性なども調査して分析してください。
現時点で顧客の嗜好に加えて、潜在的なターゲット層やこれらの層に好まれるものなども把握します。
ほかにも、飲食店の基本となるメニューなどのコンセプトについても再度洗い出しておくと、「お客様にどのような食事をしてほしいか」「どのような食材を味わってほしいか」などもはっきりしてきましょう。
2.新メニューのアイデアを出していく
次に新メニューのアイデアを出していきます。新メニューでは、食事を通してどのような体験をしてほしいか、どのような味や食材を楽しんでほしいかなどを考えます。
新メニューを考える際には、新規顧客の獲得、顧客単価アップ、リピート率向上などの面からも考えなくてはなりません。
既存メニューの傾向、顧客層なども分析して新メニューの評判が高まるようにします。
3.原価率・利益率を計算して価格を決定する
新メニューのコンセプトや名前などについて決まってきたら、原価率や利益率を計算して価格を決定してください。
原価率は、「原価率=原価÷販売価格×100」で計算できます。
使う食材の仕入れ価格を正確に把握して、1食あたりでどれくらい使うのかを考えます。
また、メイン食材だけでなく付け合わせや調味料なども計算する必要があり、この計算式に合わせて計算し、そこで原価率や利益率を考えてから販売価格の決定です。
価格が適正かどうか、価値に合っているかなどを確認してから決定します。
原価率の目安・計算例
原価率は、売上に対して食材など仕入れた金額を意味します。原価率が高くなると利益が少なく、原価率が低いと利益が多いという考えです。
先ほどの原価率の計算式を用いて、実際に計算してみます。
【原価150円の食材を使用、500円で販売した場合の原価率】
原価率=原価÷販売価格×100
150÷500×100=30%
飲食店では、原価率を30%以内にすることが望ましいと考えられていますが、すべての飲食店がこの条件に設定しているとは限りません。
特に高級食材や生鮮食材を常に扱っている場合は、食材を残すことができずに廃棄することもあります。
使用する食材などに合わせた原価率の目安を把握するために、上記の計算を参考にしてみてください。
4.レシピを作成して試作をする
新メニュー開発である程度の内容が決まったら、次にレシピを作成します。
レシピを作成する際に意識したいことは、味のバランス、盛り付け、仕込みにかかる時間、調理して提供するまでの時間などです。
味が濃すぎたり薄すぎたりしないように、何度も微調整を重ねてお客様にまた食べたいと思わせる味つけにします。
使う食材によっては盛り付けにもこだわり、見た目の美しさなども意識してください。
調理の際にはオペレーションに負担がかからず、わかりやすい作業工程を作り、提供するまでの時間が短縮できるようにします。
何度も試作を重ねて、最適なレシピを作り上げてください。
5.食材の仕入先を選定・コスト確認する
何度も試作を繰り返して納得のレシピになったら、食材の仕入先の選定を行います。
提供する価格を中心として、仕入値、品質、供給できる量などを確認し、いくつかの仕入業者を比較しながらピックアップしていきます。
この時は、金額以外にも品質にバラつきがないかも確認してください。
安定した価格と品質で調理するには、これらの点に注意する必要があります。
最近は、食材を提案して仕入れてくれる業者もいるため、その食材からインスピレーションを受けてメニューを考えることもできます。
ほかにも少量から食材の仕入れが可能か、優先して食材を仕入れてくれるかなども確認してください。
6.試食会を開いてフィードバックを得る
メニューとして提供できる形になったら、試食会を開いて多くの意見を聞いてみてください。
実際に試食してもらい、使用する素材の大きさや調理方法の変更をしていきます。
現場の人間以外も呼んで試食会を開催することでフィードバックを得られ、改良点も見つかりやすいです。
試食イベントやアンケート調査などを開催するのもおすすめです。
7.新メニューを投入・現場への落とし込みをする
新メニューのレシピや使う食材が決まったら、スタッフに作り方を指導して安定した品質や味にします。
安定したオペレーションとなるよう、メニューの下準備からスムーズになるようにしていきます。現場にきちんと落とし込んだ時、本物のメニュー開発が完了する流れです。
飲食店で新メニューを開発する際のポイント

飲食店に限らず、新メニューを開発するのは簡単なことではありません。そこで、飲食店において新メニュー開発時に意識したいポイントを紹介します。
店のコンセプトの一貫性を意識する
新メニュー開発の際には、店のコンセプトを意識した内容にします。コンセプトの一貫性に関しては基本的な部分であり、大切なポイントです。
調理人が「新メニューを作りたい」と申し出ても、そのメニューが店のコンセプトに合っていない場合、お客様が求めているメニューではない可能性があります。
どれほど流行のメニューであっても、お客様が求めていなかったり食べたいと思わなかったりするメニューとなれば売れることはありません。
店のコンセプトとして一貫性を意識し、顧客ニーズと合わせることが大切です。
市場調査で顧客ニーズを把握する
新メニュー開発時には、市場調査で顧客ニーズを把握します。最初にターゲット層を決め、周辺エリアや競合店を調査してください。
市場調査することで、周囲の飲食店で取り扱っていないメニューがわかったり、競合にはないジャンルが把握できたりします。
競合の人気メニュー、価格帯、メニュー数などを調査して差別化を理解し、なぜ人気なのかを分析してみてください。
これらを比較、分析することで活かせるポイントが把握できます。
魅力的なメニュー名を考える
メニュー開発後にメニュー名を決めますが、その際には五感に訴える言葉を活用してください。
五感は「視覚」「嗅覚」「聴覚」「触覚」「味覚」で、見た目、香り、音、食感、味わいを意識した言葉を使います。
五感を刺激する言葉の後にメニュー名を組み合わせることで、よりメニューの内容や伝えたいことが響きやすいです。
例えば、オムライスをメニューに加えるとします。たまごにこだわっているなら「ふんわり」や「とろとろ」、「まろやか」などの言葉を組み合わせるとより五感が刺激されます。
このような言葉の組み合わせを意識して考えてみてください。
SNS映え・見た目を意識する
SNSが中心の時代の今、お客様からの発信や店側からの情報でも拡散されやすい傾向です。
SNS映えを意識した場合、いかに見た目でのインパクトを強くするかも意識したいポイントです。
SNS映えを狙うなら、盛り付け時に色彩のバランス、余白の使い方、高低差などを工夫してください。食器も見た目を意識したものに変えると、より美しさが目立ちます。
季節限定・地域性で話題性を意識する
メニュー開発時には、季節限定や地域限定メニューなどで話題性を意識してみるのもおすすめです。
季節に応じた食材を使うことで、その時にしか味わえないメニューが楽しめるだけでなく、常連客にも新しさをアピールできます。
また、口コミやSNSなどで話題になると新規顧客が来店しやすく、そこからさらに拡散される傾向があります。
季節や地域に限定したメニューは、旬の食材にすれば仕入れコストの削減や鮮度の良い食材を提供できるため、満足度の高いメニューになりやすいでしょう。
既存の設備・オペレーションで対応可能か確認する
メニュー開発の際には、既存の設備やオペレーションで対応できるかどうかも注意しなければなりません。
店舗設備で可能かに加えて、スタッフが能力を満たしているかも確認してください。
既存の調理器具で対応可能か、新たな機材準備が必要かを考えますが、新たに必要と判断した場合はそれに見合った収益かどうかも検討しなければなりません。
調理工程についても繁忙期に時間がかからないか、提供時間とクオリティが合っているかチェックしてください。
食材ロス防止・コスト削減に繋がるメニュー構成の工夫

メニュー開発時には、食材のロスをできるだけ防ぎ、コスト削減が可能なメニューを考えることを意識しましょう。
近年、食品ロスが問題視されていて、スーパーやコンビニでもロス商品の割引などが実施されています。
さらにSNS映えのために料理を注文し、食べずに去る若者も増えています。
世界中で食品ロスに関する取り組みも行われているため、できるだけ削減するように工夫してみてください。
ここでは、食材ロス防止・コスト削減につながるメニュー構成の工夫ポイントを紹介します。
汎用食材で展開するメニュー設計
食材のロスを防ぐには、汎用できる食材を取り入れたメニューを考えます。
様々な料理に利用できる汎用食材であれば、新作のメニューで使いきれなかったとしてもほかの料理で利用できます。
変わった食材や新メニューでしか使わない食材では、食品ロスになる可能性があるので汎用性についてもチェックしておいてください。
在庫回転率を上げる商品構成
食品ロスを意識したいなら、在庫回転率についても注目してください。できるだけ食品の使い切りを意識することで、在庫回転率も上がってきます。
余った食材を使った日替わりメニューの考案なども、在庫回転率を上げる方法のひとつです。
過剰在庫を避けるオーダー頻度の見直し
飲食店の場合、どうしても過剰在庫を抱えがちになる傾向があります。
当日中に使いきれなかった食材を活用するように考えるだけでなく、在庫管理に関するシステムや管理体制を徹底することも食品ロスをなくすポイントです。
また、廃棄ロスに関しても減らせるように、オペレーションに関しても徹底したコミュニケーションが取れるようにしてください。
まとめ・魅力的なメニュー開発で顧客満足度の向上を目指そう
新メニュー開発では、コンセプトの一貫性から試作、改良、原価、導入といった流れで進めていき、顧客満足度と収益性を意識した内容にする必要があります。
コスト管理も意識することが、適正価格で経営を安定させるポイントです。
新メニューを武器に集客アップを狙う挑戦は、飲食店開業の大きな楽しみのひとつです。
その一方で、資金繰りや制度対応など、知っておきたい準備ポイントも数多くあります。
『飲食開業手帳』は、 最新の外食市場動向から経営実務まで、開業を成功に導く情報 を凝縮した一冊。夢を実現するための心強いパートナーとしてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)