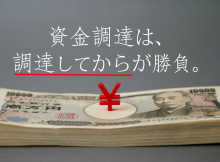個人再生とは?手続きができる条件やメリット・デメリットを解説
個人再生で返しきれない借金を軽減

借金の返済が難しくなった時、債務整理のひとつに個人再生という方法があります。
個人再生をすると借金を大幅に圧縮するので返済の負担を軽くして、再建を目指すことが可能です。
借金の圧縮以外にも債務者にとって嬉しいメリットがいろいろあります。ただし、個人再生を活用するには条件を満たさなければなりません。
今回は、個人再生の概要や条件、手続きを行うメリット・デメリットなどを紹介します.
手続きの手順やよくある質問も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
個人再生とは

個人再生は、借金の返済が困難になった際に裁判所に申し立てて認可を受けることで、借金を5分の1程に減額できる方法です。
申し立てを行うと裁判所によって再生委員が選任され、債務者と債権者の両方にヒアリングを行った上で、適切な再生計画が立てられます。
裁判所から再生計画の認可決定を受けたら、その計画に基づいて原則3年間(特別な事情があれば最長5年)で借金を返済しなければなりません。
返済が完了すれば減額された分の借金は免除される仕組みとなっています。
この債務整理は借金がすべてなくなるわけではありませんが、住宅などの資産を手放さずに借金を大幅に減らせることが大きな特徴です。
個人再生をするための条件
個人再生を利用するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
-
- このままでは借金を返済できない状況である
- 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円未満である
- 継続または反復した収入がある
個人再生は、やむを得ない事情からこのままでは借金を返済できない場合に利用できます。
また、住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下となっているので、それ以上の借金があると利用できません。
個人再生は再生計画に基づいて返済をしていく必要があるため、将来的に継続、または反復した収入があることも前提です。
個人事業主の場合、毎月定期的な収入がなくても3カ月に1回、再生計画に基づいた返済が可能であれば条件を満たしたことになります。
アルバイトの場合、雇用の継続が見込まれるのであれば問題ありません。
しかし、短期間で転職を繰り返したり、期間限定のアルバイトであったりすると認められない可能性があるので注意してください。
個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
それぞれ、最終的な返済額を決める基準や条件に違いがあるので、その点を理解してどちらで債務整理をするか選択しなければなりません。
ここで、小規模再生と給与所得者再生の特徴を紹介します。
小規模個人再生
小規模個人再生は、アルバイトで稼いでいる人や個人商店などの小規模事業者を対象とした個人再生手続きです。
上記で紹介した条件に加えて、再生計画を成立する際に債権者の半数以上から反対されないことが条件となっています。
単純に債権者の頭数だけではなく、債権額の1/2を超える債権者が反対しないことも重要なポイントです。
小規模個人再生は、民事再生法に基づいた最低弁済額、または清算価値総額(生活必需品を除く自分の全財産を処分した際に得られる金額)を比較し、どちらか高い金額で返済します。
給与所得者再生
給与所得者再生は、サラリーマンなど安定した収入があるかつ収入の変動が少ない人を対象にした個人再生手続きです。
再生計画の成立において、債権者の同意確認は省略されます。
ただし、過去7年以内に破産手続きで免責決や個人再生手続きのハードシップ免責などの決定を受けている場合、給与所得者再生の申し立てができないので注意してください。
給与所得者再生の場合、最低弁済額・清算価値総額・2年分の可処分所得(収入から税金や生活費を除外した金額)のいずれか最も大きな金額が返済額の基準となります。
可処分所得は地域や家族構成によって変動しますが、高く算定される傾向にあります。
なお、算定に結婚や出産などの将来的な生活状況の変化は考慮されないため、あえて小規模個人再生を選ぶ人も多いです。
個人再生をするメリット

借金の返済が困難になった時に個人再生手続きをすることには、以下のメリットがあります。
借金の理由や職業を問わず手続きができる
個人再生は、借金の理由や職業を問わず手続きをすることが可能です。
例えば、借金の原因が浪費やクレジットカードの借金、ギャンブルであった場合、自己破産では基本的に免責許可を受けられません。
しかし、個人再生は条件を満たしていれば、借金の理由に関係なく免責許可を受けられる可能性が高いです。
また、自己破産では、士業(弁護士や税理士など)・金融関連業(賃金業者など)・警備員・旅行業務取扱管理者といった職業に就く人は、手続きを行っている間は仕事ができないため収入を得られない状況になります。
一方、個人再生なら職業や資格の制限がなく、手続き中も仕事ができるので収入が途絶えることはありません。
借金を5分の1に減らせる
個人再生手続きを行えば、借金の元本を5分の1に減らすことが可能です。借金をすべてなくなることはありませんが、大幅な減額されることで精神的な負担を軽減させられます。
ただし、返済する借金の金額は最低弁済基準や清算価値基準、可処分所得のうち高い金額が基準となります。
最低弁済額を基準とした場合、借金総額が100万円未満だと減額されないため注意が必要です。
住宅ローン特則によってマイホームを残せる
個人再生には住宅ローン特則が設けられているので、条件を満たせばマイホームを残すことが可能です。
住宅ローン特則は、手続き中も住宅ローンを支払い続けることで、家を所有し続けられるという内容となっています。
この特則が認められる主な条件は以下のとおりです。
-
- 共有を含めて本人が所有する住宅である
- 床面積2分の1以上が居住用
- 現在、本人が当該住宅に住んでいる
- 住宅購入・リフォームを目的にローンを借りた
- 不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
上記の条件を満たさないと特則を適用できずマイホームを手放さなければならないので、注意してください。
ローン完済済みの自動車を残せる
個人再生では、ローンがすでに完済している自動車も残すことが可能です。自動車のローンを返済している間、所有権はローン会社に留保されています。
この場合、個人再生手続きをすると自動車はローン会社に回収されてしまいます。
しかし、すでにローンを完済していて所有権が自分にあれば、ローン会社から回収されることはありません。
特に車が生活必需品となっている人には大きなメリットです。
個人再生をするデメリット

個人再生をすることにはデメリットも存在します。そのデメリットは以下のとおりです。
継続的な収入を見込めないと手続きができない
個人再生は、継続的な収入が見込めないと手続きができない点に注意してください。
再生計画が認可されると、その計画に従って原則3年間で借金を返済する必要があります。
失業していたり収入が不安定だったりするために再生計画どおりに返済がするのが難しいと判断されると、借金を減額してもらえません。
個人再生を利用する際は、定期的に収入を得られる状態が前提であることを理解してください。
保証人が借金を肩代わりすることになる
個人再生では、すべての債権者が対象となり、債権者からすれば回収できる債権の額が大幅に減ることになります。
そのため、連帯保証人や連帯債務者を含む保証人がついている債権の場合、債権者は保証人に返済要求をする可能性が高いです。
要求を受けた保証人は借金を肩代わりすることになり、多大な迷惑をかける恐れがある点に注意してください。
ブラックリストに登録される
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が記録されます。
つまりブラックリストに登録された状態なので、新しくローンを借りたり、クレジットカードの利用や新規申し込みができなかったりします。
ブラックリストには5~10年程残るので、長期にわたって影響を受ける可能性が高いです。
個人再生手続きにかかる費用

個人再生手続きでは、裁判所費用と弁護士費用の2つの費用がかかります。両方を合わせると総額は50~80万円程度が相場です。
裁判所費用と弁護士費用の詳しい内訳は以下のとおりです。
| 裁判所費用の内訳 | ・予納金(官報の掲載料) ・収入印紙 ・郵便切手 |
| 弁護士費用の内訳 | ・相談料:1時間1万円程度が相場 ・着手金:20~30万円程度が相場 ・報酬金:住宅なし20万円程度、住宅あり30万円程度が相場 |
裁判費用は地方裁判所によって異なりますが、3万円程度が相場です。個人再生委員が選任される場合、15~20万円程の追加報酬が発生します。
弁護士費用は、依頼する弁護士事務所ごとに異なりますが、50~60万円が相場です。
個人再生手続きにかかる期間

個人再生手続きにかかる期間は、6カ月~1年程度が平均的です。専門家への相談から再生計画の認可決定までの大まかな期間は以下のとおりです。
-
- 個人再生の申し立て:弁護士や認定司法書士に依頼してから約1カ月~数カ月
- 個人再生手続き開始決定:申し立てから約1カ月
- 再生計画案の提出:申し立てから約3~4カ月
- 再生計画の認可決定:申し立てから約5カ月
個人再生手続きでは申し立ての準備をはじめ、手続き開始決定後も書類の提出や債権者への意見聴取、官報公告など様々な過程を踏むことになります。
そのため、専門家に依頼してから認可決定まで半年以上を見積もり、計画的に行動することが求められます。
個人再生で減額される債務の金額

個人再生によって減額される債務の金額は、返済額を決める基準によって異なります。
最低弁済額を基準とする場合は、借金総額に応じて以下のように定められています。
| 借金総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円以上3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
例えば、借金総額が2,000万円であれば、返済額は300万円にまで減額されます。3年にわたって分割払いすると、月々の返済額は約84,000円です。
自分が所有する財産が最低弁済額よりも高い場合、清算価値総額が基準となります。その場合、返済額が清算価値総額分に増えるので注意してください。
個人再生手続きの手順

個人再生手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
1.弁護士に相談
適切に個人再生手続きを行うために、債務整理に強い弁護士に相談します。依頼後、申し立てに必要な書類を収集します。
住民票や戸籍謄本など多数の書類が必要なので、弁護士に確認を取りながら書類集めてください。
弁護士に依頼すると債権者に対して、受託通知や債権調査への協力をお願いする通知を送ります。
この通知によって、今後債権者の連絡窓口は弁護士となるため、取り立てがなくなります。
2.個人再生の申し立て・開始決定
提出資料や情報に基づいて弁護士が個人再生の申し立てを行います。収集した書類や情報に基づいて弁護士が申立書を作成し、裁判所に必要書類と共に提出してくれます。
その後に実施されるのが、裁判所による個人再生委員の選任をはじめ、申立書の内容に関する追加説明・資料の追加提出の対応、計画どおりに返済可能かどうかの履行テストなどです。
個人再生委員が選任された場合、申立人は委員との面接があるので、申立書の内容確認に対応しなければなりません。
そして、委員の意見も踏まえて裁判所は個人再生手続きの開始決定を下します。
3.再生計画案の作成・提出
申し立てから2~3カ月間は、家計収支表をつけるか、通帳に一定の金額を積み立てる必要があります。
これらは開始決定後に提出する再生計画案を認可する際の可否の判断材料となります。
再生計画案は、申立人と相談しながら弁護士に作成してもらうことが可能です。個人再生委員が選任されている場合、委員がチェックしてから裁判所に提出されます。
4.再生計画認可の決定・返済開始
裁判所は、提出された再生計画案と個人再生委員の意見書をもとに、認可決定を判断します。
無事に再生計画の認可決定となれば、個人再生手続きは完了です。毎月の返金額と支払開始日、振込み口座が通知されるので、計画に基づいて返済を進めてください。
個人再生についてよくある質問

最後に個人再生手続きを成功させるために、よくある質問について回答します。
個人再生したことは家族など知人にバレますか?
同居している家族には、個人再生したことがバレる可能性があります。裁判所に提出する書類の中には、世帯の家計収支表や家族の収入を証明する書類が含まれます。
書類集めに家族の協力が必要になるので、個人再生することを隠して手続きを行うことは困難です。
裁判所から送られてくる書類を見たり、家族が保証人になっていたりする場合も個人再生をしたことが知られるきっかけとなります。
しかし、会社の人や知人などの他人に知られるリスクは低いです。
ただし、知り合いが官報をチェックしていたり、借入れ先に勤務先が含まれていたりするとバレる可能性があります。
個人再生と自己破産の違いはなんですか?
自己破産は、借金がすべて免除される点が個人再生との大きな違いです。ただし、住宅ローン特則がないので、債務者が所有する家は処分の対象となります。
また、自己破産は浪費やギャンブルなどが理由の借金は免除が認められない可能性がありますが、個人再生は要件を満たせば理由に関係なく借金の減額が可能です。
ほかにも、自己破産の場合、手続き中は弁護士や税理士、警備員など一部の職業は働けない制限があります。
それに対して個人再生は、どのような職に就いていても手続き中に制限を受けずに働くことが可能です。
自己破産は安定した収入や財産がほとんどない、自動車や住宅を所有していない人に適した債務整理方法と言えます。
個人再生が成功する確率はどれくらいですか?
2020年の司法統計では、個人再生の申し立て件数は1万2864件で、そのうち1万1988件は手続きが終結しています。つまり90%以上の確率で成功しているということです。
このことから、個人再生は比較的成功しやすい債務整理方法といえます。
ただし、必要な書類が多い上に手続きが複雑なので、弁護士としっかり連携して手続きを進めていくことが成功のポイントです。
まとめ・リスクを知った上で個人再生を検討しよう
個人再生手続きでは、住宅や自動車を手放さずに借金を減らすことができます。借金の理由や職業に特別な制限を受けずに手続きができることも大きなメリットです。
しかし、安定した収入がないと手続きができない、ブラックリストに入るなどのリスクがあります。
これらのリスクも理解した上で、借金がどうしても返せない時は個人再生手続きを検討してみてください。
創業手帳(冊子版)では、創業・起業に関することはもちろん、企業経営で知っておきたい知識や最新情報についてもお届けしています。経営に役立つ情報は創業手帳にお任せください。
(編集:創業手帳編集部)