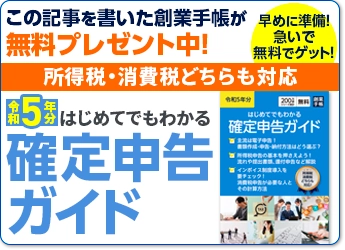個人事業主が定額減税を受けるには確定申告が必須!やり方&注意点を解説
個人事業主は「所得税の確定申告」で定額減税を受ける

個人事業主が定額減税を受けるためには確定申告をしなければいけません。この記事では、定額減税を受けるための条件や必要な手続きについて紹介しています。
調整給付を受けた場合や予定納税をした場合など、ケース別にも確定申告の方法をまとめました。今まで定額減税についてわからないままにしてきた人もぜひ参考にしてください。
無料でお配りしている「確定申告ガイド」を読めば、定額減税の注意ポイントがわかります。減税を受け損ねないよう、申告書の書き方から条件までしっかりまとめました。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
定額減税についておさらい

定率減税は2024年の6月から実施された減税制度です。デフレ脱却のための経済対策として導入され、所得税と住民税が減税対象となります。
| 対象の税金 | 減税額 | 対象条件 |
|---|---|---|
| 所得税 | 3万円 | ・国内居住者
・2024年の所得税の納税義務者 ・2024年の合計所得金額が1,805万円以下 |
| 住民税 | 1万円 | ・国内居住者
・2024年度の住民税所得割(2023年の所得に対する所得割)の納税義務者(均等割のみの納税者は対象外) ・2023年の合計所得金額が1,805万円以下 |
所得税は3万円、住民税は1万円で、1人当たり合計4万円の減税が受けられます。
本人だけでなく、条件を満たした同一生計配偶者または扶養親族も対象です。
日本国内に住んでいて所得税と住民税を納めている人のうち、所得条件を満たせば対象となります。
所得とは収入から経費を差し引いた金額です。確定申告書でいえば「所得金額等」の欄に記載される金額を指しています。
個人事業主が定額減税を受けるには?
個人事業主が定額減税を受けるには、所得税と住民税で必要な手続きが異なります。
- 所得税:確定申告が必要
- 住民税:手続きは不要
定額減税を受けるために確定申告が必要なのは所得税のみで、住民税は手続き不要です。
所得税は確定申告書類に定額減税分の記入をし、届け出れば減税されます。住民税は2024年第一期分から減税されているため、特別な手続きは必要ありません。
住民税については、2024年6月からの住民税決定通知書に減税額が記載されているので、確認してください。第一期分で控除されていない場合には第二期以降で控除されます。
調整給付金を受け取るには?
調整給付とは、定額減税によって引ききれないであろう金額をあらかじめ給付する措置です。
調整給付の対象者には、市町村から確認書が送付されます。必要事項を記載して返信すると、審査後に給付が行われる仕組みです。
給付金はその時の所得に対する納税額から以下例のように計算されます。
定額減税額:所得税分12万円、住民税分4万円
減税しきれない分:12万 – 3万 = 9万円(所得税分)、4万 – 2万 = 2万円(住民税分)
調整給付金:9万 + 2万 = 11万円
【所得税の定額減税】個人事業主の確定申告のやり方

個人事業主や自営業の人が所得税の定額減税を受ける場合、自分で確定申告をしなければいけません。
定額減税の対象となる個人事業主において、基本的な確定申告書の書き方と、ケース別の記入方法をまとめました。
基本の確定申告書の記入方法

出典:税務署「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
2024年(令和6年)分の確定申告書類には、右側に定額減税用の記入欄が設けられています。
第一表44番「令和6年分特別税額控除」の欄に、対象の人数と人数分の減税額を記入してください。e-Taxの場合も、定額減税に関する質問や入力欄が出てくるので、都度入力しましょう。
所得税の減税額は1人あたり3万円です。住民税の控除分を混合しないよう注意し、正確な金額を記載します。
配偶者や扶養親族がいる場合の記入方法
定額減税の対象となる個人事業主に家族がいる場合、家族分も定額減税を受けられるので、合算して確定申告書に記入します。カウントできるのは、次の条件下にある「同一生計配偶者」と「扶養親族」です。
| 同一生計配偶者の主な条件 | 扶養親族(子どもなど)の主な条件 |
|---|---|
| ・配偶者の年間所得48万円以下(給与所得のみで103万円以下)
・個人事業主本人の所得が年間1,000万円以下 |
・扶養親族の年間所得48万円以下(給与所得のみで103万円以下) |
同一生計配偶者の場合は、個人事業主本人の所得が年間1,000万円を超えているとカウントできないため注意しましょう。
配偶者1名、扶養親族1名の場合、自身を入れて3名が対象です。人数欄には3、所得税の減税額欄には90,000円と記入します。
また第二表の「配偶者や親族に関する事項」に、対象となった家族の情報も記入してください。

出典:税務署「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
調整給付を受けている場合の記入方法
2024年に調整給付を受けている場合でも、確定申告書類に記入する金額は人数分×3万円で変わりありません。
調整給付金を受け取っていても、2024年度分の確定申告書類には定額減税による減税額をそのまま記入し、提出します。
また調整給付で受け取った給付金は非課税です。収入として申告の必要はないので、所得に含めなくて構いません。
予定納税を利用している場合の記入方法
所得税の予定納税制度の対象者である場合、2024年第一期または第二期の予定納税額にてすでに定額減税分が控除されています。
ただし、予定納税の段階で引ききれなかった分や、配偶者や扶養親族の定額減税については、確定申告にて反映が必要です。対象人数と金額を記入することで過不足が清算されます。
あらかじめ「予定納税額の減額申請手続き」を提出している人は、配偶者や扶養親族分の定額減税も予定納税額に反映されているので、予定納税の通知書を確認してみましょう。
納税額が15万円未満であれば予定納税の対象外なので、自身と家族の定額減税はすべて確定申告にて反映します。
「青色事業専従者」の定額減税は確定申告できる?できない?

青色事業専従者とは、青色申告者のもとで働いている親族です。親族を青色事業専従者としている個人事業主は、自身の確定申告で親族分の定額減税を行えるのでしょうか。
青色事業専従者の分の定額減税は、専従者に支払っている給与の金額で取り扱いが変わります。
給与が発生していない場合
青色事業専従者への給与がまったく発生していない場合、専従者は個人事業の「同一生計配偶者」や「扶養親族」となり、定額減税の対象です。
個人事業主本人が、自身の確定申告や予定納税額の減額申請を行い、減税を反映させます。
給与が月88,000円以上の場合
青色事業専従者が給与を受け取っている場合、同一生計配偶者や扶養親族とはみなされません。ただし給与が88,000円以上あれば源泉徴収義務が生じるため、源泉徴収を通じて定額減税が行えます。
個人事業主本人の確定申告ではなく、専従者本人の源泉徴収にて定額減税を実施してください。
給与が月88,000円未満の場合
月々の給与が88,000円未満の青色事業専従者は、源泉徴収義務がなく、源泉徴収による定額減税が行えません。
さらに一定以上の給与を受け取っている青色事業専従者は、同一生計配偶者や扶養親族には該当しないため、個人事業主本人の確定申告でも定額減税を反映できないのです。
同一生計配偶者や扶養親族に当てはまらず、専従者としても定額減税を受けられない人には、2025年度に調整給付金の実施が決定しています。詳細は居住する自治体に問い合わせて確認しましょう。
所得ナシ、赤字の個人事業主は?定額減税の救済措置
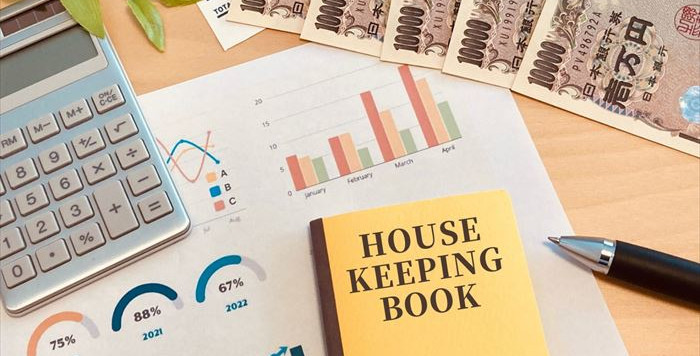
定額減税は所得税と住民税に対する減税措置であるため、所得税・住民税が課されない所得0円の人や赤字の事業者は対象外です。
しかし、こういった非課税世帯にも救済措置も設けられています。ここではケース別にどういった制度が適用されるのかを紹介します。
住民税非課税世帯の場合
個人住民税が所得割、均等割の両方で非課税となっている人だけの世帯は、定額減税ではなく給付金を受け取れます。
いわゆる住民税非課税の世帯を指し、給付額は世帯主に対して1世帯当たり7万円です。同世帯には2023年夏以降の臨時特別給付金と合わせて10万円が支給されることになります。
2024年度分から住民税が非課税になる世帯も対象で、その場合の給付額は10万円です。
住民税均等割のみ課税世帯の場合
住民税の均等割のみ課税される世帯は、一世帯当たり10万円が給付されます。2023年度で対象となっている世帯はもちろん、2024年度から該当する世帯も10万円の給付対象です。
住民税の均等割のみ課税されるケースは市町村によって条件が違います。詳細については、住んでいる自治体のホームページを確認してください。
18歳以下の子どもがいる世帯の場合
住民税が非課税、あるいは均等割りのみ課税になる世帯に子どもがいる場合、子ども加算が適用されます。加算の金額は、18歳以下の子どもひとりにつき5万円です。
例を挙げると、住民税均等割のみの世帯で子どもが2人のケースでは、10万円+5万円×2人で20万円の給付を受けられます。
子ども加算の適用範囲も、2023年度・2024年度の住民税にて給付対象となる世帯です。
個人事業主が悩みやすい定額減税×確定申告のポイント
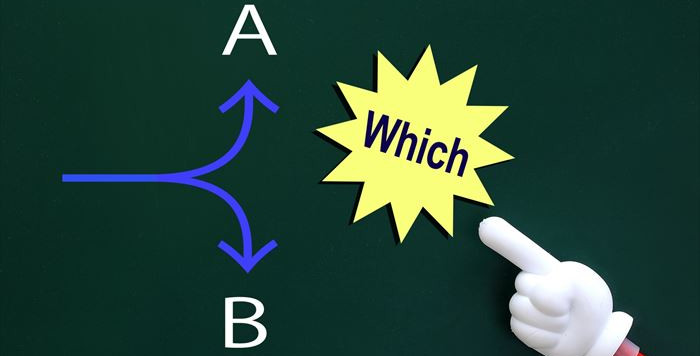
個人事業主が定額減税の適用を受けるには条件を満たさなければいけません。
確定申告時に意識しておきたい条件や注意点をまとめました。
配偶者は所得の種類と金額に注意する
同一生計配偶者を定額減税の対象とするには、同一生計配偶者の年間の合計所得金額と、所得の種類に気をつけてください。
所得の種類が給与なら103万円以下、給与以外ならが48万円以下でなければ、個人事業主本人の定額減税には含められません。
対象を超える所得がある場合、給与なら配偶者の勤務先で定額減税の処理をしてもらいます。給与でないなら配偶者自身が確定申告し、定額減税を受けましょう。
間違いで定額減税を二重で申請してしまうと後から修正が必要になるかもしれません。同一生計配偶者の所得状況を正確に把握しておいてください。
住宅ローン控除やふるさと納税には影響されない
確定申告で住宅ローン控除やふるさと納税を受けている個人事業主の場合、これらの控除に定額減税は影響しません。
定額減税は住宅ローン控除が適用された後に行われるほか、ふるさと納税の上限額は定額減税を適用する前の金額で決定します。
住宅ローン控除やふるさと納税を適用したから定額減税ができないといったことはないため、安心してください。
まとめ・個人事業主も定額減税を活用して税負担を抑えよう
定額減税は、2024年に実施される所得税と住民税の負担を軽減する制度です。個人事業主が定額減税を受けるには、確定申告をするのが基本となります。
予定納税の状況、同一生計配偶者や扶養親族の有無によっても処理が変わるため、自分にはどういった手続きが必要になるのか把握しておいてください。
定額減税の処理をし忘れると、大きな損失になります。「確定申告ガイド」では、定額減税を反映した申告書の書き方を解説中です。わかりやすい記入例があるので、申告書の作成がスムーズになります。
(編集:創業手帳編集部)