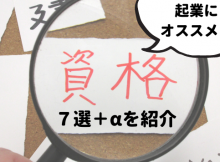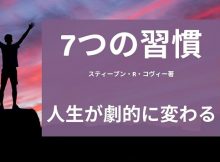経営の上半期振り返りのやり方とは?重要な理由やポイントも解説!
上半期の振り返りで現状を把握しよう
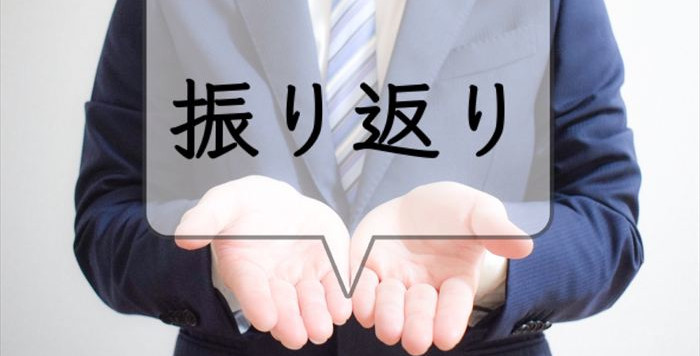
1年の折り返し地点である上半期の終わりは、企業経営において重要な節目です。
このタイミングで自社の現状を振り返ることで、達成できた成果や直面した課題を明確にし、下半期に向けた戦略を立てやすくなります。
しかし、ただ数字を確認するだけでは意味がありません。振り返りを効果的に行うには、適切な手順やポイントを押さえることが重要です。
この記事では、上半期の経営を振り返る実践的な方法や、チェックすべきポイントをわかりやすく解説します。
創業手帳では、振り返った内容を元に事業の整理ができる「事業計画シート&資金シミュレーター」を無料でご利用いただけます。あわせてご活用ください。
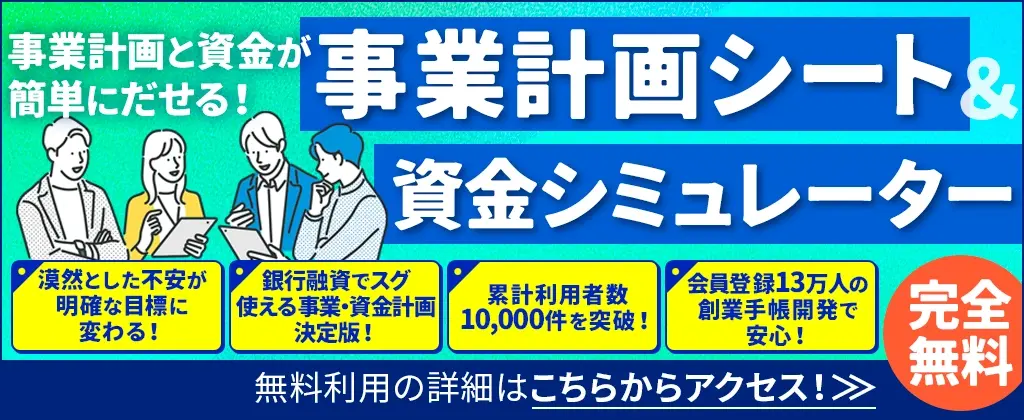
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
経営の振り返りはなぜ重要なのか?
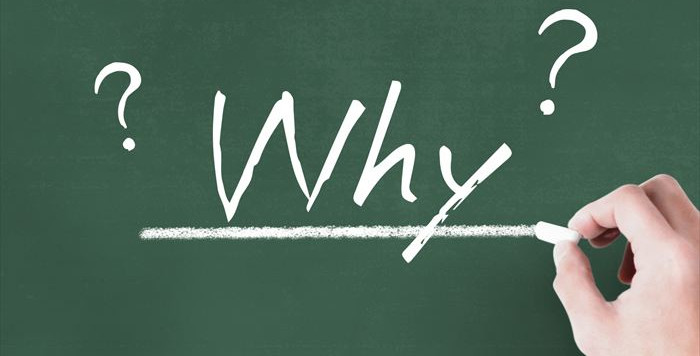
上半期が終わるタイミングで、なぜ経営の振り返りを行ったほうが良いのでしょうか。まずは、振り返りの重要性について解説します。
目標が達成できなかった原因の洗い出しができる
上半期の経営を振り返ることで、達成できた目標とそうでない目標が出てきます。
達成できなかった目標は、下半期も継続して取組むことになりますが、「なぜ目標を達成できなかったのか」という原因がわからないと、上半期と同じ結果に終わってしまう可能性があります。。
振り返りは単に原因を追究するために行うものではありません。
しかし、現状と目標とのギャップを把握でき、このギャップを埋めるためにはどうすればいいかが見えてきます。
目標達成に向けた修正作業を行える
経営の振り返りを行うと、なぜ目標が達成できなかったのか原因の洗い出しが行えますが、それだけで終わってしまっては意味がありません。
洗い出した原因について反省し、取組みに対して修正作業を行うこともできます。
それぞれの原因に対して修正や施策を打てることから、下半期では目標達成に近づけるでしょう。
成果を出せた要因がわかる
上半期の経営を振り返った時、目標達成ができなかった原因もわかりますが、達成できた目標に対してどのようなことを行ったのか、どのようなことをしたら成果につながったのかもわかります。
成果を出せた要因がわかれば、成果を出せなかった取組みに対して修正する際にも役立ち、別の事業や取組みに活かせる可能性もあります。
経営の上半期振り返りに役立つフレームワーク3選

経営を振り返る際に、上半期に起きた事をただ思い出して反省するだけでは、十分な振り返りができているとはいえません。
そこで、経営の上半期振り返りに役立つフレームワークを3つ紹介します。
KPT(ケプト)
KPTとは、今取組んでいる業務を振り返り、今後の行動方針を決めてブラッシュアップさせるフレームワークです。
もともとはシステム開発の現場で振り返るための手法として用いられていましたが、現在はビジネスからプライベートまで、様々なシーンで活用されています。
3つの要素:Keep/Problem/Try
KPTは主に3つの要素から構成されています。
| 要素 | 特徴 |
| Keep(できたこと) | 業務やプロジェクトの中で良かったことや継続すべき取組みを洗い出す。振り返る際には、具体的な数値や要因まで抽出できると効果的。 |
| Problem(問題点・課題) | 改善すべき問題点やその原因を洗い出し、客観的な事実に基づきながら分析する。また、今後起こり得る問題・リスクについても書き出す。 |
| Try(チャレンジしたいこと) | Problemで洗い出した問題点に対する解決策や、Keepで洗い出した良かったことを向上させる取組みなどを書き出す。 |
KPTのやり方
KPTのやり方は以下のとおりです。
1.フォーマットを準備する
2.Keepのブロックに上半期の経営で良かったこと・継続したほうが良いことを書き出す
3.Problemのブロックに現状の問題点や今後起こり得るリスクを書き出す
4.Tryのブロックに問題の改善策と良かったことを向上させるための取組みを書き出す
フォーマットはホワイトボードやシートなどを準備し、Keep・Problem・Tryのブロックを作ってください。この時、Tryのブロックが一番大きくなるようにします。
Tryで書き出す改善策は、「誰が」「いつまでに」「どうやって」行うのかまで決めると、次の行動に移しやすくなります。
PDCAサイクル
PDCAサイクルは、目標の達成や業務改善などを目的に取り入れられているフレームワークです。
品質管理や生産管理の現場はもちろん、経営や人材マネジメントのシーンでも活用されています。
4つの要素:Plan/Do/Check/Action
PDCAサイクルは主に4つのプロセスがあり、これをひとつのサイクルとして捉えています。
Plan→Do→Check→Actionの順番に実行し、Actionから再びPlanへと戻る形です。
例えばPlanで立てた目標を達成できなかったとしても、Actionで対策を考えてまた計画を立て、実行に移していきます。
このサイクルを繰り返していくことで、徐々に精度も高まっていき、失敗をしにくくなります。
連続的に評価と改善を重ねていくことから、中長期的な経営目標の達成にもつながるでしょう。
一方で、何回かサイクルを回しただけでやめてしまっては、効果が薄くなってしまうので注意が必要です。
PDCAサイクルのやり方
PDCAサイクルのやり方は以下のとおりです。
・Plan(計画)
PDCAサイクルは、まず計画を立てるところからはじまります。明確な目標・目的を設定した上で、どうすれば達成できるかを行動計画に落とし込んでいきます。
目標を設定する際には、数値で計測できるものを設定したほうが現状を把握しやすくなるでしょう。
・Do(実行)
行動計画を立てたら実行に移しますが、ここでプロセスや進捗状況などを細かく記録していきます。
記録した内容は次の評価段階で振り返る際に、客観的な評価ができるようにするためです。
・Check(評価)
評価段階では設定した目標の達成度や進捗などを振り返り、評価していきますが、原因まで分析することが重要です。
数字や統計データを細かく分析することで、なぜ達成できたのか、または達成できなかったのかを深く学べます。
・Action(改善)
評価によって得られた結果をもとに、改善案を出していきます。複数の改善案が出た場合は優先順位をつけて取組み、次のサイクルで取入れてください。
KPI・KGIの振り返り
上半期の経営を振り返るのに、KPI(重要業績評価指標)とKGI(重要目標達成指標)も活用します。
ビジネスの最終目標として設定するKGIに対して、KPIはKGIの達成に向けて適切にプロセスが行われているかを定量的に評価する指標になります。
目標(KGI)と指標(KPI)を振り返る
KGIとKPIを振り返る際の流れは、以下のとおりです。
1.施策を実行する中で定期的に指標を測定しておく
2.KPIのプロセスを繰り返し行い、一区切りついたら結果の分析・検証を行う
3.KPIの結果に基づいてKGIの振り返りを行う
KGIとKPIを設定したら振り返る時期・タイミングを事前に決めておき、定期的に指標を測定していきます。
指標の数値が出たら、チームや従業員全員がどれくらいKPIを達成できているのかを共有するのです。
KPIのプロセスを何度か繰り返し、一区切りがついたらこれまで測定した結果・グラフをもとに分析・検証します。
検証する際は数字ばかりを見るのではなく、プロセス全体をふかん的に捉え、どうして数値が変化したのかを検証することが大切です。
最後にKGIの振り返りも行います。KPIの結果に基づいてKGI達成までにどこまで進んだかを確認してください。
KPIを活用した改善の考え方
施策を改善していくためには、KPIの達成・未達成という結果だけでなく、「なぜその結果になったのか」などを深掘りすることが重要です。
その上で、次の施策に反映させるPDCAサイクルを回していけば、経営全体の精度とスピードが大きく向上します。
上半期のKPI分析は、下半期に向けた戦略立案の基盤となるでしょう。
外部環境や戦略の整理に役立つフレームワーク

経営の振り返りを行う際には、外部環境の分析や戦略の整理も行うことが大切です。ここで、外部環境や戦略の整理に役立つフレームワークを3つ紹介します。
SWOT分析
SWOT分析とは、内部環境と外部環境を4つのカテゴリに分けて分析し、企業やプロジェクトの現状や課題を知るためのフレームワークです。
戦略の策定や経営資源の最適化などに活用することもできます。
SWOT分析は内部環境・外部環境を総合して評価するため、企業は効率的なリソース配分とリスクを最小限に抑えつつ、経営戦略を立案可能です。
自社の強み・弱みと機会・脅威を整理する
SWOT分析は内部環境を示す「Strength(強み)」と「Weakness(弱み)」、外部環境を示す「Opportunity(機会)」と「Threat(脅威)」を設け、さらにプラス要因(強み・機会)とマイナス要因(弱み・脅威)に分かれます。
内部環境を示す自社の強みと弱みは、どちらも会社側でコントロールすることが可能です。
例えば自社の商品やサービス、資産、ブランド力、品質、顧客情報などが挙げられます。
一方、外部環境を示す機会と脅威は、自社でコントロールすることができません。例えば市場規模や競合他社の状況、法改正、社会情勢などがあります。
これらを整理していくことで、効果的な戦略の立案につながります。
SWOT分析のやり方と活用例
SWOT分析のやり方は以下のとおりです。
1.分析の目的を設定する
2.内部環境を分析する
3.外部環境を分析する
4.具体的な戦略を立てる
まずは分析の目的を設定します。目的が明確になっていないと分析や議論の方向性がブレてしまい、効果的な戦略を立てられないので注意してください。
次に自社の強み・弱みを洗い出します。様々な視点からどのような強み・弱みがあるかを考えてください。
内部環境を洗い出せたら、外部環境についても洗い出していきます。
市場動向や競合他社の状況に留まらず、政治や経済の情勢、社会的要素など、あらゆる視点から自社に影響する要素を抽出してください。
例えばお弁当を提供するお店が、来客数の増加を目的にSWOT分析を行った場合、以下のように分類できます。
-
- 強み:地域密着型、長年お付き合いがある常連・固定客が多い
- 弱み:ITリテラシーが低い、配達サービスを行っていない
- 機会:健康ブームによる健康志向の高まり、地元住民の高齢化
- 脅威:近所に大手スーパーが建った、不況にともなう低価格志向、人口減少の影響
内部環境と外部環境を洗い出せたら、最後に具体的な戦略を立てていきます。各要素を掛け合わせながら、目的に合わせて実行可能性が高い戦略を打ち出してください。
-
- 強み×機会:地元の有機野菜を取入れたお弁当の開発・販売
- 強み×脅威:常連・固定客のニーズに寄り添った商品の販売
- 弱み×機会:高齢者向けのお弁当販売・配達サービスの実施
- 弱み×脅威:SNSを活用したファンの獲得
PEST分析
PEST分析とは、自社を取り巻くマクロ環境について、将来的に自社に対してどのような影響があるかを分析するフレームワークです。
ビジネスはマクロ環境の影響を受けやすいことから、長期的な企業の成長を目指すためにもPEST分析を活用して上半期を振り返ることも重要となります。
4つの要素:Politics/Economy/Society/Technology
PEST分析を構成する要素は、以下の4つです。
-
- Politics(政治的):法律、法改正、税制、政治・政権交代、裁判・判例など
- Economy(経済的):為替、株価、経済成長率、景気動向、物価など
- Society(社会的):人口動態の変化、流行・世論、宗教、言語など
- Technology(技術的):インフラ、IT活用、新技術の普及、特許、イノベーションなど
PEST分析のやり方
PEST分析は以下の流れで行います。
1.4つの要素に関連する情報を集める
2.収集したデータをもとに分析する
3.分析結果をもとに事業戦略を策定する
4.4つの要素を定期的にモニタリングし、有効性を評価する
4つの要素に関連する情報は、できるだけ信頼性の高い情報・データを収集します。
政府からの経済指標や経済研究機関が公表したレポートなどをもとに、確かな情報を収集してください。
また、事業戦略に落とし込んだ際に複数の施策ができた時は、優先順位をつけて取組みます。
緊急性の高さや長期的・短期的などを考慮した上で、優先順位をつけてください。
5フォース分析
5フォース分析とは、5つの競争要因を分類し、自社にとってどれくらいの脅威になるか分析するフレームワークです。
PEST分析ではマクロ環境からの要因を分析しましたが、5フォース分析ではミクロ環境(業界・市場)で直接自社に影響を与える要因について分析します。
5つの要素::競合他社・新規参入・代替品・買い手・売り手
5フォース分析では、以下5つの要素を分析します。
-
- 競合他社:競合他社の数、他社の資金力・技術力・ブランド力など、差別化の状況
- 新規参入:市場規模、市場成長率、新規参入企業の資金力・技術力・ビジネスモデルなど
- 代替品:価格・コストパフォーマンス、代替品業界の利益率、市場成長率
- 買い手:買い手の数、商品の価格帯、購買条件、商品の独自性
- 売り手:売り手の数、仕入れ価格、価格交渉の買う日、サプライヤーを切り替える場合のコスト
5フォース分析のやり方
5フォース分析のやり方は、以下のとおりです。
1.5つの要素に関するデータを収集する
2.分析結果を評価する
3.事業戦略を策定する
4.定期的に見直しと更新を図る
まずは5つの要素に関するデータを収集していきます。政府が公表する統計データや企業の財務報告書などから確かな情報を収集してください。
次に収集したデータを分析し、結果を図にして評価します。
業界内の要因(買い手・売り手)を横軸、業界外の要因(代替品・新規参入者)を縦軸に置き、真ん中に競合他社を置きます。
さらに結果に基づいて、自社の競争優位性を確立するために事業戦略を策定してください。
戦略を策定・実行した後もミクロ環境は変動し続けていることから、定期的な見直しと更新を図ることも大切です。
経営の振り返りを行う際のポイント

上半期の経営を振り返ることは、企業の成長に欠かせない重要なプロセスです。感覚や印象だけで評価を済ませるのではなく、事実にもとづいた客観的な分析が求められます。
ここでは、経営の振り返りを有意義なものにするための3つのポイントをご紹介します。
客観的な視点で分析・評価する
経営の振り返りを行う際には、主観的な感想・印象に頼らず、数値や実績に基づいた客観的な視点で分析することが大切です。
売上や利益、KPIの達成度など、定量的・定性的な両面から評価を行ってください。
特に、目標に対する達成状況とその要因を洗い出すことで、成功や失敗の原因が明確になり、今後の意思決定にも役立ちます。
反省だけで終わらせず、次への行動へ繋げる
振り返りの本来の目的は、過去の失敗や成功を踏まえて、次に活かすことです。問題について反省だけで終わってしまうと、改善にはつながりません。
課題が明らかになったら、「なぜそのような結果になったのか」「今後どうすれば同じミスを避けられるのか」といった具体的な改善策や行動計画を立ててください。
メンバーや部署で共有し、再発防止・活用を図る
経営の振り返りは経営層だけで完結させるのではなく、各部門や現場のメンバーとも情報を共有することで、組織全体の成長につながります。
失敗事例は再発防止のための教訓として、成功事例はノウハウとして横展開することが可能です。
共有する際は責任追及に偏らず、建設的な雰囲気づくりを心がけると、現場からの信頼も高まります。
まとめ・上半期を振り返り、下半期の経営に備えよう
上半期の経営を今回紹介したフレームワークなどを活用して振返り、問題点や改善策を抽出することで、下半期の経営にも役立ちます。
目標を達成するのに振返りを設けることも重要なので、次のステップに進むためにも区切りのいいタイミングで経営を振り返ってください。
創業手帳では、銀行融資などにスグに使える「事業計画シート&資金シミュレーター」を無料でご利用いただけます。振り返った内容をもとに、事業計画をきちんと書き出しておくのが重要です。あわせてご活用ください。
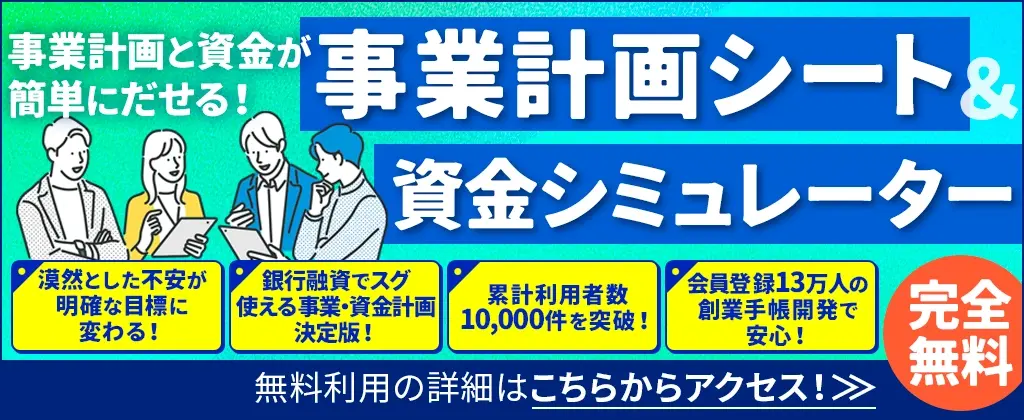
(編集:創業手帳編集部)