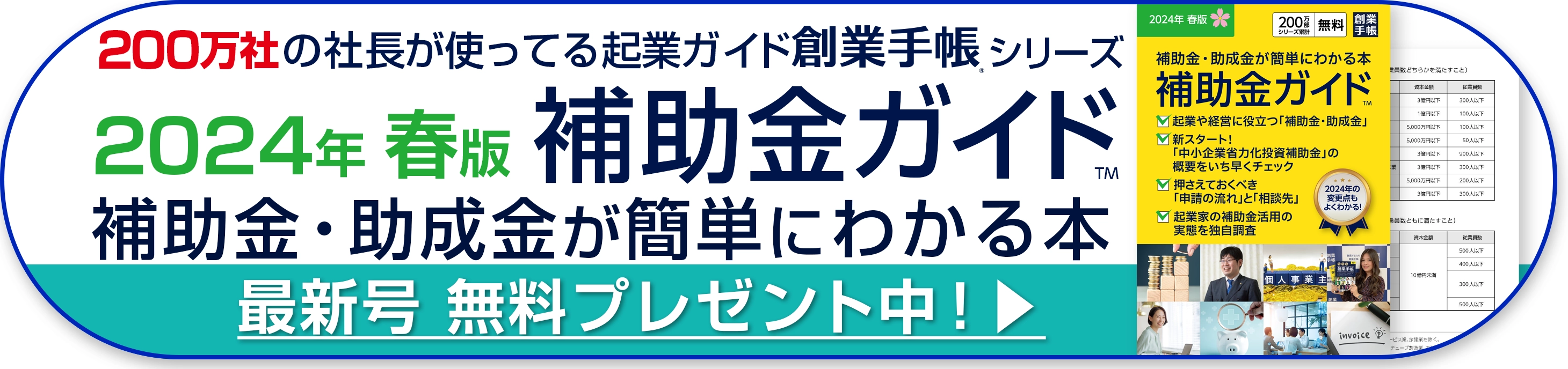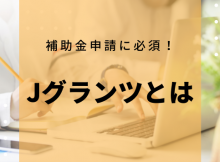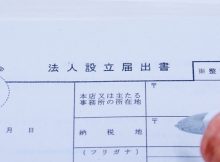補助金の申請準備を行う前に!助成金との違いや採択率を上げるコツなどを知ろう
補助金申請に向けて理解を深めよう

どのようなビジネスであっても継続するには事業資金が必要です。どうやって事業資金を捻出するかは、開業時の事業計画書でも決めておかなければいけません。
ここでは、事業資金の確保に悩む人に向けて、補助金について紹介します。
意外と知られていない助成金との違いや補助金を申請する流れ、採択率を上げるコツも紹介するのでぜひ参考にしてください。
創業手帳では、経営者の方々がよく使う補助金・助成金を厳選してわかりやすく解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。3ヶ月1度内容を更新し、最新情報をお届け。また定番の補助金についての疑問などにもお答えしています。ぜひあわせてご活用ください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
補助金と助成金の違いとは?

補助金、助成金は、国や地方自治体が定めた政策目標に沿う事業を行う事業者に支給される事業資金です。
どちらも返済不要でまとまった資金を借り受けられるため、これから起業する人、事業で資金に困窮している人も多く利用しています。
補助金と助成金はともに返済不要で給付され、どちらも多くの種類があります。しかし、双方には違いがあるので違いを理解してから申請を検討してください。
ここでは補助金と助成金の違いについて簡単に紹介します。
補助金とは
補助金は、主に経済産業省や地方自治体が管轄していて、事業拡大や設備投資といった活動をサポートする目的で支給されています。
補助金を受け取るには要件を満たして申請した上で、複数の申請の中から採択されなければいけません。
また、多くの場合は採択されてすぐに支払われるのではなく事業を実施、費用を支出した後に精算する形で補助金が交付されます。
助成金とは
助成金は、主に厚生労働省が管轄していて、雇用促進や労働環境改善といった活動をサポートする目的で支給されています。
助成金は、申請して採択されるといった流れではありません。多くの助成金は所定の要件を満たして申請すれば基本的に給付を受けられます。
当該事務局が手続きをして、一定期間後に支給されるのが一般的です。
補助金を申請するメリット・デメリット

補助金は多くの事業者が利用しているものの、初めての人にとってはわからないことも多くあります。
ここでは、補助金を申請するメリットとデメリットを簡単にまとめました。これから補助金を申請する人は事前に確認してください。
補助金を申請するメリット
補助金を申請するメリットは、まとまった資金を返済不要で受け取れる点です。不正受給などがなければ、補助金は原則返済しなくて良い資金となります。
ほかの資金調達で考えると銀行からの融資であれば返済が必要、出資を受け入れれば株式などを差し出すのが一般的です。
一方で、補助金であれば融資のように後から返済できなくなって困るようなケースはありません。
また、補助金申請のステップで事業計画書を作成することも重要な意味があります。補助金として採択されるためには、一定以上のクオリティを持つ事業計画書が必要です。
補助金申請は、事業について棚卸しして、多面的な方向で改善するきっかけになります。補助金の採択は、その事業に優位性や将来性があるというお墨付きです。
採択を勝ち取った事実は、事業計画の信頼性や価値を高め金融機関や取引先からの信用を高める効果も期待できます。
補助金を申請するデメリット
補助金は多くのメリットがあるものの、申請する手続きに時間も手間もかかる上、必ず採択されるわけではありません。
要件を満たしていたとしても不採択になることもあるため、せっかく時間や労力を投じたのに不採択で一切お金にならないこともあり得ます。
本業に割くべきリソースを補助金申請に使っては意味がありません。
自社だけで補助金申請するのが難しい場合には、申請のサポートを専門家に依頼するようにおすすめします。
専門家は、経験も豊富なため自社に適した補助金を決める相談もできます。
さらに、補助金を申請するには、本当にその補助金が必要なのか、補助金がなくても実施すべき投資なのかを考えてください。
補助金がもらえるからと安易に過剰な投資をしてしまうケースも散見されます。その結果、補助金を受け取っているのに利益につなげられない可能性もあります。
補助金の申請準備をする際に知っておきたい採択率を上げるコツ

補助金は応募条件や審査基準があり、申し込んでも採択されないケースも多々あります。そこで、ここからは補助金の採択率を上げるコツを紹介します。
採点基準や公募要領を事前に確認する
補助金に応募する時には、公募要領をよく確認して応募条件を満たせるか確認してください。不明な点は補助金を実施している機関の窓口に問い合わせておいてください。
公募要領には、補助金の目的、対象や必要書類、申請方法が記載されています。
採点基準も公開されているので、公募要領の内容を理解してから必要書類の準備に進んでください。
補助金申請をする目的・対象を明確にする
補助金には、多くの種類がありそれぞれ目的、対象が異なります。補助金の目的や対象を理解した上で、自社が補助金の対象であるとアピールする必要があります。
どれだけ熱意がある内容を記載しても、目的や対象からずれていれば採択されません。
事業計画の中で自社の事業計画が補助金の目的とどのように合致しているか明確に示すことが大切です。
誰でも理解できるように書類を作成する
補助金の申請書は誰にでもわかるように書く必要があります。誰でも理解できるようにするポイントは以下のものです。
専門用語もわかりやすく記載する
補助金の申請書では、事業の内容や計画も記載します。一般的に使われていないような専門用語や難解な言い方を申請書の中で使ってしまうこともあるでしょう。
しかし、申請を審査する人が必ずしもその分野について詳しいとは限りません。専門知識がない人にも伝わりやすいように申請書は作成してください。
難解な言葉は避けて、どうしても使う専門用語は別に解説をつけるようおすすめします。
イメージや図も使って読みやすくする
相手に事業の内容やビジョンを理解してもらうためには、パッと見た時の読みやすさも重要です。見出しを設定したり、イメージなどで伝えたい内容を簡潔に表現します。
専門用語も図を使用するとわかりやすくなることがあります。
審査する側は多くの書類を見ることになるので、イメージや図も使ってビジュアルでも伝わるようにしてください。
数字で根拠を示しながら事業の優位性をアピールする
事業計画書や申請書類で数字を使う時には、その根拠を明確にしなければいけません。根拠がない数字は、信用できない数字として審査側から受け入れられないことがあります。
調査結果やデータを引用するなど、その数字が何を根拠としているかを明示するようにしてください。
補助金の申請準備から交付までの流れ

補助金のスケジュールは、大まかに予算が成立する春ごろに公募がスタートして、会計年度が終わる3月末までに補助金事業を終えるような流れです。
また、地方自治体の補助金であればスケジュール感も違います。ここでは、一般的な補助金の申請準備から交付までの流れの紹介です。
1.公募要領の確認と必要書類の準備
補助金の申請は、その補助金の公募要領を確認することからはじまります。
補助金制度の趣旨や目的、補助対象事業者、補助対象費目といった申請するために必要な情報が公開されます。
公表された公募要領から、自社が対象となるか、必要金額を満たすかを検討して補助金を選ぶと良いでしょう。
公募要領では、申請方法やフォーマットも示されるので、様式に沿って申請準備を進めてください。
2.補助金を提供する機関・団体に申請
申請する補助金を決めたら必要書類一式を提出します。一般的には以下の書類が求められます。
-
- 申請書
- 事業計画書
- 経費明細書
- 事業要請書
上記に加えて法人であれば履歴事項全部証明書や直近の納税証明書、個人事業主であれば本人確認書類や確定申告書の控えが求められることもあるようです。
補助金の申請書は、補助金の主催である機関のWebサイトで入手できます。提出する前に必要書類リストを参照して不備や不足がないか確認してください。
3.採択の通知と交付申請
申請をしてから、提出した書類や面談をもとにして審査が行われます。採択の通知を受け取った時には、補助金を受けるための交付申請を行ってください。
交付申請に必要な書類には、以下のものがあります。
-
- 交付申請書
- 経費の相見積もり
交付申請の内容が認められると、交付決定となり補助事業の開始に進みます。
4.交付決定後に事業を開始
交付決定された内容で事業をはじめてください。もしも事業内容の変更がある場合には、計画変更申請が必要です。
補助金は後払いで、すべての手続きが終わった後に振り込まれるため、一時的に支払うための資金を用意しなければいけません。
自己資金か金融機関からの融資か検討して資金調達の準備も併せて進めます。
事業開始後は、報告のために補助金の対象である経費は領収書や関係書類をすべて保管しておくようにしてください。
5.中間報告
事業実施期間中には、定期的に実施報告書や経費エビデンスを提出するように求められます。
もしも報告や書類の提出がない、書類に不足がある場合には補助金の交付が中止されることもあります。
報告で求められる書類は以下のものです。
-
- 遂行状況報告書
- 経費明細書
- 見積依頼書
- 発注書や納品書、検収書など
報告は求められる書類も多く内容も煩雑です。一度にまとめて書類を整備しようとしても大変なので事業の進行に合わせて書類も準備するようおすすめします。
6.事業実績報告と補助金の受給
事業を実施したことを報告する事業実績報告を行います。提出するのは以下の書類です。
-
- 実績報告書
- 請求書
- 発注書や納品書、検収書など
事業実績を報告して、請求書を提出して補助金を申請します。申請からおおよそ2週間程度で補助金が所定の口座に振り込まれます。
7.定期的な事業状況の報告
補助金によっては、補助金を受給して終了にはなりません。
補助金を受け取ってからも定期的に状況を報告する場合もあるので、事前にどのタイミングで報告するのか公募要領で確認してください。
加えて、補助金の対象となる領収書、証拠書類は補助事業が終了してからも5年間保管しておかなければいけません。
補助金の申請準備について相談するなら?

補助金は、申請書類の作成や申請の流れがわかりにくいものもあるため、だれか専門家のサポートを受けたいと考える事業者もいるでしょう。
ここでは補助金の申請準備について相談できるエキスパートを紹介します。
| 相談先 | 対応できる内容 |
| 商工会・商工会議所 | 補助金や経理、労務など幅広い内容を相談可能。 |
| 行政書士や中小企業診断士などの士業 | 補助金について申請を代行している場合もある。専門分野に応じた相談も可能。 |
| コンサルタント会社 | 補助金や資金調達の計画、申請サポートまで対応可能。 |
| 金融機関 | 資金繰りや資金調達の相談。認定支援機関として確認書の作成についての相談が可能。 |
商工会・商工会議所
商工会や商工会議所は、中小企業の経営活性化のために、セミナーや相談対応といった事業を実施しています。
管轄エリアがあるので、自社が該当するエリアの窓口に問い合わせてください。
商工会・商工会議所は、「小規模事業者持続化補助金」の公的な相談先であり、商工会・商工会議所を通じて申請が必要です。
行政書士や中小企業診断士などの士業
行政書士や中小企業診断士、税理士といった専門家も補助金の相談を受け付けていることがあります。
自社に合った補助金の選定から書類作成まで依頼できますが、同じ士業でも得意分野があります。
どういった分野を得意としているのか、今までに補助金申請を手掛けたことがあるのかを確認しておくようにしてください。
コンサルタント会社
コンサルタント会社は、資金調達全般に強く、助成金や補助金の情報も多く保有しています。
そのため、どの補助金が適しているかといった提案から、申請にかかわる書類作成まで一貫してサポートを受けられます。
金融機関
資金に関わる相談であれば金融機関の対応可能です。補助金が交付されるまでの自己資金の準備についても金融機関に相談できます。
また、事業再構築補助金の申請には、認定支援機関からの確認書が求められます。確認書を作成してもらう場合にも事前に相談しておくようにおすすめします。
まとめ・補助金は準備をしっかりと整えてから申請しよう
補助金は、書類を提出してすぐにお金が振り込まれるようなイメージを持たれがちですが、実際には申請から複数回の報告が必要です。
補助金に関わる書類提出や事業は長期間にわたるため、事前にどういったスケジュールになるのか、どの段階で交付されるのかについて確認が必要です。
交付された補助金を有効活用するためにも、準備をしっかり整えておくようにしてください。
創業手帳では、経営者の方々がよく使う補助金・助成金を厳選してわかりやすく解説した「補助金ガイド」を無料でお配りしています。3ヶ月1度内容を更新し、最新情報をお届け。また定番の補助金についての疑問などにもお答えしています。ぜひあわせてご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)