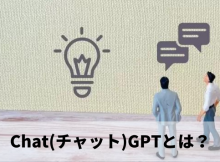フリーランスも労災保険の特別加入が可能に!対象拡大の背景や条件、メリットについて
2024年11月からフリーランスが労災保険の特別加入対象に

これまで会社員や一部の事業主しか利用できなかった労災保険が、2024年11月からはフリーランスも特別加入できるようになりました。
業務中の事故やけが、病気などのリスクを抱えるフリーランスにとって、大きな安心材料となる制度改正です。
背景には、多様な働き方が広がる中で、個人で働く人の安全と生活を守る必要性が高まっていることがあります。
今回は、対象拡大の背景や加入条件、そして具体的なメリットについて解説します。労災保険への特別加入を検討されているフリーランスの人も、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
労災保険の特別加入とは?

労災保険は、労働者が労働災害を被ってしまった場合に、保険の給付やサポートを提供する保険制度です。
労働者とは事業主から雇用されている人を指すため、例えば自営業者や個人事業主、フリーランスなどは当てはまりません。
しかし、労働保険の特別加入制度を活用すれば、必要に応じて労働保険を利用できるようになったのです。
また、以前まで特別加入の対象業種は限られていましたが、2024年4月に厚生労働者が労災保険の特別加入の対象を拡大させると発表し、同年11月から対象者の範囲が拡大されました。
特別加入の対象が拡大した背景
特別加入の対象が拡大した背景に、フリーランス新法の成立が挙げられます。
フリーランス新法は2024年11月1日から施行された法律で、フリーランスと企業など発注事業者との取引きを適正化し、就業環境を整備することを目的とした法律です。
この新法が検討されている段階から、労災保険の特別加入の対象について取り上げられており、国会での審議でも対象範囲を拡大させるべきという声が大きくなっていきました。
以前から国は労災保険の対象を拡大させています。
例えば2021年4月に芸能関係やアニメーション制作、柔道整復師などが、同年9月にはITフリーランスや自転車配達員などの特定の職種も特別加入が認められていきました。
このような拡大の動きもあったことから、フリーランス新法の施行にともない、特別加入の対象範囲も拡大したといえます。
フリーランス新法で拡大した特別加入の対象範囲

フリーランス新法の施行にともなって拡大した特別加入の範囲ですが、主に「特定フリーランス事業」が含まれるようになりました。
ここで、特定フリーランス事業の特徴やそれ以外に特別加入できる業種、特別加入の対象にならないケースもあるのか解説します。
特定フリーランス事業とは
特別加入の対象範囲に含まれることになった「特定フリーランス事業」とは、フリーランスが企業などから業務委託を受けて手がける事業、またはフリーランスが消費者から委託されて行う特定受託事業と同種の事業を指します。
業務委託は、企業などがその事業のためにほかの事業者に対して、物品の製造や情報成果物の作成、役務の提供を委託することです。
例えばフリーランスの講師が企業からセミナーの講師を務めてほしいという依頼があった場合、業務委託契約を結んで仕事に取り組むことになります。
また、企業から業務委託を受け、同種事業で消費者からも委託を受けている場合は特定フリーランス事業に含まれます。
特定フリーランス事業の対象となる事業例は、以下のとおりです。
-
- 翻訳、通訳
- 講師、インストラクター
- デザイン、コンテンツ制作
- 調査、研究、コンサルティング
- 営業 など
特定フリーランス事業以外で特別加入できる業種
対象範囲に含まれることになった特定フリーランス事業ですが、業務委託だったとしても以下の業種は特定フリーランス事業には含まれず、該当の特別加入団体を通じて加入する必要があります。
-
- 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
- ひとり親方(建設業、林業)
- 漁船の自営漁業者
- 医薬品の配置販売業者
- 再生資源取扱業者
- 船員法第1条既定の船員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
- 歯科技工士
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国や地方などが実施する訓練従事者
- 家内労働者
- 労働組合などのひとり専従役員
- 介護作業従事者
- 家事支援従事者(家政婦(夫))
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- ITフリーランス
例えばITフリーランスの場合、企業と業務委託契約を結んでいる場合、特定フリーランス事業ではなくITフリーランスの特別加入団体に申請することになります。
特別加入の対象にならないケースもある?
フリーランスとして活動している場合でも、特別加入の対象にならないケースもあります。
例えば、企業から業務委託を受けておらず、消費者のみから委託を受けている場合は対象外です。
また、企業から業務委託を受けているものの、異なる事業で消費者から委託を受けている場合も対象になりません。
業務委託とは関係なく、企業や消費者に向けて商品やサービスを販売した場合も対象外です。
フリーランスが労災保険に特別加入するメリット

フリーランスが労災保険に特別加入した場合、主にどのようなメリットが得られるのでしょうか。
治療費を補償してもらえる
第一のメリットとして挙げられるのが、治療費を補償してもらえることです。
労災保険に特別加入した場合、業務中に発生した事故などの影響でケガや病気になってしまった場合、本来フリーランスならすべて自己負担となります。
しかし、労災保険に特別加入していれば治療費の補償により、無料で治療を受けられることになります。
給付対象になるのは、診療代や手術費、入院費、薬代に加え、在宅療養の管理や介護にかかる費用、移送費などです。
労災指定の病院で治療を受けた場合は、当日に本人が支払う必要はなくなり、病院側で直接保険請求を行う「現物給付」になります。
一方、指定されていない病院で治療を受けた場合は、一旦治療費は自己負担で支払い、後日請求すると治療費分が返金されます。
治療費の補償は症状が完治、または固定するまで続くため、長期間の治療が必要となってしまった場合でも安心です。
働けなくなった場合の休業補償も受け取れる
労災保険に特別加入していると、治療費の補償だけでなく休業を余儀なくされた場合の補償も受け取れます。
例えばデザイナーが仕事中に手首を骨折してしまった場合、ペンを持つことができず仕事を休まざるを得なくなってしまいます。
フリーランスだと仕事ができない分、収入も減ってしまうことから、金銭面などに不安を感じてしまうものです。
しかし、労災保険に特別加入をしていれば休業補償が給付され、収入の一部を補填してもらえることから、治療に専念することも可能です。
特別加入時の労災保険料はいくら?

労災保険に特別加入した場合、すべて自己負担で保険料を支払うことになります。どれくらいの保険料を支払うことになるのか、計算方法などを確認しておいてください。
フリーランスの保険料率
保険料を計算する際に、保険料率を求める必要があります。保険料率は業種ごとに3/1,000~52/1,000まで分類されており、フリーランスは3/1,000です。
将来的に保険料率の見直しはあるかもしれませんが、2025年時点では3/1,000で計算します。
なお、2025年時点で保険料率は3/1,000になっていますが、今後見直しがされる可能性もあり、その際は保険料も変動するので注意が必要です。
保険料の計算方法
実際に保険料を計算する際には、「給付基礎日額×365日×保険料率」の計算式が用いられます。
給付基礎日額とは、保険料や給付額を算定する際に基礎となる金額です。年間収入に基づいて計算されます。
例えば給付基礎日額が5,000円だった場合、保険料は5,000円×365日×3/1,000=5,475円になります。
給付基礎日額が低ければ低いほど保険料も安くなっていきますが、その代わり休業補償などの給付額も少なくなってしまうため、収入に見合った金額を申請したほうが良いでしょう。
フリーランスが労災保険に特別加入する方法

実際にフリーランスが労災保険に特別加入する場合、どのような流れで加入すれば良いのかも事前に把握しておくべきです。
ここで、フリーランスが労災保険に特別加入する方法を紹介します。
特別加入団体に入会してから申請する
労災保険の特別加入は、大きく2つの方法で加入することが可能です。特に一般的なのは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に入会してから申請する方法です。
業種や職種に合わせて既存の特別加入団体を選び、加入申請を行います。特定フリーランス事業に該当する場合は、特定フリーランス事業の特別加入団体に申請してください。
加入が決まったら、団体を通じて「特別加入申請書」を作成し、労働基準監督署長に提出します。手続き自体は団体が代行して行ってくれるので安心です。
新たに特別加入団体を立ち上げて申請することも可能
既存の特別加入団体が見つからない場合は、新たに団体を立ち上げて申請することになります。
特別加入団体を立ち上げるためには、まず同業種の自営業者・フリーランスなどを集め、団体として組織を構築しなくてはなりません。
団体として認められるためには、相当数の加入希望者が必要です。
組織を構築できたら、以下の書類を所轄の労働基準監督署に提出してください。
-
- 労災保険特別加入団体設立届
- 団体の規約や事業内容が示された書類
- 加入者名簿 など
審査を受け、認められることで特別加入団体を立ち上げ、そこから申請できるようになります。
業種によって健康診断を受ける場合もある
特別加入団体を通じて申請した際に、これまで従事してきたことがある業務と期間に応じて、健康診断を受けなくてはいけないケースもあります。
| 業務内容 | 従事した期間 | 健康診断 |
| 粉塵作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
| 振動工具を使用した業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業務 | 6カ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
| 有機溶剤業務 | 6カ月以上 | 有機溶剤業務健康診断 |
健康診断の結果によっては、特別加入が認められないケースもあるので注意してください。
フリーランスが労災保険に特別加入する場合の注意点

多くのフリーランスが特別加入できるようになったことから、検討している人もいるかもしれません。
しかし、労災保険に特別加入する前に知っておきたい注意点があります。どのような注意点があるのか紹介します。
労災保険料は経費に計上できない
労災保険に加入すると保険料を支払うことになりますが、この支出は原則経費として計上できません。
経費は事業を営む上で欠かせない支出となりますが、労災保険料はフリーランスが自分でリスク管理を行うための支出になるため、事業に必要な費用とは認められないのです。
ただし、経費として計上できないものの、社会保険料控除で所得控除の対象になります。
所得控除を差し引くことで課税所得が少なくなり、その分所得税の負担も抑えられます。
労災保険料をはじめ、フリーランスの支出は「経費にできるかどうか」が大切なポイントです。
どの支出が経費になるのかを整理できる【経費チェックリスト】を無料でご用意しています。
ぜひあわせてご活用ください。

無理のない範囲で給付基礎日額を設定する
一般的な労災保険とは異なり、特別加入制度だと給付基礎日額を自分で設定することが可能です。範囲は3,500円から25,000円までの16種類から選べます。
給付基礎日額を高く設定すると給付額も増えますが、その分保険料も高くなってしまいます。
途中で金額を変更することもできますが、適用されるのは次年度からとなってしまうので、無理のない範囲で給付基礎日額は設定しましょう。
保険料以外のコストも発生する
特別加入団体に加入する場合、保険料だけでなく団体の入会費や年会費、更新手数料なども支払うことになります。
入会費や年会費、更新手数料などの費用は、加入する団体によって異なります。入会費と年会費で数千円に収まるところもあれば、1万円以上かかってしまうところもあるでしょう。
保険料の支払いだけを考えてしまうと、加入後に想定外の費用を支払うことになるため、注意が必要です。
業務中に発生したものと証明できるようにする
フリーランスの業務中に発生した事故で労災保険を利用しようとした場合、本当に業務中に発生したものかどうかを証明できるようにする必要があります。
特にひとりで作業をしていて、周囲には誰もいなかった場合、証明するのが難しいです。
このような事態に陥らないためにも、日頃から業務内容や時間を記録しておくことが大切です。
まとめ・フリーランスも労災保険に特別加入するか検討しよう
フリーランスの場合、業務中や通勤中のケガや病気で働けなくなってしまった場合、収入がストップしてしまうことから不安も大きいです。
しかし、労災保険の特別加入によって治療費の補償や休業補償を受けることができます。
万が一のトラブルに備えたい人は、労災保険の特別加入を検討してみてください。
「これは経費にできる?」「節税につながる?」と迷うことはありませんか?
労災保険料の扱いとあわせて確認しておきたいのが、日々の支出の経費区分です。
創業手帳では、フリーランス・個人事業主向けに【経費チェックリスト】を無料配布中。
安心して経費処理を進めるためにぜひご利用ください。

(編集:創業手帳編集部)