有給休暇のルールとは?取得率を上げる取組みや注意点を解説
有給休暇を取得しやすい仕組みを作ろう
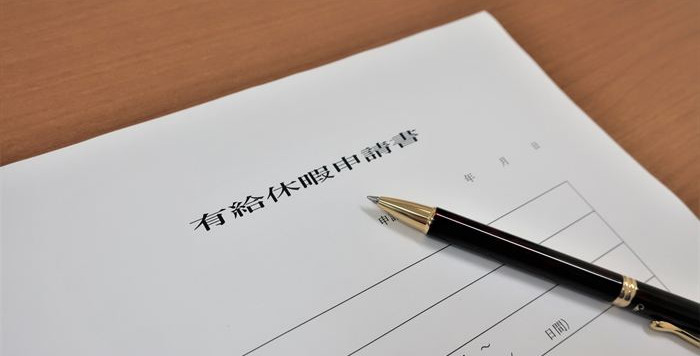
「年次有給休暇」は、労働者に対して付与することが労働基準法で定められています。
会社ごとに決められている方法に従って申請しますが、どれくらいの有給休暇があるのかわからない人もいるかもしれません。
この記事では、基本的な有給休暇の取得や設定ルールに加えて、会社としての取組みについても解説します。ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
有給休暇とは

有給休暇とは、一定期間勤務した労働者に対して付与される休暇です。
心身の疲労を回復してゆとりある生活を保つための休暇であることが、労働基準法39条1項で定められています。
有給休暇の日数は雇入れの日から計算され、基準期間において全労働日のうち80%勤務した場合に付与対象になります。
パートやアルバイトでも、要件を満たせば有給休暇が付与されます。
有給休暇は雇入れの日から6カ月後に付与され、2回目以降は前回付与された前日の1年後となります。
有給休暇は労働者の権利なので、原則として会社に承認や許可を取る必要はありません。
企業側は、社員から有給休暇の申請を受けた場合、指定日に付与するのが基本です。
有給休暇の設定ルール

続いて、有給休暇の設定ルールについてです。ここでは、細かなルールに関して説明します。
付与要件
有給休暇は労働者の権利であり、労働基準法で定められている制度です。
有給休暇が付与される労働者の条件は、「所定労働日数の8割以上出勤していること」「6カ月以上継続して雇用されていること」です。
所定労働日数とは、終業規則や労働契約書で定められた労働日数を指します。
この2点を満たしていれば、正社員に限らずパートやアルバイト従業員でも有給休暇が取得できます。
また、有給休暇は付与された日から1年ごとに発生していき、勤続勤務年数が増えると付与される日数も増えます。最終的には1年間で20日になる仕組みです。
なお、2019年4月に行われた労働基準法改正により、すべての企業で年間10日以上の有給休暇が付与された従業員に対して、年間5日を取得させることも義務付けされました。
有給休暇を取得した日は、出勤率の計算において出勤したものとみなされ、さらに以下の期間であっても同じように出勤扱いとなります。
-
- 遅刻や早退した日
- 業務上のケガや病気での休業期間
- 産前産後休業期間
- 育児休業期間
- 介護休業期間
付与日数
有給休暇の付与日数は、1日単位で取得可能です。
勤続勤務年数(年)
| 雇入れ後の勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上(8年以上) |
| 付与日数(日) | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働時間が30時間に満たない労働者は、週所定労働日数によって有給休暇の日数が異なります。
①週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日
| 雇入れ後の勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5以上(8年以上) |
| 付与日数(日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
②週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日
| 雇入れ後の勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上(8年以上) |
| 付与日数(日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
③週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が121日から168日
| 雇入れ後の勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上(8年以上) |
| 付与日数(日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
④週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が169日から216日
| 雇入れ後の勤続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上(8年以上) |
| 付与日数(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
フルタイム労働者
フルタイム労働者の有給休暇は、勤続勤務年数に応じて付与されます。労働基準法39条2項に記載されている内容を基に日数が決まっています。
| 勤続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上(8年以上) |
| 付与日数(日) | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |
パートタイム労働者
パートやアルバイトの場合、週所定の労働日数や労働時間によって有給休暇の日数が変動します。
週所定労働日数が5日以上、もしくは1年間の所定労働日数が217日以上の場合、フルタイム労働者と同じ考え方で有給休暇が計算できます。
上記の「付与日数」の項目①~④を参考にして、有給休暇の日数を確認してみてください。
また、付与日数と同じように確認したいのが、有給休暇の年5日取得義務対象者です。
1年間で10日以上の有給休暇が付与されている場合、年5日間取得する義務が生じます。これは、社員に限らずパートやアルバイトも同じです。
付与するタイミング
有給休暇を付与するタイミングは、原則雇入れ日から6カ月です。法定で決められた基準日から前倒して付与することが可能で、入社時に一括で付与することもできます。
最初に有給を付与した日が「基準日」となり、その後は最初の基準日から勤続年数を足していき、付与日数が決まる計算です。
入社日などに前倒して一括で有給休暇を付与する場合、初めて付与した日を基準日とします。その後は次の付与される日までの勤続年数に応じて付与される日数を調節します。
なお、有給休暇を付与する際には、労働者の不利にならないように気を付けなければなりません。
年度初めなどに一斉に有給休暇の付与日を決めることを「斉一的取扱い」といい、入社日などによる有給休暇付与のばらつきを解消する効果があります。
従業員数が多い企業や中途採用を積極的に行っている企業では、このような方法で適切な有給休暇の付与を設定しています。
付与日数の上限
有給休暇には付与日数の上限が設けられています。
付与された日から2年間が有効期限であり、付与された年に使いきれない有給休暇が翌年に繰り越すことができる仕組みです。
例えば、入社日に付与された有給休暇を1年以内に使ったものの、2日分使いきれなかった場合、翌年に使いきれなかった2日分が繰り越されます。
また、有給休暇は年間最大付与日数が20日と法定で決められています。
このうち、年10日以上の有給休暇が付与されている従業員は年5日の取得を義務としていますが、前年度の繰り越し分で満たしてしまった場合、翌年度には20日が繰り越せる仕組みです。
当年に付与された最大20日の有給休暇に加えて、前年度から繰り越している最大20日分を合わせた最大40日まで保有できます。
なお、一般的な有給休暇は最大40日ですが、社内規程によって上限以上の有給休暇が付与されることもあります。
社内の就業規則で有給休暇の有効期限を2年以上に設定できますが、2年未満にはできません。
有給休暇の取得ルール

有給休暇を取得する際には、いくつかのルールが設けられています。ここでは、取得ルールについて解説します。
1日単位での取得が原則
基本的に有給休暇は自由に取得できるものであり、労働者の正当な権利です。
また、1日単位で付与されますが、労働者の希望で使用者が同意した場合に限り、半日単位で有給休暇を付与することも可能です。
この時に企業側が労働者の有給休暇取得の理由を聞いて拒否したり、希望日の取得を拒否したりしてはいけません。
もし、時間単位で有給休暇を付与する場合は、労使協定においての事項を定める必要があります。
-
- 時間単位で有給休暇を付与できる労働者の範囲
- 時間単位で有給休暇を付与できる有給休暇日数(5日以内に限る)
- 時間単位で有給休暇を付与できる有給休暇一日の時間数(1日の所定労働時間数を下回らないこと)
- 1時間以外の時間を単位として有給休暇を付与する場合にはその時間数(1日の所定労働時間数に満たないこと)
取得するタイミングは労働者が決めて良い
有給休暇の取得は労働者の正当な権利であり、取得するタイミングや理由については問われません。
どのような理由であっても労働者には有給休暇を取得する権利があるからです。有給休暇取得のタイミングは原則として労働者が決められます。
ただし、時季変更権が認められる場合を除いて、使用者は労働者の請求する時季に有給休暇を与える必要があるので注意してください。
年有給付与10日以上なら5日取得が義務(時季指定業務)
労働者から求められた時季に有給休暇を与えると、正常な事業運営ができなくなる場合は時季変更権が認められます。
時季変更権について、以下の例のようなケースで認められます。
-
- 同時期に有給休暇取得希望者が重なった
- 本人の参加が欠かせない業務がある
- 代替の人員を確保できない
- 長期間の有給休暇となる
ここで注意したいのは「業務が忙しくなりそうだから」「繁忙期だから」などの漠然とした理由では使えないことです。
時季変更権は、正当性を裏付けるための具体的な理由が求められます。
なお、労働者は退職直前に残った有給休暇を取得する権利があるため時季変更権は使えません。
このタイミングで時季変更権を行使すると、有給休暇取得妨害とみなされる可能性があります。
有給休暇に関する注意点
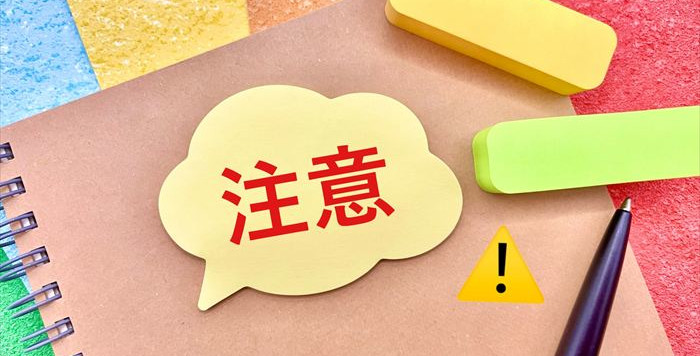
有給休暇には他の注意点もあります。申請や許可の際には、以下の内容を確認してください。
年次有給休暇管理簿の作成・保存が必要
2019年4月に施行された改正労働基準法では、年5日の年次有給休暇の取得が義務になりました。また、年次有給休暇管理簿の作成や保存も義務です。
年次休暇管理簿は、従業員の年次有給休暇を取得した際の状況を記録したり管理したりする帳簿であり、企業側が従業員に対して有給休暇を適切に取得、付与させているか把握するためのものです。
有給休暇を与えた時に「日数」「基準日」「時季」を労働者ごとに記載して、3年間保存します。
不利益な取り扱いは禁止されている
労働基準法136条では、年休取得日を欠勤扱いにしたり年休権の行使抑制などを行ったりすることを禁止しています。
年休の取得やその理由、目的など使用者への干渉は認めていません。
例として、「賃金の減額」「有給休暇取得により賞与査定のマイナス要素として考慮する」「有給休暇取得により皆勤手当てを不支給にする」「有給休暇取得による解雇」などの扱いをした場合は労働基準法違反です。
取得機会を確保しないとペナルティが科せられる
有給休暇においては、取得機会を適切に与えなかった場合は企業側にペナルティが与えられます。
年間有給休暇付与日数が10日以上の従業員に対して、1年以内に5日取得させるように義務付けられており、違反した場合は1人あたり30万円の罰金が科せられることに注意してください。
また、就業規則に時季指定が記載されていなければ、1件につき30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
さらに、正当な理由なく有給休暇の拒否や放置を行った場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
有給休暇の取得率を上げる取組み
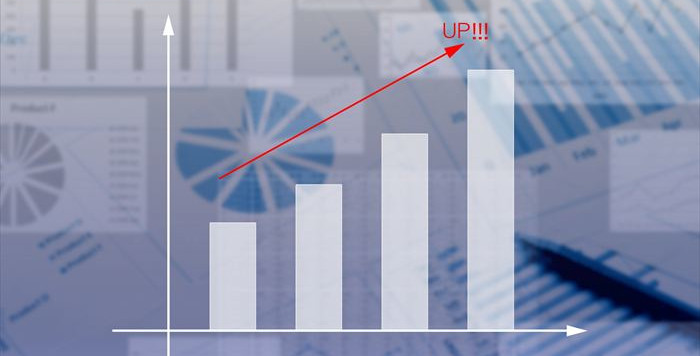
企業側も労働者側も有給休暇取得を意識する必要があります。特に企業側は、労働者が有給休暇を取得しやすい環境を整えなければなりません。
ここでは、有給休暇の取得率を上げるための取組みを紹介します。
年次有給休暇取得計画表の作成
有給休暇を取得しやすいように、企業側は積極的に環境を整備する必要があります。年次有給休暇取得計画表を作成すれば、確認しやすいです。
計画的な有給休暇の取得に適していて、業務運営を可能にしながら休暇取得の確実性も高めます。
社員に対して継続的に周知させる
企業側が積極的に有給休暇取得を促進させるには、取得しやすい環境作りと同時に雰囲気を作ることが重要です。
有給休暇取得を遠慮する雰囲気にならないように、従業員の目に留まりやすい環境に啓発ポスターなどの資料を貼るなどして継続的な周知を心がけてください。
特に、企業の雰囲気を課題に感じる場合、プライベートの充実やリフレッシュの大切さを周知させ、夏季休暇、大型連休などまとまった休暇のタイミングと合わせて取得できる方法を提案するのもおすすめです。
取得目標を設定して管理を行う
有給休暇は、取得に関連する管理職により左右されるケースがあります。
環境に左右されないためには、有給休暇取得状況の全国平均数や企業内での部署、職種などを落とし込み、取得日数に加えて取得率も含めて目標を決めることが重要です。
目標に届かなかった場合、該当者に加えて上司に対して今後の有給休暇取得予定の確認、業務スケジュールの管理などを行った後に再度目標を設定し直します。
管理することで、有給休暇の取得率が向上するかもしれません。
半休または時間単位での取得システムを導入する
有給休暇は基本1日単位での付与ですが、半休または時間単位で取得できるシステムを取り入れることで、より柔軟性の高い働き方につながります。
子どもの学校行事に参加したり、家族の病院に連れ添ったりする関係で、半日または2~3時間程度休みたい従業員もいるかもしれません。
有給休暇を使うのはもったいないと考えてしまうかもしれませんが、半休や時間単位で取得できるシステムなら心理的抵抗も少なくできます。
ただし、時間単位の有給休暇付与制度を導入するには、労使協定を結ぶ必要があり、就業規則にもその旨を記載する必要があります。
取得促進のための支援制度「働き方改革推進支援助成金」

有給休暇取得のための支援制度に、「働き方改革推進支援助成金」があります。
働き方改革推進のために制度の導入や改善を行った事業主に対して助成されるものです。支給対象となる取組みを行い、その目標を達成したことで受給条件をクリアできます。
いくつものコースがあるだけでなく、それぞれの成果目標も異なっているため、自社に適した課題に合ったものを選ぶのが良いかもしれません。
まとめ・有給休暇を取得しやすい環境づくりを目指そう
有給休暇は労働者に取得権利があり、会社側の許可や承認などが不要で取得できるものです。社員に限らず、パートやアルバイトでも取得できます。
従業員のリフレッシュを目的としており、雇い入れた日から6カ月間の勤務のうち8割以上の出勤率を獲得した際に付与されます。
企業側が与えなかった場合はペナルティが課せられるため、取得しやすい環境に整えていくことが大切です。
創業手帳(冊子版)では、有給休暇のルール以外にも、経営者が働けなくなった場合を想定して備えておくべきことなども掲載。この機会にぜひご活用ください。
(編集:創業手帳編集部)




































